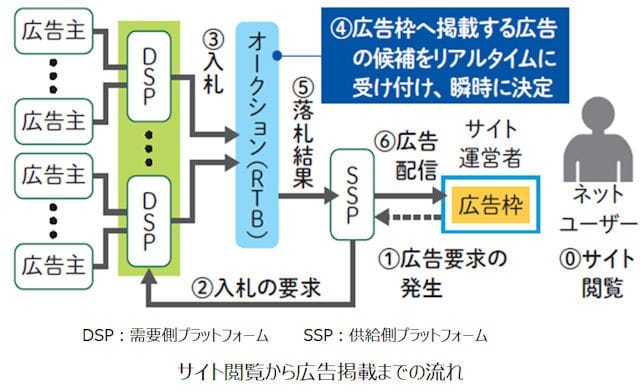窓のない部屋やあっても外の景色が悪い部屋などへの設置が想定されている、窓のような形をした液晶画面で、そこに映し出される映像があたかも窓から見える景色であるかのように感じられるデバイスのことです。私たちの生活空間に癒しや開放感を提供してくれる新しいデバイスとして注目されているようです。
デジタル窓を利用することで、窓のないあるいは景色の悪い部屋やオフィス・ホテル・店舗でも開放感を感じられたり、自宅等にいながら世界各地の風景を見てリフレッシュできたり、テレワーク中の気分転換や集中力アップにも活用できたり、といった効果が期待されます。
デジタル窓には、(1)あらかじめ本体に保存されている映像、(2)インターネット経由で専用の映像配信サービスやストリーミングサービスから取得した映像、(3)HDMIケーブル等を経由して外部機器から取得した映像などを表示することができるようです。
液晶ディスプレイは、4Kやそれ以上など高解像度のものが利用され、天気予報やニュース、カレンダー、時計などの情報も表示できたりするようです。また、内蔵スピーカーからは撮影時の自然音や映像に合わせたサウンドなどが流せる他、スマートスピーカーと連携させることで音声操作に対応できたりするようです。
デジタル窓メーカーとしては、新興企業のアトモフ(Atmoph)株式会社(2014年8月14日設立、京都市、https://atmoph.com/ja/about_us)が知られています。当企業は、スマートなデジタル窓”Atmoph Window"をクラウドファンディングの利用により世界に先駆け開発し、2015年に初代版として発表しているようです。その後も積極的な活動を展開し、2020年には”Atmoph Window 2"を販売開始しています。
本体製品は、BtoC市場(主に一般家庭向け)を中心に展開されており、オンラインストア(ATMOPH Store)にて購入できるようです。また、風景の映像コンテンツは、個別に購入することも可能ですし、サブスクリプションサービス(月額制)で利用することも可能なようです。
海外の色々な風光明媚な景色等をリアルのような映像で楽しむことにより、自宅にいながらにして、あたかも海外旅行しているような気分になったりできるのはと思ったりします。
”Atmoph Window 2"関連のプレスリリース(2020.9.30)のページは、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000013724.htmlです。