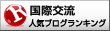私が生まれたのは斜里岳と藻琴山の間の厚生開拓村だが、
小学校3年生の時に斜里町郊外のに引っ越した。
北海道では行政区画に「」という名称があり、本州で言う「村」規模の集落を指す。
高校卒業後、関西に出てきた当時は「問題研究会」という看板を見て、
「過疎地の問題を考える研究会」だと思っていた。
若くて未熟者丸出しの頃の話だ。
(かと言って今熟成しているかと問われると頭を垂れるしかない。歳だけは十分重ねているのだが)。
引っ越した学校は以久科(いくしな)小学校と言った。
ちなみに「以久科」や「斜里」(しゃり)は元来アイヌ語であり、
「以久科」(「幾品」とも書く)は「それを突き抜けている」という意味だとか(「それ」が何を指すかは不明)。
「斜里」は「サル」=「葦の繁るところ」の意味である。
以久科はビート(甜菜)、ジャガイモを中心にした畑作地帯が広がっていた。
今、作物の種類はもっと多様化しているかも知れない。
小学校のある場所から子どもの足で1時間ほど歩けばオホーツク海に出る。
小学校3年生の春の遠足の目的地がオホーツク海の砂浜だった。
今回、東京から帰京した甥の晋也君と我がデコボコ3代女達が共に海の傍のお墓にお参りし、
車で5分ほどの以久科の浜辺まで足を延ばした。
あらら、ここも世界自然遺産のエリアだったのか、と看板を見て初めて知った。

そこは昔と変わらずハマナスが群生していた。
花の盛期は6月後半から8月初め頃だったはず。
ビッシリと実をつけていたので、一つ食べたら予想以上に甘くておいしかった。
(すいません、この時点では自然遺産だとはつゆ知らず、エヘヘ(^_^;))


まだつぼみも少し残っている。

散る寸前の花。子どもの頃は棘があるので好きな植物ではなかったが、
今は特別な思いが湧く。

ハマナス以外にも多種類の植物が生息している。


このブッシュを越えると海だ。

この小道は砂地なので、都会育ちの我が娘は「足に砂がついて汚い感じ」と言う。
私は今まで一度も砂が汚いと思ったことはない。

ジャーン!海が開けた。遠くに知床連山が見える。

波穏やか。

孫娘はオホーツク海で海デビューを飾った。

娘はこの(下の)写真を見て、
「私たち母娘は孤独な二人組だけど、がんばって生きていこうね」
と物語を作っていた。
やはり沖縄の青い海とは雰囲気が違う。
北の海は地味で厳しいムードが漂うのである。
『津軽海峡冬景色』がオホーツク海の仲間である。

オホーツク海の浜辺、甥と私たち以外に誰もいなかった。