娘のところに預かってもらっていた留守中の郵便物をチェックしていて、
釜ヶ崎の友達というか先輩のマリ子さんからの
「おとなが育ち会いたい集まり通信No.46 」を見つけた。
もう何十年も続いているこの通信には、
大阪釜ヶ崎で暮らす女性や若者たちの声が載っている。
野宿労働者の越冬支援パトロール活動報告文や、
人として生きる感性を綴った詩、
読者からの便りなどに混じって、
3月末に大阪鶴橋であった、
「日本・コリア友情のキャンペーン」報告文が載っていた。
在特会の鶴橋行動に抵抗するためのキャンペーンということだ。
私が生まれてこの方見聞した中で最も愚かな現象の一つである在特会の、
憎しみを煽り、殺人までをも示唆する活動に対して、
大阪在住の人たちがきちんと反撃していたのが嬉しい。
嬉しいのでブログを読んでくださっているみなさんと分かち合いたい。
---------------
「日本・コリア友情のキャンペーン」
3月31日、連れだって鶴橋に向かう。
鶴橋駅近くの公園に人が続々と集まる。
多数の警官と私服の姿、緊迫している。
「鶴橋大虐殺」を叫ぶ「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などが、
鶴橋に来るというので、
抵抗しようと“日本・コリア友情のキャンペーン”の呼びかけがあって、
みんなが集まった。
公園から駅のガード下に歩いていくと、
道路の向こう側に大きな旭日旗や日の丸を掲げて
何十人も在特会が拡声マイクで叫んでいる。
背広を着た男や着物を着た女の人もいた。若い人もいる。
「ゴキブリ」「死ね」「強制連行も従軍慰安婦もなかった、出ていけ」
…とがなり立て、憎悪と暴力の言葉を投げつけている。
ここ、朝鮮市場で働くオモニたちはどんなにか怖いだろう。
私たちは“日本・コリア友情のキャンペーン”の
ポスターやビラを掲げて駅前の歩道を歩いて訴える。
友情のキャンペーンを伝え聞いた様々な多くの人たちが
どんどんやって来て、仲間が増えていく。
赤ちゃんをおんぶして手作りのプラカードを持ってきた人もいる。
韓国の民主化闘争でこうして闘ったという“人間マイク”をやろうと、
リーダーが声を上げる。
「差別!」と言うと、みんなが「反対!」と一緒に声を上げる。
「人権!」「平和!」
「長時間マイクで!」「喋り続けて疲れませんか!」
「休憩しませんか!」「お水でも飲みませんか!」「もう止めませんか!」
リーダーが呼びかける言葉にみんなが唱和する。
そして、それはひとつの大きな肉声となって、在特会に呼びかける。
私たちも思わず笑いながら、繰り返し、精いっぱいの声を上げる。
すばらしいシュプレヒコール。
歩いている人が声をかけてくる。
「何してますか?」
その若い女性はベトナム人だという。
連れの女性に今聞いたことをベトナム語で話していた。
黙って手を差し伸べてビラをもらっていく人もいた。
通りがかった男性が、
「日本人として恥ずかしい。自分も反対したかった」
と、ポスターを受け取って最後まで行動に参加していた。
一人の女の人が、
“友情のキャンペーン”を掲げている女性を見つめて泣いていたという。
嬉しかったんだと思う。
マリ子さんが言う。
「日本人の差別意識の問題。うちらが問われているのよ」
と。閉塞感の中で在特会のような差別と暴力が公然と出てくる
社会の空気があるということが恐ろしいと思う。
でも、かけつけて抵抗の声をあげる人たちもいる。
行動する、そんな仲間がほんとに大勢集まったことが嬉しかった。
(エノキ)
付記:当日のビラの文章
日本にはたくさんの在日コリアンの人たちが暮らしています。
そして、たくさんの外国人の人たちが暮らしています。
そして、たくさんの「ちがい」のある人たちが暮らしています。
その人たちは、いろんな「歴史」を持っています。
その人たちは、いろんな「ちがい」を持っています。
その人たちは、いろんな「つながり」を持っています。
私たちは、いろんな「歴史」を尊重したいと思います。
私たちは、いろんな「ちがい」を尊重したいと思います。
私たちは、いろんな「つながり」を尊重したいと思います。
そして、
差別や排除のない、お互いを尊重する「共生社会」を、
日本とコリア、ちがいのある人たちが友情を育める
そんな社会を望んでいます。
『おとなが育ち会いたい集まり通信46号』より
釜ヶ崎の友達というか先輩のマリ子さんからの
「おとなが育ち会いたい集まり通信No.46 」を見つけた。
もう何十年も続いているこの通信には、
大阪釜ヶ崎で暮らす女性や若者たちの声が載っている。
野宿労働者の越冬支援パトロール活動報告文や、
人として生きる感性を綴った詩、
読者からの便りなどに混じって、
3月末に大阪鶴橋であった、
「日本・コリア友情のキャンペーン」報告文が載っていた。
在特会の鶴橋行動に抵抗するためのキャンペーンということだ。
私が生まれてこの方見聞した中で最も愚かな現象の一つである在特会の、
憎しみを煽り、殺人までをも示唆する活動に対して、
大阪在住の人たちがきちんと反撃していたのが嬉しい。
嬉しいのでブログを読んでくださっているみなさんと分かち合いたい。
---------------
「日本・コリア友情のキャンペーン」
3月31日、連れだって鶴橋に向かう。
鶴橋駅近くの公園に人が続々と集まる。
多数の警官と私服の姿、緊迫している。
「鶴橋大虐殺」を叫ぶ「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などが、
鶴橋に来るというので、
抵抗しようと“日本・コリア友情のキャンペーン”の呼びかけがあって、
みんなが集まった。
公園から駅のガード下に歩いていくと、
道路の向こう側に大きな旭日旗や日の丸を掲げて
何十人も在特会が拡声マイクで叫んでいる。
背広を着た男や着物を着た女の人もいた。若い人もいる。
「ゴキブリ」「死ね」「強制連行も従軍慰安婦もなかった、出ていけ」
…とがなり立て、憎悪と暴力の言葉を投げつけている。
ここ、朝鮮市場で働くオモニたちはどんなにか怖いだろう。
私たちは“日本・コリア友情のキャンペーン”の
ポスターやビラを掲げて駅前の歩道を歩いて訴える。
友情のキャンペーンを伝え聞いた様々な多くの人たちが
どんどんやって来て、仲間が増えていく。
赤ちゃんをおんぶして手作りのプラカードを持ってきた人もいる。
韓国の民主化闘争でこうして闘ったという“人間マイク”をやろうと、
リーダーが声を上げる。
「差別!」と言うと、みんなが「反対!」と一緒に声を上げる。
「人権!」「平和!」
「長時間マイクで!」「喋り続けて疲れませんか!」
「休憩しませんか!」「お水でも飲みませんか!」「もう止めませんか!」
リーダーが呼びかける言葉にみんなが唱和する。
そして、それはひとつの大きな肉声となって、在特会に呼びかける。
私たちも思わず笑いながら、繰り返し、精いっぱいの声を上げる。
すばらしいシュプレヒコール。
歩いている人が声をかけてくる。
「何してますか?」
その若い女性はベトナム人だという。
連れの女性に今聞いたことをベトナム語で話していた。
黙って手を差し伸べてビラをもらっていく人もいた。
通りがかった男性が、
「日本人として恥ずかしい。自分も反対したかった」
と、ポスターを受け取って最後まで行動に参加していた。
一人の女の人が、
“友情のキャンペーン”を掲げている女性を見つめて泣いていたという。
嬉しかったんだと思う。
マリ子さんが言う。
「日本人の差別意識の問題。うちらが問われているのよ」
と。閉塞感の中で在特会のような差別と暴力が公然と出てくる
社会の空気があるということが恐ろしいと思う。
でも、かけつけて抵抗の声をあげる人たちもいる。
行動する、そんな仲間がほんとに大勢集まったことが嬉しかった。
(エノキ)
付記:当日のビラの文章
日本にはたくさんの在日コリアンの人たちが暮らしています。
そして、たくさんの外国人の人たちが暮らしています。
そして、たくさんの「ちがい」のある人たちが暮らしています。
その人たちは、いろんな「歴史」を持っています。
その人たちは、いろんな「ちがい」を持っています。
その人たちは、いろんな「つながり」を持っています。
私たちは、いろんな「歴史」を尊重したいと思います。
私たちは、いろんな「ちがい」を尊重したいと思います。
私たちは、いろんな「つながり」を尊重したいと思います。
そして、
差別や排除のない、お互いを尊重する「共生社会」を、
日本とコリア、ちがいのある人たちが友情を育める
そんな社会を望んでいます。
『おとなが育ち会いたい集まり通信46号』より










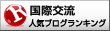





 )
)
















