先日、落として壊してしまった LUMIX TZ60 。
その後、散歩にはミラーレス一眼の LUMIX GX7 を持って出ていっていたのですが、単焦点の小さなレンズをつけても、やっぱりかさばるんです。

それに、ずっしりと重い(500g)。
やっぱり、きょうは、写真を撮りに行くぞというときに持ち出すカメラなんですね。
ということで、やっぱり、コンデジを買うことにしました。
TZ60 の最新型、TZ95 で、よかったのですが、
どうせ、新しいコンデジにするなら、今までのとは違ったもの(デザインも性能も)にしよう(でも、LUMIX からは離れたくない)ということにしました。
そこで、選んだのが、LUMIX DMC-TX1
4年前に発売されて、すでに後継機種の TX2(2018年2月14日発表) が出ているのですが、
ズームが10倍から15倍に大きくなった代わりに、レンズが暗くなったり、価格も大幅にアップしているなど、あまりメリットが多くなかったので、古い機種ではありますが、TX1 にしました。

なんか、LEICA の雰囲気がすごくします。
 LEICA C-LUX
LEICA C-LUX
それもそのはず、LEICA C-LUX は、LUMIX TX2 をベースにしたものです。
で、壊してしまった DMC-TZ60 から、TX-1 は、どのくらい性能がアップしているのか一覧表にしました。
<style type="text/css"></style>
| |
DMC-TZ60 |
DMC-TX1 |
| 発売時価格 |
43,000円 83,000円
|
| 発売日 |
2014年2月13日 |
2016年3月10日 |
| カメラ有効画素数 |
1810万画素 |
2010万画素 |
| 撮像素子 |
1/2.3型MOS 総画素1890万画素 原色カラーフィルタ |
1.0型 総画素2090万画素高感度MOSセンサー 原色フィルター |
| 構成 |
9群12枚(非球面10面5枚) LEICA DC VARIO-ELMAR |
10群12枚(非球面レンズ9面5枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| 光学ズーム |
30倍 |
光学10倍ズーム |
| 超解像iAズーム |
60倍 |
20倍 |
| デジタルズーム |
最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) |
最大4倍(iAズーム時は最大2倍) |
| EX光学ズーム(EZ) |
最大36.7倍(4.3、12M時)、最大45.0倍(4:3、8M時)、最大57.4倍(4:3、5M時)、最大71.7倍(3M以下時) |
最大20倍 (3:2アスペクト、S時) |
| 開放絞り値 |
F3.3~6.4 |
F2.8 - 5.9 |
| 焦点距離 |
f=4.3mm~129.0mm(35mm換算:24~720mm) |
f=9.1-91mm(35mm 判換算:25-250mm) |
| 撮影可能範囲 |
通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ |
通常:50cm(W端) / 70cm (T端) - ∞ |
| |
マクロ/インテリジェントAUTO/動画:3cm(W端)/2m(T端)~∞ |
AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:5cm(W端) / 70cm(T端) - ∞ |
| 手ブレ補正 |
○(ON/OFF) 5軸ハイブリッド手ブレ補正、傾き補正
POWER O.I.S.
|
動画:アクティブモード(光学式)、5軸ハイブリッド手ブレ補正※1、傾き補正
静止画:POWER O.I.S.(ON/OFF可) |
| フォーカスモード |
通常/AFマクロ/ズームマクロ/MF
AF測距:1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/23点/顔認識/追尾AF |
[AFS(シングル) / AFF(フレキシブル) / AFC(コンティニュアス)] 、[AF / AFマクロ / マクロズーム / MF](メニュー切換え)
|
| DFD-AF(空間認識AF) |
ー |
〇
|
| |
|
|
| AF補助光 |
○(ON/OFF) |
〇 |
| 外形寸法 |
約幅 110.6×高さ64.3×奥行 34.4mm(突起部を除く) |
約110.5 x 64.5 x 44.3mm(突起部を除く) |
| 質量 |
約214g(本体)、約240g(バッテリー、メモリーカード含む) |
約310g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) |
| ISO感度 |
オート/i.ISO/80/100/200/400/800/1600/3200/6400
高感度モード:1600~6400 |
(静止画)
オート / i.ISO / 80※5 / 100※5 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600※5 (1/3EVステップに変更可能)
(動画)
オート / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3EVステップに変更可能) |
| ホワイトバランス |
オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード、プリセット値から微調整(オート以外) |
オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位) |
| 露出 |
プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) |
プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) /マニュアル露出(M) |
| ファインダー |
カラー液晶ビューファインダー 0.2型 20万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
カラー液晶 LVF(ライブビューファインダー) 0.2型 約116万ドット 視度調整付き(-4~+4diopter) 視野率約100% |
| 液晶モニター |
3.0型 92万ドット IPS /TFT液晶 |
アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率 約100% |
①大きな性能アップが、センサーサイズ。1/2.3型から、面積にして4倍の1インチがついています。

これは、光学ズームが3分の1(30倍→10倍)になった ハンディーを補完するため、iAズーム(10倍→20倍)を使ったときに、絶対有利だと思います。
ためしてみました。
まず、25mm

250mm

500mm

1,000mm(デジタルズーム)

さすがに、デジタルズームの40倍(1,000㎜)は、厳しいですが、20倍(500㎜)は、十分に使えそうです。
②更に、レンズが、LEICA ELMAR (F3.3)から ELMARIT(エルマリート F2.8)に明るく(1.59倍)なっています。
LEICA レンズを名乗るには、最低このぐらいの明るさは欲しかったところです。
③4K動画が撮れるようになりました(30pですが)。
4Kをスムーズに記録するには、UHSスピードクラス3 (U3) 規格以上のUHS-I SDメモリーカードが推奨されていますので、これも用意しました。
④カラー液晶 LVF(ライブビューファインダー) の解像度が5倍の約116万ドットになりました。TZ-60 はちょっとファインダーがしょぼかったので、これはありがたい。
実際にのぞいてみると、すごく明るくて見やすくなっています。
⑤オートフォーカスに、DFD-AF(空間認識AF)が取り入れられた。これは、 ピント位置の異なる複数のライブ画像から空間を認識して、被写体までの距離情報を瞬時に算出、一気に合焦領域までピント合わせを行うAF制御。
以上、発売当時はハイエンドコンデジに位置付けられただけあって、性能はだいぶ高いようで、これから毎日使って実証していきたいと思います。

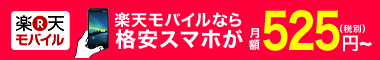


















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10219935.3295ba26.10219936.16e626a8/?me_id=1269553&item_id=11876400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3151%2F00000004524664_a01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)











![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d2f88de.8782062a.1d2f88df.0133529f/?me_id=1312153&item_id=10022424&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdear-book%2Fcabinet%2Famayahoo%2F07201291%2F1190-020281.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1376daec.50c6fc0a.1376daed.db73ad9d/?me_id=1202242&item_id=10444459&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_020%2F4545350044183_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0ff76658.bfbf5146.0ff76659.92325524/?me_id=1270903&item_id=10239133&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2F95%2F1867726_01l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)













![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1376daec.50c6fc0a.1376daed.db73ad9d/?me_id=1202242&item_id=10329439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_076%2F4984824926097_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cf9b395.737ab107.1cf9b396.eb9bef42/?me_id=1387840&item_id=10205861&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaimonoking%2Fcabinet%2Fimg0_mil0%2Foht_6%2Fremval_31%2Ft9bp5fhzqgsaxvmy.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1376daec.50c6fc0a.1376daed.db73ad9d/?me_id=1202242&item_id=10438387&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_036%2F4902704781680_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1376daec.50c6fc0a.1376daed.db73ad9d/?me_id=1202242&item_id=10480731&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_026%2F4549077174048_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1376daec.50c6fc0a.1376daed.db73ad9d/?me_id=1202242&item_id=11372280&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_098%2F4549980318164_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10e33e84.bf71710a.10e33e85.b8ea59df/?me_id=1217830&item_id=10191032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2Fmc538%2F269071.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17872cf3.e7d13742.17872cf4.ee9baad4/?me_id=1313470&item_id=10723399&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokka-com%2Fcabinet%2F430%2F4549980250587.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10e33e84.bf71710a.10e33e85.b8ea59df/?me_id=1217830&item_id=10077327&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femedama%2Fcabinet%2Fmc115%2F57931.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14826b3c.d74f4e27.14826b3d.f112e0fb/?me_id=1306791&item_id=10020683&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwinkstore%2Fcabinet%2F203500%2F203125.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
 LEICA C-LUX
LEICA C-LUX














![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/198c0113.f554f3b7.198c0114.fb595a0e/?me_id=1195022&item_id=11120593&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foutletplaza%2Fcabinet%2F004%2F4549526500299.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foutletplaza%2Fcabinet%2F004%2F4549526500299.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1998787e.96aa6f9f.1998787f.833c250f/?me_id=1311916&item_id=10000170&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftonarinoshop%2Fcabinet%2F06135986%2F01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftonarinoshop%2Fcabinet%2F06135986%2F01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10219935.3295ba26.10219936.16e626a8/?me_id=1269553&item_id=12417001&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3983%2F00000006229479_a01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3983%2F00000006229479_a01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19ee1b14.b2e96ae7.19ee1b15.5d49ecc8/?me_id=1351063&item_id=10002089&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flifepower%2Fcabinet%2F03000%2Ftrdst03_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flifepower%2Fcabinet%2F03000%2Ftrdst03_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/137691af.7466f445.137691b0.090131b8/?me_id=1276560&item_id=19219894&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-cutestyle%2Fcabinet%2Fimg020%2Fp000000617096_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-cutestyle%2Fcabinet%2Fimg020%2Fp000000617096_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












