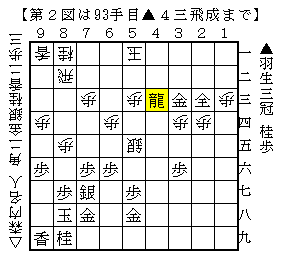「今は、生き抜くことが戦だ。
生きていれば、いつかきっと、会津に帰れる。
それを支えに生きていくべ」
「今でも、三郎の、おとっっぁまの…死んだみんなの無念を晴らしてえ。
んだけんじょ、恨みを支えにしていては、後ろを向くばかりで、前には進めねえのだし。
さっきのこづゆが、あんまりおいしくて、
みんなで頂けるのが、うれしくて。
もうしばらく、こうして生きていっては、なんねえべか」
八重だけでなく、多くの会津の者は、逆賊の汚名を晴らすため、会津を復興するため、「生きる」ことを誓う
・陸奥(下北)に領地替えになり、お家再興を誓う山川大蔵、広沢富次郎ら藩士たち
28万石から3万石、しかも本州の北の果て。「まるで島流しではねえかぁ!」と言うのももっともだ。(下北のみなさん、ごめんなさい)
それでも、「斗南」の名に「会津復興」の思いを託し、斗南に向かう(現代の東北に重なる)。それにしても、寒そう。
梶原平馬は、会津敗戦の責任を感じ職を辞した。
・西郷頼母は函館五稜郭で戊辰戦争の最後を迎える。
命を差し出して容保の除名を願うつもりであったが
「わしは生きる……わしらの会津を踏み潰していった奴らが、どんな世の中つくんのか、この目で見届けてやる」
・大蔵の弟・健次郎は長州で学問に励む
この際、秋月悌次郎も同行したと思われるが、佐川官兵衛はどうなったんだあ?
八重の言葉と対極にあるのは、過去に囚われて死にゆく萱野権兵衛(柳沢慎吾)の言葉
「ただ一つ無念なのはなあ、会津が逆賊の汚名を晴らす日を見届けずに死ぬことだ。
戦で失われたものは、戦で取り返すのが武士の倣い。頼むぞ。
そうでねえと……そうでねえと、死んだ者たちの無念が晴れぬ!」
たぶん、≪演じた柳沢慎吾はもう一つの無念があっただろう≫と彼をよく知る視聴者は思ったはず。
「さらば」ではなく「あばよ」と言いたかったはずだと。
八重の過去の心情を再現したのは千代。
夫の仇を討つため、息子を鍛え、自らも八重に鉄砲の教えを乞うという復讐に凝り固まった様は、過去の八重を見るよう。
八重は鉄砲を教えるつもりはないと言い、会津を愚弄する商人に妾として囲われてまで生きていこうとする千代に「今は、生き抜くことが戦だ」と励ます。
今回は「生きる」ということがテーマであった。
こづゆのエピソード、「斗南」に託した思いなど非常に良かった。
しかし、1話分飛んだ(抜かした)感がして仕方がない。
八重の心情の変化が
「仇を討つため、敵をひとりでも多く倒して死ぬ覚悟」から「生き抜くことが戦だ」に変わった心の分岐点が描かれていない。会津戦争で鉄砲に生きた「幕末のジャンヌ・ダルク」「戦う女武士」の八重が、新時代で「日本のナイチンゲール」「新時代のハンサムウーマン」へと転身していく(番組サイトのイントロダクションにも謳われている)、ドラマ・ヒロインの重大な転機であるというのに……
戦で、復讐に燃え、鉄砲で敵兵を打倒していく八重だが、戦が終結した新時代では、鉄砲を撃つことの価値は皆無に近くなった。
砲術師範役の家に生まれ、女であるが≪鉄砲がすべて≫という人生を歩んできた八重である。一気に人生の目標を失い、さらに、会津をなくし、夫や仲間とは離れてしまうという絶望の淵に立ったはずである。
なのに、前話の最後に、何もかもなくしてしまったと呆然とたたずむ八重に、いつもと変わらず陽の光が差し込む。それを感じる八重というシーンがあっただけである。
【その他の疑問】
・夢(悪夢)の意味は?
あの夢は、人の命を奪うことの畏れ、家族や仲間を失った悲しみや怒り、砲弾を受けた恐ろしさ、汚名を着せられた憤り……何によるものだったのか?すべて?
「日本のナイチンゲール」と謳うのであれば、命を奪うことへの畏れをもう少し掘り下げてほしかった。
・八重は、なぜ積極的に庄之助の様子を聞かなかったのか?
【追記】
容保の助命嘆願が萱野権兵衛ひとりの命で済んだ(萱野さん、ごめんなさい)のは、安麻衣気がしたが、会津を下北に配置換え(減石)したことと併せて考えると、絶妙な捌きに思えた。
お家断絶にして深い遺恨を残すより、僻地に追いやった方がよいと考えたのだろう。
で、私が不満に思うのは、こういった会津の戦後処理、元号が明治になり、新政府側の体制や動きが全く見えない点だ。やはり、一話分が欠落しているように思う。
【ストーリー】番組サイトより
会津戦争から半年が過ぎ、八重(綾瀬はるか)たちは米沢藩の知人宅に身を寄せながら、食いぶちを稼ぐため反物の行商をしていた。捕らえられた尚之助(長谷川博己)からの便りはなく、八重は不安を募らせる。
その後、会津藩は家老・萱野権兵衛(柳沢慎吾)の斬首という犠牲によってお家断絶を免れ、斗南へ移されることが決まった。そして、筆頭の大参事となった大蔵(玉山鉄二)は、いつの日か会津の土地を取り返すため思いを募らせる。
一方、箱館の五稜郭で戦いを続けていた旧幕府軍は、萱野の処刑が執行されたのと同じ日に降伏。「鳥羽・伏見の戦い」から始まった戊辰戦争がついに終結した。
1870(明治3)年3月、会津藩士たちは次々と新天地を目指し北へ進んでいく。そして、八重たちもまた会津に戻れることを信じて米沢で生きていく決意をする。
生きていれば、いつかきっと、会津に帰れる。
それを支えに生きていくべ」
「今でも、三郎の、おとっっぁまの…死んだみんなの無念を晴らしてえ。
んだけんじょ、恨みを支えにしていては、後ろを向くばかりで、前には進めねえのだし。
さっきのこづゆが、あんまりおいしくて、
みんなで頂けるのが、うれしくて。
もうしばらく、こうして生きていっては、なんねえべか」
八重だけでなく、多くの会津の者は、逆賊の汚名を晴らすため、会津を復興するため、「生きる」ことを誓う
・陸奥(下北)に領地替えになり、お家再興を誓う山川大蔵、広沢富次郎ら藩士たち
28万石から3万石、しかも本州の北の果て。「まるで島流しではねえかぁ!」と言うのももっともだ。(下北のみなさん、ごめんなさい)
それでも、「斗南」の名に「会津復興」の思いを託し、斗南に向かう(現代の東北に重なる)。それにしても、寒そう。
梶原平馬は、会津敗戦の責任を感じ職を辞した。
・西郷頼母は函館五稜郭で戊辰戦争の最後を迎える。
命を差し出して容保の除名を願うつもりであったが
「わしは生きる……わしらの会津を踏み潰していった奴らが、どんな世の中つくんのか、この目で見届けてやる」
・大蔵の弟・健次郎は長州で学問に励む
この際、秋月悌次郎も同行したと思われるが、佐川官兵衛はどうなったんだあ?
八重の言葉と対極にあるのは、過去に囚われて死にゆく萱野権兵衛(柳沢慎吾)の言葉
「ただ一つ無念なのはなあ、会津が逆賊の汚名を晴らす日を見届けずに死ぬことだ。
戦で失われたものは、戦で取り返すのが武士の倣い。頼むぞ。
そうでねえと……そうでねえと、死んだ者たちの無念が晴れぬ!」
たぶん、≪演じた柳沢慎吾はもう一つの無念があっただろう≫と彼をよく知る視聴者は思ったはず。
「さらば」ではなく「あばよ」と言いたかったはずだと。
八重の過去の心情を再現したのは千代。
夫の仇を討つため、息子を鍛え、自らも八重に鉄砲の教えを乞うという復讐に凝り固まった様は、過去の八重を見るよう。
八重は鉄砲を教えるつもりはないと言い、会津を愚弄する商人に妾として囲われてまで生きていこうとする千代に「今は、生き抜くことが戦だ」と励ます。
今回は「生きる」ということがテーマであった。
こづゆのエピソード、「斗南」に託した思いなど非常に良かった。
しかし、1話分飛んだ(抜かした)感がして仕方がない。
八重の心情の変化が
「仇を討つため、敵をひとりでも多く倒して死ぬ覚悟」から「生き抜くことが戦だ」に変わった心の分岐点が描かれていない。会津戦争で鉄砲に生きた「幕末のジャンヌ・ダルク」「戦う女武士」の八重が、新時代で「日本のナイチンゲール」「新時代のハンサムウーマン」へと転身していく(番組サイトのイントロダクションにも謳われている)、ドラマ・ヒロインの重大な転機であるというのに……
戦で、復讐に燃え、鉄砲で敵兵を打倒していく八重だが、戦が終結した新時代では、鉄砲を撃つことの価値は皆無に近くなった。
砲術師範役の家に生まれ、女であるが≪鉄砲がすべて≫という人生を歩んできた八重である。一気に人生の目標を失い、さらに、会津をなくし、夫や仲間とは離れてしまうという絶望の淵に立ったはずである。
なのに、前話の最後に、何もかもなくしてしまったと呆然とたたずむ八重に、いつもと変わらず陽の光が差し込む。それを感じる八重というシーンがあっただけである。
【その他の疑問】
・夢(悪夢)の意味は?
あの夢は、人の命を奪うことの畏れ、家族や仲間を失った悲しみや怒り、砲弾を受けた恐ろしさ、汚名を着せられた憤り……何によるものだったのか?すべて?
「日本のナイチンゲール」と謳うのであれば、命を奪うことへの畏れをもう少し掘り下げてほしかった。
・八重は、なぜ積極的に庄之助の様子を聞かなかったのか?
【追記】
容保の助命嘆願が萱野権兵衛ひとりの命で済んだ(萱野さん、ごめんなさい)のは、安麻衣気がしたが、会津を下北に配置換え(減石)したことと併せて考えると、絶妙な捌きに思えた。
お家断絶にして深い遺恨を残すより、僻地に追いやった方がよいと考えたのだろう。
で、私が不満に思うのは、こういった会津の戦後処理、元号が明治になり、新政府側の体制や動きが全く見えない点だ。やはり、一話分が欠落しているように思う。
【ストーリー】番組サイトより
会津戦争から半年が過ぎ、八重(綾瀬はるか)たちは米沢藩の知人宅に身を寄せながら、食いぶちを稼ぐため反物の行商をしていた。捕らえられた尚之助(長谷川博己)からの便りはなく、八重は不安を募らせる。
その後、会津藩は家老・萱野権兵衛(柳沢慎吾)の斬首という犠牲によってお家断絶を免れ、斗南へ移されることが決まった。そして、筆頭の大参事となった大蔵(玉山鉄二)は、いつの日か会津の土地を取り返すため思いを募らせる。
一方、箱館の五稜郭で戦いを続けていた旧幕府軍は、萱野の処刑が執行されたのと同じ日に降伏。「鳥羽・伏見の戦い」から始まった戊辰戦争がついに終結した。
1870(明治3)年3月、会津藩士たちは次々と新天地を目指し北へ進んでいく。そして、八重たちもまた会津に戻れることを信じて米沢で生きていく決意をする。