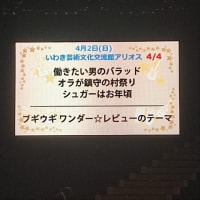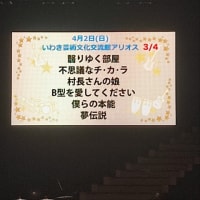2017年9月25日に木村幸雄先生が亡くなったという葉書が昨日届いた。
私は学部を出てから先生に師事するという経験がなかったから、国語の教師として恩師と呼べるのは誰よりもまず木村先生だ。
しかし最近、お会いすることのないまま数年が過ぎていた。
昨年だったか入院の報を聞いたときもお見舞いに行かず、その後退院して回復された、と伝え聞いて安堵しただけだった。
卒論の担当教官としてお世話になってから約三十年間、会合の種類や内容はその時々で違ってはいたが、読書会や勉強会で、師匠の傍らで自分の読みを示すことが当たり前だった。
中でも大学卒業後から十数年続いた 「戦後文学を読む会」では、テキストを読む、ということの意義を一から教えていただいた。
毎月一回、当番が作品をレポートし、メンバーが疑問や意見、批判をやりとりする読書会なのだが、読書会を始めるとき、先生に顧問をお願いにいったとき、彼は
・3人以上いるうちは続ける。
・自分も一会員として参加する。
・話し合いの成果を読める形で文字に残す。
という3つの条件で参加を快諾してくれた(これは今思えば彼のミニマムな「政治論=活動論」だったかもしれない)。
毎月一回ずつコンスタントに続け(夏冬は合宿)、雑誌を出したときは互いに合評もしつつ、100回ちかく続いた。
その後木村先生が中国の武漢大学に客員の教授として招聘されてから次第に毎月の開催ではなくなり、先生が戻ってきてからは夏冬の合宿のみになり、20年過ぎてそれも間遠になっていったが、20代~30代にかけてテキストを読むという訓練を先生の下で続けられたことの意味は、私にとっては計り知れないほど大きかった。
昨日訃報を聞いてから、自分が何を喪失したのかをずっと考えている。
育ててもらった 「恩」を感じる 「師」は他にも幾人か挙げることができる。小学校の時、ADHDの自分を「見所がある」と接してくれた佐藤先生もその一人だ。彼は、おちつきのない私を面白がって、そのまま放っておいてくれた。
そうか。
考えてみれば木村幸雄先生もそうだった。石川淳『処女懐胎』論を野火2号に書いたとき彼に貰った評言を思い出す。
「君の文章はいつも中心から少し外れたところを狙っているんだよ。だから背筋をのばして読むと落ち着かない。しかし寝転がって読むとこれが面白いんだ」と笑われ、
「でもね、この『女子供』という表現は直すべきだ。いや、たとえ逆説的であっても、使うべきではない」
と厳しく指摘された。
また、井上光晴『黄色い河口』論を書いたときは
「書きたい気持ちはわかるけど、ほとんど要らないね。最後の五、六節から書き始める、それが文章ってものだよ」
そうだ、放し飼いにしながらも見捨てずに面白がってくれている恩に報いられるような、師匠に面白がってもらえる文章、 「書かれていないその先」を本当はもっと書かねばならなかった。そうなのだ。
そしてそれはもうかなわない。
師を失うということはそういうことか。
「間に合わなかった文章」を、私は今から書かねばならない。
これから書くものを、木村先生ならどう評してくれるだろう。
どんなにヒドい文章でも、学生がこだわった論点があれば 「力作だね」とまずねぎらった後で 「ほとんど不要な部分だけど」と笑いながらバッサリ斬ってくれた。
つまり、一つのレポートもまた表現なのだ、と教えてもらっていたのだろう。教育学部の学生は、研究者としての論文執筆の厳密な基準を身につける必要がない。しかし、どんな小さなものであっても、それは一つのテキストであり、表現としての真実の欠片の現れにほかならないのだ、と知らず知らずに教わっていたのではなかったか。
木村幸雄先生が 「いる」ということを自分がどんなに頼みにしていたのか、これから身にしみて感じていくことになる。
それは断じて懐古や郷愁ではない。
テキストの読まれるべき 「今」、そして書かれるべき 「可能」において、 「じゃあきみはどうしたいのかね」と問い続ける師匠 「装置」として 「わたし」の中で駆動し続けるということ。
弟子である、とはそういうことなんじゃないかな
「宇宙の粒子」になった木村先生に差し出すべきテキストを(安倍と小池という、こんなにもヒドいウルトラネオコン同士の対決選挙のなかでも)紡いでいかねばなるまい。
この追悼もまた 「的を幾分か外してるね」 「書くべきことはこれを捨ててから先だね」と言われそうだ(笑)
許してください。今から始めます。
不肖の弟子 島貫 真