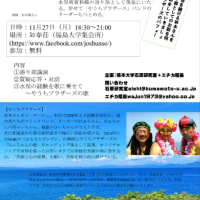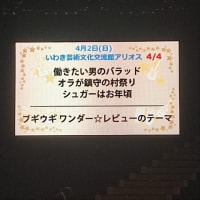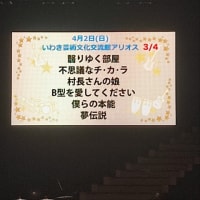先日TVで放映されたアニメ版『時をかける少女』を、ソニー製のレコーダーと連動してスマホ転送ができるソフトがあったので、試しにやってみたのだが、その環境自体は快適だった。
びっくりしたのはそのストーリー。
「え、こんな話の展開だったけ?」
と、驚きを通り越してあきれるほどほぼ何も覚えていないに等しかったのだ。
いくら記憶は曖昧なものだといっても、主人公がタイムリープできるようになった切っ掛けも忘れていたし、その「安易な」タイムリープが周囲に与える影響の描写も覚えていなかった。
さらには、重要なモチーフになる踏切事故がどんな形でクライマックスに用いられるのかも忘れていた。
つまりは、ほとんど覚えていなかったということになる。
すみません、作品の感想じゃなくて。
最近推理小説やテレビドラマなどでも、途中まで読んだり観たりしてから、
「あれ、これって読んだ(観た)ことがあるかも……」
となることが多くなってきたのは確かだ。
しかし、どちらかといえばお気に入りの映画だったはずのものが、これほど杜撰な記憶にすり替わっているとなると、全ての「印象」はみせかけのものかもしれない、というSFじみた(いやいや、還暦近い脳みそとしてはきわめてリアルな?)感慨を抱かされる。
ちなみに『時をかける少女』はNHKドラマと、大林宣彦監督の映画版と、このアニメ版を観ているが、大林版とアニメ版の違い(前者の主人公が叔母として後者に出てくる)違いは分かっているつもりだった。しかし、あらため考えてみると、NHKドラマと映画版の違いはまったく覚えていない。
全てのものは何も分からなくなっていくのだろうか……。うちの祖父は司馬遼太郎を寝床で読みながら
「1冊あれば足りるんだ。途中で眠ったら、また次の日同じところから読めばいいんだからな」
と笑っていたが、かなり笑い事ではない。
この忘却が本格的に始まる50代こそが、瞬間的に花火のような「本質理解」をもたらす、というのが私の仮説(笑)なのだが、そういう意味では私の「本質理解」からは遠いストーリーだった、ということになるのだろうか。
タイムリープという概念を丁寧に説明しているところが私の「忘却エンジン」からいえば「無駄」だったのだろう。
断っておきますが、いうまでもなくこれは作品批評でも作品批判でもありません(誰もそんなことは考えないか)。
私の身体がこのアニメ版『時をかける少女』という気に入っているはずの映画の、ストーリー部分は取りこぼしていた、ということが驚きでもあり、面白くもあった、というだけの「ボケ話」です。
びっくりしたのはそのストーリー。
「え、こんな話の展開だったけ?」
と、驚きを通り越してあきれるほどほぼ何も覚えていないに等しかったのだ。
いくら記憶は曖昧なものだといっても、主人公がタイムリープできるようになった切っ掛けも忘れていたし、その「安易な」タイムリープが周囲に与える影響の描写も覚えていなかった。
さらには、重要なモチーフになる踏切事故がどんな形でクライマックスに用いられるのかも忘れていた。
つまりは、ほとんど覚えていなかったということになる。
すみません、作品の感想じゃなくて。
最近推理小説やテレビドラマなどでも、途中まで読んだり観たりしてから、
「あれ、これって読んだ(観た)ことがあるかも……」
となることが多くなってきたのは確かだ。
しかし、どちらかといえばお気に入りの映画だったはずのものが、これほど杜撰な記憶にすり替わっているとなると、全ての「印象」はみせかけのものかもしれない、というSFじみた(いやいや、還暦近い脳みそとしてはきわめてリアルな?)感慨を抱かされる。
ちなみに『時をかける少女』はNHKドラマと、大林宣彦監督の映画版と、このアニメ版を観ているが、大林版とアニメ版の違い(前者の主人公が叔母として後者に出てくる)違いは分かっているつもりだった。しかし、あらため考えてみると、NHKドラマと映画版の違いはまったく覚えていない。
全てのものは何も分からなくなっていくのだろうか……。うちの祖父は司馬遼太郎を寝床で読みながら
「1冊あれば足りるんだ。途中で眠ったら、また次の日同じところから読めばいいんだからな」
と笑っていたが、かなり笑い事ではない。
この忘却が本格的に始まる50代こそが、瞬間的に花火のような「本質理解」をもたらす、というのが私の仮説(笑)なのだが、そういう意味では私の「本質理解」からは遠いストーリーだった、ということになるのだろうか。
タイムリープという概念を丁寧に説明しているところが私の「忘却エンジン」からいえば「無駄」だったのだろう。
断っておきますが、いうまでもなくこれは作品批評でも作品批判でもありません(誰もそんなことは考えないか)。
私の身体がこのアニメ版『時をかける少女』という気に入っているはずの映画の、ストーリー部分は取りこぼしていた、ということが驚きでもあり、面白くもあった、というだけの「ボケ話」です。