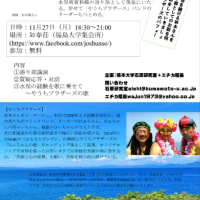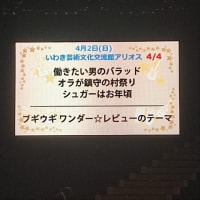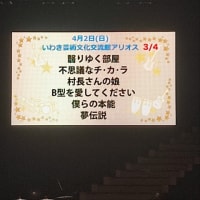25年前出版された講談社学術文庫の
『リヴァイアサン』長尾龍一
を読んだ。とても面白かった。20世紀前半のドイツにおける
ヨハン・ケルゼン
と
カール・シュミット
の2人についてその法律論および国家論を、それぞれのホッブズ受容を比較検討しながら考察していく一冊。
今年読む予定の
ホッブズ『リヴァイアサン』
に取り掛かる準備運動としては好適な文庫本だった。
マルキシズムとナチズムを眼前に踏まえつつ、アナーキズムとカトリシズムを縦軸に置き、「自然状態」、「自然法」、「擬制的」な国家・神の人格、などなど、基本的なものの見方に触れつつ説明を展開してくれている本で、非常に勉強になった。レオ・シュトラウスとの距離、ルソーの「取り上げ方」、スピノザの「ダメさ」の扱い、また、ケルゼンとシュミットの二人に限らずホッブズが歴史的にどう受容されてきたか、などなどの整理もあって、国家論に興味がある素人にとってはとても得るものが多かった。
勝手なことをいわせてもらえば、最終的な著者の主張は正直チャンチヤラおかしいという感じはする。だが、そんなことは大した問題ではない。
この本を読んでみると学問って、その人の主張が問題じゃないんだということが少しだけ分かってきた感じだ。
もう一度國分さんの『近代政治哲学』をおさらいしてからホッブズにチャレンジしてみようかな。