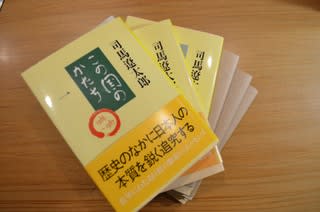

正月明けの軍師官兵衛に続いて、司馬遼太郎の「この国のかたち」を読んでいる、この
本を読むきっかけは単純だ、人間ドックに入るにあたって暇な時間何を読もうか?
本屋で司馬遼太郎シリーズを見ても読んだものばかり、その中で お!これまだ読んで
無いぞ・・・で読むことに。
そのタイトルどおり この国のかたちの小節で始まるこの本は、雑誌「文藝春秋」の巻頭
随筆欄をまとめて単行本にしたもので、1巻は24回分を収録してあり以下同様に6巻まで続く
が「あとがき」があるのは5巻まで6巻はない。
多分書き手の司馬遼太郎さんが逝去されたからと思う、記録的には司馬さんは1996年2月
12日が没日だ、ちなみに5巻のあとがきの日付は1995年暮とある。
まぁ そんなことはどうでもいいのですが、この本結構むずかしい・・・読み手に判断を
迫っている感じだ、小節毎は関東随筆ですから読み切りになっているのですが、それを無数
に並べてエキスを取れ・・・・と。
司馬さん自身が書いているように、「この国の習俗・習慣、あるいは思考や行動の基本的
な型というものを大小となく煮詰め、もしエキスのようなものがとりだせるとすればと思い
、「かたち」をとりだしては大釜に入れているのである」・・・・とある。
更に言えることは、当然ですが司馬史観に基づいて選んだ「かたち」を煮詰めてあり、同
じ軍隊でも日露戦争を戦った明治の軍隊はいい?が、第二次大戦を統帥権の名のもとに引き
起こした昭和の軍隊いや軍人は駄目・・・・といった感じだ。
坂の上の雲とか竜馬がいくとか、菜の花の沖、最後の将軍等々の小説を書くに当たって、
調べた資料や知識が「かたち」の元となっているので随所に出てくる、その意味では司馬史
観そのものかも・・・・?
ただ勉強になります、例えば村長も何度となく行ったことのある岩国の錦帯橋、鎖国時代
の長崎出島の唐通事(通訳)であった穎川官兵衛(帰化して)が隠居したあと僧となり独健
となり。
もう一人浙江省の名医が出家して独立となり、この二人が周防岩国城主の吉川広政正・広
嘉父子の診察のため岩国に入り、その時に眼前の錦川の氾濫で橋がいつも流される・・・と
相談を受け。
独立がたまたま持っていた湖水のアーチ式石橋を紹介し、その後木造でアーチ式の橋が出
来た・・・というもの、錦帯橋が主役の話でなく唐通事や通詞が蘭学・医学・画法等に与えた
影響が大きいと言う話。
長く成ってしまったので止めますが、只今1.2.4巻が済 明日から3.5.6巻読みます。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます