
先日も実名で書きました「手越川」。
今日も回り道をして通ると、なんと!!藍色(あいいろ)の染料の垂れ流しか・・・川が群青色に染まっている。
底さえ見えないほどの濃さです。
上流の有松の駅の辺では特に濃い色でした。

下流の方全域にわたって変色している。
この川の本流には沢山の多様な水性生物がいる。合流した地点から満潮ではこの汚染された水が逆流して水性生物たちにふりかかる。
先日見たわずかなフナさえ見ることはできませんでした。
役所に連絡しなければならない・・・。

先日もここで確認した錦鯉、なぜここにいるのか理由が判った。
手前左支流からから濁っていない水が合流しているからである。
かろうじて濁っていない水から命をつなぎとめているのだ。
こうなったら区だろうが、市だろうが『垂れ流し』を連絡しないといけない。
と帰り道をいつもの川沿いを歩いていると、
名古屋市の環境局の人たちに出会った。
話を聴くと「雪ノ下さん」が撮影した「カミツキガメ」を捕獲にきているという。
いろいろ話をして「手越川の汚染」のことも話しておいた。
ことは手越川に留まらず、本流川にまで被害が及びます。
『汚染のことも話しておきます』との返事をもらえました。
















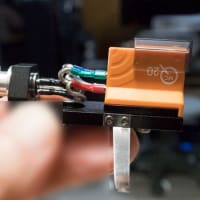


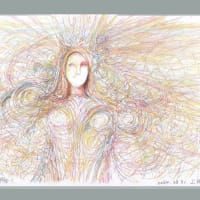
たまたま操作ミスで流れ出たというのならまだしも、(それでもこまりますが)ひょっとすると、いつも垂れ流ししているのかもしれませんね。
おそらく名古屋市も出所はつかんでいるのではないでしょうか。早く対策ができるといいですね。
いつもの川も工事現場の近くで合流する川からときどき黄色い水が流れてくるのを見かけます。
これも何とかしないといけないですね。
水質悪化水域は下水道の普及や水草等の設置など課題はいろいろありますが、ダム同様堰の問題が大きい場合があります。
定期的に開けるとかしてとにかく水の通りを良くすることです。
ただし、何年も開いたことのない堰の場合、底に沈澱したヘドロが一気に流れ出てしまう恐れがあるので、この水域があまり工程がない場合は機械等で川底をすくうのがまずは必要でしょうね。
その後はとにかく川底がヘドロ化しないように堰などがある場合は定期的に開けることです。
私の住んでいる地域の川にも無数の堰があり、しかも開閉式の堰にも関わらず開いたところを見たことがありません。
田んぼに水を引く時期はともかく、そうでない時期は開けるべきです。
川にいろいろな物が沈澱してヘドロ化するだけです。
しかしこの色が本流まで流れているので鳴海駅周辺下流から変色がわかるはずです。
有松の踏み切りの直下の川の出口から真っ黒い濃厚な汚染液が出ていました。いくら文化を作る絞り染めでもゆるせませんね。この町内の有力者に今度会うので県会議員や国会議員へも陳情が行くように掛け合ってみます。
ネットにこの川などの構造図が掲載されていたものを見た記憶がありますが、ページがすぐには出てこないので捜しておきます。
周辺住民の無関心がこのような結果を招いているわけですが、しいては本流また伊勢湾にまで汚染が進んでいくわけです。
今日話しをした名古屋市環境局の人は生物多様性企画室の人たちですからその辺の重大さが判っていると思います。
ただ県の方の対応は『ほおって置けばよい』というような無責任・無関心のようです。
言い方は悪いですが、ニシキゴイはまた放せばいいですが、天然の生き物はそうはいきません。
同じ種類でも遺伝子的に地域差がありますから、もし、この水域の生き物で姿をまったく見られなくなった生き物がこれからいるとすれば、それは絶滅を意味します。
この水域の汚染度がわかりませんが、水質調査等が早急に望まれ、さらに、調査結果から流れ込む水域への影響を調べるべきでしょうね。
とにかく生き物が自由に行き来できる環境が望まれます。
田んぼの補助整備等で田んぼに水が必要な時期にしか水を入れなくなったこと、また周辺の水路や小川も同様。
農薬散布等は昔よりはるかに少なくなりました。
メダカの減少などは水質の悪化より(メダカは比較的水質悪化に強い)田んぼや周辺水路等に必要な時期にしか水を入れなくなったことが大変大きいと思われます。
生き物の行き来と言うより水の流れ、通りをとにかく良くすることです。
まずは、ここでお聞きするこの汚染?水域の改善後の話になるとは思いますが。
ただこの土地は市長は変わっても、呼び声だけの革新ばかりで、ものすごく保守的な土地です。一昔まえなら染物が売りの場所で水質検査でもしようものなら袋叩きの場所です。
今回「カミツキガメ」で名古屋市が動いたのは名古屋で開催される「COP10」の影響もあるでしょう。
今回の通報で動きが無かったら自分で水質検査をしてみます。何とか検査法を調べて・・・。
他人頼みでは何も動かない土地柄です。