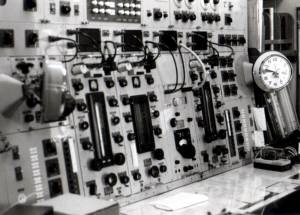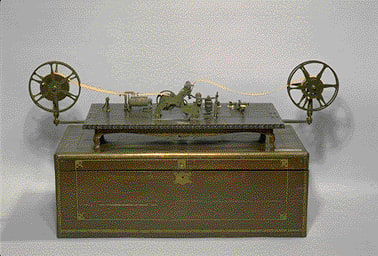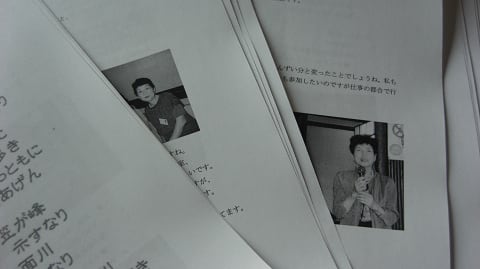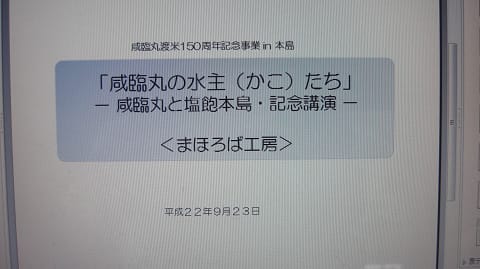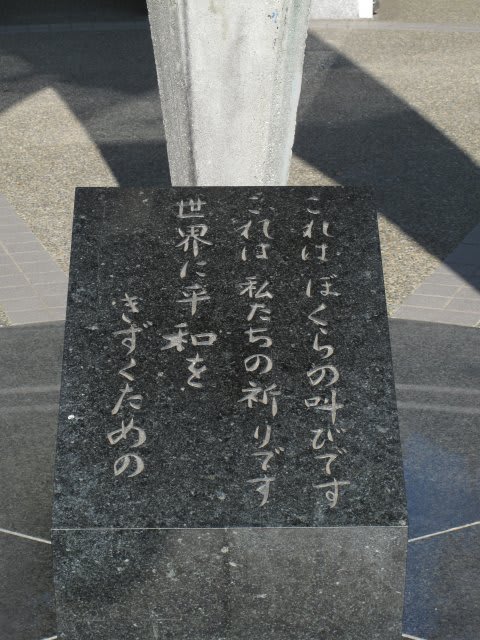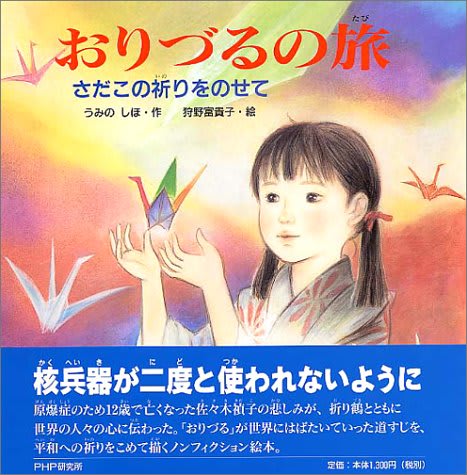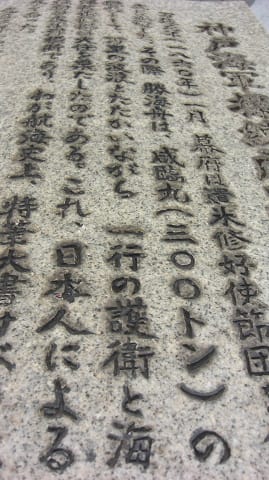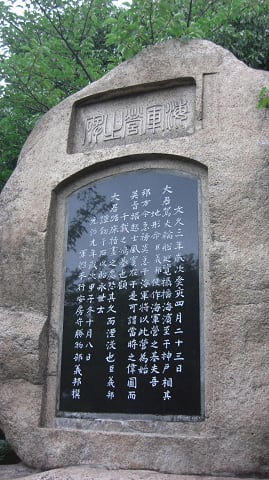今日はまた、底冷えのする肌寒い一日になった。風が強くないので楽ではあったが、足下からじわじわと「冷え」が上がってくるような感じだった・・。
で、町内にあるさぬき市歴史民俗資料館に資料画像になるものを探しに出かけたら、今日は・・・旧恵利(えり)家住宅 が開放されていたので寄ってみた・・。

この旧恵利家住宅というのは、19世紀初めに現在のさぬき市大川町新名(しんみょう)に住み着いて、以降、農耕に励み、安政年間(1854~59)の頃、かつて集落の「長:おさ」百姓を務めていた旧家の建物を譲り受けて住居にしたもの。
この恵利家に住居を譲った旧家がいつ、この地に入植したかは定かではないが、初代が没した記録が元禄12年(1699)で、この建物の構造や手法などがその時期に該当することから、建築年代も17世紀末に建築された香川県内最古の農家住宅とされ、その後、国の重要文化財に指定されている。

恵利家住宅はもともと大川ダムの東方、津田川支流域に所在する「新名」という谷あいの集落に建っていたが、昭和40年代になって老朽化が進むのと、周辺の農家も近代的な住宅に建て替えられていく中で、恵利家でも主家の建て替えを計画した。それを聞いた地元では貴重なこの建物の保存運動が起こり、当時の大川町が寄贈を受けて解体保存し、同町砕石(われいし)地区、大川ダム東側に移築されていた。しかし、当時は管理人もいないため風を通すこともなく雨漏れやシロアリなどが発生し、建物の大幅修理が考えられた。そこで、その機会にと、平成13年に現在の場所、みろく自然公園内に再移築された。

屋根は装飾性の少ない簡素な茅葺きの寄棟造で、屋根周囲を瓦葺の庇とせずに軒先まで茅で葺き降ろした「つくだれ」というこの地方には珍しい屋根をしている。天井は大和天井という、半丸竹を敷き、つづらで編み、その上に藁を敷き詰め、土を塗り付けたものになっている。柱は主に栗が使用され、木材、竹、つた、赤土などそのあたりにあるものをうまく使って建てられている。

主屋は寄棟造り・茅葺で外観が大壁で閉鎖的であり、土間が大きく、土間上手の床上部が手前が一部屋だが、ミナミザ(南座)には囲炉裏が切られており、竹を並べた竹座にムシロが敷かれていて応接間兼リビングであった。キタザ(北座)が台所兼食堂であった。そこに北座から火を焚くようにかまど「おくどさんが」つながっていたが、今はその姿はない。
『土間』は、三方を土壁で囲まれ開口部は二箇所出入り口で窓はない。広々とした土間では、収穫した農作物の仕分け作業や保存をしていた。
間口は広く障子が入ってなく広々としているが、本来はここに障子戸があった。ここで日常の生活を営んでいた。 下は足踏みカラウス(唐臼)で、左手上の踏み板に子供が乗って、シーソーのように米や麦をこなした。

旧恵利家は、日本を代表する三間取り形式の住まいで、奥には、座敷と納戸があり、「座敷」には畳が敷かれ床の間があり、南側には、障子戸その外側には、縁側が付いていて、この家では、一番立派な部屋で、客間として使われたり、仏間があり、法事や葬式もここで行われたが、ここは普段には使うことはなかった。

「納戸」は、座敷の北側にあり板式で櫃・箪笥などが置かれていた。昔はここも竹座にムシロ敷きだった。現状の「ツノヤ」部分は、当初からあったものではなく、後に納戸を拡張したもの。ここが夫婦の寝室で、子供らや親たちは・・・ミニナミザで寝た・・。
四方寄せ棟の茅葺住宅を讃岐では「ツクダレ」又は「ツクダリ」というが、正面から見て棟中央にちょこんと乗る煙出しが大変柔らかなイメージを醸しだしており、民芸的な美しさがある。棟の押さえに「ガップリ」(瓦)が渡してある。住宅の左側に設けられた「座敷」前に、造り付けの「縁側」が付くのも江戸期の農家住宅では珍しい。座敷奥の増築された「納戸」は単純な家周りに変化を与えている。

屋内に入り、「土間」に立って天井を見上げると、木の曲がりや太さの大小をそのまま生かした梁の美しさに、昔の人たちの巧みな技に感動してしまう。
| 所在地 | 香川県さぬき市大川町富田中3277-1(みろく自然公園内) TEL 0879-43-0622 |
| 開館時間 |
9:00~16:30 |
| 休館日 |
|
| 入館料 | 無料 |
| Web | さぬき市文化財保護協会大川支部 |
記事は、『旧恵利家住宅』パンフレットより転載。

で、今日のお昼は・・手近な・・・ところでここになった。

今日はのれんが上がっていないが・・・開店中。さぬき市大川町富田中にある「手打ちうどん・すぎもと」に行った。久々のお店だった・・・。

で、注文したのは・・しっぽくうどん・・。前回は・・・野菜がよく煮込まれていなくておいしくないイメージがあって、しばらくここはスルーしていたのだけれど。こう、寒いと・・・遠くへも行けないもので、「安い」「近所」「短距離」みたいなことで、ここに落ち着いたが、それなりにおいしいと思った・・・。ただ・・、麺が・・・硬いかなぁとは思った・・・。単なる体験者の感想だけれど・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。