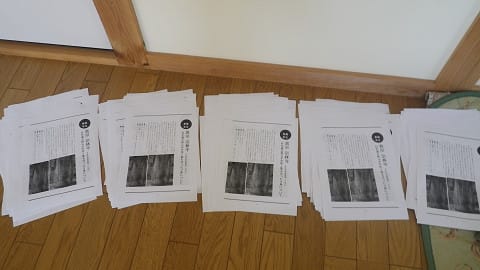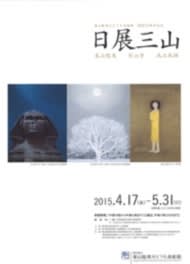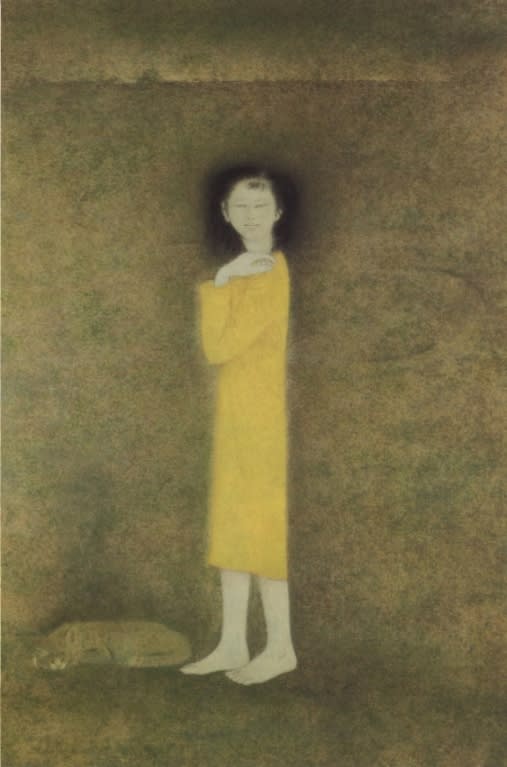さぬき市地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、西部を中心に雲が広がり、雨の降っている所があった。気温は14度から24度、湿度は92%から50%、風は1mから47mの東南東の風が少しばかり。明日の5月1日は、次第に高気圧に覆われて、晴れる見込みらしい。

昨日の懇親会の席上で、私の「山頭火句碑集」を納本した人が、お礼をしたいと言うてると、役員さんからの連絡があった。その人にメールを送ろうとしたが、どうにもアドレスが違うようで、あちこちの名簿を探したり、アドレスを何カ所かいじくって、たった一つのメールを送るのに二時間近くもかかってしまった。

そのおじさんが、9時半から10時半の間にお見えになるというので待機状態が続いた。その合間に、ホームページの更新やら法話原稿の修正やらをやって時間を過ごした。

そのおじさんがやって来たのは10時半過ぎ。あちこちと道を間違ったらしい。で、持って来てくれたお礼というのが、焼き肉店のランチョンマット(紙製)。そこには山頭火の自由律俳句が印刷されている。有り難いやら、なんとやら・・・。私、別に山頭火のファンでもないんですけれど・・・。

おじさんというか、先輩が帰られたので、私はいつもの「香川県立図書館」に行ってみた。先週の土曜日に借りた本はほとんど役に立たなかったので、すみやかに返却して、別な本を借りようと思ったが、欲しい本は貸し出されているようで見えなかった。わずか数日で、こんなにも若葉が萌えだしていた。

それでは・・・ということで、高松市飯田町にある岩田神社にやってきた。テレビだかで、「満開だ」ということだったので、「そんなに簡単に満開になるんか・・」ということでやってきたのだけれど。

確かにのぼりも立っているし、お客さんも多いし、露店も出ているし・・・。

でも、「へ・・・・」と思うような藤の花。

場所によっては、こんなものかなぁとも思う花もある。

でも、全体的に房の長さが短い。ここは1mから2mにもなる「孔雀藤」と呼ばれるもの。

ここは駐車場がないのに、大勢の人がやって来るので、狭い道路は押し合いへし合い。介護施設のマイクロバスが来ると騒然とする。

私は写真だけ撮ると、早々に引き上げた。

早くも四月は最終日。明日からはいよいよ5月。だからと言って何があるわけでもない。カレンダーをめくって歩くだけなのかも知れない。確かに、やらねばならないことは多いし、やっておかねばならないものも多い。その優先度、重要度が難しい・・。

とりあえずは、月末処理とホームページの更新などをやっておかねば。

今日の掲示板はこれ。「過去が咲いている今 未来のつぼみで一杯な今」というもの。陶芸家・河井寛次郎さんの「意味ある人」から。「静岡県人づくり百年の計委員会」による提言の基本理念ですがこの言葉も 河井さんの言葉だと聞いている。「今」を大切にしなければ・・・と思わせる言葉の一つである。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。