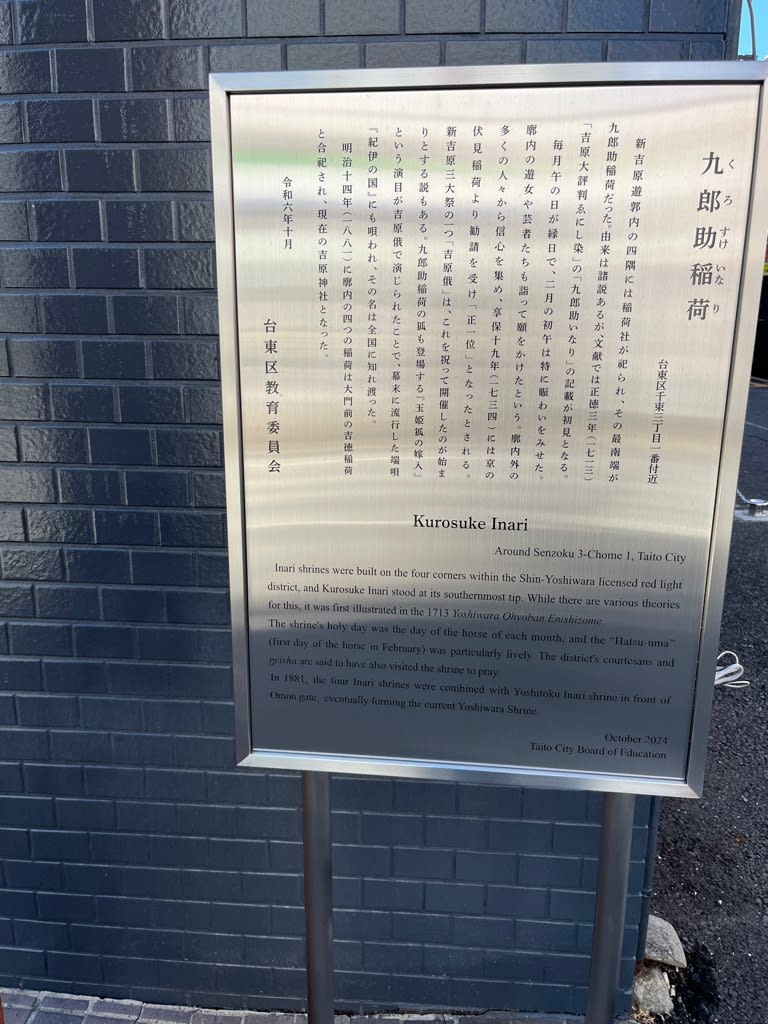徳川将軍のなかで名前に「家」が付いていない人物が四人います。
・二代将軍秀忠は、豊臣秀吉に「秀」の字を与えられたことと、父家康がギリギリまで家督を譲るかを悩んでいたともされている
・五代将軍綱吉は、兄家綱の死によって館林藩主であった立場から宗家を継いだため
・八代将軍吉宗は、七代将軍家継が夭折したために紀州藩主から宗家を継いだため
・十五代将軍慶喜は、十四代将軍家茂の急死で一橋家当主から宗家を継いだため
と、元服時に徳川宗家を継ぐことが決まっていなかったからと考えられているためです。
逆説的に、無理にでも宗家を継がせたかった十四代将軍家茂は、紀州藩から宗家の養子に入った時に慶福から家茂に改名することで、権威付けを測ったとも考えられるのです。
徳川宗家にとって元服時に名前に「家」という字を付けることは将軍になる人物であることも示していたのですが、そんななかで江戸時代の徳川家で名前に「家」が付きながら将軍になれなかった唯一の人物が徳川家基でした。
徳川家基は十代将軍徳川家治の嫡男、母親は側室お知保の方。
家治は正室である五十宮倫子との仲が良く、側室を持つつもりがなかったのですが、後継ぎが生まれなかったために周囲から側室を持つことを勧められていました。
幕閣や大奥の意見を受けて田沼意次が家治に進言した時、家治は「意次が側室を持つならば自分も側室を持つ」と言ったとの逸話があります
意次は、楊弓場(射的を使った風俗)の女性を蘭方医千賀道隆の養女として妾にします。この道隆の息子が『べらぼう』で時々名前が出てくる(平賀源内がエレキテルを披露する時に屋敷を貸していた)千賀道有です。
話を戻して…
お知保の方は期待に応えて男子を生み、徳川宗家の幼名である竹千代と名付けられました。
幼い頃の竹千代は、病弱であったとの説がありこれが元服した後のイメージに重ねようとする動きもあるが、十歳をすぎた辺りから鷹狩を楽しむようになり、体が鍛えられていくのです。
元服してからも家基は何度も鷹狩に出掛け特に弓術に秀でた青年として成長しました。
安永6年(1777)、16歳になった家基は年に10回以上の鷹狩を行う。それは翌年にもある変わることはなかったのですが、安永8年、18歳の家基は3回の鷹狩を楽しみ、4度目の2月21日に急死するのです。
この日、早朝と言える時間に江戸城を出た家基一行は御殿山近くの東海寺を休憩地点にするための準備の使者を派遣して、鷹狩のために新井宿に向かいました。
新井宿は、歴代将軍が利用した狩場のひとつですが、家基は浅草や千住を好んで利用していて新井宿は2年ぶり2回目でした。
しかし、東海寺の記録によると寺に入った家基は御殿山の桜がキレイだったことから新井宿に向かわずに御殿山に出掛け、昼餉に東海寺に戻ったあと再び御殿山に向かったのです。
つまり、花見をして鷹狩はしていない…
しかし、他の記録では新井宿、御殿山、目黒など個々に違う場所を記して鷹狩を行ったことになっています(公式記録の『徳川実記』は新井宿)。
そして『徳川実記』などでは東海寺で食事中に急に倒れたとされ、別の記録では鷹狩中に具合が悪くなり東海寺に運ばれたとあります。
何にしても、いったん東海寺にて手当が行われ、その後に急いで駕籠で江戸城に運ばれ西の丸大奥に入ったのでした。
そして、3日後の2月24日に家基は18歳で亡くなったのです。
不思議なのは、家基が倒れた翌日に東海寺住職が家基を見舞いに行くと元気な姿を見せてくれたとの記録を残していて、裏工作の匂いもします。
鷹狩好きの健康な青年が、自らが企画した大好きなイベントの最中に急死する。
この様な普通では想像できない出来事のため、当時から毒殺説が囁かれていました、そして黒幕として挙げられたのが田沼意次であり、意次が犯人であるかのような噂が作られた流布してゆきます。
しかし、徳川家重・家治からの信任によって幕閣に食い込んでいた意次が家治を暗殺しても利益はなく、意次黒幕説は考え難いのです。そして家基鷹狩の日は田沼意次は非番、何かが起こっても簡単に動ける日ではなかったので逆にこの日が狙われたようにも感じられるのです。
徳川家基急死については、現代においても真相は判明していません。
そもそも、鷹狩が行われたのか花見であったのか?
本来ならば一番近い現場である東海寺の記録に沿うべきですが、他の記録との違いもあり改竄された可能性も否めないのです。
ただ、この事件により田沼政権の土台が崩れ始めるのです。