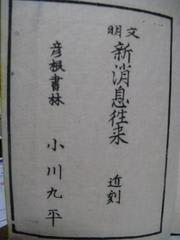数年前にも書きましたが、5月28日は肥田城水攻めが終わった日です。
今年(2009年)はその450年目の記念の年になります。
あれから様々な調査をして、管理人や『どんつき瓦版』独自の見解を、新しい瓦版に発表しました。
これは、「肥田城水攻め450年」の言い出しっぺである管理人の責任だと感じています。
このイベントについて動いたのですが、結局実を結ぶことは無く、某大学(ここにも1年前に声を掛けに行きました)でも授業として計画されていた話がありましたがインフルエンザで中止となり、唯一『どんつき瓦版』のみが今日に間に合った肥田城水攻め450年になります。
昨年の弥千代姫婚礼150年も、結局今年になって幾つかの弥千代姫イベントがありましたし…
彦根のイベント事情に幾分かの事前調査を要望したい時もあります(ちょっと苦言です・汗)
では、『どんつき瓦版』として管理人が示した水攻め記事をご紹介します。
~~以下、記事加筆~~
溢れんばかりに満々と水を湛え、建物の大部分がその水の中に沈む―
高い場所に逃れた人々は、足場を失いつつ狭い場所に集まり、絶望のどん底で周囲に造られた土塁を見つめ、自分たちを苦しめている巨大土木工事を行った敵に怨嗟の声を上げ、不甲斐ない領主を恨む。雨が降れば水嵩が増し、その度に人々の声無き声は悲鳴となった…
戦国史を少しでも齧った事がある方々が“水攻め”と聞いて思い浮かべるのはこの様な光景ではないでしょうか?
時代劇などで目にするのは天正10年(1582)に羽柴秀吉によって行われた備中高松城の水攻めですが、この時もやはり水に沈むお城の姿が印象的に浮かんできます。
今(2009年)から450年前の永禄2年(1559)、それまで仕えていた六角義賢の元を去り、浅井長政へ仕える事となった高野瀬隆秀は宇曽川沿いの肥田城に立て籠もる。
これに怒った六角義賢は息子の義弼と1万5千の兵を率いて肥田城に向けて出兵、4月3日に肥田城を囲む形で幅12間(約23m)長さ58町(約6.3㎞)の堤防を築き、宇曽川と愛知川(当時は今よりも北に流れていた)から水を引き込んで水攻めにしたのです。しかし5月28日に豪雨によって堤防の2ヶ所が決壊し水攻めは失敗に終わる。寛政4年(1792)に彦根藩士・源義陳がまとめた『近江小間攫』には“本朝(この国)水攻ノ最初ハ此時ナリ”と記されるように日本最初の水攻めとして戦国史に事績を残す攻城戦となったのです。
実際には日本最初の水攻めは文明15年(1483)の若江城水攻めまで遡ってしまいますが、それでも備中高松城水攻めよりは20年以上前の出来事として価値があるものだったのです。
では実際にどのような戦いが行われたのでしょうか?残念ながらそれを示す一級資料は皆無と言っても過言ではない状態です。そこで『どんつき瓦版』編集部では他の水攻めとの比較によって肥田城水攻めを多方面から検証してきたのです。
まず目を付けたのが、肥田城を攻めた六角氏にそれほどの経済力があったのか?との疑問でした。
よく出される記録によると天正10年の秀吉による備中高松城水攻めでは、底の幅12間(約23m)・上部の幅6間(約11m)・高さ2丈余(約6m)・長さ30余町(約3.3㎞)の土塁を造る為に約70万貫文(約1千億円)の費用が掛ったと言われています。70万貫文という数字を現代の価値に直すのは難しいですが、永禄11年(1568)に織田信長が禁裏修繕の為に出した費用が1万貫文と言われていますのでその70倍、俗説では「安土城を2つ築城してもまだお釣りが出るくらい」とも言われているのです。
高松城の費用から単純に計算して58町の土塁を築くとなると約135万貫文(約1930億円)の費用が必要となるのです。しかも最近では「秀吉が高松城で実際に造った土塁は300mほどの長さで残りは元々地元で利用されていた堤防を使った物だった」との説も出ているのです。同じ説は秀吉の他の水攻め(紀州太田城・竹ヶ鼻城)や石田三成が行った忍城水攻めでも検証されつつあり、肥田城でも同様の可能性が考えられるのです。
また戦費についても多額に計上されます、翌年に起こった桶狭間の戦いの時の戦費から単純に割合で計算しても水攻め期間中約60日で米だけで3億円の費用が掛るのです。これに副菜・馬の餌代・軍備の費用などを含めると1万5千人の兵を動かすだけでどれ程の戦費が掛ったのか想像もできなくなります。
そして、通説では宇曽川の水を堰き止めて肥田城に流し込んだかのように言われてきましたが、もし宇曽川を堰き止めるとなれば地方との貿易の為の運送川だった宇曽川を通る船から“川銭”と呼ばれる通行税を徴収していた豪族たちに六角氏は損害金を支払わなければならなくなってしまいます。
応仁の乱で六角氏と敵対した細川氏が京で勢力を握ると、京から何度も六角征伐軍が派遣され、戦費に苦しんでいました。この為に重臣の蒲生定秀に借金があったくらいだったのです。
続いて、土塁は本当に六角氏が築いたのか?という疑問も浮かび上がってきます。
肥田城の遺跡としてよく知られている、町中に残る土塁の数々は1988年に滋賀県教育委員会から発行された『肥田城遺跡発掘調査報告書』によって江戸時代以降に造られた物である事が明らかになっています。肥田城を守る為の戦略的土塁ではなく、水害から肥田の地域を守る為の防災的土塁だったと考えると戦国時代に肥田城を守る為の戦略的土塁が別に存在したとも考えられるのです。
肥田は、中世でも早い時期に城下町として形成された城でした。城の周りに町ができると主は領民の安全保護という責任を負う事となり、城が攻められると領民も城に入れて守る義務も生じるのです。
城攻めは、それによる城下の経済封鎖が一番の効果となっていて、城主が城を囲まれ領民や家臣からの信頼を失った時点で結果がでるものです。つまり籠城されて領民が経済的損失を被った時点で「領主の負け」と判断される事が多い為に城下町に危険が及ばない範囲で防御壁を築くことが最適でした。
そして江戸時代以降の肥田で防災用の土塁が必要だったという事は、中世の肥田でも防災土塁が必要だった筈です。
こう考えると、肥田城には高野瀬氏によって元々防災と防御の機能を併せ持った土塁が築かれていたと考える方が自然です。
●編集部が考える肥田城水攻めは…
1万5千の兵で肥田城に向かって六角義賢の軍が居城・観音寺城を発したのを知った高野瀬秀隆は、あまりの大軍に驚き城下町の領民を肥田城に入れて保護し、同時に自軍も浅井長政の援軍が来るまで城の防御に徹する覚悟を決めたのです。
もしかしたら、この時に自ら城の周りに水を入れて濠のようにしたのかもしれません。肥田に到着した六角軍が肥田城を囲む土塁を占領、そこから城までに水が入っている事から逆に利用して水攻めを決意します。この時に防波堤として利用したのが占拠した土塁でした。
城を囲った六角軍の大半はこの後に観音寺城に戻り少しでも経費を抑えようとしたのかもしれません。しかし、川の流れを守る為の堤防と水を堰き止めるダムとでは強度が違うために残った兵は土塁の強化に追われたのです。
土のダムでは水が徐々に染み込むために、水圧と長時間の二重苦に耐えられるものではないので、肥田城周辺に溜まった水は精々人の膝から腰が沈む程度だったと予想されます。だからこそ約60日弱の水攻めに土塁が耐えられたのです、そうでなければ途中で決壊したことでしょう。
5月28日に土塁が2ヶ所決壊したとの話があります。旧暦に置き換えれば梅雨の真っ最中ですから、雨によって土塁の許容範囲を超える水が溜まったのでしょう。この後に高野瀬軍と六角軍との戦いが行われた記録がない事を考えると、肥田城周辺には既に六角軍が殆ど居なかったとしか思えず、戦費節約の為に必要最低限の人数以外は撤兵していたのではないでしょうか?
あまり水に浸からない建物、少しだけの土木工事、少ない攻城軍。知れば知るほどイメージから遠ざかっていく肥田城水攻めは450年を経てもまだまだ謎に満ちているのではないでしょうか?
以上、知りうる限りでの疑問や比較から独自の意見を展開しましたが、素人の域を超えるものではなく確実とは言えません。今後、河川や地層・土木工学などの専門知識を持った方々の研究を期待していきたい。
●肥田城主の高野瀬氏について
肥田城水攻め450年を記念して紹介していますが城があるということはそこには攻める者と守る者という人間の存在が大きく関わってきますので、守る立場であった高野瀬一族についてご紹介しましょう。
高野瀬氏の始まりについては二つの話があります。
・近江守護佐々木氏の分家が高野瀬村を与えられて住んだという説。
・『三上山の大ムカデ退治』や平将門の乱を平定した事で有名な藤原秀郷の子孫が源平合戦の時に源頼朝に従い、高野瀬に住むようになったという説です。
どちらにしても高野瀬氏が鎌倉時代末期までに高野瀬村(豊郷町)に落ち着いて、この地名を氏とし城を築城した事はほぼ間違いないとされています。この城は現在その形を留めていませんが、近くには高野瀬氏が信仰していた天稚彦神社が鎮座しています。この御祭神である天稚彦命が肥田城近くにある勝鳥神社の御祭神である事も興味深いかもしれませんね。
鎌倉幕府滅亡の折、六波羅探題であった北条仲時を番場宿で自害に追い込んだ事件に高野瀬隆重という人物に功があったと伝わっています。
古いうちから高野瀬村に土着した高野瀬一族は、そのまま勢力を広げてゆきます。14世紀後半から15世紀頃に佐々木六角氏の命で肥田城を築城したとされていますが、肥田町内にある金毘羅神社には養和元年(1181)に肥田城主・高野瀬備前守が宇曽川の安全のために城内に金毘羅宮を勧進したとの案内があるので、もしかしたら高野瀬城と同時期に肥田城が築城された可能性もあるのです。また平流城(現在の稲里公民館辺り)も高野瀬氏が治めた城であったと言う説もあり最大時には600~700石の支配地があったのではないか?と言われています。鎌倉時代から戦国時代まで高野瀬村周辺を治めた間に、明(中国)との貿易も行いました。城跡からはそれを示す資料として明銭が大量に出土しています。また紙の生産や瓜の取引も行っていて、佐々木(六角)氏を通して皇室に瓜が献上されていたのです。そして東山道(中山道)には下枝の関を設け関銭五十文(通行税:500円程度)を徴収していることから、小さな小豪族ではなく豊富な財源を持っていた有力者のイメージが浮かび上げってきます。
しかし、高野瀬一族の繁栄に陰りが見えるのが応仁元年(1467)から始まった応仁の乱でした。近江守護だった佐々木一族もこの大乱で北の京極氏(東軍)と南の六角氏(西軍)に分かれて戦うようになり、現在の彦根市が両家の勢力の境目として何度も戦乱に巻き込まれるようになったのです。この間、高野瀬氏は六角氏に従い戦い抜きました。
やがて応仁の乱は終わりますが全国的に戦国の時代となり戦が止む事は無かったのです。西軍に味方していた六角氏は都で権力を握った東軍の細川氏との戦乱に明け暮れ一時期は足利将軍の出兵も受けて、居城・観音寺城から逃れる事態も起こったのでした。それはそのまま京極氏の侵略を意味するもので、16世紀初頭に高野瀬備中守(頼定か?)が川瀬氏などの近隣の豪族と共に六角氏に反乱を起こしたのです。この反乱は六角氏の肥田城攻めで鎮圧され備前守は陳謝し再び六角氏に従属したのです。
天文22年(1553)、京極氏を追い出して湖北の実権を握った浅井久政に対し六角義賢が兵を進めました。地頭山で行われた合戦で六角氏は大勝利を収めますが、高野瀬備前守は討ち死にしてしまうのです。
詳しい事は分かりませんが、備中守の後を継いで肥田城主になったのが高野瀬秀隆であったと考えられます。もしそれが正しいのならば先代の仇とも言える浅井氏に秀隆が従うには、浅井有利の確信が余程大きくなければできないと思えてきます。
永禄2年の肥田城水攻めと翌年の野良田表の戦いで浅井長政が勝利した事から、以降の高野瀬氏は浅井氏が滅びるまで従ったように思えますが、この後にも六角氏が佐和山城攻めを行っている事実を考えると、浅井氏と六角氏の間を何度も行き着した豪族のしたたかさを持ちながら戦国期の近江を生きていったのではないでしょうか。その最後の君主が織田信長だったのです。
信長の家老・柴田勝家に属した高野瀬秀隆と隆景親子の最後は遠く離れた越前で突然訪れ、高野瀬一族嫡流は歴史の表舞台から消えてしまいますが、足跡は確実に近江に刻まれたのです。
ちなみに残った一族は彦根藩にも仕えていたと子孫の方がおっしゃっていました。
今年(2009年)はその450年目の記念の年になります。
あれから様々な調査をして、管理人や『どんつき瓦版』独自の見解を、新しい瓦版に発表しました。
これは、「肥田城水攻め450年」の言い出しっぺである管理人の責任だと感じています。
このイベントについて動いたのですが、結局実を結ぶことは無く、某大学(ここにも1年前に声を掛けに行きました)でも授業として計画されていた話がありましたがインフルエンザで中止となり、唯一『どんつき瓦版』のみが今日に間に合った肥田城水攻め450年になります。
昨年の弥千代姫婚礼150年も、結局今年になって幾つかの弥千代姫イベントがありましたし…
彦根のイベント事情に幾分かの事前調査を要望したい時もあります(ちょっと苦言です・汗)
では、『どんつき瓦版』として管理人が示した水攻め記事をご紹介します。
~~以下、記事加筆~~
溢れんばかりに満々と水を湛え、建物の大部分がその水の中に沈む―
高い場所に逃れた人々は、足場を失いつつ狭い場所に集まり、絶望のどん底で周囲に造られた土塁を見つめ、自分たちを苦しめている巨大土木工事を行った敵に怨嗟の声を上げ、不甲斐ない領主を恨む。雨が降れば水嵩が増し、その度に人々の声無き声は悲鳴となった…
戦国史を少しでも齧った事がある方々が“水攻め”と聞いて思い浮かべるのはこの様な光景ではないでしょうか?
時代劇などで目にするのは天正10年(1582)に羽柴秀吉によって行われた備中高松城の水攻めですが、この時もやはり水に沈むお城の姿が印象的に浮かんできます。
今(2009年)から450年前の永禄2年(1559)、それまで仕えていた六角義賢の元を去り、浅井長政へ仕える事となった高野瀬隆秀は宇曽川沿いの肥田城に立て籠もる。
これに怒った六角義賢は息子の義弼と1万5千の兵を率いて肥田城に向けて出兵、4月3日に肥田城を囲む形で幅12間(約23m)長さ58町(約6.3㎞)の堤防を築き、宇曽川と愛知川(当時は今よりも北に流れていた)から水を引き込んで水攻めにしたのです。しかし5月28日に豪雨によって堤防の2ヶ所が決壊し水攻めは失敗に終わる。寛政4年(1792)に彦根藩士・源義陳がまとめた『近江小間攫』には“本朝(この国)水攻ノ最初ハ此時ナリ”と記されるように日本最初の水攻めとして戦国史に事績を残す攻城戦となったのです。
実際には日本最初の水攻めは文明15年(1483)の若江城水攻めまで遡ってしまいますが、それでも備中高松城水攻めよりは20年以上前の出来事として価値があるものだったのです。
では実際にどのような戦いが行われたのでしょうか?残念ながらそれを示す一級資料は皆無と言っても過言ではない状態です。そこで『どんつき瓦版』編集部では他の水攻めとの比較によって肥田城水攻めを多方面から検証してきたのです。
まず目を付けたのが、肥田城を攻めた六角氏にそれほどの経済力があったのか?との疑問でした。
よく出される記録によると天正10年の秀吉による備中高松城水攻めでは、底の幅12間(約23m)・上部の幅6間(約11m)・高さ2丈余(約6m)・長さ30余町(約3.3㎞)の土塁を造る為に約70万貫文(約1千億円)の費用が掛ったと言われています。70万貫文という数字を現代の価値に直すのは難しいですが、永禄11年(1568)に織田信長が禁裏修繕の為に出した費用が1万貫文と言われていますのでその70倍、俗説では「安土城を2つ築城してもまだお釣りが出るくらい」とも言われているのです。
高松城の費用から単純に計算して58町の土塁を築くとなると約135万貫文(約1930億円)の費用が必要となるのです。しかも最近では「秀吉が高松城で実際に造った土塁は300mほどの長さで残りは元々地元で利用されていた堤防を使った物だった」との説も出ているのです。同じ説は秀吉の他の水攻め(紀州太田城・竹ヶ鼻城)や石田三成が行った忍城水攻めでも検証されつつあり、肥田城でも同様の可能性が考えられるのです。
また戦費についても多額に計上されます、翌年に起こった桶狭間の戦いの時の戦費から単純に割合で計算しても水攻め期間中約60日で米だけで3億円の費用が掛るのです。これに副菜・馬の餌代・軍備の費用などを含めると1万5千人の兵を動かすだけでどれ程の戦費が掛ったのか想像もできなくなります。
そして、通説では宇曽川の水を堰き止めて肥田城に流し込んだかのように言われてきましたが、もし宇曽川を堰き止めるとなれば地方との貿易の為の運送川だった宇曽川を通る船から“川銭”と呼ばれる通行税を徴収していた豪族たちに六角氏は損害金を支払わなければならなくなってしまいます。
応仁の乱で六角氏と敵対した細川氏が京で勢力を握ると、京から何度も六角征伐軍が派遣され、戦費に苦しんでいました。この為に重臣の蒲生定秀に借金があったくらいだったのです。
続いて、土塁は本当に六角氏が築いたのか?という疑問も浮かび上がってきます。
肥田城の遺跡としてよく知られている、町中に残る土塁の数々は1988年に滋賀県教育委員会から発行された『肥田城遺跡発掘調査報告書』によって江戸時代以降に造られた物である事が明らかになっています。肥田城を守る為の戦略的土塁ではなく、水害から肥田の地域を守る為の防災的土塁だったと考えると戦国時代に肥田城を守る為の戦略的土塁が別に存在したとも考えられるのです。
肥田は、中世でも早い時期に城下町として形成された城でした。城の周りに町ができると主は領民の安全保護という責任を負う事となり、城が攻められると領民も城に入れて守る義務も生じるのです。
城攻めは、それによる城下の経済封鎖が一番の効果となっていて、城主が城を囲まれ領民や家臣からの信頼を失った時点で結果がでるものです。つまり籠城されて領民が経済的損失を被った時点で「領主の負け」と判断される事が多い為に城下町に危険が及ばない範囲で防御壁を築くことが最適でした。
そして江戸時代以降の肥田で防災用の土塁が必要だったという事は、中世の肥田でも防災土塁が必要だった筈です。
こう考えると、肥田城には高野瀬氏によって元々防災と防御の機能を併せ持った土塁が築かれていたと考える方が自然です。
●編集部が考える肥田城水攻めは…
1万5千の兵で肥田城に向かって六角義賢の軍が居城・観音寺城を発したのを知った高野瀬秀隆は、あまりの大軍に驚き城下町の領民を肥田城に入れて保護し、同時に自軍も浅井長政の援軍が来るまで城の防御に徹する覚悟を決めたのです。
もしかしたら、この時に自ら城の周りに水を入れて濠のようにしたのかもしれません。肥田に到着した六角軍が肥田城を囲む土塁を占領、そこから城までに水が入っている事から逆に利用して水攻めを決意します。この時に防波堤として利用したのが占拠した土塁でした。
城を囲った六角軍の大半はこの後に観音寺城に戻り少しでも経費を抑えようとしたのかもしれません。しかし、川の流れを守る為の堤防と水を堰き止めるダムとでは強度が違うために残った兵は土塁の強化に追われたのです。
土のダムでは水が徐々に染み込むために、水圧と長時間の二重苦に耐えられるものではないので、肥田城周辺に溜まった水は精々人の膝から腰が沈む程度だったと予想されます。だからこそ約60日弱の水攻めに土塁が耐えられたのです、そうでなければ途中で決壊したことでしょう。
5月28日に土塁が2ヶ所決壊したとの話があります。旧暦に置き換えれば梅雨の真っ最中ですから、雨によって土塁の許容範囲を超える水が溜まったのでしょう。この後に高野瀬軍と六角軍との戦いが行われた記録がない事を考えると、肥田城周辺には既に六角軍が殆ど居なかったとしか思えず、戦費節約の為に必要最低限の人数以外は撤兵していたのではないでしょうか?
あまり水に浸からない建物、少しだけの土木工事、少ない攻城軍。知れば知るほどイメージから遠ざかっていく肥田城水攻めは450年を経てもまだまだ謎に満ちているのではないでしょうか?
以上、知りうる限りでの疑問や比較から独自の意見を展開しましたが、素人の域を超えるものではなく確実とは言えません。今後、河川や地層・土木工学などの専門知識を持った方々の研究を期待していきたい。
●肥田城主の高野瀬氏について
肥田城水攻め450年を記念して紹介していますが城があるということはそこには攻める者と守る者という人間の存在が大きく関わってきますので、守る立場であった高野瀬一族についてご紹介しましょう。
高野瀬氏の始まりについては二つの話があります。
・近江守護佐々木氏の分家が高野瀬村を与えられて住んだという説。
・『三上山の大ムカデ退治』や平将門の乱を平定した事で有名な藤原秀郷の子孫が源平合戦の時に源頼朝に従い、高野瀬に住むようになったという説です。
どちらにしても高野瀬氏が鎌倉時代末期までに高野瀬村(豊郷町)に落ち着いて、この地名を氏とし城を築城した事はほぼ間違いないとされています。この城は現在その形を留めていませんが、近くには高野瀬氏が信仰していた天稚彦神社が鎮座しています。この御祭神である天稚彦命が肥田城近くにある勝鳥神社の御祭神である事も興味深いかもしれませんね。
鎌倉幕府滅亡の折、六波羅探題であった北条仲時を番場宿で自害に追い込んだ事件に高野瀬隆重という人物に功があったと伝わっています。
古いうちから高野瀬村に土着した高野瀬一族は、そのまま勢力を広げてゆきます。14世紀後半から15世紀頃に佐々木六角氏の命で肥田城を築城したとされていますが、肥田町内にある金毘羅神社には養和元年(1181)に肥田城主・高野瀬備前守が宇曽川の安全のために城内に金毘羅宮を勧進したとの案内があるので、もしかしたら高野瀬城と同時期に肥田城が築城された可能性もあるのです。また平流城(現在の稲里公民館辺り)も高野瀬氏が治めた城であったと言う説もあり最大時には600~700石の支配地があったのではないか?と言われています。鎌倉時代から戦国時代まで高野瀬村周辺を治めた間に、明(中国)との貿易も行いました。城跡からはそれを示す資料として明銭が大量に出土しています。また紙の生産や瓜の取引も行っていて、佐々木(六角)氏を通して皇室に瓜が献上されていたのです。そして東山道(中山道)には下枝の関を設け関銭五十文(通行税:500円程度)を徴収していることから、小さな小豪族ではなく豊富な財源を持っていた有力者のイメージが浮かび上げってきます。
しかし、高野瀬一族の繁栄に陰りが見えるのが応仁元年(1467)から始まった応仁の乱でした。近江守護だった佐々木一族もこの大乱で北の京極氏(東軍)と南の六角氏(西軍)に分かれて戦うようになり、現在の彦根市が両家の勢力の境目として何度も戦乱に巻き込まれるようになったのです。この間、高野瀬氏は六角氏に従い戦い抜きました。
やがて応仁の乱は終わりますが全国的に戦国の時代となり戦が止む事は無かったのです。西軍に味方していた六角氏は都で権力を握った東軍の細川氏との戦乱に明け暮れ一時期は足利将軍の出兵も受けて、居城・観音寺城から逃れる事態も起こったのでした。それはそのまま京極氏の侵略を意味するもので、16世紀初頭に高野瀬備中守(頼定か?)が川瀬氏などの近隣の豪族と共に六角氏に反乱を起こしたのです。この反乱は六角氏の肥田城攻めで鎮圧され備前守は陳謝し再び六角氏に従属したのです。
天文22年(1553)、京極氏を追い出して湖北の実権を握った浅井久政に対し六角義賢が兵を進めました。地頭山で行われた合戦で六角氏は大勝利を収めますが、高野瀬備前守は討ち死にしてしまうのです。
詳しい事は分かりませんが、備中守の後を継いで肥田城主になったのが高野瀬秀隆であったと考えられます。もしそれが正しいのならば先代の仇とも言える浅井氏に秀隆が従うには、浅井有利の確信が余程大きくなければできないと思えてきます。
永禄2年の肥田城水攻めと翌年の野良田表の戦いで浅井長政が勝利した事から、以降の高野瀬氏は浅井氏が滅びるまで従ったように思えますが、この後にも六角氏が佐和山城攻めを行っている事実を考えると、浅井氏と六角氏の間を何度も行き着した豪族のしたたかさを持ちながら戦国期の近江を生きていったのではないでしょうか。その最後の君主が織田信長だったのです。
信長の家老・柴田勝家に属した高野瀬秀隆と隆景親子の最後は遠く離れた越前で突然訪れ、高野瀬一族嫡流は歴史の表舞台から消えてしまいますが、足跡は確実に近江に刻まれたのです。
ちなみに残った一族は彦根藩にも仕えていたと子孫の方がおっしゃっていました。