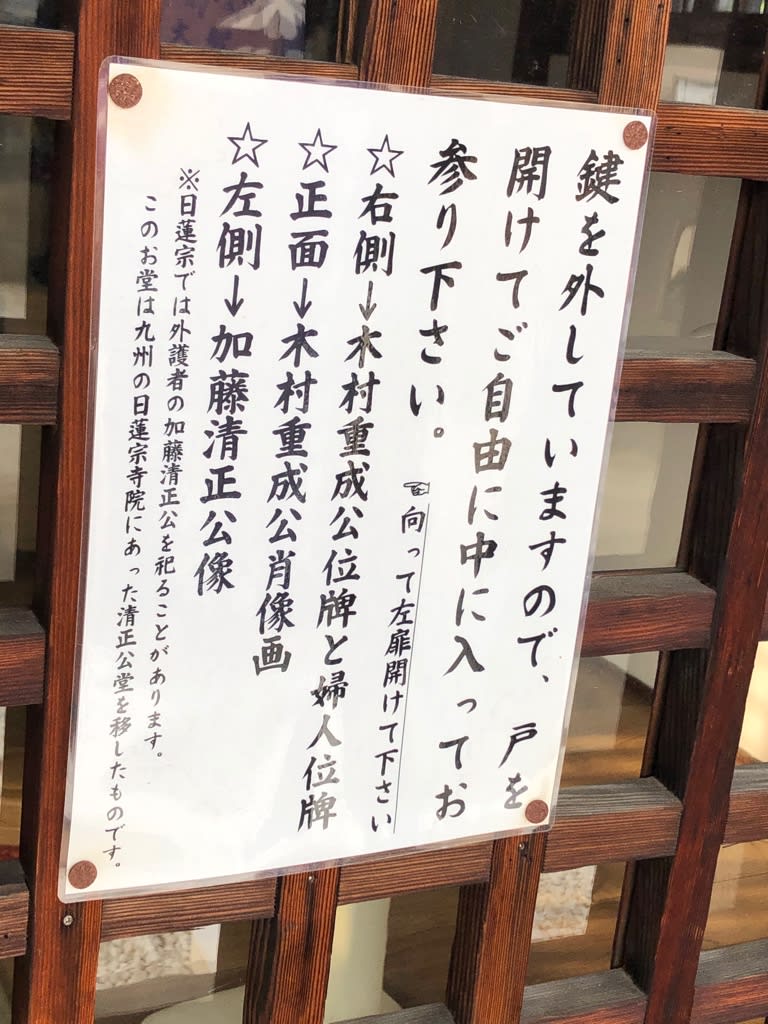日本史を俯瞰すると海外では考えられない日本人独特の好みがある。それは「世襲」と呼ばれる代々の血や名誉の繋がりである。
海外でも世襲は存在するが、どちらかといえば権力者が主張するものであり一般人がそれを完全に是とはしていない。
しかし、日本では平安時代初期に財力を失った天皇が千年を超えた現在でも国民の象徴として残り、歴史上の有名人の子孫はそれだけで一目置かれる。政治・文化・宗教などさまざまな分野において世襲が通用している。
封建社会では今よりも世襲が強い時代であり、世襲には独自の責任が付加されたが個々の判断で簡単に捨てられるものでもない。民衆は生活を保護してもらうために年貢を支払い、権力者がその一部を私用に使うのは謝礼のようなものであると解釈しているが、受ける側はそれに甘んじてはならず、先祖から続き自らも受けた恩恵を守り、子孫に伝えていかねばならなかったのである。そして武士たちは常に質素倹約を強いられるほど慎ましい生活であった。年貢の多くは開墾や治水などの公共工事によるインフラ整備、自然災害・飢饉などに備えた備蓄、軍事にも使用されていたのだ。
昔の時代劇などでは民衆を苦しめる悪代官を正義の味方が斬る物語が定番だったが、戦国時代以降の日本で定番の悪代官は数えるほどしか存在しない。民衆を苦しめると年貢が減り権力者自身が困ることになるからだ。悪代官など支配者側の失敗は、家禄減俸や重ければ死罪など目に見える形での罰として裁かれた。
さて、日本の封建社会においては地方分権の上に中央政府が置かれていたため、地方によって政策が違い地域に即したものであった。また責任範囲が限られていたため緊急時における救民活動の動きも早かった。江戸時代では各藩に物資を備蓄する蔵が点在し緊急時にここから囲米・囲籾と呼ばれる食糧や金銭が配られたのである。
彦根藩では、井伊直孝の時に京で彦根藩領出身の生活困窮者17人が保護されたことを恥として直孝は家臣を叱責し領内改革に着手した。また井伊直幸の頃に城下で起きた大火の救済として、世子直富が父の許可を得るより早く自らの判断で彦根城の蔵を開いて救援物資を配るなどの政策もある。
各藩は緊急事態で財政が逼迫すると年貢の値上げよりも先に藩士たちの俸給を藩が借受ける形でカットした。その額も半分や8割など状況によって信じられないような高額の対策が行われた。年貢や税を徴収する者は、それほど大きな責任を背負っていたのであり、それは先祖代々の身分と責任の世襲であることが社会の仕組みとして完成していたのだ。
もちろん全ての者が自らの身分を顧みていたわけではなく、身分に胡坐をかいた者の多さが明治維新に繋がっていくが、迅速な救民、責任を持って状況を打破する施政者は期待できない。悪代官に近いような人物が横行するのは明治以降であると断言できるのである。
彦根城梅園

海外でも世襲は存在するが、どちらかといえば権力者が主張するものであり一般人がそれを完全に是とはしていない。
しかし、日本では平安時代初期に財力を失った天皇が千年を超えた現在でも国民の象徴として残り、歴史上の有名人の子孫はそれだけで一目置かれる。政治・文化・宗教などさまざまな分野において世襲が通用している。
封建社会では今よりも世襲が強い時代であり、世襲には独自の責任が付加されたが個々の判断で簡単に捨てられるものでもない。民衆は生活を保護してもらうために年貢を支払い、権力者がその一部を私用に使うのは謝礼のようなものであると解釈しているが、受ける側はそれに甘んじてはならず、先祖から続き自らも受けた恩恵を守り、子孫に伝えていかねばならなかったのである。そして武士たちは常に質素倹約を強いられるほど慎ましい生活であった。年貢の多くは開墾や治水などの公共工事によるインフラ整備、自然災害・飢饉などに備えた備蓄、軍事にも使用されていたのだ。
昔の時代劇などでは民衆を苦しめる悪代官を正義の味方が斬る物語が定番だったが、戦国時代以降の日本で定番の悪代官は数えるほどしか存在しない。民衆を苦しめると年貢が減り権力者自身が困ることになるからだ。悪代官など支配者側の失敗は、家禄減俸や重ければ死罪など目に見える形での罰として裁かれた。
さて、日本の封建社会においては地方分権の上に中央政府が置かれていたため、地方によって政策が違い地域に即したものであった。また責任範囲が限られていたため緊急時における救民活動の動きも早かった。江戸時代では各藩に物資を備蓄する蔵が点在し緊急時にここから囲米・囲籾と呼ばれる食糧や金銭が配られたのである。
彦根藩では、井伊直孝の時に京で彦根藩領出身の生活困窮者17人が保護されたことを恥として直孝は家臣を叱責し領内改革に着手した。また井伊直幸の頃に城下で起きた大火の救済として、世子直富が父の許可を得るより早く自らの判断で彦根城の蔵を開いて救援物資を配るなどの政策もある。
各藩は緊急事態で財政が逼迫すると年貢の値上げよりも先に藩士たちの俸給を藩が借受ける形でカットした。その額も半分や8割など状況によって信じられないような高額の対策が行われた。年貢や税を徴収する者は、それほど大きな責任を背負っていたのであり、それは先祖代々の身分と責任の世襲であることが社会の仕組みとして完成していたのだ。
もちろん全ての者が自らの身分を顧みていたわけではなく、身分に胡坐をかいた者の多さが明治維新に繋がっていくが、迅速な救民、責任を持って状況を打破する施政者は期待できない。悪代官に近いような人物が横行するのは明治以降であると断言できるのである。
彦根城梅園