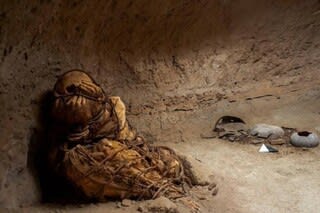zakzak 2021.12/4 15:00
 旭川市博物館の展示品。おそらく欧州由来のトンボ玉からなるタマサィ(山根一眞撮影)
旭川市博物館の展示品。おそらく欧州由来のトンボ玉からなるタマサィ(山根一眞撮影)
先週、北海道の旭川市博物館を訪ね、展示品のひとつにくぎ付けになった。
きれいな模様があるガラス玉をつなげた首飾りだが、「どうしてアイヌ文化にこれがあるんだ!」と大声をあげてしまった。
説明パネルには、「代々、アイヌの女性に受け継がれて、儀式などの盛装の際に身につける」とある。このように「玉を連ねたものをタマサィと呼ぶ」のだそうだ。詳しい説明パネルはなかったが、学芸員の杉山一彦さんに話を聞くことができた。
展示品のタマサィは美しい模様のガラス玉に穴を空けて、ひもを通したもので、28個の大粒のガラス玉が連なっている。この種のガラス玉はトンボの眼になぞらえ「トンボ玉」として知られているが、私がびっくりしたのはブラジル、アマゾンの奥地の村、そしてアフリカ、セネガルの首都、ダカールの市場の骨董(こっとう)店で見たものとまったく同じものだったからだ。
およそ30年前、私はアマゾン河中流のニャムンダという小さな町を訪ねた。かつて勇猛な女族がいたとされる地で、ギリシャ神話の女族、アマゾネスにちなんでアマゾンと名付けられた地名の由来がこの地なのだ。
その女族、アマゾネスにはムイラキタン(ムラキタンとも呼ぶ)という緑の蛙型の秘宝伝説があり、私はその秘宝を探しに行ったのである。古老から「奥地に魔術師ばかりが住む村があり、ムラキタンがあるかも」と聞き、苦労の末その村へ行き所有者を発見。交渉を重ね、ついにアマゾンの秘宝を入手したのだが、それは緑の蛙ではなく丸い玉だった。
何かおかしいとは思っていたが、その数年後、ダカールの市場の骨董店で「アマゾンの秘宝」そっくりのモノを大量に見たのだ。それがトンボ玉だった。
アフリカではトンボ玉が多く流通していた時代があり、その多くは16―17世紀のベネチア製だ。欧州人はその美しいガラス玉を交易に使い、「ガラス玉1つで奴隷1人が買えた」とも。つまり、トンボ玉は通貨だった。
あの「アマゾンの秘宝」は、アフリカとアマゾン間で大西洋を介した交易が盛んだったことを思わせたが、わが秘宝の夢は消えてしまった。その後、正倉院にもトンボ玉があると知り、このガラス玉による世界規模の経済圏を調べたいと思いつつ、およそ30年が過ぎてしまった。今回訪れた旭川市博物館で、その経済圏がアイヌにまで及んでいたことを知り驚いたのである。
旭川市博物館では、アイヌが13世紀頃から小型のカヌーで現在のロシアや中国との交易を行い、トンボ玉以外にも多くの貴重な輸入品を得ていたことを知った。それらに関する展示もあった(アイヌ文化はすごい。不勉強でした)。北海道白老町にある文化公園、ウポポイ(民族共生象徴空間)の国立アイヌ博物館では、アイヌの首飾りを中心とした「ビーズ アイヌモシリから世界へ」という特別展が開催中だったが、残念ながら訪ねることはできなかった(12月5日まで)。
https://www.zakzak.co.jp/article/20211204-OFG6YCYVZVONNK662CA22MOUDU/
 旭川市博物館の展示品。おそらく欧州由来のトンボ玉からなるタマサィ(山根一眞撮影)
旭川市博物館の展示品。おそらく欧州由来のトンボ玉からなるタマサィ(山根一眞撮影)先週、北海道の旭川市博物館を訪ね、展示品のひとつにくぎ付けになった。
きれいな模様があるガラス玉をつなげた首飾りだが、「どうしてアイヌ文化にこれがあるんだ!」と大声をあげてしまった。
説明パネルには、「代々、アイヌの女性に受け継がれて、儀式などの盛装の際に身につける」とある。このように「玉を連ねたものをタマサィと呼ぶ」のだそうだ。詳しい説明パネルはなかったが、学芸員の杉山一彦さんに話を聞くことができた。
展示品のタマサィは美しい模様のガラス玉に穴を空けて、ひもを通したもので、28個の大粒のガラス玉が連なっている。この種のガラス玉はトンボの眼になぞらえ「トンボ玉」として知られているが、私がびっくりしたのはブラジル、アマゾンの奥地の村、そしてアフリカ、セネガルの首都、ダカールの市場の骨董(こっとう)店で見たものとまったく同じものだったからだ。
およそ30年前、私はアマゾン河中流のニャムンダという小さな町を訪ねた。かつて勇猛な女族がいたとされる地で、ギリシャ神話の女族、アマゾネスにちなんでアマゾンと名付けられた地名の由来がこの地なのだ。
その女族、アマゾネスにはムイラキタン(ムラキタンとも呼ぶ)という緑の蛙型の秘宝伝説があり、私はその秘宝を探しに行ったのである。古老から「奥地に魔術師ばかりが住む村があり、ムラキタンがあるかも」と聞き、苦労の末その村へ行き所有者を発見。交渉を重ね、ついにアマゾンの秘宝を入手したのだが、それは緑の蛙ではなく丸い玉だった。
何かおかしいとは思っていたが、その数年後、ダカールの市場の骨董店で「アマゾンの秘宝」そっくりのモノを大量に見たのだ。それがトンボ玉だった。
アフリカではトンボ玉が多く流通していた時代があり、その多くは16―17世紀のベネチア製だ。欧州人はその美しいガラス玉を交易に使い、「ガラス玉1つで奴隷1人が買えた」とも。つまり、トンボ玉は通貨だった。
あの「アマゾンの秘宝」は、アフリカとアマゾン間で大西洋を介した交易が盛んだったことを思わせたが、わが秘宝の夢は消えてしまった。その後、正倉院にもトンボ玉があると知り、このガラス玉による世界規模の経済圏を調べたいと思いつつ、およそ30年が過ぎてしまった。今回訪れた旭川市博物館で、その経済圏がアイヌにまで及んでいたことを知り驚いたのである。
旭川市博物館では、アイヌが13世紀頃から小型のカヌーで現在のロシアや中国との交易を行い、トンボ玉以外にも多くの貴重な輸入品を得ていたことを知った。それらに関する展示もあった(アイヌ文化はすごい。不勉強でした)。北海道白老町にある文化公園、ウポポイ(民族共生象徴空間)の国立アイヌ博物館では、アイヌの首飾りを中心とした「ビーズ アイヌモシリから世界へ」という特別展が開催中だったが、残念ながら訪ねることはできなかった(12月5日まで)。
https://www.zakzak.co.jp/article/20211204-OFG6YCYVZVONNK662CA22MOUDU/










 『鬼滅の刃』遊郭編 キービジュアル(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable(アニメ!アニメ!)
『鬼滅の刃』遊郭編 キービジュアル(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable(アニメ!アニメ!)