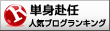今日、以前から行こうと思ってたサントリー美術館 若沖と蕪村(生誕300年)を鑑賞した。

六本木の東京ミッドタウンはかなりの人出だった・・
表の芝生にはごろりと休憩しながら日光浴?の人が大勢・・

日本画の展覧会は昨年の徒然草の展覧会以来です。
日本画の興味は洋画ほどはなかったのですが
この展覧会にて一気に日本画の魅力にはまった・・・
二人の初期の作品から順次みていくと作風が大きく変わっていく様子がわかる。
特に蕪村に関しては、素朴な墨画から中国風の作風に 水墨の世界にどっぷりという感じです。
若沖の中でも 象と鯨の大きな屏風画の迫力はすごかったな・・・

二人の作品がこれほどあるのかと思うだけですごい
計230点の作品
じっくりと鑑賞させていただいた。
これは引用・・・
正徳6年(1716)は、尾形光琳(おがたこうりん)が亡くなり、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)と与謝蕪村(よさぶそん)というふたりの天才絵師が誕生した、江戸時代の画壇にとってひとつの画期となりました。
伊藤若冲(享年85、1800年没)は、京都にある青物問屋の長男として生まれ、23歳の時に家業を継ぎますが、30代中頃には参禅して「若冲居士(こじ)」の号を与えられ、40歳で隠居して絵を描くことに本格的に専念します。
一方、与謝蕪村(享年68、1783年没)は、大坂の農家に生まれ、20歳頃に江戸へ出て俳諧を学びます。27歳の時、俳諧の師匠の逝去を機に、北関東や東北地方をおよそ10年間遊歴します。その後40歳頃から京都へうつり俳諧と絵画のふたつの分野で活躍しました。
若冲は彩色鮮やかな花鳥図や動物を描いた水墨画を得意とし、蕪村は中国の文人画の技法による山水図や、簡単な筆遣いで俳句と絵が響き合う俳画を得意としていました。一見すると関連がないようですが、ふたりとも長崎から入ってきた中国・朝鮮絵画などを参考にしています。