
(ウィキペディア
「日本マクドナルド」より引用。)
マクドナルドの売り上げ急降下は、チキンナゲットの中国工場の不潔問題がきっかけです。あのときすっぱりナゲットを発売中止にしておけばよかったのではないかと私は思います。
中国産からタイ産に移しただけで、「愛好者がいる」との口実で発売中止にしなかったのがマズかったのではないでしょうか?日本人にとってはどちらにせよ外国産で、中国とタイの違いがわかりませんから、ナゲットそのものに対する不信感を払しょくできませんでした。(未練たらしく発売を続けるのだな、という印象が残っただけでした。私の場合、経営姿勢に疑問を感じ、ハンバーガーも食べたくなくなりました。)
私は業界に詳しい者ではありませんが、経営の名手といわれる原田泳幸氏が社長だった時代から、斜陽の影があったそうです。原田氏によって業績がV字回復してから、原田氏はすぐに「レジメニューの廃止」、「60秒チャレンジ」を始めました。
「レジメニューの廃止」はレジで立ち止まって注文を考える客をなくし、客の流れをスムーズにさせるためです。「60秒チャレンジ」は注文から品出しまで60秒を切るようにスタッフに競わせたことです。
ところがレジメニューでない背後や上の看板メニューはわかりにくく、評判がよくありませんでした。また60秒チャレンジでミスが多く発生するようになりました。
そんな中での中国工場不潔問題の露見でした。やっぱりここは工場をタイに移すのではなく、チキンナゲットをすっぱり中止すべきだったと、素人ながら私は思っています。
(経営というものにはセオリーがないようですね。セオリー通りで経営ができるなら、他と差がつきません。だから「賭け」のようになります。原田氏は最初は「賭け」に勝っていたのですね。国の経営も同じではないでしょうか?アベノミクスも勝てば安倍さんは歴史に名を残すでしょう。負ければ逆です。いまのところ、東京オリンピック誘致に成功したり「運」が安倍さんに味方していますよね。日銀総裁の首をすげ替えたのも大きな「賭け」ですね。これまで日銀総裁を交代させた総理大臣はいなかったのではないでしょうか?)
※今日、気にとまった短歌
駅弁を食べた後にはひと眠りこだまが一番ゆっくりできる (浜松市)松岡良枝















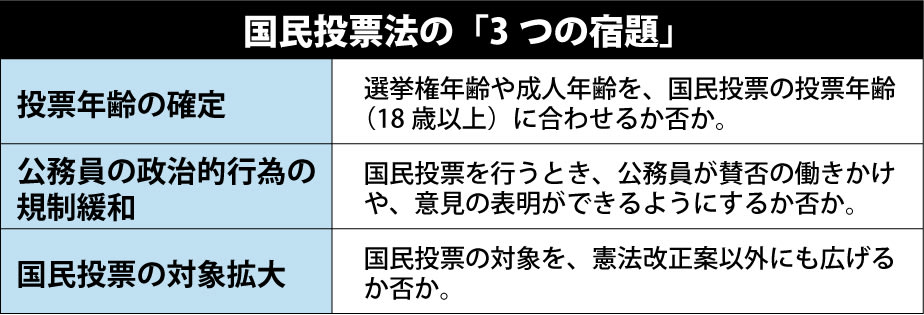





 (みすず書房刊。)
(みすず書房刊。)
