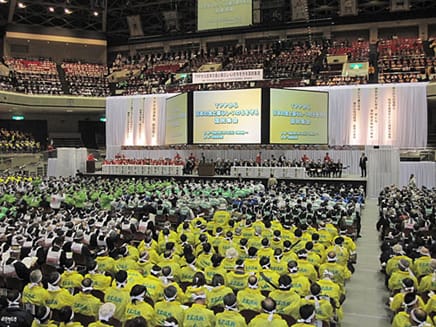(旧東インド会社、アムステルダム本社。ウィキペディア
「オランダ東インド会社」より引用。)
株式会社という仕組みは、東インド会社以来350年の歴史があります。株式会社とは、経営者と投資家を分離した初めての制度です。分離することで成功を納めたので今日まで続いてきたのでしょう。
これまで投資家が株式会社に投資してきたのは、経済が350年間右肩上がりだったからです。なぜなら、右肩下がりの経済に、損すると分かって投資する投資家はいないからです。
前回ご紹介した『グローバリズムという病』という書物は、先進国の経済はすでにピークに達した、それを端的に表すのが人口減少だと主張しています。それでは、先進国の株式会社はこれからどうしたらよいのでしょうか?じつは未開発国に手を伸ばす必要があります。未開発国はまだ人口増加を続けています。
本書によれば、未開発国を巻き込むのが「グローバル企業」であり「経済のグローバル化」ということです。私見では、おおむかしの植民地政策が形を変えて現代に現れたものと見なせます。もっとも、著者は株式会社の賞味期限切れを主張し、「グローバル化」はうまくいかないだろうと予想しています。
そのため、わが国の株式会社はローカルルールを捨てる必要はない、というわけです。(著者はそこまではっきりとは言っていませんが、私見を混ぜるとそうなります。)
私はさらに著者が言っていない理由から、日本の株式会社がグローバル化できるか、するべきかという点に疑問をもっています。というのは、多くの株式会社が実質的に「個人」(同族)だからです。例えば、ヤンマーディーゼル(株)や日本メナード化粧品(株)などは非上場です。
上場するのは資金調達を求めているというよりも、会社の箔づけとか見栄の部分が大きいのではないでしょうか?
いずれにせよ、日本のサラリーマンは「個人」(同族)にいいように使われてきたので、これ以上外国人(の資本)にまでこき使われる必要はないと私は考えます。
(著者は最貧国ウルグアイの大統領、
ムヒカ氏の”国連持続可能な開発会議・リオ+20(2012)”での演説を参照せよと言います。演説の要点は「各世帯に車があるドイツ人と同じ生活をインド人全世帯がやるだけの資源が地球にあるのか?」という素朴な疑問です。私の文明論からは、ムヒカ大統領の批判は、人類が農耕を発明したときにまで遡ることができます。)
(きのう(2012-11-12)まで名古屋の国際会議場で皇太子ご夫妻ご来臨のもと、「持続可能な開発についての教育(ESD)」という国連の国際会議が開かれていました。マスコミの中で「持続可能な開発」という用語の語義矛盾を指摘した社はありませんでした。開発には必ず限界があります。)













 (東洋経済新報社刊。)
(東洋経済新報社刊。)