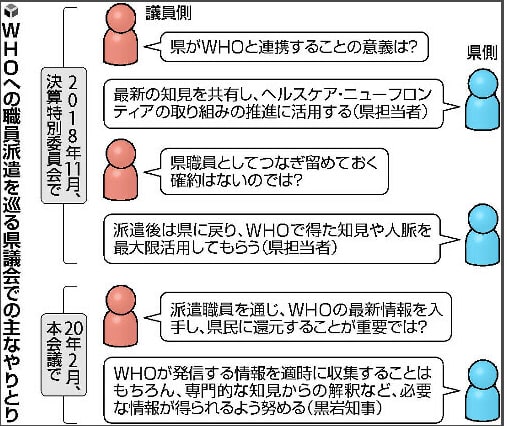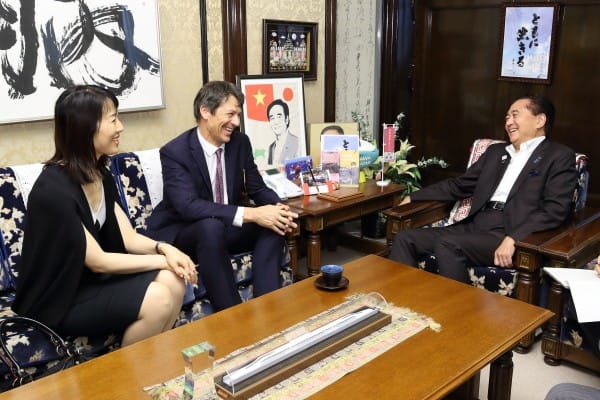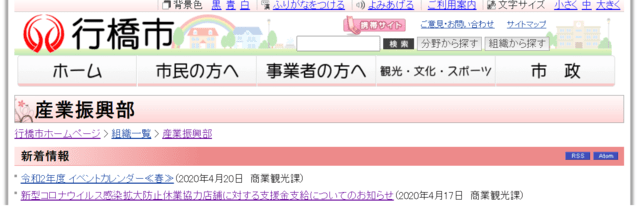どうもこんばんは、若年寄です。
今回は、数年前の新聞記事がツイッターで流れてきたので、それをお題に「私的領域の保護とアウトリーチ福祉」について考えてみます。元ネタの新聞記事は、日本学術会議の任命拒否で話題となった6人の一人、加藤陽子氏が「私的領域と公的領域」について書いた文章です。(今回、日本学術会議には触れません。)
======【引用ここから】======
世界中で国家と国民の関係が大きく変化しています。ここで国家とは行政府を意味します。世界では、国民の側が国家に「NO」を突きつけましたが、日本では国家の側から国民との関係を急速に変えた点が特徴的。今の混沌(こんとん)の理由も、ここにあります。
戦後日本が培った原理に、「私的領域」と「公的領域」の明確な区別があります。近代立憲国家として必須のこの原理に、安倍政権は第一次の時から首相主導で手をつけ始めました。
2006年に60年ぶりに改正された教育基本法では、前文の「真理と平和を希求」が「真理と正義を希求」に修正されました。「平和」は一義的ですが、「正義」の内容は価値観によって違い、国家が定義すべきものではありません。
明治の日本が学んだ西欧の憲法は、過去の宗教戦争の惨禍に学び、国民の思想や信条に国家の側は介入しないという良識を確立していました。だから、教育勅語という精神的支柱の必要性が説かれたとき、明治憲法の実質的起草者だった井上毅(こわし)は「君主は臣民の良心の自由に干渉」すべきでないとして反対しました。
結局、教育勅語は出されましたが、国務大臣が副署しないことで、政治上の命令でなくなった。国家は国民の「私的領域」に立ち入るべきではないとの良識が、この段階では保たれていたのです。
======【引用ここまで】======
日本が培ってきたはずの私的領域と公的領域の明確な区別が、近年崩れつつあります。
国家は国民の私的領域に立ち入るべきではない、全くもってそのとおりです。
私的領域と公的領域は明確に区別すべき、全くもってそのとおりです。
井上毅は、君主は臣民の良心の自由に干渉すべきでないと主張しました。
国家・行政府が国民の私的領域に立ち入ってはならないのです。
私的領域を思想・良心・内心の自由に限定して捉えた時、公的領域はそれ以外という事になります。財産権、プライバシー権、家族関係等が公的領域となれば、行政府の管轄となり、管理・介入・指導・干渉の対象となります。この考え方を採用した場合、行政府は、個人の思想には介入しませんが生活には介入することになります。
「行政府は思想・良心・内心には立ち入りませんが、あなたの所有地に立ち入り生活状況を監視し介入します」というのは、実際のところ、私的領域/公的領域の区別を無意味にします。行動は思想の表れであるので、行動を監視し生活に介入できるのであれば、結局のところ思想そのものへの介入が可能になります。
思想・良心・内心の自由は、私有財産の保障が無ければ空虚なものとなります。財産権が保障されていなければ、思想に基づく表現行為も容易に制約できてしまいます。表現の自由はそもそも財産権の派生でしかない、という見方もできます。また、私的領域という日本語からは、私的な生活空間が含まれると考えるのが自然です。こうした観点から、私的領域の保障のためには、思想・良心・内心に限らず、財産権・プライバシー権、家族関係等も含めて捉え、これらをひっくるめた私生活全般に対し行政府は立ち入るべきでない、という考え方が、私的領域/公的領域の区別の重要なポイントになってきます。(うろ覚えですが、ハンナ・アーレントも、私的領域をかなり広く捉えていたように思います。)
アウトリーチ | 介護用語集 | 老人ホーム選びのパートナー ベネッセの介護相談室
======【引用ここから】======
本来は「手を差し伸べる」または「手を伸ばして取る」という意味。援助が必要な状態であるにもかかわらず要請をしない人たちに対して、支援者のほうから家庭などに出向いて手を差し伸べる「積極的な取り組み」のことをいう。
======【引用ここまで】======
福祉や介護の分野では、様々な論者が論者ごとに「あるべき生活水準」「あるべき生活様式」を設定し、これに適合しない生活をしているケースを全て掘り起こし、国民全員に漏れなく、健康で文化的な最低限度の生活をさせるのが行政の責務だ、という意見が幅をきかせています。そのための取り組みが、アウトリーチです。
こうしたアウトリーチの取り組みを、近隣住民や私的団体が行っている段階では、お節介で済むかもしれません。しかし、私的団体が自治体に繋いだり、あるいは、自治体が直接家庭を訪問して介入したりするようになると、私的領域/公的領域の問題が生じます。
アウトリーチ論が全面的に肯定された場合、全住民の生活が自治体の担当者の監視下に置かれます。プライバシーや自己決定権といったものが大きく後退し、個人の生活は公的領域に取り込まれてしまいます。
Aさん本人は現状を良しとしていても、第三者が
「私の考える『あるべき生活水準』に、Aさんの生活は達していない」
と判断し、Aさんの家の中に調査員が入り込み、行政や介護サービス事業者ら多くの人がAさんの生活に介入し、その費用を行政府に負担させるという事例が、介護分野を中心に多発しています。
また、特定の業種について、事業者に対し「廃業しろ」と声高に叫び、その業種の従業員に対し「辞めて福祉を使え」と主張する差別主義者・藤田孝典氏のように、独立生計を立てていた人の生活や仕事に干渉しわざわざ自治体に依存させようと斡旋し、その過程で手数料や補助金を得ようとする活動家も存在します。
アウトリーチの名の下に、私的領域は行政府の介入を受けています。個人の自由を守る防波堤が、アウトリーチ論によって穴を開けられています。
「支援を必要とする人全てに、申請を待たず、行政の側から福祉サービスを漏れなく提供しよう」
という理屈は、優しいようでいて非常に危険です。支援を必要とする人全てに公的福祉サービスを提供するためには、全ての人の生活実態を把握することが原理的に必要になります。「サービスを必要としていそうな人」を洗い出すためには、全ての人の生活情報を持っていなければならないからです。
これに対し、私的領域/公的領域の区別という、戦後日本で培われた原理を福祉分野に適用したのが「申請主義」です。すなわち、個人の私生活へ行政は不干渉とするのを原則としつつ、税金を原資として行政府が用意した給付メニューを利用したい場合は、当事者からの申請によらなければならないとする考え方です。
この申請主義であれば、当事者からの申請がなければ行政府による生活への介入は行われません。給付要件に該当するかどうかの調査も申請者に対してのみ行われることになり、プライバシー権の侵害もある程度抑えられます。
申請主義に対しては、
「公的福祉サービスを受けたいのに受けられない人が出てくる」
「自分の受けられる福祉制度がどれか、有るのかどうか分からない」
といった批判があります。
これについては、
「制度や申請方法を知る手段を増やす」
とか、
「役所の営業時間を伸ばす」
といった対処法が考えられますが、あくまで申請主義の枠組みの中で取り組むべきです。
他方、アウトリーチの場合は、全住民に対し、福祉サービスの条件に該当するかどうかを役所が網羅的に調べることになります。
申請主義とアウトリーチとを比べると、福祉サービスの給付件数・金額ともにアウトリーチの方が増える事になります。加えて、網羅的に調べるのですから、人件費を中心とした調査費用が膨らむことになります。
もし、他の公共事業を見直しして、
「福祉サービスAをアウトリーチで実施するために、別の福祉サービスBを廃止し、そこで浮いた人手と費用をAに回そう」
といった予算の組み替えをするのであれば、歳出の膨張をある程度は抑えることができます。
しかし、アウトリーチを主張する人々から、そういった意見を聞いたことがありません。福祉予算総額は膨らむ一方であり、同時に、行政府の権限と裁量も膨らんでいます。福祉メニューはどんどん増えて細分化・複雑化しています。左派も民族右派も、「福祉を拡充しろ」「きめ細かい福祉を」の一辺倒です。
冒頭、加藤陽子氏は
「国家が国民の私的領域を侵そうとしている」
と嘆いていましたが、これは安倍政権下だから生じた問題ではなく、きめ細かな福祉行政を望む国民が自分の首を絞めていただけの話です。福祉分野を中心に、行政府による私的領域への介入を大幅に認めてしまい、むしろ国民が国家からの介入を積極的に求めた結果、国家による思想・良心の自由への侵害のハードルが下がってしまったのです。
今回は、数年前の新聞記事がツイッターで流れてきたので、それをお題に「私的領域の保護とアウトリーチ福祉」について考えてみます。元ネタの新聞記事は、日本学術会議の任命拒否で話題となった6人の一人、加藤陽子氏が「私的領域と公的領域」について書いた文章です。(今回、日本学術会議には触れません。)
【私的領域の擁護】
国家が国民の私的領域を侵そうとしている 加藤陽子さん - 2017衆議院選挙(衆院選):朝日新聞デジタル 2017年10月6日======【引用ここから】======
世界中で国家と国民の関係が大きく変化しています。ここで国家とは行政府を意味します。世界では、国民の側が国家に「NO」を突きつけましたが、日本では国家の側から国民との関係を急速に変えた点が特徴的。今の混沌(こんとん)の理由も、ここにあります。
戦後日本が培った原理に、「私的領域」と「公的領域」の明確な区別があります。近代立憲国家として必須のこの原理に、安倍政権は第一次の時から首相主導で手をつけ始めました。
2006年に60年ぶりに改正された教育基本法では、前文の「真理と平和を希求」が「真理と正義を希求」に修正されました。「平和」は一義的ですが、「正義」の内容は価値観によって違い、国家が定義すべきものではありません。
明治の日本が学んだ西欧の憲法は、過去の宗教戦争の惨禍に学び、国民の思想や信条に国家の側は介入しないという良識を確立していました。だから、教育勅語という精神的支柱の必要性が説かれたとき、明治憲法の実質的起草者だった井上毅(こわし)は「君主は臣民の良心の自由に干渉」すべきでないとして反対しました。
結局、教育勅語は出されましたが、国務大臣が副署しないことで、政治上の命令でなくなった。国家は国民の「私的領域」に立ち入るべきではないとの良識が、この段階では保たれていたのです。
======【引用ここまで】======
日本が培ってきたはずの私的領域と公的領域の明確な区別が、近年崩れつつあります。
国家は国民の私的領域に立ち入るべきではない、全くもってそのとおりです。
私的領域と公的領域は明確に区別すべき、全くもってそのとおりです。
井上毅は、君主は臣民の良心の自由に干渉すべきでないと主張しました。
国家・行政府が国民の私的領域に立ち入ってはならないのです。
【私的領域の範囲は?】
ではここで、私的領域とは、思想・良心・内心の自由に限られるものでしょうか。それとも、財産権、プライバシー権、家族関係といったものも含まれる概念と捉えるべきでしょうか。私的領域を思想・良心・内心の自由に限定して捉えた時、公的領域はそれ以外という事になります。財産権、プライバシー権、家族関係等が公的領域となれば、行政府の管轄となり、管理・介入・指導・干渉の対象となります。この考え方を採用した場合、行政府は、個人の思想には介入しませんが生活には介入することになります。
「行政府は思想・良心・内心には立ち入りませんが、あなたの所有地に立ち入り生活状況を監視し介入します」というのは、実際のところ、私的領域/公的領域の区別を無意味にします。行動は思想の表れであるので、行動を監視し生活に介入できるのであれば、結局のところ思想そのものへの介入が可能になります。
思想・良心・内心の自由は、私有財産の保障が無ければ空虚なものとなります。財産権が保障されていなければ、思想に基づく表現行為も容易に制約できてしまいます。表現の自由はそもそも財産権の派生でしかない、という見方もできます。また、私的領域という日本語からは、私的な生活空間が含まれると考えるのが自然です。こうした観点から、私的領域の保障のためには、思想・良心・内心に限らず、財産権・プライバシー権、家族関係等も含めて捉え、これらをひっくるめた私生活全般に対し行政府は立ち入るべきでない、という考え方が、私的領域/公的領域の区別の重要なポイントになってきます。(うろ覚えですが、ハンナ・アーレントも、私的領域をかなり広く捉えていたように思います。)
【アウトリーチ】
さて、昨今、福祉・介護分野においては「アウトリーチ」という考え方が蔓延しています。アウトリーチ | 介護用語集 | 老人ホーム選びのパートナー ベネッセの介護相談室
======【引用ここから】======
本来は「手を差し伸べる」または「手を伸ばして取る」という意味。援助が必要な状態であるにもかかわらず要請をしない人たちに対して、支援者のほうから家庭などに出向いて手を差し伸べる「積極的な取り組み」のことをいう。
======【引用ここまで】======
福祉や介護の分野では、様々な論者が論者ごとに「あるべき生活水準」「あるべき生活様式」を設定し、これに適合しない生活をしているケースを全て掘り起こし、国民全員に漏れなく、健康で文化的な最低限度の生活をさせるのが行政の責務だ、という意見が幅をきかせています。そのための取り組みが、アウトリーチです。
こうしたアウトリーチの取り組みを、近隣住民や私的団体が行っている段階では、お節介で済むかもしれません。しかし、私的団体が自治体に繋いだり、あるいは、自治体が直接家庭を訪問して介入したりするようになると、私的領域/公的領域の問題が生じます。
アウトリーチ論が全面的に肯定された場合、全住民の生活が自治体の担当者の監視下に置かれます。プライバシーや自己決定権といったものが大きく後退し、個人の生活は公的領域に取り込まれてしまいます。
Aさん本人は現状を良しとしていても、第三者が
「私の考える『あるべき生活水準』に、Aさんの生活は達していない」
と判断し、Aさんの家の中に調査員が入り込み、行政や介護サービス事業者ら多くの人がAさんの生活に介入し、その費用を行政府に負担させるという事例が、介護分野を中心に多発しています。
また、特定の業種について、事業者に対し「廃業しろ」と声高に叫び、その業種の従業員に対し「辞めて福祉を使え」と主張する差別主義者・藤田孝典氏のように、独立生計を立てていた人の生活や仕事に干渉しわざわざ自治体に依存させようと斡旋し、その過程で手数料や補助金を得ようとする活動家も存在します。
アウトリーチの名の下に、私的領域は行政府の介入を受けています。個人の自由を守る防波堤が、アウトリーチ論によって穴を開けられています。
【申請主義の再評価】
アウトリーチを全面的に肯定した場合、行政府は網羅的に生活実態の調査し情報を収集する根拠を得ることになります。「支援を必要とする人全てに、申請を待たず、行政の側から福祉サービスを漏れなく提供しよう」
という理屈は、優しいようでいて非常に危険です。支援を必要とする人全てに公的福祉サービスを提供するためには、全ての人の生活実態を把握することが原理的に必要になります。「サービスを必要としていそうな人」を洗い出すためには、全ての人の生活情報を持っていなければならないからです。
これに対し、私的領域/公的領域の区別という、戦後日本で培われた原理を福祉分野に適用したのが「申請主義」です。すなわち、個人の私生活へ行政は不干渉とするのを原則としつつ、税金を原資として行政府が用意した給付メニューを利用したい場合は、当事者からの申請によらなければならないとする考え方です。
この申請主義であれば、当事者からの申請がなければ行政府による生活への介入は行われません。給付要件に該当するかどうかの調査も申請者に対してのみ行われることになり、プライバシー権の侵害もある程度抑えられます。
申請主義に対しては、
「公的福祉サービスを受けたいのに受けられない人が出てくる」
「自分の受けられる福祉制度がどれか、有るのかどうか分からない」
といった批判があります。
これについては、
「制度や申請方法を知る手段を増やす」
とか、
「役所の営業時間を伸ばす」
といった対処法が考えられますが、あくまで申請主義の枠組みの中で取り組むべきです。
【行政府の肥大化】
申請主義の場合は、申請者に対し、役所が把握している基本情報と申請書に書かれた生活情報とを照らし合わせて、福祉サービスの条件に該当するかどうかが判断されます。他方、アウトリーチの場合は、全住民に対し、福祉サービスの条件に該当するかどうかを役所が網羅的に調べることになります。
申請主義とアウトリーチとを比べると、福祉サービスの給付件数・金額ともにアウトリーチの方が増える事になります。加えて、網羅的に調べるのですから、人件費を中心とした調査費用が膨らむことになります。
もし、他の公共事業を見直しして、
「福祉サービスAをアウトリーチで実施するために、別の福祉サービスBを廃止し、そこで浮いた人手と費用をAに回そう」
といった予算の組み替えをするのであれば、歳出の膨張をある程度は抑えることができます。
しかし、アウトリーチを主張する人々から、そういった意見を聞いたことがありません。福祉予算総額は膨らむ一方であり、同時に、行政府の権限と裁量も膨らんでいます。福祉メニューはどんどん増えて細分化・複雑化しています。左派も民族右派も、「福祉を拡充しろ」「きめ細かい福祉を」の一辺倒です。
冒頭、加藤陽子氏は
「国家が国民の私的領域を侵そうとしている」
と嘆いていましたが、これは安倍政権下だから生じた問題ではなく、きめ細かな福祉行政を望む国民が自分の首を絞めていただけの話です。福祉分野を中心に、行政府による私的領域への介入を大幅に認めてしまい、むしろ国民が国家からの介入を積極的に求めた結果、国家による思想・良心の自由への侵害のハードルが下がってしまったのです。