【詳報】行橋市議による市有地不法占拠を巡る議会答弁 | 選報日本
======【引用ここから】======
質問者(下記枠内)は小坪慎也議員。
「行橋市議による私有地の不法占拠はあったのか?」
小森総務部長「平成27年の区画整理完了後から畑として使われている。顧問弁護士は不法な占有と」
松本副市長「顧問弁護士の判断で現場においては不法占拠という見解」
======【引用ここまで】======
この記事を読んで最初に感じたのが
「へぇ、ここの市役所に顧問弁護士がいたんだ!」
という驚きでした。
以前、当ブログにて、行橋市の使途不明金問題を取り上げたことがありました。この時に一連の報道を追いかけましたが、顧問弁護士が登場した場面を見た記憶がありません。
職員によって多額の使途不明金が発生した場合、他の自治体では、外部の弁護士や会計士の調査を経て、あるいは警察の捜査や裁判の状況を見て、当該職員に対し免職や停職といった懲戒処分を下しています。
ところがこの行橋市では、内部調査のみ。そして、文書訓告で済ませてしまっています。免職や停職と比べた時、文書訓告は遥かに軽い取り扱いです。
使途不明金疑惑の時に、顧問弁護士に調査を依頼していたら、果たしてどんな結果が出ていたでしょうか。
また、この使途不明金の調査に際し、行橋市は
「実行委員会の文書は、市の情報公開の対象外」
と判断し、領収書などを非開示扱いにし、情報公開請求や市議会委員会からの資料要求を断っています。この市の判断は、最高裁の考え方に明らかに反しています。
最高裁の見解を調べず、
「実行委員会の文書は非開示でいいですよ」
と意見する弁護士がいるでしょうか?
使途不明金疑惑の時、
前回の使途不明金疑惑の時は顧問弁護士の見解が出てこなかったのに、今回は顧問弁護士に相談しその見解を議場で紹介している、この差はどこにあるのでしょうか。
ここの行政は、誇りと威厳をもって、市民の方を向いて、多額の使途不明金を出した職員の処分を決定したのでしょうか。
また、二元代表制の一翼を担う市議会は、チェック機能を十分に果たし、この使途不明金の解明に全力を尽くしたのでしょうか。
刑法には「名誉毀損罪」というものがあります。
○刑法第二百三十条
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
国会議員の場合、国会での発言については憲法第51条により民事上・刑事上の責任を免除されます。しかし、これは地方議会には当てはまりません。地方議員には憲法上の免責措置は適用されません。このため、地方議会において個人名を挙げてその人の名誉を傷つけた場合、上記の名誉毀損罪に問われる可能性があります。
この点を配慮し、
(2) 令和元年9月定例会 本会議3日目(R元.9.11)②小坪慎也議員一般質問 - YouTube
======【テキスト起こし】======
5分15秒頃
田中議長「議長から申し上げておきたいと思います。固有名詞につきましては、注意をしていただきたいと思います。」
5分45秒頃
田中議長「議場内での発言について、議長から申し上げます。特定個人名を発言する場合には、個人の人権やプライバシー等、十分配慮した上で発言を行うこととする、ということが議会運営委員会の申し合わせ事項で規定をされておりますので、注意いたします。
======【テキスト起こし】======
と注意喚起されています。
こういう慎重を要するものであるため、休憩をとり、議会運営委員会で検討し直すことは決して無駄ではないと思います。
ところが、冒頭の報道の続編を書いた記者は、
======【引用ここから】======
まさかの「休憩動議」連続提出
「議事妨害」行為
======【引用ここまで】======
として、本会議を中断し議会運営委員会の開催を求めた動議を「議事妨害」と評価しています。
国会と地方議会の差異を考えた時、議場外の出来事を、個人名を伴って取り扱うことに慎重になるのは当然のことです。
この記者の評価に、私は賛同できません。
行橋市は、この令和元年9月11日時点で、市有地占有の違法性がどの程度のものか把握していたのでしょうか。田中市長は、市有地の管理のあり方を問われ、
「まことにごもっとも。異論はない。市民の通報で知ったことも職務怠慢で失態。管理不行届。市民に陳謝する」
「自ら処分する方向で検討する」
と、市長としての市有地管理責任について自らを処分する意向を述べていますが、およそ1ヶ月たった現時点で処分をしたという情報はなく、逆に、処分しないという発言をした報道すらあります。
土地占有にどの位の違法性があるのかを考える時、
といった諸要素があると思うのですが、これらを総合的に検討した上での「自ら処分する」発言だったのでしょうか。自らを処分しないという市長発言報道に照らすと、市長も、強い違法性があるような占有ではなかったと認めていると思えるのですが。
こうした中、

2019年10月5日 西日本新聞
======【引用ここから】======
行橋市副市長の突然の解職 市長「信頼できず」 松本氏「理解されず」
行橋市の松本英樹副市長(61)が田中純市長(73)から4日付の解職を通告されたのは、当日の朝だった。「君とは路線が違った」と告げられたという。辞職を勧めることもなく、突然の解職。田中市長は「辞職では甘い。私の意図を明確に伝えるため」と話す。市トップ2の間に、いったい何があったのか―。
記者会見した田中市長は、解職理由について「この4、5年、彼が私の補助機関として機能しているか、不満だった。それが臨界点に達した」と語った。数日前に決心したという。
市長が例示した小さな不満の積み重ねとは①市の政策を批判する言動が目立つ②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い③再建中のホテルを支援する企業の取締役に就任したが報告もなく何をしているか不明―など。「意思疎通できず、信頼できなくなった」のが最大の理由という。
一方、松本氏は「外部で政策批判などするはずがない」と反論。「意思疎通がなかったのは確かだが、事実関係を確認してほしかった」と不満を漏らした。また、市職員出身の松本氏は、事業の進め方などで職員から相談を受けることも多く、職員側に立った対応が「市長が求める働き方とはずれがあったのだろう」とも語った。 (石黒雅史)
======【引用ここまで】======
今回の不法占有に関する議会答弁も、解職理由として挙がっている
「②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い」
の一例に当たると述べているのが、この一般質問を行った小坪市議。
【行橋市】市長が、副市長を解職。市長「補助機関としての役割を果たしていないと判断」 | 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員
メモのやり取り等、振る舞いの部分に関しては、見た人の受け取り方次第なのかな、と思います。現場で生で見たら印象が違うのかもしれません。
では、答弁の内容はどうでしょうか。
例えば、
(2) 令和元年9月定例会 本会議3日目(R元.9.11)②小坪慎也議員一般質問 - YouTube
======【テキスト起こし】======
23分30秒頃
田中市長「・・・我々、行政が知りえたのが市民の方の通報によるということが、二重三重の意味で行政とすれば職務怠慢であり、ある種の失態であったと、管理の不行き届きであったという反省は十二分にして、重ねて市民の方に陳謝を申し上げたいと思っています。」
松本副市長「市長の発言のとおり、市の管理不行き届き、これがあったと思います。ただ、先ほど、前段で小坪議員の質問で、税金だとか賃借料の話がありましたけども、申し訳ない、そこの質問は前段の質問とちょっと矛盾しているんじゃないか、質問がですね、と思っています。なぜかといいますと、固定資産税ですから、個人の土地でないとかけられない。かけられないから公有地です。非課税。だから過去に遡ってかけられない、これは課税権の、忖度しているとか、そんなものでは全くありません。非課税だからかけられない。であればどうするかというと、先ほど総務部参事が答弁した、じゃあ賃借料で払っていただくということになります。ですから、私どもは、税金をまけるとかまけないとか、そんな話を我々はするつもりは全くありませんし、議員がそういう風におっしゃいましたけども、我々はそういうつもりで課税業務をやっているわけではありません。そこだけは言っておきます。」
======【テキスト起こし】======
・・・これが、市長の方針に反した答弁と言えるでしょうか。あくまでも市長答弁の補足の域を出ていないと思ったのは私だけでしょうか。市長答弁を補足するのは、まさに補助機関の役割と言えます。
これが市長の方針と反しているのであれば、市長は市有地の賃借料を払わせると同時に固定資産税を賦課しようとでもしていたのでしょうか。所有の意思の無い占有に時効取得は成立せず、市有地はあくまで市有地であり、固定資産税をかけることはできないという普通の話を補ったものが市長の方針に反するのであれば、市長の方針がそもそも誤っている可能性が出てきます。
「②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い」を理由として挙げるのであれば、具体的にいつのどの答弁なのか田中市長に聞いてみたいものです。①や③はよくわかりませんが、②を解職理由に含める辺り、この市長の器量・度量を窺い知ることができたような気がします。
(2019.10.27追記)
地方自治法
第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
======【引用ここから】======
質問者(下記枠内)は小坪慎也議員。
「行橋市議による私有地の不法占拠はあったのか?」
小森総務部長「平成27年の区画整理完了後から畑として使われている。顧問弁護士は不法な占有と」
松本副市長「顧問弁護士の判断で現場においては不法占拠という見解」
======【引用ここまで】======
この記事を読んで最初に感じたのが
「へぇ、ここの市役所に顧問弁護士がいたんだ!」
という驚きでした。
以前、当ブログにて、行橋市の使途不明金問題を取り上げたことがありました。この時に一連の報道を追いかけましたが、顧問弁護士が登場した場面を見た記憶がありません。
職員によって多額の使途不明金が発生した場合、他の自治体では、外部の弁護士や会計士の調査を経て、あるいは警察の捜査や裁判の状況を見て、当該職員に対し免職や停職といった懲戒処分を下しています。
ところがこの行橋市では、内部調査のみ。そして、文書訓告で済ませてしまっています。免職や停職と比べた時、文書訓告は遥かに軽い取り扱いです。
使途不明金疑惑の時に、顧問弁護士に調査を依頼していたら、果たしてどんな結果が出ていたでしょうか。
また、この使途不明金の調査に際し、行橋市は
「実行委員会の文書は、市の情報公開の対象外」
と判断し、領収書などを非開示扱いにし、情報公開請求や市議会委員会からの資料要求を断っています。この市の判断は、最高裁の考え方に明らかに反しています。
最高裁の見解を調べず、
「実行委員会の文書は非開示でいいですよ」
と意見する弁護士がいるでしょうか?
使途不明金疑惑の時、
顧問弁護士はいなかったのか、
顧問弁護士に相談しなかったのか、
顧問弁護士の意見を伏せ政治的判断を優先したのか、
顧問弁護士に相談しなかったのか、
顧問弁護士の意見を伏せ政治的判断を優先したのか、
前回の使途不明金疑惑の時は顧問弁護士の見解が出てこなかったのに、今回は顧問弁護士に相談しその見解を議場で紹介している、この差はどこにあるのでしょうか。
ここの行政は、誇りと威厳をもって、市民の方を向いて、多額の使途不明金を出した職員の処分を決定したのでしょうか。
また、二元代表制の一翼を担う市議会は、チェック機能を十分に果たし、この使途不明金の解明に全力を尽くしたのでしょうか。
【名誉毀損罪の可能性を考慮したのか】
さて。刑法には「名誉毀損罪」というものがあります。
○刑法第二百三十条
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
国会議員の場合、国会での発言については憲法第51条により民事上・刑事上の責任を免除されます。しかし、これは地方議会には当てはまりません。地方議員には憲法上の免責措置は適用されません。このため、地方議会において個人名を挙げてその人の名誉を傷つけた場合、上記の名誉毀損罪に問われる可能性があります。
この点を配慮し、
(2) 令和元年9月定例会 本会議3日目(R元.9.11)②小坪慎也議員一般質問 - YouTube
======【テキスト起こし】======
5分15秒頃
田中議長「議長から申し上げておきたいと思います。固有名詞につきましては、注意をしていただきたいと思います。」
5分45秒頃
田中議長「議場内での発言について、議長から申し上げます。特定個人名を発言する場合には、個人の人権やプライバシー等、十分配慮した上で発言を行うこととする、ということが議会運営委員会の申し合わせ事項で規定をされておりますので、注意いたします。
======【テキスト起こし】======
と注意喚起されています。
こういう慎重を要するものであるため、休憩をとり、議会運営委員会で検討し直すことは決して無駄ではないと思います。
ところが、冒頭の報道の続編を書いた記者は、
======【引用ここから】======
まさかの「休憩動議」連続提出
「議事妨害」行為
======【引用ここまで】======
として、本会議を中断し議会運営委員会の開催を求めた動議を「議事妨害」と評価しています。
国会と地方議会の差異を考えた時、議場外の出来事を、個人名を伴って取り扱うことに慎重になるのは当然のことです。
この記者の評価に、私は賛同できません。
【占有の違法性はどの程度か】
さてさて。行橋市は、この令和元年9月11日時点で、市有地占有の違法性がどの程度のものか把握していたのでしょうか。田中市長は、市有地の管理のあり方を問われ、
「まことにごもっとも。異論はない。市民の通報で知ったことも職務怠慢で失態。管理不行届。市民に陳謝する」
「自ら処分する方向で検討する」
と、市長としての市有地管理責任について自らを処分する意向を述べていますが、およそ1ヶ月たった現時点で処分をしたという情報はなく、逆に、処分しないという発言をした報道すらあります。
土地占有にどの位の違法性があるのかを考える時、
土地管理に関する担当職員の承諾、黙認等があったのか、
市有地の一般的な管理のあり方と比較してどうなのか、
他に市有地が無断利用されているものは無いか、
あるいは借地契約が切れて無権限利用が放置されているものは無いか、
原状回復が容易なのかどうか、
土地の利用者が支払うべき土地利用料は幾らだったのか、
市が管理していた場合に市が負担すべき維持管理費は幾らだったのか、
市有地の一般的な管理のあり方と比較してどうなのか、
他に市有地が無断利用されているものは無いか、
あるいは借地契約が切れて無権限利用が放置されているものは無いか、
原状回復が容易なのかどうか、
土地の利用者が支払うべき土地利用料は幾らだったのか、
市が管理していた場合に市が負担すべき維持管理費は幾らだったのか、
といった諸要素があると思うのですが、これらを総合的に検討した上での「自ら処分する」発言だったのでしょうか。自らを処分しないという市長発言報道に照らすと、市長も、強い違法性があるような占有ではなかったと認めていると思えるのですが。
【副市長の解職】
さてさてさて。こうした中、

2019年10月5日 西日本新聞
======【引用ここから】======
行橋市副市長の突然の解職 市長「信頼できず」 松本氏「理解されず」
行橋市の松本英樹副市長(61)が田中純市長(73)から4日付の解職を通告されたのは、当日の朝だった。「君とは路線が違った」と告げられたという。辞職を勧めることもなく、突然の解職。田中市長は「辞職では甘い。私の意図を明確に伝えるため」と話す。市トップ2の間に、いったい何があったのか―。
記者会見した田中市長は、解職理由について「この4、5年、彼が私の補助機関として機能しているか、不満だった。それが臨界点に達した」と語った。数日前に決心したという。
市長が例示した小さな不満の積み重ねとは①市の政策を批判する言動が目立つ②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い③再建中のホテルを支援する企業の取締役に就任したが報告もなく何をしているか不明―など。「意思疎通できず、信頼できなくなった」のが最大の理由という。
一方、松本氏は「外部で政策批判などするはずがない」と反論。「意思疎通がなかったのは確かだが、事実関係を確認してほしかった」と不満を漏らした。また、市職員出身の松本氏は、事業の進め方などで職員から相談を受けることも多く、職員側に立った対応が「市長が求める働き方とはずれがあったのだろう」とも語った。 (石黒雅史)
======【引用ここまで】======
今回の不法占有に関する議会答弁も、解職理由として挙がっている
「②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い」
の一例に当たると述べているのが、この一般質問を行った小坪市議。
【行橋市】市長が、副市長を解職。市長「補助機関としての役割を果たしていないと判断」 | 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員
メモのやり取り等、振る舞いの部分に関しては、見た人の受け取り方次第なのかな、と思います。現場で生で見たら印象が違うのかもしれません。
では、答弁の内容はどうでしょうか。
例えば、
(2) 令和元年9月定例会 本会議3日目(R元.9.11)②小坪慎也議員一般質問 - YouTube
======【テキスト起こし】======
23分30秒頃
田中市長「・・・我々、行政が知りえたのが市民の方の通報によるということが、二重三重の意味で行政とすれば職務怠慢であり、ある種の失態であったと、管理の不行き届きであったという反省は十二分にして、重ねて市民の方に陳謝を申し上げたいと思っています。」
松本副市長「市長の発言のとおり、市の管理不行き届き、これがあったと思います。ただ、先ほど、前段で小坪議員の質問で、税金だとか賃借料の話がありましたけども、申し訳ない、そこの質問は前段の質問とちょっと矛盾しているんじゃないか、質問がですね、と思っています。なぜかといいますと、固定資産税ですから、個人の土地でないとかけられない。かけられないから公有地です。非課税。だから過去に遡ってかけられない、これは課税権の、忖度しているとか、そんなものでは全くありません。非課税だからかけられない。であればどうするかというと、先ほど総務部参事が答弁した、じゃあ賃借料で払っていただくということになります。ですから、私どもは、税金をまけるとかまけないとか、そんな話を我々はするつもりは全くありませんし、議員がそういう風におっしゃいましたけども、我々はそういうつもりで課税業務をやっているわけではありません。そこだけは言っておきます。」
======【テキスト起こし】======
・・・これが、市長の方針に反した答弁と言えるでしょうか。あくまでも市長答弁の補足の域を出ていないと思ったのは私だけでしょうか。市長答弁を補足するのは、まさに補助機関の役割と言えます。
これが市長の方針と反しているのであれば、市長は市有地の賃借料を払わせると同時に固定資産税を賦課しようとでもしていたのでしょうか。所有の意思の無い占有に時効取得は成立せず、市有地はあくまで市有地であり、固定資産税をかけることはできないという普通の話を補ったものが市長の方針に反するのであれば、市長の方針がそもそも誤っている可能性が出てきます。
「②議会で市長の方針に反する答弁や振る舞い」を理由として挙げるのであれば、具体的にいつのどの答弁なのか田中市長に聞いてみたいものです。①や③はよくわかりませんが、②を解職理由に含める辺り、この市長の器量・度量を窺い知ることができたような気がします。
(2019.10.27追記)
地方自治法
第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。















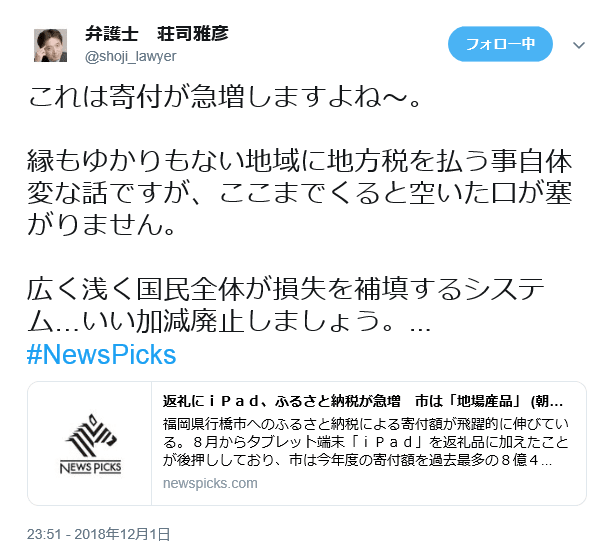

 Blomberg
Blomberg



