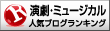小説学校時代 05
教師時代、しんどい仕事の一つが自習監督でした。
教師も人の子なので、病気もするし、よんどころない用事もあります。
で、そういう時は受け持ちの授業は自習になります。
これは昔も今も変わりません。
ただ、昔の生徒は「大人扱い」されていたので、自習監督の先生が自習課題などという野暮なものを持ってきて監視するというようなことはありません。
「6時間目と4時間目自習なんで、調整してきます」
てなことを言って、世話女房タイプの副委員長が職員室に掛け合いに行き、授業のコマを弄り、5・6時限を自習にしてクラス全員午前中でおしまいにするというような要領もかましていました。
むろん普通に自習になっても、自習監督の先生が来ることはありません。
無茶をやる生徒も居ましたが、たいていは教室か図書室で本当に自習していたように思います。自習時間中の早弁はおろか食堂で早めの昼食もOKだ。OKどころか、昼休みの食堂の込みようは尋常ではないので、合理的なことだと思っていました。
先生も生徒もハメをはずすことはめったにないので、こういうことができていた。平和な時代です。
もちろん、当時も後の時代で言うところの困難校はあったわけで、そういう学校の苦しさは後の時代と変わらないようで、クラブの用事で女子高に行った時、一年生の教室の前に『上級生は無断で一年生の教室に入ってはいけない 学校長』という張り紙に驚きました。
ごくごくたまに酔狂で自習監督に来る先生が居ました。
大方は生徒が好きな先生で、来ると一時間いろんな話をしていく。学校の裏話であったり、先生の自分史であったり、恋愛論であったり。あの頃の先生は大正生まれが中心で、年配の先生は明治生まれでありました。大陸や半島からの引揚者も多く、話の中身も分厚く豊かでした。
けして巧みな話術ではありませんが、実際に体験した人の話は面白いもんです。
戦争で乗っていた船が撃沈され丸二日間海に投げ出された人。疎開先でいじめにあった話。女郎屋でモテたことを話し半分に聞いたこと、モテたことはともかく、その中で話された学生やお女郎さんの生活、関東大震災の体験談、幼児の頃に見た「生きた姿の徳川慶喜」などというものもありました。
当時の高校生は、そういう話をきちんと聞くという習慣が身についていたし、下手な話でも頭の中でイメージする力が(今よりは)あったような気がします。
あの時代、まだ知性や経験で人を圧倒することができたし、そういう大人の知性や経験を、とりあえず生徒も尊重するという空気があったように思います。
あの時代、教師が、もう少しきちんと生徒に向いていたら、学園紛争や校内暴力による荒廃も、少しはちがったものになっていたような気がするのですが、どうでしょう。
先生が1時間目と6時間目の授業を忌避して講師につけを回しているようではどうにもならない、後の学校の荒廃は自明の理であったと言えるでしょう。
わたしの教師時代の自習監督は、大げさに言えば命がけでありました。
自習課題をやる生徒は半分もおらず、居ても10分ほどで適当に片づけてしまい、教室は無政府状態です。
「セン(先生という意味)、トイレ」「あ、おれも」「あたしも」「うちも」「拙者も」
一人にトイレを許可すると、クラスのほとんどが居なくなることもありました。居なくなった生徒は学校の内外で悪さをするので、身体を張って教室を死守する。対教師暴力の多くが自習監督時間内に起こっていたことでも困難さが分かると思います。
教務では自習監督表というものをつけていて、自分が出した自習と、請け負った自習監督数のバランスを取り不公平が出ないようにしていました。新任三か月で入院を余儀なくされたわたしは体調不良や通院で自習を出すことが多く、自習監督表を見るのがとても苦痛でした。
この項、続く……かもしれません。