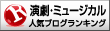少し怒ったような顔で、それでも約束の5分前に着いたT病院玄関前、栞はちゃんと待ってくれていました。
え?
家にいたころから、めったに目を見て話さない栞ですが、「朝からすまんなあ」の言葉に反応もせずに、じっと私の顔を見ています。
「どこに穴が開いてんの?」
「え?」
「目に穴が開いてんでしょ?」
「開いてんのは網膜だから外からは見えないよ」
「え、あ、そうなんだ」
「でも、白内障だから瞳が濁ってるだろ?」
「え、いや、お祖父ちゃん、昔からそんな目だったし」
何年かぶりで孫娘と目が合って、ちょっと嬉しかったのですが、それもほんの十数秒。
再び目どころか顔をそらせて私の斜め前を歩きます。
その斜め後姿は、久々に会ったからだけではない緊張感がありました。
思い出しました。
四歳の時、髄膜炎を患ってひどい目に遭っていたんです。
夜間に高熱を発して隣接するH市の病院に救急搬送されました。救急当直の医者は「多分風邪ですね、熱が続くようなら電話していただくか、かかりつけのお医者さんに行ってください」と、なにも処置されること無く帰されました。
帰宅しても、熱は下がることなく40度近くになります。意識も朦朧としてきた様子で、呼びかけにも応えません。
すぐに救急ではなく、掛かりつけの小児科に運びました。
何人か先客がいましたが、看護婦さんが先生に言ってくださって、すぐに診ていただけました。
「髄膜炎よ。こっちから電話するから、すぐ市民病院に行って!」
先生はタクシーの手配までしてくださって、そのまま市民病院に直行。運転手さんも心得ていて、救急搬送口に着けてくださって、すぐに診察の上処置していただきました。
その時、右手の甲と脊髄にぶっとい注射。おそらく手の甲は点滴、脊髄のが髄膜炎治療のための注射です。
「おねがいぃ! やめてくらしゃいー(><)!」
それまで熱で朦朧としていた栞が、そこだけははっきり叫んで泣いて頼んでいました。
あの時の恐怖が身に染みているんでしょう。
「治るんでしょ?」
待合で座っていると、横顔のままポツンと言います。
「ああ、治るさ」
答えながら、実はビビっておりました。
わたしも、自分のことで病院の世話になるのは15年ぶり。手術と名のつくものは42年ぶりです。
実は、栞と同じく4歳の頃に、目に鉄粉が入ってめちゃくちゃ痛く、一晩おふくろになだめられて眼医者に連れていかれました。
たぶん、そうとう怖かったんでしょう、眼医者でどんな治療を受けたのか記憶がありません。
どころか、眼医者がどんな人だったか、眼医者がどんな建物で、どこにあったのかまるで憶えていません。
「目を洗浄してもらった」
お袋がそう言って、子どものわたしは――くり抜かれた目玉がホーローの洗面器の中で洗われてるの図――を想像してしまいました。
『大橋さん、一番診察室へ』
呼び出しがかかって、栞に茶封筒を渡します。
「手術したらろくに見えないだろうから、支払いとかはこれで頼む。余ったら、栞の生活費にしたらいいからな」
「う、うん」
さすがに緊張した顔で茶封筒を受け取りました。
そして、簡単な手術が始まる……のかと覚悟したのですが、その日は改めて診察。一週間後の手術を決めるだけでした。
一週間後も付き添ってくれることを打ち合わせ、予定よりも早く終わったので「飯でも食いに行くか」と水を向けましたが「バイト、間に合うから……」と、そのままY駅目指して足早に去っていきました。
どうも、あれから一年半ぶりになります。
武者と朝顔を愛でながらスイカを食って、あくる日にもう一度話すつもりでおりました。
ですから副題も34『朝顔と西瓜・1』として、当然35『朝顔と西瓜・2』になるはずでしたが果たせませんでした。根気よく読んでくださっている読者のみなさんには申し訳ない限りです。
じつは、武者のやつ『朝顔と西瓜・1』の夜に頭の線が切れて救急車で運ばれましたが間に合いませんでした。
息子さんが家族葬で見送られたのですが、付き合いの古いわたしには声をかけてくれました。
おそらくは死んだという自覚も無いまま逝ってしまったのでしょう、昼寝をしているような穏やかな顔で棺に収まっておりました。
もう一年以上たつのですが、総括できずにおります。書けるようなら号を改めて触れられたらと思います。
ただ、息子さんは武者の遺言……というほどではないのですが、日ごろ『蛍の光』で送って欲しいということを、わりと真剣な顔で言っていたので、アカペラではありますが、全員で『蛍の光』を歌って霊柩車に乗せてやりました。
卒業式でもめったに歌われなくなった『蛍の光』でしたが、まだ日本人の血脈にはしみ込んでいるようで、会葬者全員が神妙になりました。
パァーーーーーーーーーーーーーーーン
歌い終わると同時に霊柩車のクラクションが長鳴きします。まるで武者が「さよならぁ、世話になったぁ」と最後の挨拶をしたようでした。
それから、明くる年、栞が家を出ていきました。
これは、大学進学なので仕方ありません。通学できない距離ではないのですが、かみさんも栞の学費用にと相応のものを残してくれていましたので無事に追い出せました。
最初は週に一度は戻って来ていたのですが、それがきっかけだったのか夏休みのバイトで、丸々ひと月空いて、それからは月一になりました。
この正月には帰って来ると言っていたのですが――松が明けたら帰る――とラインを寄こして『うん、楽しみにしてるよ』の返事には既読スルーのままです。
松が明けたらとは、わたしが教えてやった言葉です。
松の内というのは、昔は15日まで、この三十年くらいは7日までを指す言葉です。
はてさて、栞の松の内はどちらでしょうか。
まあ、こけつまろびつしながらも、自分の道を歩き始めている様子。了としておきます。
わたしは錆びの周った滅鬼の刃を、ゆっくり研ぎ直すところから始めることにします。
滅鬼の刃 エッセーラノベ
「ほう、懐かしいなあ」
声に振り返ると半玉のスイカをぶら下げた武者が立っています。
「せやけど、こんな北向きで育つんか?」
「昨日までは三階のベランダに置いたんだけどな、育ちすぎるんで移したんだ」
「なるほど、抑制栽培というわけか」
「まあな」
栞が近所の小学生に分けてもらった朝顔の種を鉢に入れ、日の当たるベランダに置いていたらノンノンと育ちました。
この調子では育ちすぎてしまうので、昨日から北側の玄関前に移したのです。
北向きなので、もう花は開かないかと思ったのですが、まだ余力があるのか、キチンと咲いています。
「栞ちゃんのやろ?」
「ああ」
付き合いの長い武者には、こういうことが似合わないジジイだと見抜かれています。
「昨日から、泊りがけでアルバイトに行ってるんで、ピンチヒッターだ」
「まあ、水と日当たりさえありゃ勝手に育つからなあ」
今日は一階の元ガレージだった和室で喋ります。
エアコンの電気代節約と、さっきの朝顔が見えるからです。
「子どもじみた花やけど、朝顔っていうのは、けっこう大人なんやなあ」
「ああ、大人だから、夏休みの自然観察にも使われる」
「そこへいくと、スイカいうのは、手のかかる子どもみたいなもんやろなあ……」
ペペ
ジジイ二人そろって種を吐き出します。
「わしらも朝顔みたいなもんやったなあ」
「ヒネた朝顔だ」
「教室いう植木鉢と、窓の日当たりさえあったら三年で卒業していった。あ、大橋は四年やったなあ」
「教室の日当たりが悪かったからなあ」
「ホームルームなんか、全部生徒でやってたなあ。学期の始めのホームルームでホームルーム計画話し合ったやろ」
「担任は横に座って聞いてるだけ」
「そうか、時どき口挟んでなかったか?」
「え、そうだったか?」
「グランドでバレーボールとかサッカーしたい言うたら使用許可とれよとか、音楽室借りてレコード鑑賞に決まりかけたら『音響機器は視聴覚部の許可』とか、お菓子買って来て茶話会言うたら『生活指導』と相談しとけとか」
「ああ、そういう意味か」
武者は逆説めいた言い方をしているのだと気付きました。
「憶えてるか、社会のS先生、卒業式でクラスの生徒の名前読み間違えたの」
「あ、せやったか?」
「東(ひがし)って男子を(あづま)って読んじまって、横の先生に『そのまんまヒガシです』って注意されて」
「あはは、もう二十年後やったら大爆笑やったやろなあ」
「下の方の名前は、もう詰まりまくりで、さすがにヒンシュクものだった」
「ああ、せやったっけ」
「あ、ああ……すまん、講師時代の話だった」
わたしは母校で三年間講師をしていたので、記憶がごっちゃになっています。
「て、いうか、S先生て担任したことあったんか?」
「え、ああ……」
このあたりは武者の方が記憶が正確です。わたしは――有ったこと――は聞憶えていますが――無かったこと――については曖昧です。
武者は在学した三年間でS先生が一度も担任していないことを憶えていたのです。武者は一二年上の先輩たちとも付き合いがあって、いろいろ情報を知っていたので、S先生が、ちょっと札付きであったことを生徒の頃から知っているようです。
それから二三の先生を思い出しながら、半玉のスイカの半分を平らげました。
「ええ話もあったよなあ」
先生の棚卸ばかりでは詰らないので方向を変えます。
「ええと……野球部が府大会で優勝した!」
「え、せやった?」
「応援賞で、一位とったぞ」
高校野球というのは部活動に励みが出るようにと、優勝・準優勝の他にも各賞を用意しています。
その中に応援賞というのがありました。
特に応援団やチア部があるわけでもなく、吹奏楽さえ廃部状態だったので、有志の生徒たちが自主的にチームを作って応援したことが評価されて応援賞をもらったことがありました。
「ああ、三島由紀夫の事件があった年かぁ……」
三島事件と重なったので、みんなの記憶から消えている……という、武者の気遣いなのですが、三島事件は11月。高校野球は7月でしたから、ハナから記憶にないのでしょう。
武者を見送って振り返ると、朝顔はすでに萎んでいました。
蕾が三つ四つあるので、まだまだ咲くでしょう。
せめて、午後だけでもと心変わりして、三階のベランダに戻してやりました。
明日の朝には一階に戻します。
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
- 武者走 腐れ縁の友人
滅鬼の刃 エッセーラノベ
ニオイの話が続きます。
「中学校のころ、理科室の匂いが好きだった」
「ああ、ちょっと酸っぱいような焦げ臭いようなニオイがしてたなあ」
「よく実験をやってたから、いろんな薬品が混ざったニオイだったんだろうなあ。ろくに換気扇も無かったから」
「理科部やったか化学部やったかかがあって、そこの三年生なんか、放課後は制服の上に白衣を着てたりしてさ、なんかそこだけ学校の平均的な雰囲気から突き抜けてたよなぁ……あ、中三の秋にU先生に呼び出されてな」
「ああ、職員室に居るよりも理科の準備室に居ることが多い先生だったなあ」
「『時をかける少女』で、主人公の七瀬は理科準備室でラベンダーの匂いを嗅いで気を失なってさ、タイムリープの能力を身に付けるやろ」
「あ、ああ」
武者もわたしも、中三から高校にかけて小松左京や筒井康隆をよく読んでいました。
「七瀬やないけど、理科室の匂いで運命が変わったんや」
「男七瀬か(^_^;)?」
「先生はなぁ進路指導の極秘資料を見せてくれたんや……ほら、進路希望調査をやったら、希望校ごとに成績順の資料作るやろ」
「ああ、懐かしいなあ」
自分たちも高校の教師でしたので、三年の担任をやった時は同じような資料をもとに進路指導をしました。
「『武者走、これがA高校を受ける生徒の一覧や』って言うてな見せくれんねん。バリバリの個人情報やで、80人分ほどあってよ、成績順にダーーって並んでるんや。真ん中あたりに赤い線が入っててなぁ、そこから下は受けても落ちるってことや、説得して受験校を変えさせようって、まあ、当たり前の指導やな」
「ドンケツだったのか、おまえ?」
「ああ、俺が担任だったら、ぜったい受けさせへん」
「先生、どう言ってた?」
「『武者走は、A高受験者の中ではドンケツや。ええか、2ページ戻ったとこに赤い線が引いたあるやろ。ここから下の生徒は受けても落ちる、ぜったい落ちる、必ず落ちる』って言って、俺の目をジーっと見た」
「無言の指導だなあ」
「ああ、あの目で見られたら、十五の中坊は絶えられへん」
「だろうなぁ」
「直ぐには返答でけへん、俯いたら、理科部の女の子の名前が目についてなあ……ほら、CKさん。六年の時は大橋のクラスやったやろ。むろん、赤線のずっと上やけどな」
「あ、ああ(゚д゚)!」
思わず感動の声が出てしまいました。
金曜ロードショーだったと思うのですが『ローマの休日』をやっていて、ヒロインのアン王女を見てビックリしました。アン王女の父の王様が日本女性と浮気したら、こんな女の子が生まれただろうという感じの美人です。
同じように感動した武者が、アン王女を演じたのはオードリー・ヘプバーンという女優さんなんだと教えてくれました。
「それでな――ぜったい受ける!――って決意したんや!」
「そうか、理科室の匂いが、それを増幅したんだな」
「いや、そうなんやけどな。CKさんの白衣は、いつも洗濯したての匂いがした」
「おまえ、嗅いだのかぁ?」
「ちゃうちゃう、狭い廊下やから、すれ違うと匂うんや」
「わざとすれ違ってたんだろ、理科室は南館の一階だから、用事が無きゃ行かねえとこだぞ」
「用があったんや、用が」
「用がなあ……まあ、いいけどな(*¬_¬*)」
「それで、併願することを条件に認めてもらってなあ……」
「ジジイが遠い目をすんな、気持ち悪いぞ」
「思うんや」
「なにを?」
「もし、あの進路指導が教室でやられてたら、オレ、A高校は受けてへんかったと思う」
「ん? 教室でも同じ指導だろうから、CKさんの名前は見えただろーが」
「ああ、けども、あっさり志望校は変えてたと思う」
「え、どうしてだ。CKさんの思い出は変わらんだろう」
「いや、理科室のニオイとのコントラストがあったからこそやったと思う」
「理科室の臭いで、CKさんの匂いが際立ったって言うんなら、ちょっと……フェチめいてないか。怪しいぞ」
「洞察力のないジジイやなあ」
「なんだ、仕返しか?」
「確かにな、理科室のニオイは妖しくて変なニオイや。そのニオイの中で化学部の実験やってる彼女は、ちょっと妖しいやないか。ほんの5%ほどやけど、お仲間て感じがしてな……ん、臭わへんか?」
「え……」
なんだか、理科実験のような臭いがしてきました。
ゲホゲホゲホ
階下で栞が咳き込む声がします。
「どうした、栞!?」
ゲホゲホゲホ
「ちょっとヤバイいぞ」
「栞!」
階下に降りると、窓やサッシを全開にして栞が咳き込んでいます。
「ごめん、お祖父ちゃん、風呂掃除してて、洗剤注ぎ足したら……ゲホゲホ」
「あ、栞ちゃん、似たボトルやけど、メーカーが違うよ!」
風呂場から、洗剤のボトルを取り出して、庭に放り出す武者。
我が家にも新しいニオイの記憶が刻み込まれました(;'∀')。
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
- 武者走 腐れ縁の友人
滅鬼の刃 エッセーラノベ
この暑いなか、武者は回転焼きを持ってやってきました。
「昔は、たこ焼きやってる店やったら回転焼きもやってたけどなあ、いまは回転焼きやってる店はめったにない。それが、M駅の近くで見つけてなあ、嬉しくなって買うてきた」
「このクソ暑いのに、元気なじじいだ」
「もう年やねんからさ、一期一会やろ。涼しくなってからなんて思てたら命がないかもしれへん」
「ハハ、まあいいさ、茶でも淹れよう」
「うんと熱いやつな(^▽^)/」
「はは、なんだか我慢会になりそうだ」
「そういやなんやなあ、夏場は冷やし飴とか冷やしコーヒーとかもやってたなあ」
「うんうん、でっかい氷をいくつも入れたとこに入ってて、柄杓ですくってコップに注いでくれるんだ」
「そうそう、二口目か三口目で、こめかみのあたりがキーーンと痛なってきよるんや」
「夏の風物詩だったなあ」
「冷房とかは無かったけど、昼過ぎになると、近所のおばちゃんらがホースで水撒いとったなあ」
「うんうん、小さな虹が立ったりして、水のニオイがしたっけなあ。水なのに、ちょっとかび臭くってさ。あれは一種の化学反応なのかなあ」
「あれは、飛び散った水滴が地面の砂やら埃を含んでて、それのニオイやて話やぞ」
「そうなのか?」
「ああ、せやから、アスファルトやコンクリートの道は匂えへん」
「なるほどなあ……そういや、昔の学校ってニオイがしたなあ……」
「ああ、そうやなあ……」
回転焼きから、ジジイ二人の話は学校のニオイになってきました。
「昔の学校って床も廊下も板張りだったから油のにおいがしたなあ」
「うん、学期に一回ぐらい油引きしてたなあ、登校して油のにおいがすると、なんか新鮮な気持ちになった」
「あの油びきって、子どもがやってたっけ?」
「ああ、技能員室でバケツに入った油とモップをもらってさ、やってた」
「え、そうかぁ、それってワックスがけと勘違いしてないか?」
わたしたちが現場の先生になったころは、どこの学校も教室は木のタイル張りで、これは油では無くてワックスでした。どちらもモップを使いますがにおいも見た目も全然違います。
「子供にやらせてたかなあ?」
「武者はやってないのか?」
「どうやったかなあ……生徒といっしょにやったことはあるけど、自分が子どもやったころはやってないかなぁ。先生らの仕事やったんやないのか?」
「低学年は先生がやってたけど、高学年は児童がやってたぞ」
「え、あ、そうかぁ……」
「おまえ、ずっとサボってたんじゃないのか?」
「あはは、よう逃げてた(^_^;)」
「それで、現職になってからは主に生徒にやらせてた?」
「ああ、教育の一環や。最初とか、時どきはいっしょにやってたけどなあ」
「女子とだろう」
「ああ、制服汚れたらかわいそうやからなあ」
思い出しました。武者もわたしも学校の先生をやっていましたが、同じ学校に勤務したことがありません。
「武者、おまえの最後の勤務校はKだったと思うんだけど、その前は、どこだ?」
「あ、ああ、NとH」
「イニシャル合わせたら、NHKか」
「え、あ、ほんまや。あははは」
ちょうどお湯が沸いたので、話題をもどす昼下がり。
ついさっきまで喧しかった蝉の声が、いつの間にか止んでいました。
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
- 武者走 腐れ縁の友人
滅鬼の刃 エッセーラノベ
武者走は、よく武者小路と間違われていました。
武者走という苗字は稀で、武者小路は、みなさんご存知のように白樺派の大作家であります。
学校の教科書や副読本にも必ず出ていて、作品を読んだことが無い人でも名前は知っておられるでしょう。
飲み屋のお品書きの横に――仲良きことは美しきかな――と書かれた野菜の絵がありますが、あれの作者です。
武者走のフルネームは武者走幸次(むしゃばしりこうじ)と云います。
約めれば「むしゃこうじ」で、武者小路と言っても、そうそう間違いでもないというのが奴の理屈です。
郵便物も『武者小路』と誤記されていても、ちゃんと届くそうです。
「でも、一度だけ新米の郵便屋が『武者足さんのお宅でいいんでしょうか?』って訊ねてきやがった」
「むしゃたり?」
「ああ『むしゃたり』って読みやがった(^_^;)。それ以来、武者小路の表札も出したある」
「アハハハ」
お茶を出しに来て、そのまま居ついてしまった栞も笑います。
「武者のおじさん、よかったら晩ご飯食べてってください。スーパーの朝市でしめじいっぱい買っちゃったから炊き込みご飯にするんです」
「おお、そりゃありがたい。今日は息子夫婦も出かけてるから、コンビニ飯で済まそうと思ってたところや」
「じゃ、味には文句言わないってことで承ります(^▽^)」
タタタタ
古希のジジイには真似のできない軽やかさで階段を下りて行きます。
「いい娘さんになったなあ」
「その分、こっちもいいクソジジイになったけどな。で、初回のネタはなんだ?」
「おっと、その前に電話しとくわ」
武者はスマホを持って廊下に出ます。
『……おお、おれおれ。今日は大橋んちで飯食って帰るから、あ、ああ、憶えてるぅ。とちくるって晩飯買って帰らんようにな「念のため電話」や。じゃあな、勤労中年』
「あいかわらず、声でかいなあ……」
「あはは、お互い小声じゃ通じひん職場におったからなあ」
「そうだな」
「息子にはウザがられてるけどな。連絡やら情報は、直に音声で伝えるのが基本や」
「確かにな」
「そういや、中学のH先生は声でかかったなあ」
「あ、ああ……」
何年かぶりでH先生を思い出しました。
転任の挨拶で朝礼台に立ったH先生は、地声で「気を付けえっ!!」とかましました。
1200人の生徒が、ビシっと気を付けになります。
人の体というのは吸音体で、それが露天のグランドに1200人も居るとマイクを通さない声など届くものではありません。
70年の人生で、大声の人間に二人で会いましたが、二人とも恩師あるいは先輩の先生です。
H先生は旧海軍の御出身で、乗っていた艦が魚雷にやられて、まる一日フィリピンの海に浮いておられました。
「先生の腕の傷、見たか?」
「あ、ああ……」
元気な先生で、受け持ちの体育の授業は、冬でも半袖を通しておられ、右腕の傷がよく見えました。
ただ、先生自身が無頓着で、明るく授業をやられるので、いつのまにか生徒も気にしなくなりました。
「あのころのオッサンは、チラホラ居たなあ……」
昔は銭湯でしたので、たまにそういう人を見かけました。
たいていは、戦時中の傷です。そして、たいていは銃創であったり、破片に肉を持っていかれたりの傷でした。
「火傷のケロイドいうのもあったなあ」
「あ、ああ……」
ごく小さいころは、お袋に連れられて女風呂に入っていました。
数は少ないのですが、女性の中にもそいう方がいらっしゃって、子ども心にも驚いた記憶があるのですが、ジロジロ見たりはしません。大人たちの態度で見て見ぬふりをするものだと思っていました。
「そうやったなあ、あのころの風呂屋は教育の場でもあった。せやけど、H先生の傷は、ちょっと違たやろ」
そう言われて思い出しました。
先生の傷は二の腕にあって、少し欠けているのですが、欠けた周囲には歯形のようなものがついていました。
だからかもしれません、先生の傷のわけを聞いた話は聞いたことはありません。
それを武者走は聞いたようなのです。
「あれはなあ、魚に食われた痕やそうや」
「魚に?」
「うん、漂流して、ほとんど死んでもたようになってると、ごく普通の魚が食いにくるそうや。魚は、みんな肉食やからなあ」
「え、そうなんか……」
こういう秘密めいた話は、驚いたり感心した方が負けです。
こっちも一発かまします。
「海軍にはな、高声電話というのがあった」
「こうせい電話?」
「ああ、高い声の電話と書く」
古本屋で『丸』というミリオタ雑誌を見ていたので、少しばかりは知識があります。
「海軍は艦内通信には伝声管を使っていたんだけどな、なかなか明瞭には伝わらなかったので、音量を電気的に増幅して伝える電話が使われるようになった」
「へえ、そんなものがあったんか?」
「ああ、海軍は進んでいてな。新造の大型艦には冷房もあったし、照明は蛍光灯だった」
「え、蛍光灯なんて、俺の家は小学校に入ってからやったで」
「うちも、そうだったけどな。あ、高声電話。それをH先生に聞いてみたことがあるんだ」
「『ああ、あれはな、大きな声でなきゃ通じないから高声電話っていうんだ』だ、そうだ」
「え、そうなんかぁ」
「それで、遠くに味方の船が見えて、ここ一番の大声を張り上げたら気が付いて助けられたそうだ」
「あ、ああ、なるほど……」
けっきょく、第一回目の内容に踏み込むことも無く、武者は栞のしめじご飯を食べて帰って行きました。
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
- 武者走 腐れ縁の友人
滅鬼の刃 エッセーラノベ
『お祖父ちゃん、お友だちがいらっしゃったわよ!』
図書館に行くと言っていた栞が階段の下から呼ばわります。
ドアホンの調子が悪いので、来客は玄関の戸を叩いています。
「はい、どちらさまでしょうか?」
「○○と申します、大橋さんは御在宅でしょうか?」
「あ、祖父ですね、少々お待ちください」
というやり取りがあって、最初の『お祖父ちゃん、お友だちがいらっしゃったわよ!』に繋がります。
栞は、こういうところがあります。
来客があると、その声の調子でおおよそのところを察してしまいます。
セールスや勧誘などは、いちいちわたしに次げずに対応し、たいていは撃退してしまいます。
わたしへの来客も、勘なのか、どこかで憶えたのか「町会の○○さん」「公〇党の▢▢さん」「共〇党▢▢さん」「同窓の○○さん」「お友だちの○○さん」と告げる、あるいは呼ばわります。
小さな家なので、たいてい栞の声も来客に聞こえてしまいます。
単に「お客さ~ん」とか「誰か来てるよ」ではそっけないと思っているようです。
来客も「お友だちの~さん」などと呼ばれると気分が良いようで、栞の評判は上々です。
一度「お友だちの○○さんよ」と言って失敗したことがあります。
やってきたのは、友人○○の息子でした。
前の月に○○は亡くなっていて、葬儀の後、遺品の整理やら連絡を手伝ったお礼に息子さんがお礼に来たのを間違えたんですね。声がよく似ていたので、つい間違えたのです。
栞は恐縮していましたが、息子の方は「ひょっとしたら、親父も付いてきたのかもしれません」と床しく思ってくれました。
さて、今日の来客は武者走といいます。
お気づきになったかもしれませんが、わたしのサブペンネームが武者走で、こいつの苗字をそのまま使わせてもらっています。武者走はずっと高校の先生をやっていたのですが、再任用も五年前に終わって、暇を持て余している不良老人です。
「もう古希も超えてしもたし、ちょっと現役時代のことを振り返っとこと思てなあ。自分で書いてもええねんけど、お前以上に根気も文才もあれへんし、ブログに書いてアクセス少なかったら凹むしなあ。お前やったら、しょっちゅう書いてて慣れてるやろ。気の向いた時でええからさ、まあ、散歩のついでに寄って語る感じでさ、文章にしてくれへんか」
「その気の向いた時っていうのは、俺のか? お前のか?」
「あはは、まあお互さまや(^_^;)」
そこへ、栞がお茶を持ってやってきました。
「なんだ、図書館行くんじゃないのか?」
「ふふ、こっちの方が面白そうだし。お祖父ちゃん、引き受けたら?」
「簡単に言うなよ」
「お祖父ちゃんもネタ切れで、ここのところ停まってたじゃない」
「そうか、ひんなら話は決まりや!」
「おいおい」
「おいおい書いてくれるんだそうです」
「そうか、話は決まった。そうや、記念に一杯やろうや。栞ちゃん、お代は俺が持つからデリバリーでなにか頼んでくれへんか」
「あ、やったー! 晩御飯の心配無くなったぁ(^▽^)/」
ピザと寿司と缶ビールで盛り上がり、肝心の記事のネタは次回からと言うことで、迎えに来た息子に介抱されながら悪友は帰っていきました。
はてさて、どうなることやら。
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
- 武者走 腐れ縁の友人
滅鬼の刃 エッセーラノベ
うっかり同じテーマで二回書いてしまいました。
23回と28回、タイトルも同じ『元日の新聞』で、いやはや焼きが回りました。
28回目を書き終えて、三日目に栞に指摘されました。
「え、そんな馬鹿な……」
「ほらぁ(^_^;)」
「あちゃ~~」
それで、今日は『二回目』をテーマに書いてみようと思い立ちました。
五十数年前、うかつにも高校二年を2回やってしまいました。
早い話が落第したわけです。
当時、生徒の身でありながら高校演劇の役員をやっていたわたしは、年度末の役員会を終えて帰宅して、茶の間の沈鬱な空気に――ヤバイ――と思いました。
小学校に入って間がないころ、いつもとは一本違う道に入り込んで、大きな野良犬と目が合ってしまったことがあります。あの時の――ヤバイ――に似ていました。
お袋は、担任の先生と、もう一人えらい先生が来て留年を宣告していった事実を目を合わせることも無く伝えました。
親父は、こんな話をしました。
わたしには、三つ年下の妹がいたと言うのです。
わたしには三つ年上の姉がいて、ずっと、その姉との二人姉弟だと思っていました。
姉は、勉強も出来て、弟のわたしから見ても器量よしで、しっかり者の姉ちゃんでした。
ところが、わたしが生まれた三年後、三人目が宿ったことが分かって、親父とお袋は堕ろすことに決めました。当時の家計では三人目を育てることは無理と判断したんですね。
「……女の子だった」
そんなつもりは無かったのかもしれませんが、言外に、女の子が生まれていたら――きっと落第などしないいい子だったろう――という、強烈な残念さを感じました。
高校二年というのは修学旅行のある学年です。ご丁寧に、二度目の修学旅行にも行きました。
わたしが親なら「バカモン! 二回も修学旅行に行くやつがあるか!」と叱っていたでしょう。
親父は、あっさりと二回目の修学旅行費を一括で払ってくれました。
修学旅行は二回目も同じ信州方面。同じコースを同じバス会社のバスで、あれ?っと思ったらバスガイドさんまで一回目と同じ人でした(^_^;)。
留年と修学旅行に関しては面白い話もあるのですが、それは、また別の機会ということにします。
二回目というテーマに戻ります。
ちょっとした運命のいたずらで孫娘の栞といっしょに暮しています。
娘の娘で、正真正銘の孫娘なのですが、早くに引き取ったので、なんだか子育ての二回戦という感じです。
栞も「二回目の父親だ!」などと言って、境遇を面白がっているように言います。
わたしも「二回目の娘だ!」と言って調子を合わせております。
これも踏み込むと奥が深すぎますので、主題に入ります。
主題は「二回目の人との接し方」です。
大人になってからでも半世紀以上生きておりますと、初対面の人とはソツなく接するようになります。あるいは出来るようになります。
「どうも、お世話になります」「大橋と申します」「武者走などと大層なペンネームですが」「いやあ、今日は暑いですねえ」「お噂はかねがね」「ごいっしょさせていただきます」「お隣り、よろしいでしょうか」「あ、そうだ」
切り出し方はさまざまですが、切り出して、その反応で(あまり話しかけない方がいい)とか(この話題でいこう)とか(こっちの話の方が)とか感じながら接していきます。
友だちがイタ飯屋を経営していて、仕事の帰りなど看板までいたものですが、テーブルが二つに、カウンター席が八つほどでしたので、ちょっと客同士の距離が近いのです。
その客も、友人であるマスターの友だちや知り合いが多く、こちらもマスターの友人。場合によっては「こいつ、古い友だちで大橋っていうんだ」的に振られます。
こういう時に「あ、ども」だけでは、なんとも素っ気なさすぎるので、まあ、互いに気を遣ってしまう訳ですね。
それで、話題を探るわけです。
持病で、月に一回病院に通っていました。十年ほどはお袋の車いすを押して週一回病院に連れていきました。二年ほどは父を別の病院に、老人ホームにも通いました。
待っている間に、隣の人と話になることもあります。こちらは馴染みの患者、あるいは付き添いなので、病院や施設の事情にも詳しいので、時どき訊ねられます「薬局はどちらでしょう?」「待ち時間長いですか?」「問診票のここ、どう書くんでしょう?」「トイレどこでしょう?」「ちょっと見ててもらえます?」など、ちょっとしたやり取りなのですが、病院の待ち時間は一時間を超えることはザラなので、控え目にしながらも話すことがあります。
そういう人たちと、二度目に会った時が、ちょっと厄介です。
「あ、先日は……」
向こうから話しかけてこられたり、話しかけるのではなく目礼などされると、話さざるを得ません。
そうすると、もうなおざりな話では済まないような気になって、話題を考え、返事を考えしたりできりきり舞いになってしまいます。お天気の話がいちばん無難なんですが、そうそうお天気の話ではもちません。趣味の話は押しつけがましいし、そうだ、前回はなにを話したっけ、えと……えと……。
一番困るのは――え、知ってるようなんだけど、どこで会ったかな? 勘違いかなあ?――とか悩みます。
あ、二回目なんだけど名前が出てこない! えと……お名前は……(-_-;)
「あ、先日はどうも(^_^;)」と、適当に先手を打って「え、初めてですが?」的に返されたら目も当てられません。
間違いなく――適当なやつだなあ――と思われます。
さらに困るのは、こちらが最初気づかなくて、相手が先に気付いて――失礼なやつ、シカトしやがって――と気まずくなる時ですねえ。
電車の向かいのシートで、なんだか不機嫌な年寄りが座っていて――なんだ、この爺さんは?――と視線を避け、しばらくしてから――あ、先輩だ!――と気づいたあとの気まずさ(-_-;)。
ププ( ´艸`)
ここまでキーボードをたたいていると、後ろで二回目の娘が噴き出しました。
「もう、神経質な文章書いてぇ、もう、お風呂入ってしまってよね」
「え、晩御飯まだだぞ」
「え……」
真顔になる二回目の娘。
「え、あ……ハハ、うそうそ」
冗談でかましたのですが、翌朝、学校に行くまで心配そうな顔をされたのには参りました(^_^;)
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
滅鬼の刃 エッセーラノベ
元日の新聞を一文字も読むことなく古紙回収に出してしまいました。
幼稚園の頃には、ろくに文字を読めないにもかかわらず読んでいました……いや、眺めていたというのが正しいでしょうか。
ヘッドラインの文字の面白さや、写真の面白さ、四コマ漫画、風刺漫画、広告の新鮮なデザインなどを子ども心に楽しく眺めていました。
くしゃ~み三回 ルル三錠♪
風邪薬のフレーズは、テレビが来る前に新聞の広告で知っていました。
そうそう、夕刊だったと思うのですが、連載小説も面白かったですねえ。
うちは、ほとんど産経新聞でした。おかげで、朝日や毎日の色には染まらずにすみました。
むろん、子どもが新聞の銘柄を選ぶわけはなく。大正生まれの両親の都合です。当時は、産経が他紙よりも安かったのが理由でしょう。
あ、連載小説です。
産経の連載と言うと、わたしぐらいの歳では司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』ですね。小学生には難しい字がいっぱいありましたが、日露戦争の旅順攻略、203高地のくだりや、奉天会戦、日本海海戦などは拾い読みでしたがワクワクして読んだ、いや眺めていました。
203高地を奪取に成功したと聞き、児玉源太郎が、すぐに野戦電話を掛けるところがあります。
「旅順港は見えるか!?」
電話を受けた隊長が、こう言います。
「はい、丸見えであります!」
丸見えという言葉が面白く、また雰囲気を良く表しています。子ども心にも嬉しくて、安心して思わず笑ってしまいました。旅順の下りは長くて三か月ぐらいやっていた記憶がありますので――やったあ!――というカタルシスがありました。
小学生でも、ある程度は読める、眺められるようにお書きになった司馬さんはすごいですね。
まだ、ろくに字が読めない頃は、小説の真ん中に載っていた挿絵を眺めて喜んでいました。『坂の上の雲』の前は今東光氏の『河内太平記』でした。文章はさっぱり読めませんでしたが、挿絵は、子どもの目ではありますが漫画的に面白く、納得もしていました。
例えば、戦で人の首を獲る時は、相手をうつ伏せに組み伏せ、兜の眉庇に手をかけ喉首を晒して、鎧通で一気にかき切るのを見てなるほどと思いました。テレビや映画では、馬乗りになって突き刺したら、次の瞬間に首が取れていたので納得していなかったんですね。
挿絵の人物の描写も、時には三頭身や四頭身。戦の様子などは幼稚園で見た猿蟹合戦と被ってワクワクしていました。
あ、また少しずれてますねえ。元日の新聞です。
元日の新聞は、一面と他の何ページかがカラー印刷でした。今でこそ、新聞の色刷りは当たり前ですが、当時は新鮮でした。三つ上の姉が、富士山の写真が載っているのを見て「うわあ、天然色やあ!」と叫んでいました。
当時は、カラーとは言わずに天然色でした。
カラーという言葉が天然色を凌駕するのは、カラーテレビの普及と重なっていると思います。
テレビ欄は、普段の夕刊ぐらいの別冊になっていて、三が日分のテレビ番組表が載っていて、新番組の特集とかがあって、本紙よりも家族で取り合いでした。
東海道新幹線のことを『夢の弾丸列車』という見出しで出ていたのは、ローマオリンピックの次の年の元日の新聞だったと記憶しています。紙面の半分近くが新幹線の完成予想図、いや、イラストでした。そして、三年半後、新聞の通りの新幹線が開通し、首都高速が開通。親父の給料もボチボチ上がって、ひょっとしたら高校ぐらいは行かせてもらえるかと思いました。
なんというか、自分の成長と日本の成長が並行していて、世の中は、どんどんいい方向に向かっているんだと思えました。むろん、不便なことや、しんどいことも多くありましたが、総じて面白い時代ではありました。面白さの予感と元日の新聞の分厚さと天然色ぶりが重なりました。
今年の元日の新聞は、孫の栞が年賀状といっしょにポストから出してくれていました。
「あれ、お祖父ちゃん読まないの?」
上目遣いに聞いてきました。
「え、ああ、あとでな」
実は、年賀状を見ているうちに忘れてしまったのです。
おでこの一つもたたいて「あ、いかんいかん」と座りなおせばよかったのですが、栞の目つきがお見通しと言う感じで、つい見栄を張って、とうとう読む潮を失ってしまいました。
廊下の古新聞の山に置いてあるのは承知していましたが、昔の少年雑誌並みに分厚い新聞が目に留まると、ついつい日延べになって、今朝気づいたら栞が他の古新聞もろとも縛ってしまっていたという次第です。
嗚呼、やんぬるかな!
☆彡 主な登場人物
- わたし 武者走走九郎 Or 大橋むつお
- 栞 わたしの孫娘
滅鬼の刃 エッセーラノベ
鼻歌を口ずさむってことありますか?
週に五度くらいは散歩に出ます。たいてい自転車で、10~20キロ、時間にして1~2時間。時には30キロを3時間くらいかけて走ります。
春や秋、お天気がいいと、つい鼻歌が口を突いて出てきます。
レパートリーに脈絡はありません。フォークソング、アニソン、オールディーズ、ポップス、どうかすると、インターナショナルの次に轟沈を口ずさんでいることもあります。
人生のあちこちで聞いたり憶えたりした歌が、脈絡があったり無かったり、浮かんでは口から出てきます。
十八番というか、よく出てくる歌があります。数えたことはありませんが、十八曲以上あることは確かです(笑)
そんな十八番の中に『ここに幸あり』があります。
嵐も吹けば~風も吹く 女の道よ何故険し~ キミを頼り~に~ わたしは~生きる~♪
ジェンダーフリーの方々からはNGで、張り倒されかねない歌詞なのですが、春や秋の晴れ渡った空の下を走っていると、似つかわしい歌です。わたしの中では『青い山脈』と双璧の人生の応援歌であります。
鼻歌というのは、歌っている本人は気持ちのいいものです。ですが出くわした人には、いささかはた迷惑なものですから、人が多いところ、踏切や横断歩道では中断します。
たまたま周囲に人影のない公園横の横断歩道で、歌いきりが悪いので「ここに幸あ~り、あ~おいそ~ら~♪」と歌いきってしまったことがあります。
「いやあ、テレビ結婚式やねえ(^0^)」
わたしより5~6歳は年上と思われるオバアサンが斜め後ろから声を掛けてこられました。
不意打ちでもありましたので、アハハと不得要領に愛想笑いするしかありませんでした。
横断歩道を渡って思い出しました。たぶん花王石鹸かなにかがスポンサーであったと思うのですが、テレビで結婚式の中継をやる番組がありました。
幼稚園か小学校の低学年のころですから、昭和の三十年代でしょう。
徳川無声さんの司会だったと思います。
毎週見ていたわけではありませんが、なんだかドキドキして神妙に見ていた記憶があります。
たいてい横で、お袋が内職の針仕事をやっています。
共に大正十四年生まれの親父とお袋は、終戦間もない時に所帯を持ちましたので結婚式をあげていません。
子ども心に、ちょっとまずいかなあ……と思いながらも、その緊張感と晴れがましさが刺激的で、チャンネルを変えられませんでした。
調べると、最初の頃は有名人の結婚式などをやっていたらしいのですが、わたしの記憶では一般募集で当選した三組ほどのカップルが同時に式を挙げておられたような記憶があります。
中には、すでに結婚していて、わけあって式を挙げられなかったご夫婦なども出ておられたような記憶があります。
戦争で瀕死の重傷を負った同士で結ばれたカップルがおられました。
徳川無声さんが、しみじみとお二人の越し方を述べられるのですが、参列している親族知人の方々もことごとくが戦争体験者であります。あちこちから忍び泣きや嗚咽が聞こえてきます。
シンとしていると思ったら、お袋が裁縫の手を停め、メガネを外して割烹着の裾で目を押えていました。
子ども心に、このつぎは別のチャンネルにしようと思いました。
もう少し書こうとおもったのですが、栞の「ただいま~」が聞こえてきましたので、またいずれかの機会に。
RE滅鬼の刃 エッセーノベル
お祖父ちゃんと暮らすことになった最初の日、お祖父ちゃんが聞きました。
「どうだ、栞、これからはお祖父ちゃんの事『お父さん』て呼んでみるか?」
ショックでした。
なんと言っていいか分からなくて、俯いていたら涙が溢れてきて、両手をグーにして目をゴシゴシ拭きました。
それでも、涙は溢れてきて、その日初めて着た白のワンピースにポタポタ落ちてきて、シミになったらお母さんに怒られると思って、でも、もうお母さんに会うことは無くって、そう思ったら混乱して、ますます涙が止まらなくなって。
でも、声を上げて泣くことはしなかったですね。
声を上げて泣いたら、もう、張り詰めた髪の毛一本でもっているような心が壊れて、元に戻らなくなってしまいそうで、必死にこらえました。
お祖父ちゃんを『お父さん』と呼んでしまったら、二つの大事なものが二度と返ってこない。
一つは、おうち。子どもの言葉で『おうち』です。
家庭、ファミリー、絆、そういったものです。それが『お父さん』という言葉で永遠に消えてしまいそうな、そんな怖れを感じていました。たとえ100点満点でなくとも、おうちはおうちです。
ジブリの『ラピュタ』で、怖いシーンがありますね。
パズーとシータがムスカ大佐に追い詰められて、二人で飛行石を握って「「バルス」」って言うじゃないですか。
あれで、何百年、何千年続いたラピュタが分子結合を失ったみたいにバラバラになって落ちて行ってしまうじゃないですか。
あんな感じで、怖くて言えませんでした。
二つ目はお祖父ちゃんそのもの。
お祖父ちゃんを『お父さん』て呼んでしまったら『お祖父ちゃん』が居なくなってしまうじゃないですか。
わたしは、親の都合で、しょっちゅうお祖父ちゃんちに預けられていました。
お祖父ちゃんは、いつも優しくって、何かの拍子で誰かの胸で眠ってしまって、目が覚めた時、お祖父ちゃんだったらホッとしました。もっと昔はお祖母ちゃんも生きていて、よく、お祖父ちゃんとお祖母ちゃんに挟まれて寝ていたもんです。
お母さんでもよかったんですけどね。
お母さんの場合、目が覚めたら、そこから、もうよい子を演じなければならないので、ちょっとくたびれるんです。
お祖父ちゃんの姿をしたお父さん。そんなのは釈然としません。
でも、大きくなって少し分かりました。
友だちの中にお祖母さんと暮らしてる人が居たんです。その子が『お母さん』と呼んでいて、ちょっと「え? ええ?」って思って、その子は説明してくれました。
その子にも、そこには居ないお母さんにも、むろんお祖母さんにも、なにも問題はありません。
ただただ、居心地が悪いんです。
お祖父ちゃんを『お父さん』と呼んでしまったら、目の前にいるのは『お父さん』と呼ばれるお祖父ちゃんの姿をした怪物になってしまいます。
http://wwc:sumire:shiori○○//do.com
栞2号のドクロブログ☠!
なんで『お父さん』て呼ばなかったかって?
キモイからに決まってんじゃん。
ジジイと暮らすようになったのは五歳になってすぐだったと思う。
五歳っていうと、もう赤ちゃんじゃない。でしょ? 異議無いよね?
今ほど具体的にアレコレ知ってたわけじゃないけど、分ってたよ、これから大変だって。
もう一年くらい、ジジイとは、いっしょにお風呂に入ってなかったし。
お母さんは問題アリアリな人だったけど、そういうとこは、いっしょだったし。
ジジイのとこは、しょっちゅう来てたというか来させられてた。ま、家庭の事情ってやつさ。
でもさ、毎日ってわけじゃないよ。
お母さんは破滅的な性格だったけど、ドラマとかは、橋田寿賀子とか好きでさ、そういうのに憧れあるのよ。
渡る世間は鬼ばかりと笑いながら、渡る世間に鬼はなしとも願ってる。
世間の鬼は自分だと自覚しながら、自分の相手をしてくれる世間には鬼ではないと憧れてんのよ。
虫良過ぎ!
憧れてんだったら、自分ちをそうしろって思ったけどさ。ま、それは置いといて。
わたしもね、うちでは母親似の剥き出し幼女だったけど、ジジイんちじゃ仮面孫娘やってたわけ。
加齢臭は、ま、いいとして、ベタベタされんのは勘弁してよですよ。
いっしょにお風呂どころか、いっしょに洗濯もNG!
わたしがね、小五から洗濯してんのは、そういうことですよ。
家庭科の洗濯実習で手際がいいもんで、感心されて「あ、お祖父ちゃんと暮らしてますから」ってコソッと担任の先生に言ったら、EテレのMCてか、24時間テレビ的な微笑み返されてゲロ出そう。
そういや、24時間テレビも苦しいみたいね。もう何年も続かないでしょ?
わたしもね、こんな仮面孫娘、そう何年もやってるつもりないし。
あ、突然思い出した。安倍さんてさ、一発目と二発目の間に倒れてるよね。動画、何回も見たし。
弾が見つからないとか、現場検証が五日後って、もう終わってるでしょ。
ま、思っただけでさ、わたし的には、そういうことには目をつぶって、統○協会がーとか、テレビのワイドショー的に生きて生きればいいっす。
滅鬼の刃 エッセーノベル
自分の親をなんと呼んでいらっしゃったでしょうか。
お父さん・お母さん お父ちゃん・お母ちゃん パパ・ママ 父ちゃん・母ちゃん 父上・母上
おっとう・おっかあ おとっつあん・おっかさん おでいちゃん・おもうちゃん ムーター・ファーター
ダディー・マミー 親一号・親二号 おとん・おかん
散歩をしていると、たまに子どもが親を呼んでいるところに出くわします。たいてい、公園で遊んでいる小さな子が回らぬ下で母親を呼ぶ声です。
たまに、スーパーとかで「おかあさん、これ買ってぇ」とか「お父さん、さき行くよ!」とかを耳にします。
いちど、そばを通過中の車から「お父さん、ブレーキ!」という切羽詰まった呼びかけを聞いたことがあります。呼びかけたのは奥さんで、年恰好から見て旦那さんのことであったようです。
自分の配偶者を「おとうさん」「おかあさん」と呼ぶのは日本だけではないのかと思うのですが、これは主題から外れそうなので、別の機会に触れたいと思います。
思い返すと、友だち同士やご近所同士の会話の中で三人称として使われているのを耳にするのが大半なのだと思い至ります。
「きのう、お母さんと買い物行って……」「お父さん、会社の帰りに猫拾てきて……」「お母さん、めっちゃ怒って……」「うちのおとんも歳やからねえ……」など二人称として聞こえてくることが多いですね。
近ごろは流行り病のこともあって、屋外や電車の中で人の話し声を聞くことも稀ですが、おおよそは、こんな具合なのではないかと思います。
なぜ、名前のことを書きだしたかというと、孫の栞が、あまり「お祖父ちゃん」と言わなくなったからです。
これまでは「お祖父ちゃん、ごはん!」とか「お祖父ちゃん、あした燃えないゴミだよ」とか「お祖父ちゃんの年賀状多いねえ」とか枕詞のように言っていました。
「ご飯だよ」「あした燃えないゴミ」「はい、年賀状」とかで済まされます。
まあ、そういう年齢なんだろうと思っているのですが、ちょっと寂しいのかもしれません。
小学三年生のとき、国語科なにかの授業で時間が余ったのか「うちで、親の事をなんと呼んでいますか?」と先生が聞いたことがあります。先生は、みんなに手を挙げさせ、学級役員選挙のように「正」の字を書いていきました。
「お父ちゃん・お母ちゃん」というのが一番多かったですね。次いで「お父さん・お母さん」。「父ちゃん・母ちゃん」はクラスで二三人、「パパ・ママ」と同じくらい少数派だったと思います。
わたしは「父ちゃん・母ちゃん」と呼んでいました。
近所の子たちは「お父ちゃん・お母ちゃん」がほとんどであったように記憶しています。
近所のニイチャンが「パパ・ママ」と呼んでいて、ええしの子や! と、たじろいでしまったのを憶えています。
上皇陛下の結婚パレードを、そのニイチャンの家で見ていました。
白黒の14インチで、カメラが引きになって馬車全体が画面に収まるようになると、人物の目鼻立ちもはっきりしないくらいの画質でしたが、姉とニイチャンと三人で見ていてドキドキしたのを憶えています。
馬車が何度目かのアップになった時、急に画面が歪んで上下に流れるようになりました。昔のテレビは不安定でした。
「ママー! テレビ変になったー!」
ニイチャンが叫ぶと、エプロンで手を拭きながらママがやってきて「こうするとね……」といいながら、テレビを張り倒しました。
パンパン!
すると、テレビは正気に戻って、ご成婚パレードの続きを映し出します。
ご成婚は、昭和33年ですから、リアル『三丁目の夕日』の鮮やかな記憶です。
ニイチャンは、町内でただ一人、校区の違う小学校に行きました。
「やっぱし、ええしはちゃうなあ」
同い年で、ひそかにニイチャンとの集団登校を楽しみにしていた姉は、残念を通り越して嘆息していました。
孫の栞を引き取るにあたって、ちょっと勇気を出して聞いてみました。
「どうだ、お祖父ちゃんの事『お父さん』て呼んでみるか?」
学校へあがると、いろいろあるだろうと思い、聞いてみたのです。
「………………………」
栞は、沈黙をもって答えにしました。
数秒、わたしの顔を見上げて俯いてしまいました。気が付くと、両手をグーにして目をこすっています。
「そうかそうか、むつかしいよな、むつかしいこと聞いてごめんよ。ま、いままで通りでいこうか、とりあえず」
ひそかに『パパ』という呼び方も思っていたのですが、それは止めて正解でした。
わたしは、両親の事を「父ちゃん・母ちゃん」と呼んでいましたが、両親は自分の親(わたしの祖父母)のことは「お父さん・お母さん」と呼んでいました。
母の里は、蒲生野(いまの東近江市)の真宗寺院で、五人居た叔父叔母も母と同様「お父さん・お母さん」でした。
おそらくは、最初に所帯を持った町のマジョリティーに合わせたものだと思います。
小三の調査で少数派と知って少しショックでしたが。おそらく、日本人の四人に一人ぐらいは呼んでいたであろう、この呼び方は好きです。『ニ十四の瞳』だったと思うのですが、大石先生の受け持ちの子が、親の事をそう呼んでいて親近感を持ったのを思い出して、コーヒーを淹れなおしました。