邪馬台国の所在地については、北九州説と畿内説(奈良県桜井市纏向遺跡説が多い)が主流だが、吉備、東北、房総、四国、沖縄など、四百箇所も候補に挙げられてきた。畿内説と北九州説の論拠はネットで無数にみつかるが、http://www2.wbs.ne.jp/~jrjr/nihonsi-1-3-4.htmは比較的うまくまとめてあるので、これをご覧頂くことにする。
畿内説は、『魏志倭人伝』の記述“南至邪馬壹国女王之所都水行十日陸行一月”に関して、南は東の間違いであると推測する。実際に14世紀に書かれた『混一疆理歴代国都之図』では、九州が北端にあり、本州などはその南に連なる形になっているから、南北の間違いが決してなかったとは言い切れない。
一方、北九州説では“水行十日陸行一月”の部分に間違いがあると推測する。
ともあれ、学者たちは自説にとって都合が悪い部分を、『倭人伝』の誤りとする傾向があるが、『「邪馬台国」はなかった』(注1)の著者、古田武彦は『倭人伝』に誤りはなく、そのまま読み解くべきだと主張する。今回は北九州説の代表として古田武彦説を取り上げる。
古田説の論点の一つは邪馬台国という名称。畿内説では邪馬台がヤマトを意味するという前提に立つが(北九州説でも福岡県山門郡大和町周辺とする説がある)、原本では邪馬壹国となっている。古田は「邪馬台の台は臺の簡略体で、臺は皇帝の居場所を示す神聖な字だから蕃族の国名に使用することはありえず、編者の陳寿がそんな重大なミスをするはずがない」と主張する。実際に、邪馬臺国と書かれている文献もあるが、古田によれば、「それは『倭人伝』を書き写した時におきた間違いである」。そして、「邪馬臺(台)国の誤りと推測するのは、大和であってほしい学者たちの願望に過ぎない」と批判する。
さらに、古田はこれまで学者たちが解けなかった距離と方角の矛盾を論理的に解決した。
『倭人伝』による邪馬壹国への行程と距離の説明は次のようである。
1)行程:
帯方郡→(水行および陸行 七千余里)狗邪韓国→(海上千余里)対馬国→(海上千余里)壱岐国→(海上千余里)末蘆国(佐賀県松浦)→(東南へ陸行 五百里)伊都国→(東南へ百里)奴国→(東へ百里)不弥国→(南へ水行二十日)投馬国→(南へ水行十日、陸行一月)邪馬壹国
2)距離の補足説明:
帯方郡―邪馬壹国 “自郡至女王国万二千余里” 12,000余里
狗邪韓国―邪馬壹国 “周旋可五千余里” 5,000余里
帯方郡から倭国の北端の狗邪韓国までは、1)にあるように7,000余里だから、12,000マイナス5,000となって、計算が合う。










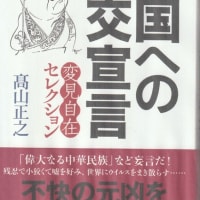








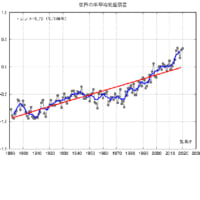
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます