去る7月3日に土石流災害が発生した熱海の伊豆山地区は、爺の日常生活圏内である。交通が遮断されている135号線は、熱海に行く時にバスで通る道だし、現場の逢初橋*近くには贔屓の焼鳥屋もある。爺にとっては、非常に関心がある事件ということもあり、今回はこの災害を「避けることができなかったのか」という観点から考えてみたい。
(注)逢初橋は二つある。一つはTV画面にでてくる国道135線にかかっているもので、もうひとつ同名の橋が同じ逢初川の上流にある。しかし、ここでは後者を無視する。
本題に入る前に、土石流が発生した逢初川について、説明しておく。
逢初川はこれでも「川」の部類に入るのかと思うくらい幅が狭い。135号線と交わる逢初橋のあたりでは、両岸がコンクリートで補強されている上に、すぐそばまで家が立て込んでいるから、用水路と呼ぶ方が相応しい。
特に、JR東海道線と新幹線の線路の下の部分は、しっかり補強されているから、土石流は二つの線路の下をくぐり抜けた。そして、逢初橋と交わる地点で、土石流は川から勢いよく溢れ出て、家屋を吹っ飛ばして135線にまで張り出した。
さて、あるメディアの記者が熱海市長に「レベル4の避難指示を発出するのが遅かったのではないか」と質問し、斎藤市長は「昨日(2日)の段階でレベル3の<高齢者等避難>を出した時点で、すでに雨はピークを越えることが予想されていた」と答えた。なお、レベル5の<緊急安全確保>が発出されたのは、土石流発生の約30分後である。
市当局は水害を想定していたと思うが、3日の午前10頃には雨足は弱まっていた。爺の携帯にも熱海市の警戒通報が自動で流れたから、よく覚えている。だから、その時点で水害の危険はないと判断したのは正しい。
そもそも、熱海市当局は熱海市全体を対象に警戒レベルを判断していたはずで、伊豆山地区を特に重視する理由はなかった。そして、伊豆山地区も熱海市の市街地もすべて斜面であり、通常は雨量が多くてもたちまち海に流れ込み、洪水になることはない。豪雨であっても、せいぜい側溝から溢れた雨水が道路を勢いよく流れる程度である。
だから水害に関するかぎり、市当局は警戒レベルの判断を誤ったとはいえない。「土石流災害も警戒すべきだった」という議論もあるだろうが、そこまで市当局を責めるのは酷だと思う。
マスコミ情報では、土石流の起点に大量の盛り土があり、それが流れ出したのが土石流発生の原因らしいが、たとえそこに盛り土があることを事前に認識していたとしても、それが土石流発生につながると予想するのは難しい。
要するに、今回の土石流災害は不可抗力だったと考える。
それでも納得いかないことがある。それは、盛り土が行われたのは10年前で、その後も作業は続いているようだが、スローすぎる。まぁ、その内に全貌が明らかになるだろう。










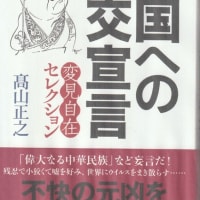








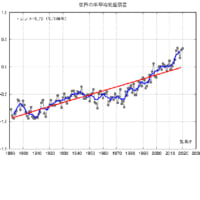
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます