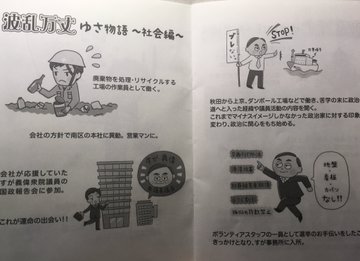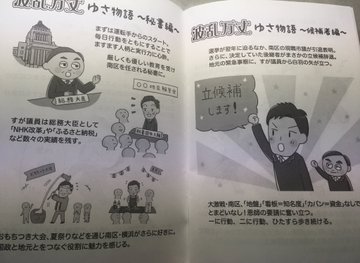新制度に期待と不安
外国人材の受け入れを拡大する新たな制度について、山形県では、期待と不安の声が上がっています。
このうち、天童市の建設関連の会社「エスユーエス」では、新制度の導入で「外国人材の受け入れが進む」と期待しています。
建設現場での足場の組み立てや解体を請け負うこの会社では、日本人だけでは必要な人手を確保できず、従業員のおよそ2割を外国人技能実習生が占めています。
「エスユーエス」の結城克久所長は、「技能実習生の雇用期間は基本的に3年で終わってしまうので、新しい制度で雇用期間が長くなることを強く期待しています」と話していました。
外国人材の受け入れを行っている団体からは不安の声も出ています。山形市の「SISEI協同組合」では、ベトナムから技能実習生を受け入れて日本語の読み書きや、ごみの出し方といった日本で生活する上での基本的なルールなどについておよそ1か月かけて研修で教えたあと企業に派遣しています。
組合の平林和美さんは、新しい制度について「人手不足の現状のなかでは期待している」としたうえで「都市部と地方では給料水準に格差があり、今は外国人もSNSでそういった情報を調べている。現在のように生活支援をしたとしても実習生が都会の給料に魅力を感じて、地方から流れてしまうのではないか」と話していました。
被災地の建設会社は期待
東日本大震災と原発事故の後、人手不足が顕著となっている福島県の沿岸部の企業からは制度をうまく活用し、技能実習生に長く働いてほしいと期待する声が聞かれました。
福島県の沿岸部を中心に道路の舗装工事などを行っている南相馬市の建設会社では、原発事故のあと、求人情報を出してもなかなか人手が集まらず、3年前(H28)の11月からベトナム人の技能実習生2人を受け入れています。
新たな制度では「建設」や「介護」など14の業種では3年間の技能実習を修了した外国人は、要件を満たせば、通算で5年間滞在可能な「特定技能1号」に無試験で移行できるため、この会社では制度を活用してベトナム人2人にさらに延長して働いてもらうことも検討しているということです。
「グレーダ施工」の栗原兼郎社長は「今後も復興に向けて人手が必要となっていく中、技能実習生の2人はもっと長く会社にいてほしいと思っている。賃金面などより労働環境がよい首都圏に流出してしまうのではないかという不安もあるが、うまく制度を活用していければと思う」と話していました。
南相馬市や双葉郡などが含まれる福島県沿岸部の相双地域では原発事故のあと、人手不足が顕著になっていて、福島労働局によりますとことし2月末時点の有効求人倍率は2.72倍で、全国平均の1.63倍と比べても高くなっています。
全国最少の秋田 人材確保が課題
外国人材の受け入れを拡大する制度がスタートする中、外国人労働者が全国で最も少ない秋田県にあるしいたけの生産現場では、貴重な戦力になっている外国人技能実習生を今後も確保できるかが課題となっています。
全国有数のしいたけの産地、秋田県八峰町では人口の減少や高齢化で思うように日本人の働き手が集まらず、地元のJAは生産拡大のため、去年の秋、ベトナムから5人の外国人技能実習生を初めて受け入れました。
5人は、しいたけの箱詰めや収穫作業などを担当し貴重な戦力になっていて、地元のJAは、ことし秋、さらに5人の技能実習生を受け入れる予定だということです。
しかし、秋田県内で働く外国人労働者は去年10月末時点で1900人余りと5年連続で全国で最も少なく、外国人材の受け入れを拡大する制度がスタートし、全国で受け入れに向けた動きが強まる中、今後も確保できるかが課題となっています。
「JA秋田やまもと」の北部営農センターの金谷成悦センター長は「技能実習生がいないとしいたけの生産規模の拡大はできないと思う。都会よりも秋田の環境がベトナムに近いことなど、メリットをアピールしていきたい」と話していました。
農業現場では戸惑い
多くの外国人によって農業が支えられている茨城県では、外国人材の受け入れを拡大する新たな制度が始まった1日、改めて戸惑いの声が聞かれました。
このうちおととしの農業産出額が全国の市町村で3位の茨城県鉾田市では、市内に住む若い世代のうち5人に1人が外国人でその多くが技能実習生として農業の現場で働いています。
1年間に50人余りの外国人技能実習生を受け入れている鉾田市の監理団体、「大地事業協同組合」の加藤了代表理事は「県などから制度に関する説明を受けていますが、具体的な手続きなど始まってみないとわからないことが多いです。農家への説明も全く進んでいないので、実際に運用が始まるのは先になりそうです」と話していました。
また茨城県大洗町などでにんじんやサツマイモを生産している農家の米川清さんは、中国人とベトナム人の4人の外国人技能実習生を受け入れています。
米川さんは「新しい制度について十分に理解できないままきょうになってしまったので、これからどうなるのか不安があります。今の実習生たちも3年で国に帰りたいと言っているので、技能実習生たちが、新しい在留資格に移行するようになるまで、時間がかかると思います」と話していました。
そのうえで、「新しい制度では、給料などの条件がいいところに外国人材が集中してしまうのではと不安に感じています」と、話していました。
準備加速する介護施設
人手不足に悩むさいたま市の介護施設では、新たな人材確保に向けて準備を加速しています。
さいたま市岩槻区にある特別養護老人ホームでは、日本人だけでは十分な介護スタッフを確保できないことから、ことし1月に4人のモンゴル人の技能実習生を受け入れ、さらに早ければ5月にもモンゴルに面接に行って新たな人材確保を進めたいとしています。
新たな制度では原則、外国人の生活などの支援を事業所が担うことになるため、この介護施設では外国人スタッフのために住まいを提供したり、通訳を採用して生活の相談に乗ったりして受け入れ体制を整えています。
一方、施設では在留資格が得られる「特定技能」の試験の日本語や介護の技能試験の内容について「難易度が高い」と受け止めていて合格できる人材を確保できるか不安もあるということです。
特別養護老人ホーム「しらさぎ」の新井浩二統括事務長は「即戦力になる人材を短い期間で確保できる点が魅力的だが、まだ制度にわからない点が多い。ただ人材確保競争が激しくなっているので早めに動いていきたい」と話していました。
自動翻訳機導入の自治体も
外国人材の受け入れを拡大する新たな制度が始まった1日、群馬県で最も多くの外国人が暮らす伊勢崎市は、市役所に70以上の言語に対応する自動翻訳機を導入しました。伊勢崎市が導入したのは日本語を含む74の言語に対応し、端末に向かって話しかけると翻訳したことばが画面に表示され、音声も流れる自動翻訳機2台です。伊勢崎市には、群馬県で最も多いおよそ1万2700人の外国人が暮らしていて、市役所の相談窓口では、30年近く前から職員が英語やポルトガル語など5つの言語で医療保険や住民登録などの相談を受け付けてきました。ただ、伊勢崎市によりますと3月の時点で、市内で暮らす外国人の出身地は64の国と地域に上っているうえ、外国人材の受け入れを拡大する新たな制度が始まり、さらに外国人の増加が見込まれています。このため、これまで対応が難しかったベトナム語や中国語などでも相談に応じられるように翻訳機を導入しました。伊勢崎市国際課の石原真二国際化係長は「今後ますますいろいろな国の人が増えてくる中、翻訳機の導入によって、より多くの外国人に安心して生活してもらえるようにしていきたい」と話していました。



























 」
」 、本当になったなー。」と。
、本当になったなー。」と。