人口が減り続ける、その一つの反作用(反応)として空き家は増え続ける。
4年に一回の選挙をやってきて、選挙区内をくまなく回ることがパターンだった身としては、あちこちに空き家が増え、次の時には建物が傾いて危険に・・そんなことは珍しくなくなった。
自身、相続で兄弟で共有して遠方の住宅2棟があった。一つは、雨漏りのヒドイ状態で、そのままでは住むことが困難。改造して再利用することより、業者を頼んで撤去することにした。
もう一つは、2年ほど前、「役所からスズメバチが巣を作って、近在の人が危険と通報があった。対処して」と連絡がきた。ネットで駆除業者を調べたら、幸い当該自治体内に業者が居た。電話したら、その地区のことはわかる、8000円ほどの費用、という。すぐに除去を依頼。発注するとその日に除去してくれた。携帯で進行形の報告があった。後日、請求書とともに写真も送られてきた。素早さと依頼人への対応の良さに感謝して(上乗せして)1万円送金。
・・・それでも、役所からは固定資産税の請求は来るし・・・そんなことで、維持管理は大変。
全国で空き家が増える。「利用」の模索が続くこと自体は結構なこと。しかし、それを超える勢いで増える空き家。日経は「空き家 止まらぬ増殖」と連載している。再利用できない空き家の方が数がはるかに多いから、先行きはやっぱり「増殖」だろう。
そんなことで今朝は以下を見ておく。
●空き家率が過去最高、「景観崩壊予備軍」が4割に/nippon.com 2019.05.24
●2033年には10軒中3軒が空き家…老いていく日本社会の陰/東亜日報 2017,12. 26
●佐賀市で空き家4棟燃える火事 けが人なし/佐賀 2019/06/06
●増加する空き家対策に欠かせない相談体制の構築を。「空き家相談の担い手育成講座」がスタート/LIFULL HOME'S PRESS 2019年 05月30日
●空き家 止まらぬ増殖(下) 使わないのに手放さない 遅れる解体、費用が重荷/日経 2019/5/24
●子育て世帯、高齢者支援 空き家活用に補助金 JA、農家施設も対象 国交省/日本農業新聞 2019年06月16日
●行政代執行で解体へ 老朽化激しい空き家マンション/東京 2019年5月23日
●空き家撤去で行政代執行へ 安城市、特措法で県内初/中日 2019年6月15日
●訪日外国人リピーターを「民泊」に誘客すべき3つの理由とは?利用者のニーズと空き家対策で需給がマッチ、文化財保護…沖縄では移住の例も/エキサイトニュース 訪日ラボ 2019年6月20日
●空き家知事公舎「県民のアイデア聞きたい」/中日 2019年6月19日
なお、今朝の気温は18度。昨日6月20日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,104 訪問者数1,968」。
●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点
●空き家率が過去最高、「景観崩壊予備軍」が4割に
nippon.com 2019.05.24
少子高齢化を背景に、空き家の増加に歯止めが掛からない。「景観崩壊の予備軍」とも言われる放置されたままの問題物件が特に増えている。
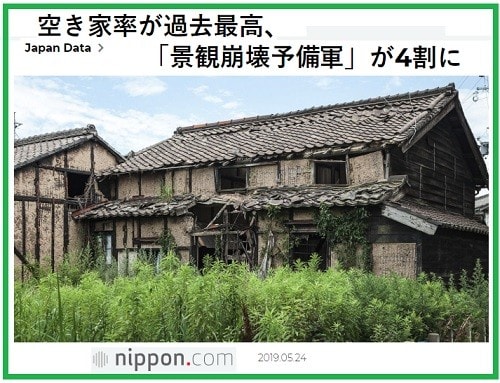 総務省が5年ごとに行う住宅・土地統計調査によると、2018年の全国の空き家は846万戸と、前回(13年)に比べ3.2%増加し、過去最高を更新。総住宅数に占める空き家率は13.6%(13年は13.5%)だった。空き家の増加は、親世代が高齢化すると同時に、子どもの世代が実家を離れて暮らす核家族化が進展しているためだ。人口減少も空き家増に拍車を掛けている。 総務省が5年ごとに行う住宅・土地統計調査によると、2018年の全国の空き家は846万戸と、前回(13年)に比べ3.2%増加し、過去最高を更新。総住宅数に占める空き家率は13.6%(13年は13.5%)だった。空き家の増加は、親世代が高齢化すると同時に、子どもの世代が実家を離れて暮らす核家族化が進展しているためだ。人口減少も空き家増に拍車を掛けている。
空き家には、賃貸や売却に向けて不動産会社や自治体の空き家バンクに登録している物件もあれば、所有者の意思がはっきりせず、借り手や買い手を積極的に探す形跡のない物件もある。後者のような放置物件が空き家全体に占める割合は今回、調査開始以来、初めて40%の大台に乗った。
これについて、民間調査会社シンクダインの米山秀隆・研究主幹は「手入れされていればまだいいが、取り壊しもせずに放置された物件も数多くあり、街の景観を崩す予備軍だ」として、空き家問題の深刻化を示すと話す。街に老朽化した空き家が増えれば、犯罪の増加や行政サービスの無駄も招く恐れがある。
地域別では、特に人口流出に直面する地方圏で空き家の増加が目立つ。別荘などを除いた空き家率は、和歌山(18.8%)、徳島(18.6%)、鹿児島(18.4%)の各県の順に高い。一方、空き家率が低かったのは移住者増の沖縄や埼玉、神奈川、東京の都心3都県。しかし、米山氏は「東京では北区や荒川区など下町を中心に放置物件の数自体は増えており、都心部にも空き家問題は忍び寄っている」と指摘している。
●2033年には10軒中3軒が空き家…老いていく日本社会の陰
東亜日報 2017,12. 26
16日午前9時、千葉県西船橋の閑静な住宅街。20坪ほどの古い木造住宅の撤去作業が始まった。フォークレーンが片側の壁を壊し始めると、1人の作業員が準備していたホースで水をかけて埃が立たないようにした。子供たちはすでに独立し、暮らしていた老夫婦も亡くなって10年間空き家になっていた。
工事期間は12日から27日まで、費用は200万円ほどかかる。近隣住民の川田聡さん(85)は、「数年前から周辺の住民たちが『火事でも起こったらどうするのか』と問題視してきた。町内のあちこちにこのような空き家がある」と話した。
現場作業を指揮するユタカ産業の曽我部裕一主任は、「撤去の依頼が殺到し、土曜日も作業している。家は人が住まなければダメになる。人口減少はこのようなところにも暗い影を落とす」と話した。
急増する「空き家」が日本で社会問題になっている。日本総務省が5年ごとに実施する実態調査によると、2013年の空き家の数は約820万軒で全世帯数の13.5%を占めた。ベビーブーム世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上になる2025年頃には相続急増によりさらに増える見通しだ。富士通総合研究所は2033年には空き家が全住宅の30%の2015万軒に達すると見ている。
空き家が増える理由は様々だ。人口減少や核家族化、交通が便利な都心や新築住宅を好む若年層のライフスタイルも影響を及ぼした。
●佐賀市で空き家4棟燃える火事 けが人なし
佐賀 2019/06/06
5日夜、佐賀市で空き家の建物あわせて4棟を焼く火事がありました。けが人は今のところいないということです。・・・(略)・・・
火は付近の建物に燃え広がり、およそ4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての建物4棟、およそ550平方メートルを焼きました。警察によりますと燃えたのはすべて空き家で今のところけが人はいないということです。また、普段火の気はないということで、警察と消防が火事の詳しい原因を調べています。
●増加する空き家対策に欠かせない相談体制の構築を。「空き家相談の担い手育成講座」がスタート
住まいの「本当」と「今」を伝える情報サイト LIFULL HOME'S PRESS 2019年 05月30日 編集者・ライター 淵脇祐樹
846万戸もの空き家。有効な活用方法が見つからず、どうしていいかわからないから空き家のまま?
2019年4月、総務省統計局が発表したデータによると、全国の空き家数は846万戸。5年前、2013年の820万戸より26万戸増加し、空き家率は13.6%となり、ともに過去最高となった。
2013年の同調査時の資料によると、「空き家となった住宅を取得した経緯」では56.4%が「相続して取得」で、空き家所有者の約4分の1が遠隔地(車や電車などで1時間超)に居住しているという。
また、「空き家にしておく理由」については、「物置として必要」「解体費用をかけたくない」「特に困らない」「将来、自分や親族が使うかもしれない」「さら地にしても使い道がない」「取り壊すと固定資産税が高くなるから」などの理由が多くなっている。結局のところ、「有効な活用方法が見つからず、どうしていいのかわからない」というのが空き家になっている理由のようだ。
野村総合研究所では、世帯数の減少と総住宅数の増加に伴い、2033年の空き家数は約2,166万戸、空き家率30.4%になると予測(2017年)。日本の全物件の約3軒に1軒が空き家になるという計算だ。
そのまま放置すると・・・(以下、略)・・・
●空き家 止まらぬ増殖(下) 使わないのに手放さない 遅れる解体、費用が重荷
日経 2019/5/24
6月、京都府南丹市の木造平屋の空き家に東京都から30代の女性が移り住むことになった。空き家バンクに登録されたのを見て申し込み、すぐに契約に至った。女性から見ればとんとん拍子で進んだが、同市の空き家バンクが軌道にのるまでにはかなりの時間と費用負担がかかっている。
空き家をウェブサイトに掲載し、買い手や借り手を募る空き家バンクの運営を始めたのは2013年。自然が豊かで、京都市内も通勤・通学圏の南丹市…・・・(略)・・・
●子育て世帯、高齢者支援 空き家活用に補助金 JA、農家施設も対象 国交省
日本農業新聞 2019年06月16日
国土交通省は今年度から、空き家を改修し、住まいに困っている子育て世帯や高齢者世帯向けの住宅を作る際の改修費用を一部負担する事業を始めた。農山村の空き家や、JAや農家が使用していない施設などを改修し、住宅にする場合も補助対象になる。同省によると、農福連携での障害者雇用や、外国人技能実習生の受け入れのために用意する住宅を改修するときも申請できる。……
●行政代執行で解体へ 老朽化激しい空き家マンション
東京 2019年5月23日
滋賀県野洲市にある老朽化が激しい空き家の分譲マンションで、市が行政代執行で解体に踏み切る事態となっている。所有者全員が合意して自分たちで解体するのが本来だが、一部の所有者と連絡がつかないなどで長年、危険な状態で放置されており、市が代執行を決めた。分譲マンションの代執行による解体は極めて珍しいが、今後は、同様のケースが増えると懸念されている。 (河郷丈史)
トラックや乗用車がせわしなく行き交う道路沿いに、廃虚のような建造物がたたずむ。一九七二年築の鉄骨三階建て「美和コーポB」。外壁が崩れ、鉄骨に吹き付けられたアスベストが露出し、階段の踊り場は床が抜け落ちている。あちらこちらに植物が生い茂り、敷地内はごみだらけ。風が吹くたびに「ガラッ、ガラッ」と部材の一部が崩れ落ちる音が響いた。
市によると、美和コーポは全九戸で、十年以上前から空き家になっている。管理組合がなく、管理されないまま荒れ放題となっていた。すぐ隣には民家もあり、近隣住民に危険が及ぶ恐れがあることから、市は昨年九月に空き家対策特別措置法に基づく特定空き家に指定した。
分譲マンションは建て替えの場合、所有者の五分の四以上の賛成でできる。解体でも、被災した物件や耐震性が不足した物件なら、五分の四以上の賛成で可能だが、それ以外は、全員の同意が原則。しかし、美和コーポでは、所有者の一部と連絡が取れなかったり、実体のない会社の名義だったりで、全員の合意は不可能だった。所有者代表の男性(75)は「自分たちで解体しなければならないと思っているが、どうにもならない」と話す。
市は建物の解体とアスベストの処理を合わせた費用として五千万円程度を見込み、十一月にも工事に取り掛かりたい考えだ。代執行の費用は所有者らに請求するが、管理組合がないため積立金はゼロ。どれだけ回収できるかは分からない。
山仲善彰市長(68)は「すべての所有者の合意形成ができない場合、危険な建物を除去するには代執行という手段を使わざるを得ず、税金で負担することになる。こんなことをしていていいのか。区分所有のマンションの法整備を、もっときちんと詰めるべきだ」と話している。
◆「解体要件の緩和が必要」 国土交通省の推計によると、築四十年超の分譲マンションは二〇一七年末の約七十三万戸から二十年後の三七年には約五倍の約三百五十二万戸になると見込まれる。管理組合が機能していない「管理不全マンション」も各地で問題化している。「限界マンション」などの著書がある民間シンクタンク「シンクダイン」研究主幹の米山秀隆さん(55)は「今後、マンションの『終活』が大きな課題になる」と指摘する。
そこで、解体も建て替えなどと同様に、所有者の五分の四以上の賛成でできるとするべきだとする。所有者が行方不明になるなどで、五分の四にも届かない事例が多いようなら「さらにハードルを下げていく方向になるかもしれない」とみる。
また、「解体して土地を売るにしても、解体費用を回収できる見込みがなければ反対が出てくる」として、マンション購入段階で、所有者があらかじめ解体費用を供託するといった仕組みが必要だと訴える。
<空き家対策特別措置法> 管理が不十分で周囲に悪影響を与えている空き家への対策として、2015年に施行された。倒壊の恐れがあったり、景観を著しく損なったりしている空き家を市町村が「特定空き家」に指定し、所有者に対して「指導・助言」「勧告」「命令」と段階を踏んで改善を求め、応じなければ代執行で撤去できる。
●空き家撤去で行政代執行へ 安城市、特措法で県内初
中日 2019年6月15日 (四方さつき)
倒壊の恐れのある安城市内の空き家に対して、市が空き家対策特別措置法に基づく行政代執行での撤去に踏み込むことが分かった。作業は二十四日から約一カ月間を予定。市によると、この特措法に基づく行政代執行は県内で初めてという。撤去される空き家は二〇一三年四月に放火により全焼しており、住人や所有者と連絡が取れない状況が続いていた。
空き家は市中心部の住宅街にあり、小学校の通学路にも当たる。敷地は四百二十六平方メートルで、全焼したのは木造二階建て約八十五平方メートル。火災後、片付けなどを巡って市が住人男性と交渉を続けていたが、その後連絡が取れなくなった。土地と家屋の所有者は宗教法人だが、代表者は死亡しているという。
市は一七年九月に立ち入り調査し、一八年八月、倒壊の恐れがあり近隣住民や通行人の人命を脅かす可能性があるなどとして「特定空き家」に認定。特措法に従い指導・助言、勧告、命令と段階を踏んだ手続きを進めており、今回の行政代執行の判断に至った。
家屋解体と、隣地まで伸びた樹木の伐採、敷地に散乱する廃棄物の撤去などで、費用は約五百八十三万円。市建築課の担当者は「住民の方からも不安の声が多くあった。今後は撤去費回収の手続きを進める」としている。
●訪日外国人リピーターを「民泊」に誘客すべき3つの理由とは?利用者のニーズと空き家対策で需給がマッチ、文化財保護…沖縄では移住の例も
エキサイトニュース 訪日ラボ 2019年6月20日
近年世界中で話題となっている民泊は、高齢者の生きがいや空き家対策、地方の文化財の保護など、地域が抱える課題を解決する手段の1つとして、効果が期待されています。
民泊を活用したインバウンドの地方誘客は、地域ならではの新たな体験ができる機会として、リピーターを中心に訪日外国人観光客のニーズにも合った取り組みと言えるでしょう。
今回は温泉旅館・高齢化空き家対策・地域の文化体験の3つのキーワードを元に、インバウンドリピーターを民泊に誘客すべき理由を、民泊の活用事例と合わせて紹介します。
訪日中国人向けメディアカテゴリの資料を一括DL訪日中国人向けメディアカテゴリの詳細はこちら
1. 民泊×温泉旅館、インバウンドのリピーターにPR
訪日外国人観光客の約60%が、訪日回数2回目以上のリピーターとなった今、より個人の趣味趣向に合わせた訪問ルートやホテル、レストランを求める傾向が高まっています。
また、訪日回数が多いリピーターほど1人あたりの旅行支出額が高いことから、東京・京都・大阪などを結ぶ「ゴールデンルート」をはじめとした主要観光地のみならず、東北や九州など地方を訪れる割合が高くなることも1つの特徴です。
リピーターは事前に日本について入念にリサーチをしてくるケースが多く、興味関心に合わせてより深い日本を体験すべく、地方への訪問や民泊の活発な利用が見受けられます。
リピーターによる滞在先の選定では、時間やコストが必要な旅行先では
民泊に複数泊することで旅費を抑え、1泊は温泉旅館に泊まるなど、日本ならではの宿泊体験を重視する傾向も顕著です。近年では・・・(以下、略)・・・
●空き家知事公舎「県民のアイデア聞きたい」
中日 2019年6月19日 (鈴木啓太)
四月に就任した杉本達治知事は知事公舎に入居せず、公舎の活用法に注目が集まっている。各都道府県を取材すると、全国で知事公舎があるのは福井を含めて三十三道県で、うち六県で知事が入居していないことが分かった。知事公舎がない十四都府県の中には、旧公舎を売却するなどし、別の施設として活用している例もある。
福井県知事公舎(福井市若杉三)は、敷地面積約三千九百四十平方メートルで、木造平屋の延べ床約五百四十平方メートル。約三億円かけ、一九九四年に完成した。栗田幸雄元知事、西川一誠前知事がそれぞれ居住した。岐阜県出身の杉本知事は就任会見で「県人として認知してもらう意味でも福井に家を持って生活することが大切だ」と述べ、公舎には入居しない方針を表明。現在は福井市内の借家で生活しており、今後新居を構える意向を示している。
取材によると、福井のほか、岩手、茨城、石川、島根、愛媛で知事公舎はあるが、自宅に住むなどして知事が入居していない。杉本知事と同じく四月の知事選で初当選した島根県の丸山達也知事は福岡県出身で、島根県内に自宅を購入する意向。これまでの公舎については「どんな活用策があるか検討中」(県の担当者)と、福井県と似た状況にある。
一方、売却や改修などにより知事公舎がないのは、東京など十四都府県。そのうち、富山県は知事公館(旧知事公舎)を改築するなどし、二〇一二年に「高志の国文学館」として開館した。富山ゆかりの文学作品や作家を紹介し、今春には来館者八十万人を達成した。県の担当者は「多くの方に来館してもらい、県内外にふるさとの文学の魅力を発信できていると思う」と手応えを語る。
写真
長崎県では〇五年、知事公舎などの跡地に長崎歴史文化博物館が開館。山形県では、東北芸術工科大(山形市)が公舎などを取得して改修し、一一年から大学施設「やまがた藝術学舎(げいじゅつがくしゃ)」として運営している。
杉本知事は十四日の会見で公舎の活用策について「地域での使用や売却など方法があるだろうが、県民の皆さんのアイデアをよく聞かせてもらいたい」と話した。
| Trackback ( )
|
 |
| |
|
|
|
