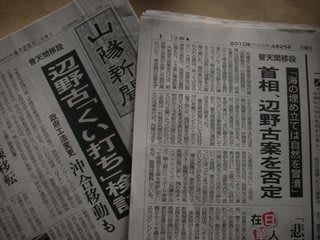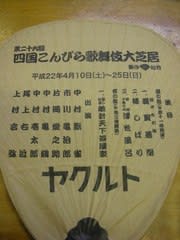相変わらず「死」に関わる本を読み続けている、高柳和江さんに励まされた
相変わらず「死」に関わる本を読み続けている、高柳和江さんに励まされた
これまでも書いてきたが、自分の逝き方や死、そして葬儀・告別式のあり方などについて、このところ本を読み考え続けている。こうした本は、公民館経由で、市立図書館から借りている。返済期限があるから、なんとか読める。
今の何冊かの本を借りて読んでいる。上坂冬子著『死ぬという大仕事』(小学館刊)では、「全てを自分で決めたいという上坂流の面目躍如」で、その著書の副題には「がんと共生した半年間の記録」とある。
上坂さんの「私はもう治るとは思っていない。いえ、治らなくていいとさえ思っています。そのかわり、痛いわけでもなく、苦しむわけでもなく、ただ穏やかに生きて、自分の寿命と一致したところで死ねればいいと考えているのです」との考え方に、私も共鳴する。
そして、高柳和江著『死に方のコツ』(飛鳥新社刊)で、ようやく「死に方」について、自分自身がある意味で納得できる考え方に出会えた。この本は、平成6年の発行となっており、ずいぶんと以前から読み続けられている本だ。
この本の中で、米国の精神科医・キューブラー・ロスの「死ぬ人の心理状態として、5段階を順番に進んでいく」ことが紹介されている。それは①否認(何かの間違い)、②怒り(何故私が)、③取引(もう少し生かして)、④抑鬱(放っておいてくれ)、⑤受容(そうか、やっばり死ぬのか)の五段階だそうだ。臆病な私は、受容まで行かないで、抑鬱で止まりそうだ。
この本には、「死ぬのは当たり前」で、「死ぬときは痛くないようにできている」、「自然な死に苦しみはない」、「耳は最後まで聞こえる」、「死ぬのは気持ちいい」など、101項目にわたって、とてもわかりやすく書かれている。
そして、この本を読むと死を当然なこととして受け入れられ、とても安心できた。もう少しだけ高柳和江さんの他のご著書を読みたいと考えている。同時に、これからもミーハー心いっぱいに、幾つかの病気と仲良く付き合いながらも、元気に暮らしていければと願う。