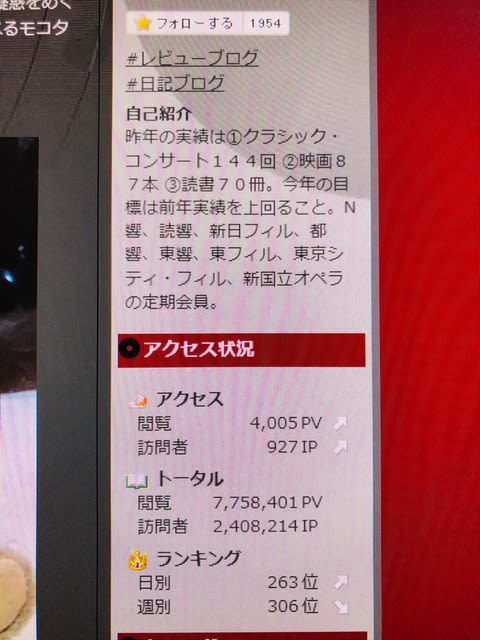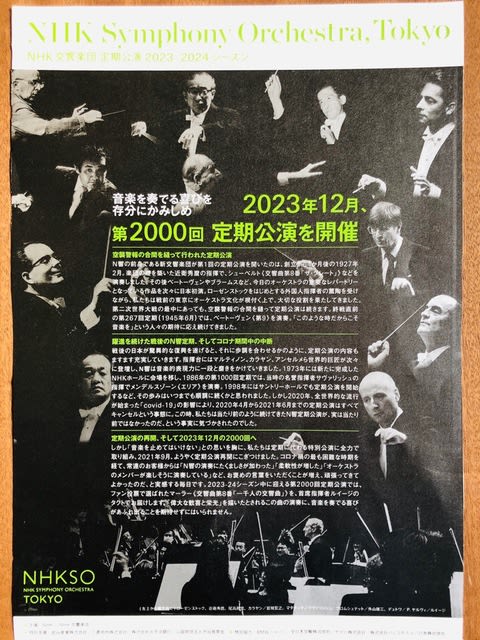20日(木)。昨日、「フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2023」の公演のうち7月25日(火)の洗足学園音楽大学の「バレエ・コンサート」と、8月5日(土)の「真夏のバッハⅧ」のチケットを取りました 昨日は午前中、整骨院に行ったり、ブランチ・コンサートを聴きに行ったりして、WEBサイトへのアクセスが午後になってしまいましたが、バレエ公演は2階センターブロックを押さえることができ、バッハ公演は1階センターブロック席が取れました
昨日は午前中、整骨院に行ったり、ブランチ・コンサートを聴きに行ったりして、WEBサイトへのアクセスが午後になってしまいましたが、バレエ公演は2階センターブロックを押さえることができ、バッハ公演は1階センターブロック席が取れました
ということで、わが家に来てから今日で3019日目を迎え、2020年の米大統領選で使われた投票集計機が不正に操作されたとするトランプ前大統領の主張を繰り返し放送されて名誉を傷つけられたとして、集計機メーカーが保守系のFOXニュースに損害賠償を求めた訴訟は18日、東部デラウェア州の裁判所で、FOX側が日本円にして1055臆円を支払うことで合意した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

嘘の巣窟トランプべったりの報道を繰り返せば こういう報いを受けるという前例

 昨日は、諸般の事情により夕食作りはお休みしました
昨日は、諸般の事情により夕食作りはお休みしました 






昨夜、新国立劇場「オペラパレス」でヴェルディ「アイーダ」を観ました 出演は アイーダ=セレーナ・ファルノッキア、ラダメス=ロベルト・アロ二カ、アムネリス=アイリーン・ロバーツ、アモナズロ=須藤慎吾、ランフィス=妻屋秀和、エジプト国王=伊藤貴之、伝令=村上敏明、巫女=十合翔子。合唱=新国立劇場合唱団、バレエ=東京シティ・バレエ団、児童バレエ=ティアラこうとうジュニアバレエ団、管弦楽=東京フィル、指揮=カルロ・リッツィ、演出=フランコ・ゼッフィレッリです
出演は アイーダ=セレーナ・ファルノッキア、ラダメス=ロベルト・アロ二カ、アムネリス=アイリーン・ロバーツ、アモナズロ=須藤慎吾、ランフィス=妻屋秀和、エジプト国王=伊藤貴之、伝令=村上敏明、巫女=十合翔子。合唱=新国立劇場合唱団、バレエ=東京シティ・バレエ団、児童バレエ=ティアラこうとうジュニアバレエ団、管弦楽=東京フィル、指揮=カルロ・リッツィ、演出=フランコ・ゼッフィレッリです
この日の公演は全7回のうち6回目の公演です 本来 4月5日のプルミエ(初日)公演を聴くはずでしたが、読響定期公演とダブったため、オペラを昨日に振り替えたのです
本来 4月5日のプルミエ(初日)公演を聴くはずでしたが、読響定期公演とダブったため、オペラを昨日に振り替えたのです 主催者側から指定された振り替え席は1階13列27番、センターブロック右から5つ目です
主催者側から指定された振り替え席は1階13列27番、センターブロック右から5つ目です 私の会員席より5列も前のセンター寄りの好条件の席ですが、どうも私は通路から中に入るほど苦手です
私の会員席より5列も前のセンター寄りの好条件の席ですが、どうも私は通路から中に入るほど苦手です とは言え、主催者としては最大限の配慮をしてくれたと思うので不平不満は言えません
とは言え、主催者としては最大限の配慮をしてくれたと思うので不平不満は言えません
私が 新国立オペラでゼッフィレッリ演出による「アイーダ」を観るのは2003年、2008年、2013年、2018年に続いて今回が5度目です つまり最初に「アイーダ」を観てから20年が経過したことになります
つまり最初に「アイーダ」を観てから20年が経過したことになります

歌劇「アイーダ」はジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)が、スエズ運河開通を記念してエジプトのイスマーイール・パシャがカイロに建てた歌劇場のこけら落としのために作曲、1871年に初演された全4幕7場から成る作品です
舞台は古代エジプト。若い将軍ラダメスは、王女アムネリスに仕える敵国エチオピアの王女アイーダと密かに愛し合っている しかしアムネリスも彼を愛していた
しかしアムネリスも彼を愛していた アイーダは父王の密令によってラダメスから軍事機密を聞き出し、ラダメスは謀反人として捕らえられる
アイーダは父王の密令によってラダメスから軍事機密を聞き出し、ラダメスは謀反人として捕らえられる アムネリスは自分を愛せば命を救おうとラダメスに迫るが、彼は決然として応じない
アムネリスは自分を愛せば命を救おうとラダメスに迫るが、彼は決然として応じない 地下牢で独り死を待つラダメスの前に牢に忍び込んでいたアイーダが現れ、二人は永遠の愛を誓いながら死を待つ
地下牢で独り死を待つラダメスの前に牢に忍び込んでいたアイーダが現れ、二人は永遠の愛を誓いながら死を待つ

新国立劇場の「アイーダ」と言えばフランコ・ゼッフィレッリの絢爛豪華な舞台・演出が頭に浮かびます スケールが大きく、その一方で細部にこだわった舞台造りが際立っています
スケールが大きく、その一方で細部にこだわった舞台造りが際立っています とくに注目すべきは第1幕第2場のアイーダ・トランペットのファンファーレで始まる「勝ちて帰れ!」の大合唱と勇壮な行進曲、そしてそれに続く巫女たちのバレエです
とくに注目すべきは第1幕第2場のアイーダ・トランペットのファンファーレで始まる「勝ちて帰れ!」の大合唱と勇壮な行進曲、そしてそれに続く巫女たちのバレエです 兵士たちの行進では、本物の馬が2頭登場し、1頭は舞台中央で一回りして舞台袖に引き上げ、もう1頭は舞台を真っすぐ横断します
兵士たちの行進では、本物の馬が2頭登場し、1頭は舞台中央で一回りして舞台袖に引き上げ、もう1頭は舞台を真っすぐ横断します あれだけの大管弦楽と大合唱の中を、よくも興奮して暴れないものだと感心しますが、訓練の賜物なのでしょう
あれだけの大管弦楽と大合唱の中を、よくも興奮して暴れないものだと感心しますが、訓練の賜物なのでしょう これが馬だったからよかったので、もし豚を登場させていたらブーイングの嵐だったでしょう
これが馬だったからよかったので、もし豚を登場させていたらブーイングの嵐だったでしょう 東京シティ・バレエ団による巫女たちのバレエが素晴らしい
東京シティ・バレエ団による巫女たちのバレエが素晴らしい 「アイーダ」は単なるオペラではなくバレエを含む「グランド・オペラ」であること強く印象付けられます
「アイーダ」は単なるオペラではなくバレエを含む「グランド・オペラ」であること強く印象付けられます

アイーダを歌ったセレーナ・ファルノッキアはイタリア出身のソプラノです 1995年フィラデルフィアのルチアーノ・パヴァロッティ国際声楽コンクールで優勝して以降、ミラノ・スカラ座を中心に数々のオペラ公演に出演し、好評を博しています
1995年フィラデルフィアのルチアーノ・パヴァロッティ国際声楽コンクールで優勝して以降、ミラノ・スカラ座を中心に数々のオペラ公演に出演し、好評を博しています 自然なコロラトゥーラが美しく、特に第3幕冒頭のロマンツァ「ああ、わが故郷」ではアイーダの切ない感情を抒情的に歌い上げていました
自然なコロラトゥーラが美しく、特に第3幕冒頭のロマンツァ「ああ、わが故郷」ではアイーダの切ない感情を抒情的に歌い上げていました
ラダメスを歌ったロベルト・アロ二カはイタリア出身のテノールですが、ヴェルディのオペラを中心に世界中の歌劇場で活躍しています 警備隊長ラダメスに相応しい情熱的な歌唱と卓越した演技力が印象的です
警備隊長ラダメスに相応しい情熱的な歌唱と卓越した演技力が印象的です
アムネリスを歌ったアイリーン・ロバーツはアメリカ出身のメゾソプラノで、ベルリン・ドイツ・オペラ専属歌手として様々なオペラ公演に出演しています メゾにしては声が良く通り、まろやかで深みのある声が魅力で、存在感が圧倒的でした
メゾにしては声が良く通り、まろやかで深みのある声が魅力で、存在感が圧倒的でした アイーダに次ぐ主役と言って良いかもしれません
アイーダに次ぐ主役と言って良いかもしれません
アモナズロを歌った須藤慎吾は国立音大大学院修了のバリトンですが、エチオピア国王に相応しい力強い歌唱力と迫真の演技力で聴衆を魅了しました
ランフィスを歌った妻屋秀和は何を歌っても抜群の安定感で歌い上げます
特筆すべきはアイーダの、アムネリスの、あるいはラダメスの心情に寄り添いつつ、場面を盛り上げるドラマティックな演奏を展開したカルロ・リッツィ指揮東京フィルの演奏です カルロ・リッツィはイタリア出身の指揮者ですが、イタリア・オペラを中心に世界中のオペラハウスで指揮をとっています
カルロ・リッツィはイタリア出身の指揮者ですが、イタリア・オペラを中心に世界中のオペラハウスで指揮をとっています 私はMETライブビューイングで彼の指揮姿を見た覚えがあります
私はMETライブビューイングで彼の指揮姿を見た覚えがあります 素晴らしい歌心と卓越した統率力で東京フィルをまとめ上げていました
素晴らしい歌心と卓越した統率力で東京フィルをまとめ上げていました

カーテンコールが繰り返され、終演は21時57分でした ゼッフィレッリの演出による「アイーダ」を観ないうちは、オペラを観たことにならない、と言いたくなるような華麗な舞台です。まだ観たことのない人は一度は観ることをお勧めします
ゼッフィレッリの演出による「アイーダ」を観ないうちは、オペラを観たことにならない、と言いたくなるような華麗な舞台です。まだ観たことのない人は一度は観ることをお勧めします 残念ながら日本では21日(金)の千穐楽を残すのみです
残念ながら日本では21日(金)の千穐楽を残すのみです これを逃すと、5年後の2028年まで待たなければなりません
これを逃すと、5年後の2028年まで待たなければなりません 新国立オペラ「アイーダ」は5年おきに上演されるからです
新国立オペラ「アイーダ」は5年おきに上演されるからです その時、あなたは何歳でしょうか
その時、あなたは何歳でしょうか














 もう何十回も弾きこなしているような完璧な演奏で、表現力が素晴らしいと思いました
もう何十回も弾きこなしているような完璧な演奏で、表現力が素晴らしいと思いました 演奏時間が長く50分近くかかります。演奏する側も大変ですが、聴く側も大変だと思います
演奏時間が長く50分近くかかります。演奏する側も大変ですが、聴く側も大変だと思います 」と本音を語っていました
」と本音を語っていました




 「茄子の~」は麵つゆを使ったので簡単に出来ました
「茄子の~」は麵つゆを使ったので簡単に出来ました

 不穏な出来事が連鎖し、得体のしれない恐怖が徐々に正体を現し始める
不穏な出来事が連鎖し、得体のしれない恐怖が徐々に正体を現し始める





 この人の素晴らしいところは自主企画公演を精力的に開催しているところです
この人の素晴らしいところは自主企画公演を精力的に開催しているところです






 と思いました
と思いました
 音楽評論家・江藤光紀のプログラム・ノートによると、「ここで描かれるのは、ドイツ帝国の大ブルジョワの楽しい夏のバカンスの1日」です
音楽評論家・江藤光紀のプログラム・ノートによると、「ここで描かれるのは、ドイツ帝国の大ブルジョワの楽しい夏のバカンスの1日」です このタイトルを見ると、ベートーヴェンの「交響曲第6番”田園”」(1807~08年作曲)の第4楽章「雷雨と嵐:アレグロ」を思い出します
このタイトルを見ると、ベートーヴェンの「交響曲第6番”田園”」(1807~08年作曲)の第4楽章「雷雨と嵐:アレグロ」を思い出します しかし、ここで立ち止まってよく考えてみると、ベートーヴェンの「田園」は全曲と各楽章に描写的な標題が付けられているものの、ベートーヴェン自身が語っているように「絵画的描写ではなく、感情の表出」です
しかし、ここで立ち止まってよく考えてみると、ベートーヴェンの「田園」は全曲と各楽章に描写的な標題が付けられているものの、ベートーヴェン自身が語っているように「絵画的描写ではなく、感情の表出」です




 透明感のある美しい合唱で、シマノフスキの「スターバト・マーテル=悲しみに暮れる聖母」の素晴らしさがダイレクトに伝わってくるコーラスでした
透明感のある美しい合唱で、シマノフスキの「スターバト・マーテル=悲しみに暮れる聖母」の素晴らしさがダイレクトに伝わってくるコーラスでした


 天才は早死にします
天才は早死にします
 高関の指揮で第1楽章に入る時、彼女はニコッと笑みを浮かべました
高関の指揮で第1楽章に入る時、彼女はニコッと笑みを浮かべました 彼女は 多分「いいんです。良いと思ったら拍手をしてくれても
彼女は 多分「いいんです。良いと思ったら拍手をしてくれても ニュアンスに富んだナイーブな演奏で、ここでも美しいヴィブラートが会場に響き渡りました
ニュアンスに富んだナイーブな演奏で、ここでも美しいヴィブラートが会場に響き渡りました

 住吉駅から半蔵門線で永田町まで行き、南北線に乗り換えて六本木一丁目に向かいました
住吉駅から半蔵門線で永田町まで行き、南北線に乗り換えて六本木一丁目に向かいました


 どうやら演奏前5分間の「プレトーク」が佐渡氏のルーティーンのようです
どうやら演奏前5分間の「プレトーク」が佐渡氏のルーティーンのようです



 内容は2022年5月21日にすみだトリフォニーホールで演奏された佐渡裕指揮によるベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」のライブ録音です
内容は2022年5月21日にすみだトリフォニーホールで演奏された佐渡裕指揮によるベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」のライブ録音です