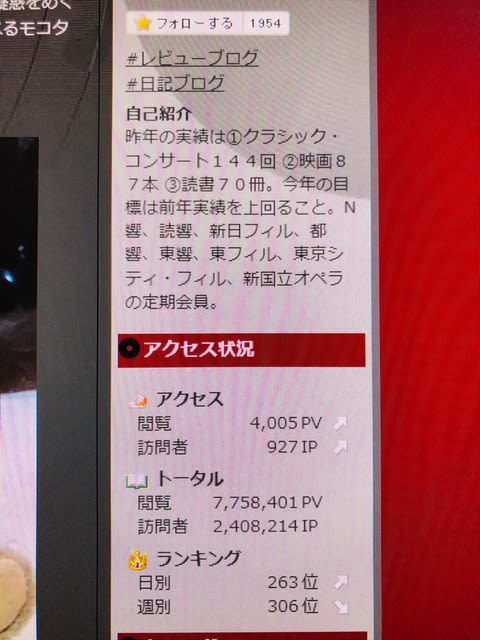15日(土)。わが家に来てから今日で3014日目を迎え、トランプ前米大統領は13日、東部ニューヨーク州の検察当局で、親族企業「トランプ・オーガニゼーション」の不正会計疑惑をめぐる民事訴訟に関連した尋問を約7時間にわたり受けた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

刑事訴訟の次は民事訴訟と これほど忙しい被告人は滅多にいない いよっ元大統領!





昨日、夕食に「舌平目のムニエル」「ミニトマトとアボカドのサラダ」を作り、カツオの刺身、カツオの酒盗と一緒にいただきました 和食はいいですね
和食はいいですね






昨日、すみだトリフォニーホールで新日本フィル「クラシックへの扉」第14回定期演奏会を聴きました プログラムは①レスピーギ「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲、②ラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲 作品43」、③ドヴォルザーク「交響曲第9番 ホ短調 作品95"新世界より”」です
プログラムは①レスピーギ「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲、②ラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲 作品43」、③ドヴォルザーク「交響曲第9番 ホ短調 作品95"新世界より”」です 演奏は②のピアノ独奏=辻井伸行、指揮=佐渡裕です
演奏は②のピアノ独奏=辻井伸行、指揮=佐渡裕です

この日のコンサートは佐渡裕氏の新日本フィル第5代音楽監督就任第1回目の「扉シリーズ」公演ということもあり、開演前からロビーが賑わっています どうやらチケットは完売のようで何よりです
どうやらチケットは完売のようで何よりです
佐渡裕は京都芸術大学卒。1989年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝 現在、ウィーンのトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督を務め、国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、シエナ・ウィンド・オーケストラ首席指揮者、サントリー「1万人の第九」総監督を務めています
現在、ウィーンのトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督を務め、国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、シエナ・ウィンド・オーケストラ首席指揮者、サントリー「1万人の第九」総監督を務めています
演奏に先立って佐渡氏がマイクを持って登場、音楽監督就任の挨拶、2日間の完売御礼と、この日取り上げる曲目について簡単に説明しました どうやら演奏前5分間の「プレトーク」が佐渡氏のルーティーンのようです
どうやら演奏前5分間の「プレトーク」が佐渡氏のルーティーンのようです
オケは12型で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの新日本フィルの並び コンマスは崔文洙、サブは伝田正秀というダブルコンマス態勢を敷きます
コンマスは崔文洙、サブは伝田正秀というダブルコンマス態勢を敷きます
1曲目はレスピーギ「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲です この曲はアカデミアの図書館で見つけた古いイタリアの音楽をもとに、オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)が1931年に作曲した弦楽合奏のための作品です
この曲はアカデミアの図書館で見つけた古いイタリアの音楽をもとに、オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)が1931年に作曲した弦楽合奏のための作品です 第1曲「イタリアーナ」、第2曲「宮廷のアリア」、第3曲「シチリアーナ」、第4曲「パッサカリア」の4曲から成ります
第1曲「イタリアーナ」、第2曲「宮廷のアリア」、第3曲「シチリアーナ」、第4曲「パッサカリア」の4曲から成ります
身長187センチの巨人・佐渡裕が指揮台に上り、第1曲の演奏に入ります どこまでも繊細で優雅な演奏が繰り広げられます
どこまでも繊細で優雅な演奏が繰り広げられます 第2曲ではヴィオラ・セクションの豊かな響きが印象的です
第2曲ではヴィオラ・セクションの豊かな響きが印象的です 第3曲は優しく穏やかな曲で、NHK-FMのクラシック音楽番組のテーマミュージックとして使われていたように記憶しています
第3曲は優しく穏やかな曲で、NHK-FMのクラシック音楽番組のテーマミュージックとして使われていたように記憶しています 第4曲は特に第1ヴァイオリンとヴィオラの美しいアンサンブルが素晴らしいと思いました
第4曲は特に第1ヴァイオリンとヴィオラの美しいアンサンブルが素晴らしいと思いました

2曲目はラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲 作品43」です この曲はセルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)がパガニーニの「24の奇想曲」の第24曲(イ短調)をテーマとして1934年に作曲、同年ボルティモアで初演されました
この曲はセルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)がパガニーニの「24の奇想曲」の第24曲(イ短調)をテーマとして1934年に作曲、同年ボルティモアで初演されました 主題と24の変奏曲により構成されています
主題と24の変奏曲により構成されています
ピアノ独奏の辻井伸行は2009年米国の第13回ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクールで日本人として初めて優勝して以来、国内外で活躍しています
オケは14型に拡大します 目が不自由な辻井が佐渡と腕を組んで登場、ピアノに対峙します
目が不自由な辻井が佐渡と腕を組んで登場、ピアノに対峙します 佐渡の指揮で演奏に入ります
佐渡の指揮で演奏に入ります プレトークで佐渡氏が「辻井君とは長年にわたり共演しているが、テレパシーで通じているように感じる
プレトークで佐渡氏が「辻井君とは長年にわたり共演しているが、テレパシーで通じているように感じる われわれ二人のコンビは最強だと思う
われわれ二人のコンビは最強だと思う リハーサルも楽しく出来た
リハーサルも楽しく出来た 」と語っていましたが、その言葉の通り、辻井のソロと佐渡の率いるオケの息がピッタリ合っていました
」と語っていましたが、その言葉の通り、辻井のソロと佐渡の率いるオケの息がピッタリ合っていました 実質的には辻井に自由に演奏させて、佐渡が合わせているのだと思いますが、そんなことを感じさせない見事な演奏でした
実質的には辻井に自由に演奏させて、佐渡が合わせているのだと思いますが、そんなことを感じさせない見事な演奏でした とくに速いパッセージの変奏における辻井のピアノ独奏が鮮やかでした
とくに速いパッセージの変奏における辻井のピアノ独奏が鮮やかでした この曲では、一番有名な第18変奏が好きですが、辻井の演奏は過度にロマンティックに陥ることなく 自然体で弾いていたところに 好感が持てました
この曲では、一番有名な第18変奏が好きですが、辻井の演奏は過度にロマンティックに陥ることなく 自然体で弾いていたところに 好感が持てました
満場の拍手に辻井は、ラフマニノフ「前奏曲 嬰ハ短調 作品3-2 ”鐘”」を鮮やかに演奏、再び大きな拍手に包まれました

プログラム後半はドヴォルザーク「交響曲第9番 ホ短調 作品95"新世界より”」です この曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)がニューヨークの私立ナショナル音楽院の院長として招かれた米国滞在中の1893年に作曲、同年ニューヨークで初演されました
この曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)がニューヨークの私立ナショナル音楽院の院長として招かれた米国滞在中の1893年に作曲、同年ニューヨークで初演されました 第1楽章「アダージョ ~ アレグロ・モルト」、第2楽章「ラールゴ」、第3楽章「モルト・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「アレグロ・コン・フォーコ」の4楽章から成ります
第1楽章「アダージョ ~ アレグロ・モルト」、第2楽章「ラールゴ」、第3楽章「モルト・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「アレグロ・コン・フォーコ」の4楽章から成ります
佐渡の指揮で第1楽章に入ります。アレグロ・モルトに移ってからのスピード感溢れる演奏が印象的で、佐渡は楽員を煽り立てアグレッシブな演奏を引き出します 第2楽章はイグリッシュホルンの「森明子・オン・ステージ」です
第2楽章はイグリッシュホルンの「森明子・オン・ステージ」です どんなにフルートの野津雄太が頑張っても、オーボエの岡北斗が踏ん張っても、「遠き 空に 陽は落ちて
どんなにフルートの野津雄太が頑張っても、オーボエの岡北斗が踏ん張っても、「遠き 空に 陽は落ちて 」のメロディーを吹くイングリッシュホルンの哀愁を帯びたメロディーには敵いません
」のメロディーを吹くイングリッシュホルンの哀愁を帯びたメロディーには敵いません 佐渡氏の解説によると「新世界より」は世界中で一番多く演奏されている曲とのことで、私も様々なオケで何度も聴いてきましたが、第2楽章「ラールゴ」のイングリッシュホルンに関しては森明子さんの演奏が一番好きです
佐渡氏の解説によると「新世界より」は世界中で一番多く演奏されている曲とのことで、私も様々なオケで何度も聴いてきましたが、第2楽章「ラールゴ」のイングリッシュホルンに関しては森明子さんの演奏が一番好きです 私がこの曲を初めて聴いたのは、小学校5、6年生の時のボーイスカウトの野営キャンプの時でした
私がこの曲を初めて聴いたのは、小学校5、6年生の時のボーイスカウトの野営キャンプの時でした もっとも、その頃はドヴォルザークの名前さえも知りませんでしたが
もっとも、その頃はドヴォルザークの名前さえも知りませんでしたが 第3楽章では、弦楽器、管楽器、打楽器の総力により力強く集中力に満ちた演奏が展開しました
第3楽章では、弦楽器、管楽器、打楽器の総力により力強く集中力に満ちた演奏が展開しました 第4楽章の冒頭は、佐渡氏のプレトークにもあったように、ドヴォルザークが大好きだった蒸気機関車の発進場面を思い浮かべるような推進力に満ちた演奏が繰り広げられました
第4楽章の冒頭は、佐渡氏のプレトークにもあったように、ドヴォルザークが大好きだった蒸気機関車の発進場面を思い浮かべるような推進力に満ちた演奏が繰り広げられました また、終盤にかけては佐渡氏の体格のようにスケールの大きな演奏が展開しました
また、終盤にかけては佐渡氏の体格のようにスケールの大きな演奏が展開しました 全楽章を通してオケが良く鳴っていましたが、特に最近は、弦楽器群の充実が素晴らしいと思います
全楽章を通してオケが良く鳴っていましたが、特に最近は、弦楽器群の充実が素晴らしいと思います
満場の拍手に佐渡 ✕ 新日本フィルはアンコールにドヴォルザーク「スラブ舞曲 ト短調 作品46-8」を、これでもか という迫力で押し切り、会場の温度を上昇させました
という迫力で押し切り、会場の温度を上昇させました
カーテンコールを漠然と見ていて、写メをするのを忘れていることに気が付き、慌ててスマホのスイッチを入れて写メしましたが、何とか間に合いました


終演後、パトロネージュ部の登原さんとお話ししましたが、この日は1700人超えの入場者だったとのことで、明るい表情でした コロナ禍も「ウイズ・コロナ」の段階に移り、各地のコンサート会場にも聴衆が戻ってきたので、この流れが続くといいと思います
コロナ禍も「ウイズ・コロナ」の段階に移り、各地のコンサート会場にも聴衆が戻ってきたので、この流れが続くといいと思います 登原さんが「頑張ります
登原さんが「頑張ります 」と言われたので「頑張ってください。応援しています
」と言われたので「頑張ってください。応援しています 」とエールを送りました
」とエールを送りました 彼女には健康に留意して元気で頑張ってほしいと願っています
彼女には健康に留意して元気で頑張ってほしいと願っています
帰りがけに、定期会員特典CDをいただました 内容は2022年5月21日にすみだトリフォニーホールで演奏された佐渡裕指揮によるベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」のライブ録音です
内容は2022年5月21日にすみだトリフォニーホールで演奏された佐渡裕指揮によるベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」のライブ録音です あとでゆっくり聴こうと思います
あとでゆっくり聴こうと思います