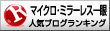映画「ヒトラー最後の12日間」で、1か所だけ、ヒトラーが笑うシーンがある。
アルベルト・シュペーアが、総統地下壕を訪ね、暇乞いをしたとき、ヒトラーは自殺することについて語った。
死ぬのは簡単だ、一瞬のことで苦痛も感じない、という。
そして、「あとは永遠の平安…。」 と言いながら、満足そうに笑う。 シュペーアは、もう何ヶ月もヒトラーの出した破壊指令(ネロ指令のこと)を実行せず、むしろ逆のことをしました、と打ち明ける。聞いたヒトラーは憮然とする。
短いシーンだが、最晩年のヒトラーの心境と置かれた状況が、見事に表現されている、と思う。
総統地下壕に潜り込み、東はソ連、西は連合国の進撃を許し、ベルリン陥落まであと数日ではないか、と言われてきた頃のことだ。軍の退却、降伏、総統自身のベルリン脱出も拒否している。
ヒトラーへの信任は、もうずいぶん前から損なわれてきていたはずであり、前年7月20日には大がかりな暗殺未遂事件も起きている。むしろここまで総統の地位にとどまり続けていたという事実の方が、不思議に思えるくらいだ。
既にイタリアではムッソリーニが、公衆の面前で死体を晒し者にされている。ヒトラーがいちばん気にしたのはただ、自分の死後、遺体を敵に引き渡されたくない、ということであった。側近はもちろん、ドイツ国民が戦後をどう生きるかなど、全く念頭になかった。むしろ、自分と一緒に消えてしまえばいいとすら、考えていた。
死ねば永遠の平安が訪れる。
開戦以来6年間に数千万人の人々を死に追いやった男は、本当に自分に平安がもたらされると考えていたのであろうか。
たぶんではあるが、本気でそう思っていたのだろう。これほどの権力者ではなくても、あらゆることを自分本位に歪曲して解釈できる人は世間にはたくさんいる。というより、自分を客観的に公平に観察できる人の方が少ないかもしれない。
ヒトラーの場合、解釈の歪曲具合があまりにも極端であり、かつ彼なりに整合のとれた世界観に基づいたものであったこと、そして、その彼だけの世界に多くの人が招き入れられ、そしてすっかり魅了させられてしまったというところが、ふつうの人とは違っていたのだろう。
先月読んだ「帰ってきたヒトラー」文庫版の解説で、マライ・メントライン氏が同様のことを述べておられた。この解説はとても見事なもので、それに付け加えるべきことはないと思う。物事をゆがんだ世界でとらえる。それも、あらゆる物事を同じ視点から、等しいゆがみ方で捉えるというのは、誰にでもできることではないのかも知れない。
しかし、ゆがんだ世界観というのは必ず破綻するものだ。40代半ば、首相になったばかりの頃のヒトラーなら、その破綻を目立たぬように見えないところに追いやるとか、一件問題ないように見せることができていたはずだ。最晩年のヒトラーは、その柔軟性やごまかしができなくなっただけで、破綻した世界観そのものは昔からそう変わっていなかったのだと思う。
まあ、あえて言うならば、彼はそうした化け物的な破綻をきちんと見せて、この世を去ってくれたと言うことにもなるのかな。
話は飛ぶけど、村上春樹「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」の「私」は、自我を守ろうとする傾向が非常に顕著な人、とされている。そして、自分の心の奥底に「世界の終わり」という物語世界を作り上げている。小説ではこうした能力は、誰にでも与えられているものではなく、「私」以外の多くの人は混沌し矛盾した物語世界しか築き得ない、のだという。
平行して語られる「世界の終わり」のなかでは、「街」の住人は「心」を失っており、それ故に平安な生活を享受している、とされている。「僕」の隣人である大佐は言う。
「あるいは君はこの街のなりたちのいくつかのものが不自然に映るかもしれん。しかし我々にとってはこれが自然のことなのだ。自然で、純粋で、安らかだ。君にもいつかそれがわかるだろうし、わかって欲しいと私は思う。・・心を捨てれば安らぎがやってくる。これまでに君が味わったことのないほどの深い安らぎだ。そのことだけは忘れんようにしなさい。」
この、一見完璧に見える世界が、実は矛盾のしわ寄せを掻い出して完璧なように見せている世界なのだ、ということに、「僕」は次第に気づいていくという物語なのだが・・。