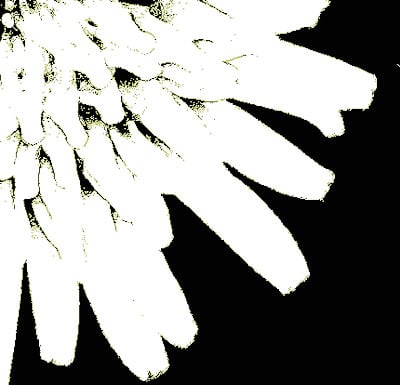2011年度 29
『假名草子集 』から「恨の介」上・下
『假名草子集 』から「恨の介」上・下
日本古典文学大系 90
P、49~P、68 上
P、69~P、88 下
岩波書店
昭和40年 1000円(P,533)
本日 「恨の介」上・下を読了。
上で色深き男五人の名が連なり、思わず白波五人男を思い浮かべたが、話は実話に基づいたもので作者未詳。
五人の名は
葛の恨の助
夢の浮き世の介
松の緑の介
君を思の介
中空恋の介
葛の恨の助は『芦屋道満大内鑑』の「うらみくずのは」なんだね、
きゃはは ははは
夢の浮き世の介は助六、 松の緑の介は松緑を思い浮かべる。
中空恋の介は難尚かとネットで検索すると、能楽「恋重荷(こいのおもに)」 の「恋よ恋 我が中空になすな恋…」からとられているらしい。
では 君を思の介はなんなのか?
ああ、君を思の介なのかと何のひねりもなく、妙に納得
この中に好みの男性はいそうにないが、葛の恨の助は 松平若狭守次と禁中女房との密通 事件を恋物語をモデルに書かれたとある。
「恨の介」下はその話に謡曲や和歌出ふくらみを持たせてあり、読み物としてかなり面白い。
「恨の介」下最後の方で年押しにもう一度 『芦屋道満大内鑑』を匂わす。
はかなさ、せつなさは「恨の介」の文字数に加え倍増する。
仮名草子や古典には物語の中に謡曲や芝居や浄瑠璃や語りや和歌や元話のパロッディーを用い、内容を膨らまし、奥行きを広げる傾向にある。
今の作家もそうなのだろうが、昔は教養がないと物語は書くことができなかったのだと、読む度に痛感する。
「恨の介」のあらすじそのものはこれから読む方の楽しみのためにここでは控えるが、面白かったことを記録しておきたい。
ところで先日から「伊勢物語」と「仁勢物語」を比較して読んだのは去年(2010年)だと書き込んでいたが、一昨年(2009年)だったようだ。
かなり好きだった「竹斎」は昨年読んでいたことに気づく。
年月がたつのは早い。
なんとか今年は去年以上に充実の年にしたい。
おつきあい下さいまして、ありがとうございました。
感謝しています。
これからもよろしく御外申し上げます。