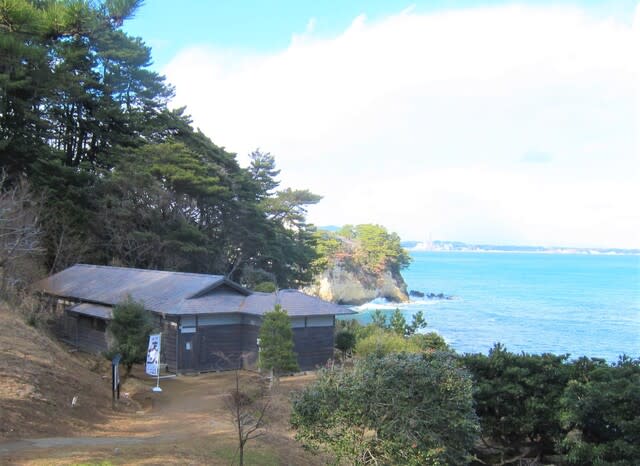オオイヌフグリ(大犬の陰嚢)は「星の瞳」ともよばれる可憐な花ですが、小型の在来種イヌノフグリの二つ連なった実が、イヌの陰嚢みたいだと牧野富太郎博士が付けてしまったため、近縁種で少し大きめの当種にも哀れな名前が付いてしまいました。


ホトケノザ(仏の座)はシソ科オドリコソウ属、茎を取り囲んだ葉が蓮華座に見えることからの命名です。いまは一年中咲いている雑草ですが、この時期がやはり一番きれいな気がします。
なお、春の七草のホトケノザは、キク科で黄色い花が咲き、ロゼット葉が地面に円形に張り付いた様子からの命名です。


ノボロギク(野襤褸菊)も可哀そうな名前が付けられてしまいました。咲いた後の綿毛が襤褸屑のように見える、花が集まって咲いている様子が襤褸雑巾のようだという説などがあるようですが、英名ではなんとold-man-in-the-spring (春の野の老人)!!…せいぜい身だしなみに気を付けようと決意を新たにしました。


ナズナ(薺)は春の七草なので新年の季語ですが、ナズナの花になると春の季語です。アブラナ科の越年草で別名のぺんぺん草の方が有名です。実が三味線のバチに似るので三味線草ともよばれるそうです。

タンポポ(蒲公英)も最近はセイヨウタンポポが圧倒的に多くなりました。花粉による受粉をしなくても単独でタネが実るため繁殖力が強く、在来種の日本タンポポを駆逐しつつあり、日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されています。
この写真を撮ったあと総苞を見たら反り返ったセイヨウタンポポでした。

最後に悪役の登場、枯れても畔道に居座っている「引っ付きむし」の代表オオオナモミです。
北米原産の帰化植物で、鉤状の棘がある実を投げ合って遊んだ少年時代を思い出しますが、衣類や動物に引っ付いて子孫を増やし、ほぼ日本全国を占領してしまいました。
なおマジックテープは、このオナモミの仲間の実からヒントを得て開発されたといわれています。
いぬふぐり星のまたたく如くなり 高浜虚子
犬陰嚢あらぬ文ン字をあてがはれ 高澤良一
畦漏りの走りわかれや花薺 高野素十
ぺんぺん草醜草であれ何であれ 阿波野青畝
三味線草咲きのぼりつつ撥つくる 山口青邨
たんぽぽの皆上向きて正午なり 星野立子
たんぽぽが絮となりゆく喪に入るごと 藤田湘子
※仙人所持の歳時記には、ホトケノザ(シソ科)、ノボロギク、オオオナモミは載っていませんでした。