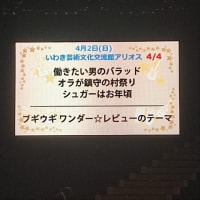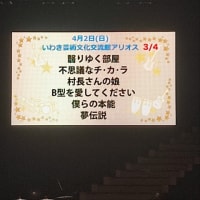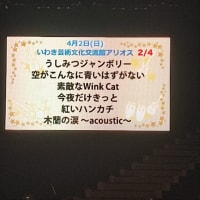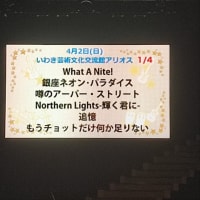大西暢夫監督に初めて会ったのは、今年の春(2020年3月14日)のことだった。
昨年の夏からずっと、大西監督に福島へ来ていただき、『水になった村』<2007年8月4日(土)公開>という映画の
上映会&監督を囲んでの対話の時間&その後じっくりお酒を酌み交わす……
という計画を立てていた。自分たちの仲間でやっているエチカ福島というイベントの第14回になるはずだった。フォーラム福島の阿部さんにサポートいただき、映画館で上映していただけることにもなっていた。特に計画を発案した友人のAは、大西暢夫監督に惚れ込んでおり、この日を心待ちにしていた。
そこに折からのコロナ禍だ。
一時は感染症対策を呼びかけた上での開催も考えたが、最終的に諸事情を勘案して開催を断念することに決めた。
だが、イベントは中止したものの、大西監督のスケジュールもガラガラになっていると聞き、イベントとは別に大西監督を迎えてお酒のみをプライベートで企画することになった。
そこでうかがった話がメチャメチャ面白かったのだが、それは最新刊の『ホハレ峠』の内容だった。
翌日、監督と朝食をとりながら、「『オキナワへいこう』という映画ができたんだよ」という話をうかがう。
これがまた抜群に興味深い。20年間毎週『精神科看護』のグラビアを撮影しつづけていて、その結果としてできあがった映画だという。
『水になった村』という映画、『ホハレ峠』という書籍も、何十年もの時を跨いでできあがった作品で、その取材の重さを感じていたが、『オキナワへいこう』も粘り強いというか、日常との出会いを継続してきた大西監督ならでは、の作品になっている。
前置きが長くなった(コロナ禍で時間だけはあるので)。
連休中、5月2日から、vimeoというサイトで期間限定有料配信がなされていた(再延長がなければ現在は終了、のはず)ものを観た。
すてきな映画だった。
70歳を過ぎた長期入院者の女性が、「沖縄に行きたい」という願いをカードに書く。それは院内のイベントか何かで書いたのだろう。ただし書いた経緯は映画には出てこない。そこも、いい。「沖縄に行きたい」という初期衝動が設定されていて、しかし映画はその直後、その女性が「私いかない」とかたくなに「あきらめる」ところを映し出す。女性の発案で5人の患者さんが沖縄に行く計画に乗り、みんなその気になって看護師と旅行のバッグや荷物を準備始めている時に、である。
映画は、日本の精神科病院が、世界標準からは大きく逸脱した(超)長期入院患者を抱えている「文化」について声高に批判したりはしない。
監督は「明るい映画」にしたかった、とメイキングの自己インタビューで語っている。
そうなのだ。この映画はどこかその「明るさ」に支えられて進行していく。
沖縄行きを希望した人の全てがそれを断念したわけでもなく、全ての人がいけたわけではない。
そのイベントの成否だけが重要なのでもないだろう。
映画が、けっして「オキナワ」にいけるどうかのドラマを描こうとはしていない、ということでもある。
徹底して映画が重視しているのは、おそらく、(ブログ子の感覚でいえば)「出会いを待ち続ける」(by ジル・ドゥルーズ)姿勢だ。具体的で繊細な出会いが、大西監督の映画には溢れている。そしてその出会いは、一瞬一瞬の一期一会で終わるのではなく、「弱い」つながりが「持続する強度」に支えられている。
後半、「オキナワ」に行った患者さんの一人に恋人ができる。その「出会い」についても映画のカメラは丁寧に追っていく。ただ恋人に出会うことだけが重要なのでもない。オキナワに行くという「物語」が重要なのでもない。この映画の目は、そういうことを跨ぎ越して、「生活」をつないでいく。
この感じは、ぜひ映画を観て味わってほしいと思う。
映画が何か人生の一部のシーンや物語を切り取ったり物語ったりするだけの現場ではないことが、そこことこそがしみじみと「明るい」姿勢を肯定できるのだと、分かってくる(ような気がしている)。
映画『オキナワへいこう』も映画『水になった村』も、最新刊『ホハレ峠』も、そういう明るくて丁寧で、繊細で
出会いを大切にしつつそれを長い時間紡いでいく努力の持続を厭わない瞳に支えられている。
私たちが必要としているのは「新しい生活様式」ではけっしてなく、この映画の瞳の力なのだ、と実感した。
ぜひ、観てください。
♯大西暢夫 ♯オキナワへいこう
昨年の夏からずっと、大西監督に福島へ来ていただき、『水になった村』<2007年8月4日(土)公開>という映画の
上映会&監督を囲んでの対話の時間&その後じっくりお酒を酌み交わす……
という計画を立てていた。自分たちの仲間でやっているエチカ福島というイベントの第14回になるはずだった。フォーラム福島の阿部さんにサポートいただき、映画館で上映していただけることにもなっていた。特に計画を発案した友人のAは、大西暢夫監督に惚れ込んでおり、この日を心待ちにしていた。
そこに折からのコロナ禍だ。
一時は感染症対策を呼びかけた上での開催も考えたが、最終的に諸事情を勘案して開催を断念することに決めた。
だが、イベントは中止したものの、大西監督のスケジュールもガラガラになっていると聞き、イベントとは別に大西監督を迎えてお酒のみをプライベートで企画することになった。
そこでうかがった話がメチャメチャ面白かったのだが、それは最新刊の『ホハレ峠』の内容だった。
翌日、監督と朝食をとりながら、「『オキナワへいこう』という映画ができたんだよ」という話をうかがう。
これがまた抜群に興味深い。20年間毎週『精神科看護』のグラビアを撮影しつづけていて、その結果としてできあがった映画だという。
『水になった村』という映画、『ホハレ峠』という書籍も、何十年もの時を跨いでできあがった作品で、その取材の重さを感じていたが、『オキナワへいこう』も粘り強いというか、日常との出会いを継続してきた大西監督ならでは、の作品になっている。
前置きが長くなった(コロナ禍で時間だけはあるので)。
連休中、5月2日から、vimeoというサイトで期間限定有料配信がなされていた(再延長がなければ現在は終了、のはず)ものを観た。
すてきな映画だった。
70歳を過ぎた長期入院者の女性が、「沖縄に行きたい」という願いをカードに書く。それは院内のイベントか何かで書いたのだろう。ただし書いた経緯は映画には出てこない。そこも、いい。「沖縄に行きたい」という初期衝動が設定されていて、しかし映画はその直後、その女性が「私いかない」とかたくなに「あきらめる」ところを映し出す。女性の発案で5人の患者さんが沖縄に行く計画に乗り、みんなその気になって看護師と旅行のバッグや荷物を準備始めている時に、である。
映画は、日本の精神科病院が、世界標準からは大きく逸脱した(超)長期入院患者を抱えている「文化」について声高に批判したりはしない。
監督は「明るい映画」にしたかった、とメイキングの自己インタビューで語っている。
そうなのだ。この映画はどこかその「明るさ」に支えられて進行していく。
沖縄行きを希望した人の全てがそれを断念したわけでもなく、全ての人がいけたわけではない。
そのイベントの成否だけが重要なのでもないだろう。
映画が、けっして「オキナワ」にいけるどうかのドラマを描こうとはしていない、ということでもある。
徹底して映画が重視しているのは、おそらく、(ブログ子の感覚でいえば)「出会いを待ち続ける」(by ジル・ドゥルーズ)姿勢だ。具体的で繊細な出会いが、大西監督の映画には溢れている。そしてその出会いは、一瞬一瞬の一期一会で終わるのではなく、「弱い」つながりが「持続する強度」に支えられている。
後半、「オキナワ」に行った患者さんの一人に恋人ができる。その「出会い」についても映画のカメラは丁寧に追っていく。ただ恋人に出会うことだけが重要なのでもない。オキナワに行くという「物語」が重要なのでもない。この映画の目は、そういうことを跨ぎ越して、「生活」をつないでいく。
この感じは、ぜひ映画を観て味わってほしいと思う。
映画が何か人生の一部のシーンや物語を切り取ったり物語ったりするだけの現場ではないことが、そこことこそがしみじみと「明るい」姿勢を肯定できるのだと、分かってくる(ような気がしている)。
映画『オキナワへいこう』も映画『水になった村』も、最新刊『ホハレ峠』も、そういう明るくて丁寧で、繊細で
出会いを大切にしつつそれを長い時間紡いでいく努力の持続を厭わない瞳に支えられている。
私たちが必要としているのは「新しい生活様式」ではけっしてなく、この映画の瞳の力なのだ、と実感した。
ぜひ、観てください。
♯大西暢夫 ♯オキナワへいこう