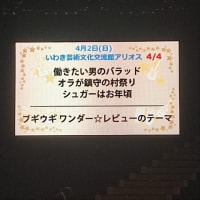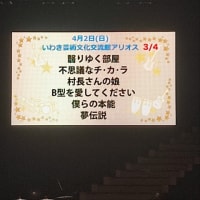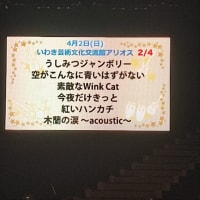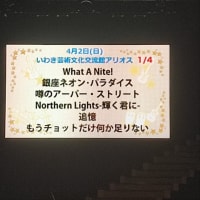『マッカラーズ短編集』を読んだ。
カーソン・マッカラーズは20世紀前半のアメリカ南部のジョージア州で、20才代で小説において圧倒的な才能を開花させた女性だった。
書かれたものは、一見すると互いに理解し合えないまま閉じた生を生きるしかない登場人物たちで満ちあふれていて、当時の時代を考えると非常に奇妙な感じの小説だ。
今で言えばそれはqueer(クィア)な、ということになるのだろう。
今回読んでみて、こんな小説を書いてみたい、という欲望が内側からせり上がってくるのを止めることができなかった。
無論、マッカラーズのような小説が書けるはずもない。
言いたいのは、これは「私のものだ」というその感触だ。
自分の中でその奇妙な(queer)感じを抱かせる、孤独で他者とすれ違い閉じていくしかない登場人物たちが、にもかかわらずこちら側に寄り添ってくるようにすら感じられる感触がある。
読書会のメンバーの一人は、これは「境界線上を描いているんだ」と言っていた。
たしかに、「天才少女」などはまちがいなく、少女から大人へと移ろっていかずにはいられないその境界線の上に立つ極めて微妙で不安定な場所、まるで天使が針の上に立ち得るのかどうかを試しているような危うい描写が、短い作品の中に凝縮している。
もちろんその境界線は、先生と生徒だけではない。子どもと大人、アル中の妻と「正常」な夫、男と男、男と女、女と女、主人公の別れた妻が今の夫との間に倦んだ子と今の恋人が以前に生まれた子どもとの関係(短編だが実に面倒くさい)、境界線はこの作品の至る所に引かれている。
その無数の境界線を描く描写は徹底的に繊細で細部に渡っていて、それが世界の今の閉塞性とその先崩壊を予感させる……。
控え目にいっても、めちゃくちゃ惹かれた短編群だった。
巷では、村上春樹が訳した『心は孤独な狩人』と『結婚式のメンバー』が有名なのだろう。
どれであってもよい、21世紀の空気を吸う私たちは、一度マッカラーズの不自由な描写の中に身を浸してみてよいのではないか。
それは境界線を巡る苦悩の描写であると同時に、境界線が崩壊していく予感や事実の描写でもある。
間違っても、ここにあるのは、村上春樹が描くような物語ではない。物語だけ読めば、不可解な話になる。
村上春樹の本当の才能は、カーバーやティム・オブライエン、マッカラーズを目利きした事実と訳業(誤訳はあるにしても)にあんじゃない?という話も読書会のメンバーから出ていた。なるほどね、という感じ。
(かつて村上春樹の「物語」をむさぼるように読んだ80年代の記憶を持つ自分にとっては、その村上春樹以前を発見する「旅」でもあったのかもしれない……が、それはまあどうでもいい話だ)
文句なく、お勧めです(極めて乏しい外国文学体験の中で、の話ですけど)。