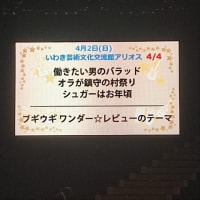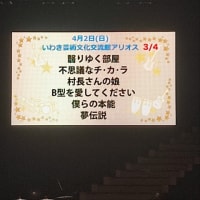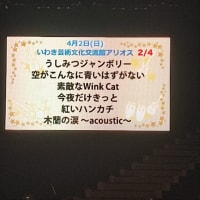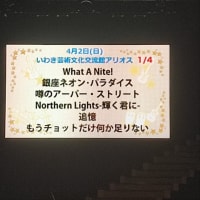熊野純彦の『レヴィナス -移ろいゆくものへの視線』(岩波現代文庫)
を読み始めた。
なんだか、長年の疑問が「溶けて」きそうな気がしている。
『レヴィナス・コレクション』
の文庫を手にしてから、折に触れて何度もページを開いて読もうとはするのだが、とにかく読めなかった。
もちろん、難しい哲学者の、とくに主著と呼ばれるようなものは素人には全く歯が立たないことの方が多い。
解説書を読んで、本人がさほど力を入れていない小著を読んで、書簡を参照して、(自分が幾分か理解でき始めたと思われる)別の哲学者の言葉をヒントにして、ジワジワと理解していくしかない。
お気に入りのはずのスピノザの『エチカ』でさえ、いろいろな先生の講座を受講し、論文を読み、解説本を並べ、たくさんのスピノザ批判を後追いしながら、ようやく面白さを感じてきたのだ。
だが、数あるスピノザ批判の多くは(当然ながら)近代以降の文脈からのもので、腑に落ちるにせよ、突っ込みどころはそこじゃねえだろうと思うにせよ、あるいはそうだね、そこはスピノザの弱いところかもね(17世紀だし)みたいなこともあるにせよ、まあ理解しやすい。
一つのものの見方をある程度体得して、自分のものの見方が「変換」される体験をくぐると、三つ目以降のものの見方についての理解のしやすさが「変化」する。そういうことを学んだような気がする。
たとえていえば、全く別のOSについて勉強することによって、自分が今まで思考してきたその思考を走らせている自分のOSについても認識できるようになるというようなことだろうか。
ところが、レヴィナスについてはそれがうまく行かなかった。
たとえばフーコーはあの大著が読めない、デリダの考え方の大枠は理解できても、テキストが本当に読めない、ということはある。カントの3批判、解説を読んで分かった気になっているとか、ホッブズのリバイアサン、途中で挫折したままだ、とか、そういうことは素人の自分にとっては当たり前のことだ(残念!)。
文学作品なら、ある程度商売だから無理にでも読み切るということはある。
大江のだらだらながい小説でも、100ページまで乗りきれば面白くなる、と思って読めたし、その経験は(順序はぎゃくなのだろうが)ガルシア・マルケスの読破にも役に立った。苦手なドストエフスキーでも、大人になってから(遅い!)修行だと思って読んだりもしている。そして、文学作品はどんなに読むのが難しくても、読んでみればそれはそれで面白い。
ところが、レヴィナスは全く違う。
根本的に、何がなんだか分からないままなのだ。
「顔」とか「他者」とか、何かに取り憑かれたようなこだわりが尋常でないものを感じさせられるキーワードがそこにあるのに、何か今ひとつつかめない、もどかしさを覚える。
スピノザと「OS」が違う、というのは分かる。
そして、よく分からないけれどスピノザ批判の論調はきわめて厳しい。
ここを理解できるようになりたい、と思いつつ何年もそのままにしてきた。
この熊野純彦さんのレヴィナス論は、それ(読めなさあ・分からなさ)を「手触り」から説き起こしてくれるような気がしている。
レヴィナスは、弟子に対して
「問題はこうです。<自分が存在していることで、ひとはだれかを抑圧しているのではないか>このようにして、まさにそのとき、じぶん自身のうえに安らい、<私>は存在するという同一性のもとにとどまりつづけていた、自己同一的な存在者が、じぶんには存在する理由があるのだろうか、と自問することになるのです。」
と語っているという。
なんと受動的というか強迫的というか、とにかく自己と他者の関係を極限まで突き詰めようとする身振りが見えてくる。
熊野純彦さんは、それを丁寧に丁寧に解きほぐしながら説明していく姿勢を止めない。
ありがたいことだ。
ホッブズが発明した「コナトゥス(自己保存の傾向性)」という概念を根本的に問い直すのがレヴィナスだという説明も、腑に落ちる。
そうか、そりゃホッブズを継承しつつある面で書き換えながら思考していったスピノザにもこの「コナトゥス」を称揚する姿勢は間違いなく顕著に存在する。
合わないわけだ。
を読み始めた。
なんだか、長年の疑問が「溶けて」きそうな気がしている。
『レヴィナス・コレクション』
の文庫を手にしてから、折に触れて何度もページを開いて読もうとはするのだが、とにかく読めなかった。
もちろん、難しい哲学者の、とくに主著と呼ばれるようなものは素人には全く歯が立たないことの方が多い。
解説書を読んで、本人がさほど力を入れていない小著を読んで、書簡を参照して、(自分が幾分か理解でき始めたと思われる)別の哲学者の言葉をヒントにして、ジワジワと理解していくしかない。
お気に入りのはずのスピノザの『エチカ』でさえ、いろいろな先生の講座を受講し、論文を読み、解説本を並べ、たくさんのスピノザ批判を後追いしながら、ようやく面白さを感じてきたのだ。
だが、数あるスピノザ批判の多くは(当然ながら)近代以降の文脈からのもので、腑に落ちるにせよ、突っ込みどころはそこじゃねえだろうと思うにせよ、あるいはそうだね、そこはスピノザの弱いところかもね(17世紀だし)みたいなこともあるにせよ、まあ理解しやすい。
一つのものの見方をある程度体得して、自分のものの見方が「変換」される体験をくぐると、三つ目以降のものの見方についての理解のしやすさが「変化」する。そういうことを学んだような気がする。
たとえていえば、全く別のOSについて勉強することによって、自分が今まで思考してきたその思考を走らせている自分のOSについても認識できるようになるというようなことだろうか。
ところが、レヴィナスについてはそれがうまく行かなかった。
たとえばフーコーはあの大著が読めない、デリダの考え方の大枠は理解できても、テキストが本当に読めない、ということはある。カントの3批判、解説を読んで分かった気になっているとか、ホッブズのリバイアサン、途中で挫折したままだ、とか、そういうことは素人の自分にとっては当たり前のことだ(残念!)。
文学作品なら、ある程度商売だから無理にでも読み切るということはある。
大江のだらだらながい小説でも、100ページまで乗りきれば面白くなる、と思って読めたし、その経験は(順序はぎゃくなのだろうが)ガルシア・マルケスの読破にも役に立った。苦手なドストエフスキーでも、大人になってから(遅い!)修行だと思って読んだりもしている。そして、文学作品はどんなに読むのが難しくても、読んでみればそれはそれで面白い。
ところが、レヴィナスは全く違う。
根本的に、何がなんだか分からないままなのだ。
「顔」とか「他者」とか、何かに取り憑かれたようなこだわりが尋常でないものを感じさせられるキーワードがそこにあるのに、何か今ひとつつかめない、もどかしさを覚える。
スピノザと「OS」が違う、というのは分かる。
そして、よく分からないけれどスピノザ批判の論調はきわめて厳しい。
ここを理解できるようになりたい、と思いつつ何年もそのままにしてきた。
この熊野純彦さんのレヴィナス論は、それ(読めなさあ・分からなさ)を「手触り」から説き起こしてくれるような気がしている。
レヴィナスは、弟子に対して
「問題はこうです。<自分が存在していることで、ひとはだれかを抑圧しているのではないか>このようにして、まさにそのとき、じぶん自身のうえに安らい、<私>は存在するという同一性のもとにとどまりつづけていた、自己同一的な存在者が、じぶんには存在する理由があるのだろうか、と自問することになるのです。」
と語っているという。
なんと受動的というか強迫的というか、とにかく自己と他者の関係を極限まで突き詰めようとする身振りが見えてくる。
熊野純彦さんは、それを丁寧に丁寧に解きほぐしながら説明していく姿勢を止めない。
ありがたいことだ。
ホッブズが発明した「コナトゥス(自己保存の傾向性)」という概念を根本的に問い直すのがレヴィナスだという説明も、腑に落ちる。
そうか、そりゃホッブズを継承しつつある面で書き換えながら思考していったスピノザにもこの「コナトゥス」を称揚する姿勢は間違いなく顕著に存在する。
合わないわけだ。
スピノザは、世界=自然=神を唯一の実体と捉え、その外部を断固拒否する。神=自然、以上、である。
レヴィナスは、徹底的に世界と自己の隔たりにこだわり続ける。
もちろん、意識以前の欲求の享受レベルでは、そんな隔たりを動物と同様生まれたての子供は感じてはいない。
しかし、動物ならぬ人間が「生きる」ということは、その世界と自己の隔たりおよびその結節点となる身体の関係について、向き合い直し、捉えなおしてこそ、初めて成立することに違いない。
レヴィナスは、徹底的に世界と自己の隔たりにこだわり続ける。
もちろん、意識以前の欲求の享受レベルでは、そんな隔たりを動物と同様生まれたての子供は感じてはいない。
しかし、動物ならぬ人間が「生きる」ということは、その世界と自己の隔たりおよびその結節点となる身体の関係について、向き合い直し、捉えなおしてこそ、初めて成立することに違いない。
自分として納得のいく結論はまだまださきだが、いろいろ考えるきっかけにはなりそうだ。