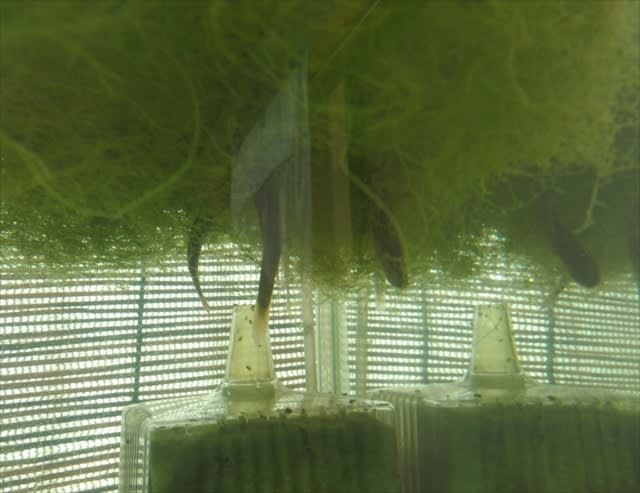梅園で出会ったこの蛾。


名前を知りたくて、「モフモフ・蛾」で検索していたら、なんと!
先日ブログに書いた「名前のわからない繭?」の答えに、たどり着いてしまいました\(^o^)/
この繭を作ったのは、「ナンキンキノカワガ」という蛾の幼虫でした。

梅園で出会った蛾とは、違う種類だと思いますが
「モフモフ」で、繭の製作者が見つかるなんて!運命を感じました(笑)
名前のとおり「ナンキンキノカワガ」は、主にナンキンハゼの葉を食べて
忍者の隠れ蓑のような繭をつくる蛾です。
他の木にもいるかもと、今日あらためて庭で探してみたら、いるいるいる!

代名詞のナンキンハゼの木に、ひとつ。
ヒョウタンボクの木には、抜け殻を含めて8個もあって
そのうち、中身が入ってるの5個に印をしました。


鉢植えの「ギンバイカ」の枝にも3個。

カクレミノ(笑)の幹にも、ちゃっかり隠れていました。

この繭の特徴は、作る場所とウリふたつ、一緒の模様になるという事です。
一本の枝の両面が違う模様なら、繭もその通り両面違う模様になっています。
これは作る工程に秘密があるんです(^^♪
繭は枝の表面に、両端から中心に向かって、交互に作られていきます。
そのとき、木の皮を剥がして繭の表面にくっ付けながら作り進みます。
なので、繭の左右の模様が違って出来上がるのです。
この様子を、動画で撮っている方のブログを見つけて感動しました。


昆虫の種類は同じでも、木の種類によって色が違う繭。
オオデマリのキノカワガ(笑)

芙蓉の枝のもの。

発砲スチロールにくっ付いてた繭は、白かったそうです(^^)
抜け殻の繭は、こんなふうになっていました。

こっちも殻だと思って剥がしたら、抜けてないサナギが入っていた(。・Д・)ゞ
中身が生きているかわからないけど、観察してみます。


白いの(笑)も、何か変化があれば、またブログに書きます。

想いつづけてると、不思議なタイミングで教えて貰えることがあります。
生きてるって、本当にドラマだ!と、思ったりします(^^)
こんなことで、大袈裟ですが(笑)


名前を知りたくて、「モフモフ・蛾」で検索していたら、なんと!
先日ブログに書いた「名前のわからない繭?」の答えに、たどり着いてしまいました\(^o^)/
この繭を作ったのは、「ナンキンキノカワガ」という蛾の幼虫でした。

梅園で出会った蛾とは、違う種類だと思いますが
「モフモフ」で、繭の製作者が見つかるなんて!運命を感じました(笑)
名前のとおり「ナンキンキノカワガ」は、主にナンキンハゼの葉を食べて
忍者の隠れ蓑のような繭をつくる蛾です。
他の木にもいるかもと、今日あらためて庭で探してみたら、いるいるいる!

代名詞のナンキンハゼの木に、ひとつ。
ヒョウタンボクの木には、抜け殻を含めて8個もあって
そのうち、中身が入ってるの5個に印をしました。


鉢植えの「ギンバイカ」の枝にも3個。

カクレミノ(笑)の幹にも、ちゃっかり隠れていました。

この繭の特徴は、作る場所とウリふたつ、一緒の模様になるという事です。
一本の枝の両面が違う模様なら、繭もその通り両面違う模様になっています。
これは作る工程に秘密があるんです(^^♪
繭は枝の表面に、両端から中心に向かって、交互に作られていきます。
そのとき、木の皮を剥がして繭の表面にくっ付けながら作り進みます。
なので、繭の左右の模様が違って出来上がるのです。
この様子を、動画で撮っている方のブログを見つけて感動しました。


昆虫の種類は同じでも、木の種類によって色が違う繭。
オオデマリのキノカワガ(笑)

芙蓉の枝のもの。

発砲スチロールにくっ付いてた繭は、白かったそうです(^^)
抜け殻の繭は、こんなふうになっていました。

こっちも殻だと思って剥がしたら、抜けてないサナギが入っていた(。・Д・)ゞ
中身が生きているかわからないけど、観察してみます。


白いの(笑)も、何か変化があれば、またブログに書きます。

想いつづけてると、不思議なタイミングで教えて貰えることがあります。
生きてるって、本当にドラマだ!と、思ったりします(^^)
こんなことで、大袈裟ですが(笑)