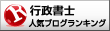昨日、「地域で学校をサポートしよう」という学校問題シポジウムを聞きに行った。精神を病んでしまったり、自殺したりしまった教員達が多数いる事が報告された。
いわゆる、ご自分の子に対する過度とも思える過信と、それによる学校側へのクレームが先生方には自子(自己ではありません、自分の子の事のようです)中心の保護者に思えるようである。そのような事案での対応に悩み、行き詰まって精神を病んだり、場合よって教師達を自殺に追い込むケースも多々あるようだ。
こういった保護者と教師とのトラブル、生徒間同士のトラブル等々、学校内で起こる様々な問題やトラブルが起こった場合には、学校側はどうしても内部でだけで処理解決しようとする傾向があるようだ。一方で保護者側は、アメリカ並の訴訟社会への様相を呈して来た昨今の社会風潮から裁判所での調停や訴訟での解決を求めようとする者達も急増しているようだ。しかしこのようなトラブルは、学校内部だけの閉鎖空間の中でうやむやの形での解決する方法や、損害賠償を基本とする裁判所での調停や訴訟で解決を目指すよりも、裁判外紛争処理(ADR)で事例を継承出来る形で、自主的に解決策を模索する方法が最も適しているし、望ましい方法だと私には思えるのである。
しかし、東京都行政書士会のADRセンターでは、外国人生徒や外国人保護者が絡むADR事案しか法務省から認可されていない。また、当の教職員側も「恥を忍んで、学校問題サポートセンターに相談する」という感覚を未だに持っている教職員がおり、教職員達内部ですべて問題を処理解決しようとする閉鎖体質が未だに残っているようにも見えた。
今でも学校側と保護者側は、問題が起こる度だけ話し合いが行われてしているように見える。本来は、問題無き日頃のコミュニケーションの中で、事が起こる前、つまり、何も起こっていない初期段階、或いは予防としてのPTAなど場で話し合いが行われる事が本来の姿だと私は思うのである。しかし、学校側も保護者側も忙しすぎるので、こういった問題も無い、緊急のテーマも無い話し合いの場を持つこと自体が現代社会の中では極めて難しい事なのかもしれない。
とはいえ、ひとたび問題が起これば、教師達や保護者達、或いは生徒達、すべての者達が同じ学校に居る以上、どうにかして問題を解決しようという双方の明確な意思があるからには、これらのタイプの紛争は、ADR紛争解決手法による解決以外には良い方法はあり得ないとも思える。
以下のような裁判になってしまっては、根本解決からさらに遠のくような気がするのだが・・・。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110118/trl11011812180030-n1.htm
そうゆう意味で、学校問題での東京都行政書士会ADRセンター、いや、ADR機能そのものが本当に実用性があるかどうかの最後の試金石となるかもしれない。
上手く行けば、各市区町村の学校内紛争に於ける調停機関として、東京都行政書士会ADRセンターで訓練された調停行政書士達は、社会的に認知され、更には調停行政書士達が、各市区町村から専門委員として登用される絶好の機会となるかもしれないのである。
もっとも、これで上手く行かなければ、行政書士会費から多額の予算を投じて、今現在殆ど機能していない東京都行政書士会のADR事業は、この際きっぱりと諦めて、完全に撤退すべきではないかとも考える次第だ。
今後の展開に期待したい東京都行政書士会北支部と、同区の小中学校関係者の実験的試みであり、画期的なシンポジウムであったと思う。