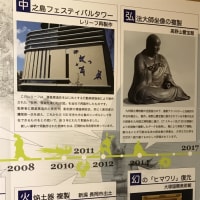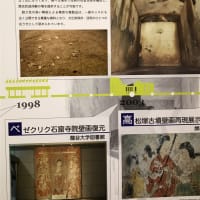フィレンツェといえばドウォーモとウフィッツィ美術館と言われるくらいの名所なので、まずはウフィッツィ美術館を訪れる。
最初、ホテルからの道を間違えたのだが、そもそもフィレンツェはとても小さな街なのですぐ元に戻れることがわかって安心。
写真のベッキオ宮殿の隣に建物としては地味な大きな凹型の建物がある。
予約がないと並ぶ、予約がないと並ぶと脅かされていたので予約を取って望んだウフィッツィであったが、さすがにクリスマス休暇期間中のためかガラガラ。かえって予約のチケットを入り口と別の窓口に受取りに行くのが手間なくらいだった。
美術館は階段を上って3階(イタリア流だと2階)。回廊だけを見ると、ああ、こんなもんか、と思うが、展示室の奥行きがけっこうある。
ちゃんと日本語版のボイスガイドもあるのでそれを聞きながらゆっくり回る。
展示物だけでなく、建物・展示室の装飾が見もの。
回廊の天井は「グロテスク様式」という。
もともとはイタリアで15世紀に洞窟で発見された古代壁画装飾の名称に由来する。そこから人間や動物、植物を空想的な形態で組合せたファンタスティックな装飾芸術の様式をいう。16世紀以降、イタリアのこのグロテスク模様が周りの国々に伝播した結果、その後文学で「グロテスク」という言葉が用いられるようになったらしい。
なので一般に言われる「グロテスク」の語感よりは醜悪な感じはしない。
また、回廊には内側(中庭に面して)は女性の胸像、外側(展示室側)には歴代ローマ皇帝の胸像が並んでいる。
ローマ皇帝の胸像はなかなかにリアルで、塩野七生「ローマ人の物語」でも引用されていて、そこでの皇帝の表情に現れた性格描写を思い出しながら、なるほど、といちいちうなずくことが多かった。
ルネサンス絵画はやはり15世紀後半から16世紀にかけての、表現が劇的に変わるあたりの表現形式の多様性・百花繚乱が魅力的。
17・8世紀に入ると、メディチ家も勢いではなく蓄積した財力と閨閥にものを言わせようという、お大尽になってしまい、絵画もフランス・ドイツが中心になってくるし、魅力が薄れる。
やはり青年期が一番勢いがあるのだろう。
でも、このあと行ったルーブルとかウィーンの美術史美術館のように「世界中から財力にあかせて古今東西の財宝をかき集めた」というのではなく、自分の身の回りのいいものを集めた、という姿勢が、とても真っ当だと思う。
フィレンツェは、町並みといい、教会や美術館といい、レストランといい、とにかく身の丈に近い、変に威張っていない、自然体で格好いいところがいい。
これは昔の街並みの中に古い建物を改装して暮らしているせいだろうか。
そのあと、アルノ川を渡って市を一望するミケランジェロ広場へ(写真)。
一面に広がる茶色い瓦の間からドゥォーモやベッキオ宮が頭を出している。
市内が立て込んでいる(それも趣があるが)分、こういう街を一望できる場所があるのは住んでいる人にとっても憩いの場になるだろう。
最初、ホテルからの道を間違えたのだが、そもそもフィレンツェはとても小さな街なのですぐ元に戻れることがわかって安心。
写真のベッキオ宮殿の隣に建物としては地味な大きな凹型の建物がある。
予約がないと並ぶ、予約がないと並ぶと脅かされていたので予約を取って望んだウフィッツィであったが、さすがにクリスマス休暇期間中のためかガラガラ。かえって予約のチケットを入り口と別の窓口に受取りに行くのが手間なくらいだった。
美術館は階段を上って3階(イタリア流だと2階)。回廊だけを見ると、ああ、こんなもんか、と思うが、展示室の奥行きがけっこうある。
ちゃんと日本語版のボイスガイドもあるのでそれを聞きながらゆっくり回る。
展示物だけでなく、建物・展示室の装飾が見もの。
回廊の天井は「グロテスク様式」という。
もともとはイタリアで15世紀に洞窟で発見された古代壁画装飾の名称に由来する。そこから人間や動物、植物を空想的な形態で組合せたファンタスティックな装飾芸術の様式をいう。16世紀以降、イタリアのこのグロテスク模様が周りの国々に伝播した結果、その後文学で「グロテスク」という言葉が用いられるようになったらしい。
なので一般に言われる「グロテスク」の語感よりは醜悪な感じはしない。
また、回廊には内側(中庭に面して)は女性の胸像、外側(展示室側)には歴代ローマ皇帝の胸像が並んでいる。
ローマ皇帝の胸像はなかなかにリアルで、塩野七生「ローマ人の物語」でも引用されていて、そこでの皇帝の表情に現れた性格描写を思い出しながら、なるほど、といちいちうなずくことが多かった。
ルネサンス絵画はやはり15世紀後半から16世紀にかけての、表現が劇的に変わるあたりの表現形式の多様性・百花繚乱が魅力的。
17・8世紀に入ると、メディチ家も勢いではなく蓄積した財力と閨閥にものを言わせようという、お大尽になってしまい、絵画もフランス・ドイツが中心になってくるし、魅力が薄れる。
やはり青年期が一番勢いがあるのだろう。
でも、このあと行ったルーブルとかウィーンの美術史美術館のように「世界中から財力にあかせて古今東西の財宝をかき集めた」というのではなく、自分の身の回りのいいものを集めた、という姿勢が、とても真っ当だと思う。
フィレンツェは、町並みといい、教会や美術館といい、レストランといい、とにかく身の丈に近い、変に威張っていない、自然体で格好いいところがいい。
これは昔の街並みの中に古い建物を改装して暮らしているせいだろうか。
そのあと、アルノ川を渡って市を一望するミケランジェロ広場へ(写真)。
一面に広がる茶色い瓦の間からドゥォーモやベッキオ宮が頭を出している。
市内が立て込んでいる(それも趣があるが)分、こういう街を一望できる場所があるのは住んでいる人にとっても憩いの場になるだろう。