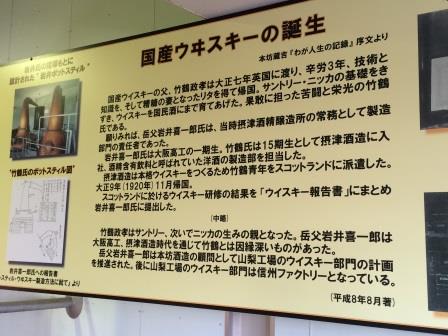TL上を飛び交っていたので読んだつもりになっていたのだが、文庫になってから購入。
科学的知識に限らず「伝えること」「理解すること」それぞれに技法があることについて、「伝えること」のプロと「理解すること」のプロが対談しているところが一番の魅力。
本書は、福島第一原発の事故後、情報を科学的に分析し発信しつづけ、さらには学校給食の陰膳調査やベビースキャン(赤ん坊の内部被ばく測定装置)を開発するなど積極的に行動している早野龍五氏と、ツイッターで早野氏を知って以降自らの行動の指針としてきた糸井重里氏の対談。
CERNを拠点にした原子核物理学者の早野氏はこう語る
物理学者というものは、やっぱり普通じゃない考え方をします。だから、一般の方々に向けて説明するときには、なるべく数式を使わないように、気を付けているんですけどね。ぼくらはグラフを見て、グラフになる元のデータを見て、それから数式を書き、数式を計算した結果を見て、そういうものと、それから自然界のものを見比べるということをやっている、非常に特殊な人たちなわけです。
・・・ですからやはり科学的には必要なくても、ベビースキャンは必要なんです。実際、稼働させてみてわかったのは、この機械はものすごいコミュニケーションツールなんだということです。
・・・ベビースキャンがあることによって、今までぼくらが話すことができなかったような、「放射線の影響をとても心配しているお母さんたち」がお子さんを連れて来てくれるわけです。それで話してみると、お母さんたちが何を心配しているのか、ということが具体的にわかります。ひとつひとつうかがっていくと、驚くようなこともありますよ。僕たちが想像できないようなことを心配したりして。やっぱり、お互い話さないと、理解できないし、心配は消えないわけです。
・・・震災以降の日々は、ぼくにとっては、あらゆるものが新鮮でした。最初は、コミュニケーションにしても非常に下手でした。四苦八苦しながら、だんだん、社会に対して語るというのがどういうことなのかが、わかってきました。その過程で、ぼくは、科学と社会の間に絶対的な断絶がある、ということを気づかざるを得ませんでした。放射線のことを知っているとか知らないとか、そういう知識の有無とはまったく別の次元です。「混乱した状態から、より真実に近い状態と思える方に向かって、手続きを踏んでいく」というサイエンスとしての考え方を、一般の人に理解してもらうのはとても難しいと知ったのです。
たぶんこれは科学と社会でだけでなく、専門分化した世の中でのコミュニケーション全般に言えることでもある。
事故などの際に業界・同業での常識や用語を前提とした説明は、それが客観的には顧客などの安全に配慮したものであったとしても、問題を大きくすることはよくある。
(身近なところでは合コンでの自己紹介が自慢にしか聞こえない、なんてのもありますな)
経済学者の議論などはそもそも同業なのに前提がすりあっていないことはしょっちゅうで、剣道の流派と違って他流試合自体が成立しないように見えるのは不思議ですらある。
政府の出す「○○戦略」もそうで、いろんな利害関係者に配慮した玉虫色にならざるを得ない部分はわからなくもないが、そういう複雑な状態から「より真実に近い状態と思える方に向かって、手続きを踏んでいく」意思を読むほうにわかるように見せているかが問われるが、今回のはどうであろうか。
話は脱線してしまったが、糸井重里は2011年のツイートを引用してこう言っている。
<ぼくは、じぶんが参考にする意見としては、
「よりスキャンダラスでないほう」を選びます。
「より脅かしてないほう」を選びます。
「より正義を語らないほう」を選びます。
そして、「よりユーモアのあるほう」を選びます。>
そう。温度の高い言葉は、語り手が熱を持つことを伝えはするが、必ずしも相手にその熱自体を伝えることにはならない。