
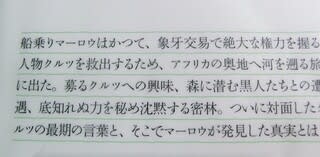
光文社の新訳シリーズだから、という理由だけでピックアップしました。
コロナ禍の図書館内滞在時間が30分以内に限られる中、借りる本をささっと選び出す☆彡 じっくり選べないものの、時と場合によっては、今までの自分なら、手にしなかったかもしれない本を手にすることもあります。✋
これも、そんな一冊でした。
まず、作家名からして、耳にしたことがありません。
原作は英語で書かれたそうですが、著者、コンラッドは1857年生まれ。父親は貴族でフランス、イギリス文学に精通していた。ロシア、プロイセン、オーストリアの間で分割されたポーランド出身。(現ウクライナ)
父はポーランド独立運動に関わった罪で妻子共にロシア北部へ流刑に。両親死亡、彼は孤児になってしまいます。
彼の生い立ちを知っただけで、何故、『闇の奥』のような小説が生まれたのかが、理解できる気がします。実体験をもとに書かれた小説らしいので。
1860年代当時、迫害を受ける側だったポーランド人の作者は、船乗りとなり新天地へ。
生まれは貴族の彼が、船乗りになる、というだけでも当時は驚きだったのでは? ヨーロッパ人なので、古代ローマ帝国の歴史を学ぶのは常識だったでしょうし、小説の前半にも、最初に新天地へ足を踏み入れた古代ローマ人達の気持ちは、恐らく、こうであっただろうという記述が出てきます。その記述...最初の方こそ私も共感するものの、後半は... 「ただの搾取にすぎない? 違うでしょ!」と言いたくなってしまった。少なくともアフリカ大陸の一部が砂漠化し始めたのは、古代ローマ帝国が衰え始めてから。それまでは緑豊かな土地だったのに。農地は耕さなければ砂漠化する。歴史を知ら... あ、そうか。かれはポーランド人。そう言いたくなる筈だ…と納得。
この小説の内容...読めば嫌い、と感じる人の方が多いかもしれません。今の価値観と照らし合わせれば猶更です。小説の主人公は船乗り。作者自身も船乗りだった。時代は、植民地から一方的に搾取することが当然という価値観だったイギリス、フランス、スペインなどが世界の覇者だった時代。(余談ですが、もし、インカ帝国を発見したのがスペイン人ではなく、(古代ローマ人のような)イタリア人だったとしたら、インカ帝国は滅びなかっただろう、と今もヨーロッパでは言われているらしいですね。私もこれに強く同感!)
幕末を描いたこちらの小説では、植民地を巡る日本人一行の驚き、ショック、「技術は優れていても、英国人は野蛮人。文化は遅れていますな」という感想を漏らす侍一行の様子が描かれており...『竜は動かず』著:上田秀人
幕末の日本人ですら、そのように感じるのだから。現地の人達がどのようにイギリス人に扱われていたかを知れば、現代人はショック死しそうです。それ故、小説の記述には批判も出そうです。ただ... あの時代はこういった価値観がまかり通っていた。だから現代の物差しで過去を理解しようにも...
それは作者のコンラッドに対しても、古代ローマの記述について、言いたいことでもありますが、すでに作者はあの世ですから。
古代ローマ帝国のガレー船を漕いでいた、いざとなれば戦士もかねる名誉ある船乗り達とは、イギリス、フランスの植民地支配下の時代では、船乗りの立ち場も随分違っていたのではないかと...小説から想像できました。あなたが生きていた時代と紀元前に生まれたローマ帝国とでは、違うのですよ、と...。
敢えてお勧めは致しませんが、こういう書物もあるのだと知りました。植民地支配を知るには良い資料であり、小説です。解説者によれば、作家の実体験が反映されているだけに。
申し訳ありませんが、この後、パラリンピック閉会式を見る為、コメント欄は閉じておきます。自分でも何を言っているのか分からない、支離滅裂な文章でもあるので

マラソン、感動的でした~☆彡 笑顔が眩しい~\(^o^)/


















