
低山へのハイク、再開第二段は同じ吉井の多胡美人と云われる朝日岳北峰と南峰。
r-71で南進して神戸(ゴウド)バス停から右折して甘楽町田口への幅広林道に入る。
100m程で吉井と甘楽町の境界線がありそこに道標。林道の名前は「草喰八丁河原線」
という変わった命名、管轄は甘楽町でこの道標が起点とされるから同じ道でも
吉井側の100mは無名かな?

林道頂点近くの登山口に着いたらたった一台分の駐車スペースには先客があり
仕方なく少々戻って看板多数の小園地風の所に駐車して林道を西に登る。

僅かの距離で「朝日岳北登山口」の道標前。

実はこの先の林道頂点には平成19年頃は「天引城登口・城主甘尾若狭守」の
道標があった。多分、出所は甘楽町史」の記述「天引城址は「一郷山・八束」両城と
一線に並んだ単峰式山城、関東管領上杉憲政の旗下・甘尾若狭守居城」辺りかな?

ところが平成24年頃から表示が変わって「天引城登口・城主小幡羊太夫宗勝」と
完全に伝説の世界に逆戻りしている。
これも爺イの知る限りの根拠は「新屋村その史話と名物」の記事に
「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として天引村に城山を築き、
物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、
城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」とか「甘楽郡史」の
「天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う」
又は羊太夫研究者の年表に「711年多胡郡建置。藤原宗勝 上野国権大目となり
六位下を授位。郡司となる。それまで住んでいた長根(辛科神社の近く)から
新屋(甘楽町)に移る。小幡羊太夫宗勝と名乗るーーーなどが在る事は確か。

閑話休題。
登山口を入ると急斜面に明瞭な登路があり斜め右に進んで高度を上げる。
登山口の標高が大体250mなので頂上の城址本丸跡までの比高は200m。

やがてこのマークと矢印道標が現れ、右から似たような登路が東進しながら
合流する。多分、林道頂点の登山口から来たものと思われる。
合流して東進なのでこちらは左に急旋回。

間も無くロープが現れ上部の平地に登り上げる。このルートは実に丁寧に
補助ロープが多く設置してあるので爺イの様な足弱には大助かり。

細長い平地に着く。

左右どちらかでも前進できるが左岩にロープがあるので岩場に向かう。

城址の概念図を当てはめるとここはもう追手(大手)虎口なのかも知れない。

岩場を過ぎると別のロープで更に上の稜線に向かって進む。

途中に可憐な花、葉の出る前に咲いているから若しかするとアカヤシオ?

急登をクリヤすると大岩の前、どうやら尾根に乗ったらしい。

尾根はやや湾曲しながら延びていくが傾斜は緩く高度稼ぎにはならない。

途中に複雑化した切れ込み、これも遺構の一つかも。

やがて左右に綺麗に展開する横堀のような処。

ロープの助けを借りて一登りすると

正面に北峰本体らしき山が見えて来たが予想以上に未だ距離がある。

暫く進んでこのコブか小ピークにも見える高み乗り越えると漸く直下に近づく。

本体への登り始めはこんな具合の所をやや左目に。

漸く台地の様なものが目の前に。いよいよ三段の虎口受けの始まりらしい。

左右に振られながら進むと平地。これは曲輪?

目の前には直ぐ高み。

ロープで這い上がると

前面に本丸跡が控える綺麗な帯曲輪が左右に広がっている。

最後の一踏ん張りで頂点に登ると下山用の道標が出迎え

広々とした本丸跡の北峰頂上台地に到着。

中央に三角点。三等で点名は「草喰」448.16m

三角点を前にして本日の爺イ。あと、何年ハイクを続けられるか判らないので
せっせと記録を残しておく。

近くに長持ちしそうな頂上標識。

東ルートの案内標識を確認してから南峰に向かう。

南峰への尾根には曲輪への下り二回と深堀切一箇所が待っていて何れも
ロープのお世話になる。
最初の曲輪への下り

二番目の下り

堀切への下りは足が段差に届かずやや苦戦するが反対側への登りには
ロープは無く左目に迂回ルートが作られている。

その先の尾根は平坦で最後に僅かに傾斜があるだけ。

今にも落下しそうな標識に迎えられて狭い岩畳のような南峰頂上着。

南向きの岩帯からは遥か下に東谷のダム湖が望める。

一呼吸置いてから稜線の西100mにある旧友に会いに行く。この旧友とは
もう10年以上の付き合いーーだが只の人面岩だ。
途中でアカヤシオらしき群落地帯を通過する。わざわざ西上州で列を作ってワサワサと
名所の山に登らなくても爺イはこれで充分。










更に西に50mでこれが友人。左は普通の姿、右は加工したもの。

ここで再び本日の爺イ、人面岩とほぼ同じ背丈。
陽だまりで軽食と休憩。

こんな斜面の細道を使って南峰に戻り下山スタート。

帰路は周回で南峰から直接東コースを使う。このコースは結構変化に富み
難所はロープ無しでは年寄りには危険。ある時期、当時使われていた麻ロープ
が老朽で擦り切れて使用不能になり爺イも長い事このコースは使っていない。
南峰から僅かに下ったところのこのマークから東コースが分岐している。

最初は大人しい尾根を下るが

やがて岩の隙間を通るようになり

難所の崖下り箇所に来る。

しかし、懸念は当たらず立派な鎖が設置されていた。

慎重に途中まで降りると鎖の先端は太目のロープに連結されそのまま
第一段をクリヤできた。

反転して第二段に掛かるとこちらはロープ。

難所が無事に通過できて調子に乗ってグングン下ったら突然周囲の
様子がオカシイ。大体マークが見当たらないし下地も荒れ放題で
とてもルートとは思えないし斜面が右に離れすぎでいる。
間違いと悟って20mほど登り返して漸く右手にマーク捕捉。

ルートはこのマークから右に急旋回していたのだ。元に戻ってこんな所を
歩く。

ロープて゜段落を下るとこのコース名物の奇岩が目の前。

振り返ると同様なものが逆光の中に見えた。もっと有ったんだろうけれど
下ばかり見ていたから見逃したかも。

路は右の稜線に着かず離れずで続く。

北にあたる左手に見えるこの頂はさっき通過した北峰だろうか?
一寸山頂台地が大きいから違う山か?

又、ロープで下降すると

目の前に巨大な奇岩。

ルートはその寸前で右に急旋回してやがて何となく終盤を期待させる
雑木と竹林にかかる。

そして墓地脇で下山は終了、結局案内にあった第二登山口へのルートは
全く気付かなかった。

ダラダラ下りで集落を抜けていくと吉井の車道近辺は花盛り











過去に何回か駐車させてもらった住吉神社通過。

神戸バスていから林道を約400mほど登って無事に帰着。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
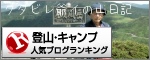
本日の蛇足。
*「甘楽郡史」より引用
天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う。されど千余年
の星霜を経たれば、今や砕かれたる。少しばかりの礎、巌に残る胸壁の跡らしき
もの、空しく往昔の面影を留めるのみ、国破れて山河あり、城春にして草木深し。
*「新屋村その史話と名物」より引用
「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として天引村に城山を築き、
物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、
城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」
(この「城山」が朝日北峰なのだが地形図では八束山に「城山」の表記)
「甘楽町史」の記述から引用
天引城址は「一郷山・八束」両城と一線に並んだ単峰式山城、山頂の径
12―13㍍の小郭。二の丸は腰曲輪状に8㍍下、その下に東と南に
小さい腰曲輪が付き其処から下に掘り切り。西北尾根に掘り切りと4段の
腰曲輪、その先3段の虎口受。
(虎口(コグチ)は城兵の出入り口、虎口受けはそれに付随する平地、一郷山とは
現在牛伏山)
上野国郡村史」に「――天引城墟、村人能ク遺事ヲ説くモノナシーー」と
書かれてしまう程度である。かってこの地は武田・上杉・北條の
三つ巴戦の台風の目の存在であったのにである。
*「上野志」より引用
東部の白倉氏、甘尾氏も小幡一族、天引城は国峰城の外防線としての61個の砦の一つ。
*「上野国志」より引用
箕輪城記に天引城ありきと云、信玄の為に屠られる。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
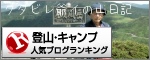
r-71で南進して神戸(ゴウド)バス停から右折して甘楽町田口への幅広林道に入る。
100m程で吉井と甘楽町の境界線がありそこに道標。林道の名前は「草喰八丁河原線」
という変わった命名、管轄は甘楽町でこの道標が起点とされるから同じ道でも
吉井側の100mは無名かな?

林道頂点近くの登山口に着いたらたった一台分の駐車スペースには先客があり
仕方なく少々戻って看板多数の小園地風の所に駐車して林道を西に登る。

僅かの距離で「朝日岳北登山口」の道標前。

実はこの先の林道頂点には平成19年頃は「天引城登口・城主甘尾若狭守」の
道標があった。多分、出所は甘楽町史」の記述「天引城址は「一郷山・八束」両城と
一線に並んだ単峰式山城、関東管領上杉憲政の旗下・甘尾若狭守居城」辺りかな?

ところが平成24年頃から表示が変わって「天引城登口・城主小幡羊太夫宗勝」と
完全に伝説の世界に逆戻りしている。
これも爺イの知る限りの根拠は「新屋村その史話と名物」の記事に
「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として天引村に城山を築き、
物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、
城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」とか「甘楽郡史」の
「天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う」
又は羊太夫研究者の年表に「711年多胡郡建置。藤原宗勝 上野国権大目となり
六位下を授位。郡司となる。それまで住んでいた長根(辛科神社の近く)から
新屋(甘楽町)に移る。小幡羊太夫宗勝と名乗るーーーなどが在る事は確か。

閑話休題。
登山口を入ると急斜面に明瞭な登路があり斜め右に進んで高度を上げる。
登山口の標高が大体250mなので頂上の城址本丸跡までの比高は200m。

やがてこのマークと矢印道標が現れ、右から似たような登路が東進しながら
合流する。多分、林道頂点の登山口から来たものと思われる。
合流して東進なのでこちらは左に急旋回。

間も無くロープが現れ上部の平地に登り上げる。このルートは実に丁寧に
補助ロープが多く設置してあるので爺イの様な足弱には大助かり。

細長い平地に着く。

左右どちらかでも前進できるが左岩にロープがあるので岩場に向かう。

城址の概念図を当てはめるとここはもう追手(大手)虎口なのかも知れない。

岩場を過ぎると別のロープで更に上の稜線に向かって進む。

途中に可憐な花、葉の出る前に咲いているから若しかするとアカヤシオ?

急登をクリヤすると大岩の前、どうやら尾根に乗ったらしい。

尾根はやや湾曲しながら延びていくが傾斜は緩く高度稼ぎにはならない。

途中に複雑化した切れ込み、これも遺構の一つかも。

やがて左右に綺麗に展開する横堀のような処。

ロープの助けを借りて一登りすると

正面に北峰本体らしき山が見えて来たが予想以上に未だ距離がある。

暫く進んでこのコブか小ピークにも見える高み乗り越えると漸く直下に近づく。

本体への登り始めはこんな具合の所をやや左目に。

漸く台地の様なものが目の前に。いよいよ三段の虎口受けの始まりらしい。

左右に振られながら進むと平地。これは曲輪?

目の前には直ぐ高み。

ロープで這い上がると

前面に本丸跡が控える綺麗な帯曲輪が左右に広がっている。

最後の一踏ん張りで頂点に登ると下山用の道標が出迎え

広々とした本丸跡の北峰頂上台地に到着。

中央に三角点。三等で点名は「草喰」448.16m

三角点を前にして本日の爺イ。あと、何年ハイクを続けられるか判らないので
せっせと記録を残しておく。

近くに長持ちしそうな頂上標識。

東ルートの案内標識を確認してから南峰に向かう。

南峰への尾根には曲輪への下り二回と深堀切一箇所が待っていて何れも
ロープのお世話になる。
最初の曲輪への下り

二番目の下り

堀切への下りは足が段差に届かずやや苦戦するが反対側への登りには
ロープは無く左目に迂回ルートが作られている。

その先の尾根は平坦で最後に僅かに傾斜があるだけ。

今にも落下しそうな標識に迎えられて狭い岩畳のような南峰頂上着。

南向きの岩帯からは遥か下に東谷のダム湖が望める。

一呼吸置いてから稜線の西100mにある旧友に会いに行く。この旧友とは
もう10年以上の付き合いーーだが只の人面岩だ。
途中でアカヤシオらしき群落地帯を通過する。わざわざ西上州で列を作ってワサワサと
名所の山に登らなくても爺イはこれで充分。










更に西に50mでこれが友人。左は普通の姿、右は加工したもの。

ここで再び本日の爺イ、人面岩とほぼ同じ背丈。
陽だまりで軽食と休憩。

こんな斜面の細道を使って南峰に戻り下山スタート。

帰路は周回で南峰から直接東コースを使う。このコースは結構変化に富み
難所はロープ無しでは年寄りには危険。ある時期、当時使われていた麻ロープ
が老朽で擦り切れて使用不能になり爺イも長い事このコースは使っていない。
南峰から僅かに下ったところのこのマークから東コースが分岐している。

最初は大人しい尾根を下るが

やがて岩の隙間を通るようになり

難所の崖下り箇所に来る。

しかし、懸念は当たらず立派な鎖が設置されていた。

慎重に途中まで降りると鎖の先端は太目のロープに連結されそのまま
第一段をクリヤできた。

反転して第二段に掛かるとこちらはロープ。

難所が無事に通過できて調子に乗ってグングン下ったら突然周囲の
様子がオカシイ。大体マークが見当たらないし下地も荒れ放題で
とてもルートとは思えないし斜面が右に離れすぎでいる。
間違いと悟って20mほど登り返して漸く右手にマーク捕捉。

ルートはこのマークから右に急旋回していたのだ。元に戻ってこんな所を
歩く。

ロープて゜段落を下るとこのコース名物の奇岩が目の前。

振り返ると同様なものが逆光の中に見えた。もっと有ったんだろうけれど
下ばかり見ていたから見逃したかも。

路は右の稜線に着かず離れずで続く。

北にあたる左手に見えるこの頂はさっき通過した北峰だろうか?
一寸山頂台地が大きいから違う山か?

又、ロープで下降すると

目の前に巨大な奇岩。

ルートはその寸前で右に急旋回してやがて何となく終盤を期待させる
雑木と竹林にかかる。

そして墓地脇で下山は終了、結局案内にあった第二登山口へのルートは
全く気付かなかった。

ダラダラ下りで集落を抜けていくと吉井の車道近辺は花盛り











過去に何回か駐車させてもらった住吉神社通過。

神戸バスていから林道を約400mほど登って無事に帰着。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
本日の蛇足。
*「甘楽郡史」より引用
天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う。されど千余年
の星霜を経たれば、今や砕かれたる。少しばかりの礎、巌に残る胸壁の跡らしき
もの、空しく往昔の面影を留めるのみ、国破れて山河あり、城春にして草木深し。
*「新屋村その史話と名物」より引用
「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として天引村に城山を築き、
物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに讒言により官軍に攻めこまれ、
城山を捨てて敗走、八束の城にて防戦す」
(この「城山」が朝日北峰なのだが地形図では八束山に「城山」の表記)
「甘楽町史」の記述から引用
天引城址は「一郷山・八束」両城と一線に並んだ単峰式山城、山頂の径
12―13㍍の小郭。二の丸は腰曲輪状に8㍍下、その下に東と南に
小さい腰曲輪が付き其処から下に掘り切り。西北尾根に掘り切りと4段の
腰曲輪、その先3段の虎口受。
(虎口(コグチ)は城兵の出入り口、虎口受けはそれに付随する平地、一郷山とは
現在牛伏山)
上野国郡村史」に「――天引城墟、村人能ク遺事ヲ説くモノナシーー」と
書かれてしまう程度である。かってこの地は武田・上杉・北條の
三つ巴戦の台風の目の存在であったのにである。
*「上野志」より引用
東部の白倉氏、甘尾氏も小幡一族、天引城は国峰城の外防線としての61個の砦の一つ。
*「上野国志」より引用
箕輪城記に天引城ありきと云、信玄の為に屠られる。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます