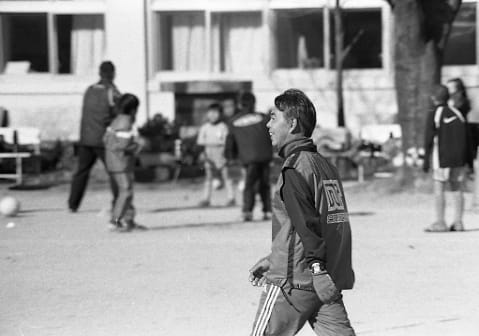この間から印画紙に最大黒を出す時間を基準に現像条件を詰めていくと、ずいぶんネガの濃度を上げなくてはいけないことがわかり、D-76(1:1)@22℃で11分も現像をやることになった。ネガはも濃度がだいぶ高くなったが、その分印画紙に露出をかけられるので、出来上がりもコントラストが高い。
ただ、問題はシャドーの諧調が失われ、要するにシャドウに多少ネガ濃度があっても印画紙に露光をたっぷりかけるので、黒がつぶれてしまうのだ。攪拌の仕方か何かで逃げようかと思ったが、なんだかそれもよくわからない。
本や富士のデータなどを見ても、標準的な現像時間は長くても9分くらいまでのようでもあり、やはり現像時間が長すぎるのはおかしい気がまたしてきた。確かにネガの濃度は現像時間が延びるほど高くはなっている。できるだけ濃度の幅を広くしたほうが良いとすればネガの濃度が飽和するまで現像時間を延ばしたほうがいいようにも思える。でも、実際は印画紙の方があまり幅広く濃度を受け入れられないことから、ネガの濃度域をMAXまで持っていくことはできないということのようだ。
結局、印画紙の最大黒までシャドーを出すことはできないということになり、そうなると印画紙に露光する時間ももう少しつめてもいいのでネガ濃度はそんなにいらないから現像時間ももうちょっと短くしてもいいということにかな。
だんだんトレードオフが見えてきた気がする。現像時間を伸ばせば黒はしっかり出るようになるもののシャドーの諧調が失われる。現像時間を短くすると軟調になって諧調は出るけど黒のしまりがなくなっていく。完璧はない。どこで折り合いをつけるかということのようだ。
理論は本を読めばわかるけど、それより大事なことはそういう違いがネガや印画紙の上で認識できるようになってきたということだと思う。理解するということはロジックだけではなく、感じることなんだから。
ただ、問題はシャドーの諧調が失われ、要するにシャドウに多少ネガ濃度があっても印画紙に露光をたっぷりかけるので、黒がつぶれてしまうのだ。攪拌の仕方か何かで逃げようかと思ったが、なんだかそれもよくわからない。
本や富士のデータなどを見ても、標準的な現像時間は長くても9分くらいまでのようでもあり、やはり現像時間が長すぎるのはおかしい気がまたしてきた。確かにネガの濃度は現像時間が延びるほど高くはなっている。できるだけ濃度の幅を広くしたほうが良いとすればネガの濃度が飽和するまで現像時間を延ばしたほうがいいようにも思える。でも、実際は印画紙の方があまり幅広く濃度を受け入れられないことから、ネガの濃度域をMAXまで持っていくことはできないということのようだ。
結局、印画紙の最大黒までシャドーを出すことはできないということになり、そうなると印画紙に露光する時間ももう少しつめてもいいのでネガ濃度はそんなにいらないから現像時間ももうちょっと短くしてもいいということにかな。
だんだんトレードオフが見えてきた気がする。現像時間を伸ばせば黒はしっかり出るようになるもののシャドーの諧調が失われる。現像時間を短くすると軟調になって諧調は出るけど黒のしまりがなくなっていく。完璧はない。どこで折り合いをつけるかということのようだ。
理論は本を読めばわかるけど、それより大事なことはそういう違いがネガや印画紙の上で認識できるようになってきたということだと思う。理解するということはロジックだけではなく、感じることなんだから。