 「今日の何時だった?」
「今日の何時だった?」黙々と朝飯を食っていた父、源治が急に思い出しでもしたかのように訊いた。
優子はハッとして台所の方へ目をやった。
そこには多津子がいて、味噌汁のお代わりを入れている。さりげなくふり返った多津子は優子にニッコリと笑って見せた。万事解決したから安心しなさいと言っている風だった。
多津子は優子にとっては二人目の母になる。俗に継母と言われるが、物心つく前から多津子に育てられて来た優子は、彼女しか母を知らなかった。正に生みの母より育ての母の典型だった。
「確か十一時には来られると言ってたわね」
「うん」
多津子の助け舟に優子は素直に頷いた。
「そうか」
源治は他人事みたいに言った。後は表情も変えずに黙々と飯をかき込んでいる。
父の無愛想なのは馴れているが、昨夜の口喧嘩のしこりが残っている分、優子は気が気じゃなかった。機嫌がいいのか悪いのか、全く判断がつかないのは困る。これまでに何度同じ立場に立たされて気を揉んだことか。
まして今日は特別な日である。優子の一生を決める大事な儀式が執り行われる段取りになっていた。十一時頃に、恋人の卓也が仲人を伴って現れる筈だった。
仲人が一緒に来ても未だ結納と言う訳じゃない。源治に「大事な娘さんを頂けないか」と正式に申し込むための訪問である。
「ああ見えても、お父さん、キッチリしないといられない性分だから、形式を踏む方が案外うまく行くんじゃない」
多津子の入れ知恵である。長年、夫婦として寄り添って暮らして来ただけに、多津子は彼の気性を充分に承知している。だからこそ、結婚話を頑固な父親にどう切り出していいものやらと悩みを募らせていた優子にとり、最高の助言者となった。
優子は卓也と相談して、急遽、卓也の叔父のの小杉に仲人を頼み込んだのである。小杉は拍子抜けするぐらいアッサリと引き受けてくれた。そして今日、決行の日を迎える事になった訳である。
「お父さん、あした家にいてくれる」
優子がそう切り出したのは前夜だった。
「なんでや?」
目の前のテレビで贔屓のチームが負けているせいもあったが、えらくぶっきら棒に源治は訊き返した。眼は画面から外しもしない。
「江森さんが来るんや。逢うてほしいねん」
「なんで逢わなあかんのや、わしは逢わん」
「そない言わんと、大事な事やから」
「大事な事て何や?」
源治の口調はますます不機嫌になった。釘付けになっている画面は、ホームランによる追加点が入っていた。ボリュームが一段と高まった感じである。
「あんた、あの事やがな」
台所で洗い物をしていた多津子が言った。
「アホ!お前に訊いとるんやない」
源治は声を荒げた。
「ほんなら、娘の頼み、ちゃんと訊いたったらどない?ほんま素直やないんから」
エプロンで濡れた手を拭いながら居間に入って来た多津子は、手を伸ばしてテレビを消した。
「チェッ」
源治は舌打ちすると、苛々した手付きで煙草を取り出して、くわえた。
「さあ、優ちゃん、これでちゃんと訊いて貰えるさかいな」
そう言うと、多津子は勝負の判定を下す審判よろしく、父と娘が向き合った間にドカッと座った。
「江森さん、仲人さん連れて来はるんや」
「だらしない男やのう。一人では来られへんのか」
「ううん、やっぱり大事な事やから、きっちりした形を取りたいんやて」
「わし、逢わへんで」
「お父さん!」
源治は煙草の煙をやけに吐いた。
「あんた、優ちゃんの結婚の事やで。折角、足運んで来はる相手さんにも失礼やし」
「まだ、うちの娘、嫁にやる気はあらへん」
源治は天井を睨んで紫煙を吹き上げた。何を考えているのか全く読み取れない父の表情だった。眉間の皺が微妙に震えている。
「そない言うたかて、本人は結婚したい希望なんやろ、前向きに考えたったらどない?」
「ほなら勝手にせんかい。大体、親の知らんとこでこそこそ段取りつけよってからに」
「それは、うちがあんたに報告して納得して貰うたやろ」
「知らん!わしは納得した覚えあらへん!」
源治と多津子はお互いに譲らぬ気らしく、言い合いはエスカレートするばかりである。
「もうええ!」
優子は堪忍袋の緒を切った。普段は声を荒げるなど殆んど見せた事のない優子だから、さすがに源治もギョッとして娘を見直した。
「もう知らん!いっつも、いっつも、そうなんやから、お父さんは…自分だけ勝手な事ばかりして、家族の事なんか…考えたりした事あらへんのや。…もうええ!」
「な、なに…!?」
怒鳴りかけた源治は、急に萎んでしまった。
目の前で娘が泣いていた。小さい頃から、いつも家に一人で留守をさせて来た娘である。根っから放蕩な血を持ったお陰で、一つ所に落ち着けず、友達も作れなかった娘である。
それでも何一つ父に泣き言を言わぬ勝気な娘で、ただじーっと我慢を続けていたのを、親らしくない親の源治にも判っていたに違いない。だから、源治は黙るしかなかった。
「ユウちゃん、今夜は、もう先に休み」
多津子が父と娘の沈黙を破るかのように口を開いた。すっかり落ち着いていた。 (続く)












 娘の結婚式が近づいている。
娘の結婚式が近づいている。
 我が家にはタロ、モモ、そして二匹の間にできた娘トトと三匹の犬がいる。タロはもう8年目、ヒゲに白いものが混じるのは、やはり年のせいか。でも、立派な一家の主人の風格を見せる。
我が家にはタロ、モモ、そして二匹の間にできた娘トトと三匹の犬がいる。タロはもう8年目、ヒゲに白いものが混じるのは、やはり年のせいか。でも、立派な一家の主人の風格を見せる。 過酷といっていい、厳しい職場環境の夜の仕事だった。そこで働く顔ぶれを見ると、まるで人生の吹き溜まりといった感がある。昼勤務には普通の会社のように若い世代が活躍しているが、夜は社員になれない中高年の天下だった。しかも半数以上は日系ブラジル人や中国研修生が占めている。残る日本人の六割は保証のない時間給で働くアルバイトかパートだった。
過酷といっていい、厳しい職場環境の夜の仕事だった。そこで働く顔ぶれを見ると、まるで人生の吹き溜まりといった感がある。昼勤務には普通の会社のように若い世代が活躍しているが、夜は社員になれない中高年の天下だった。しかも半数以上は日系ブラジル人や中国研修生が占めている。残る日本人の六割は保証のない時間給で働くアルバイトかパートだった。 野呂木を忌避する気は毛頭ないが、その饒舌に、今夜ばかりは少し距離を置きたかった。もちろん、通夜は、故人をあれこれ限りなく偲ぶための宴席(?)である。存分に生前の思い出を語り合うべき席なのは分かってはいるが、どうもそんな気分になれそうもない。ただ静かに、じっくりと、記憶の中の吉森と向き合いたかった。
野呂木を忌避する気は毛頭ないが、その饒舌に、今夜ばかりは少し距離を置きたかった。もちろん、通夜は、故人をあれこれ限りなく偲ぶための宴席(?)である。存分に生前の思い出を語り合うべき席なのは分かってはいるが、どうもそんな気分になれそうもない。ただ静かに、じっくりと、記憶の中の吉森と向き合いたかった。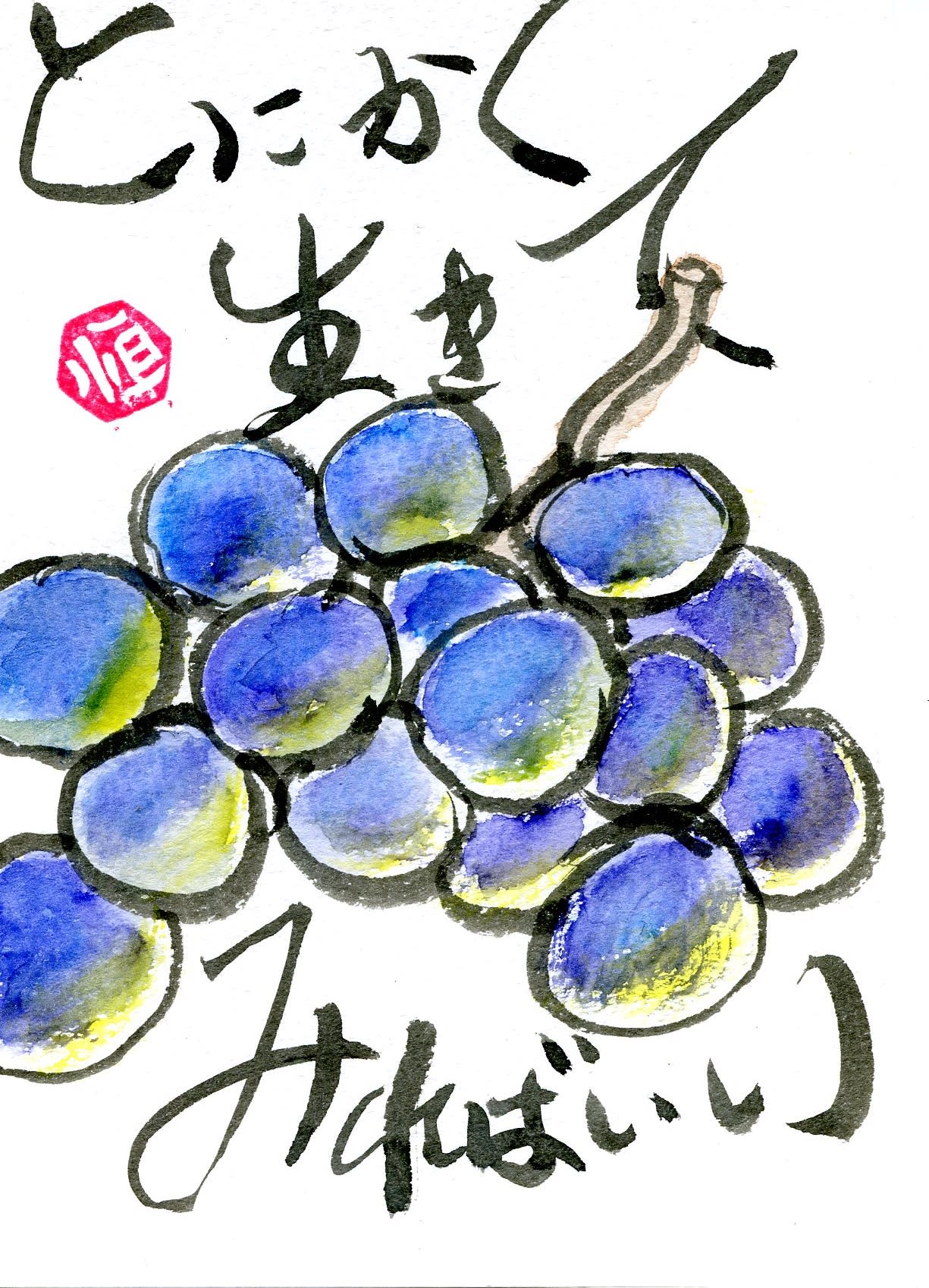 「チリチリチリ…」
「チリチリチリ…」  ある日、夫婦喧嘩をした勢いにまかせて、「怒ってばかりで、勝手なことばかりしてるお父さんなんか、みんな嫌いよね!」
ある日、夫婦喧嘩をした勢いにまかせて、「怒ってばかりで、勝手なことばかりしてるお父さんなんか、みんな嫌いよね!」





