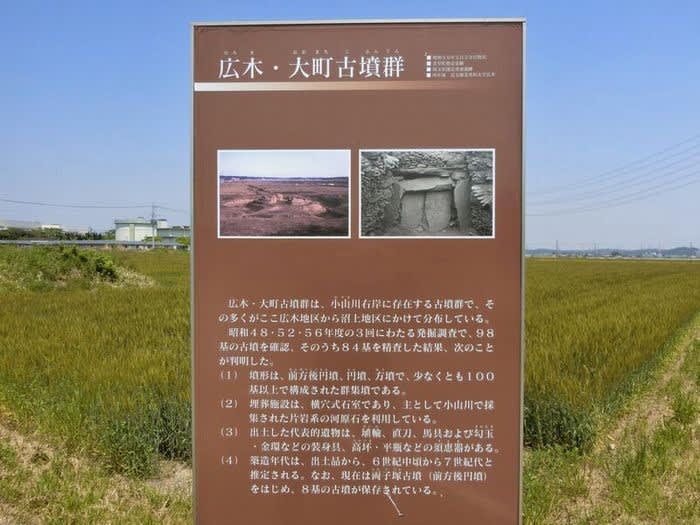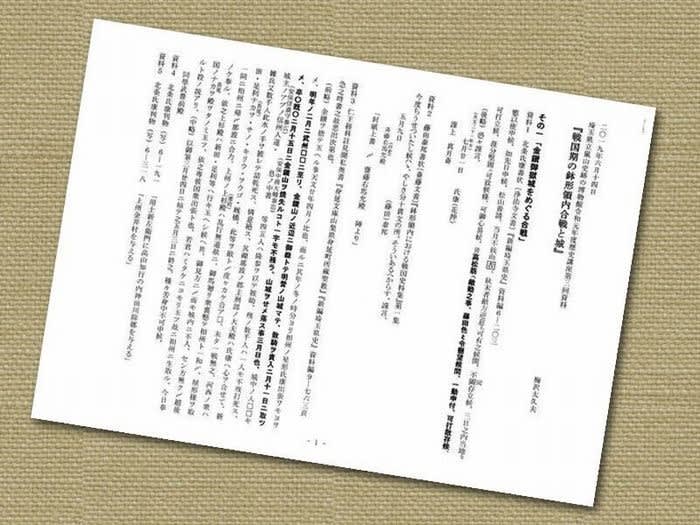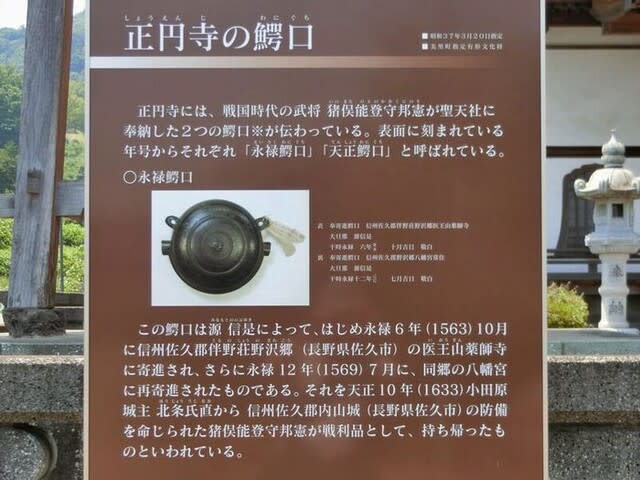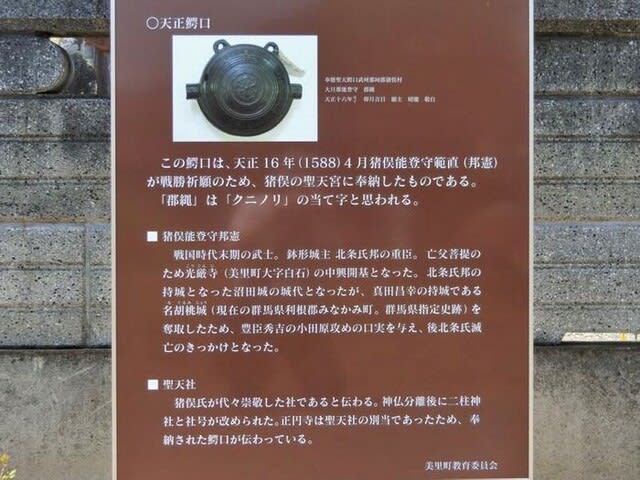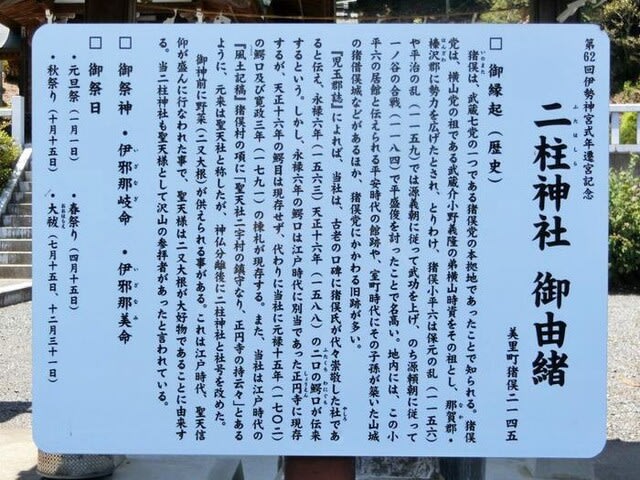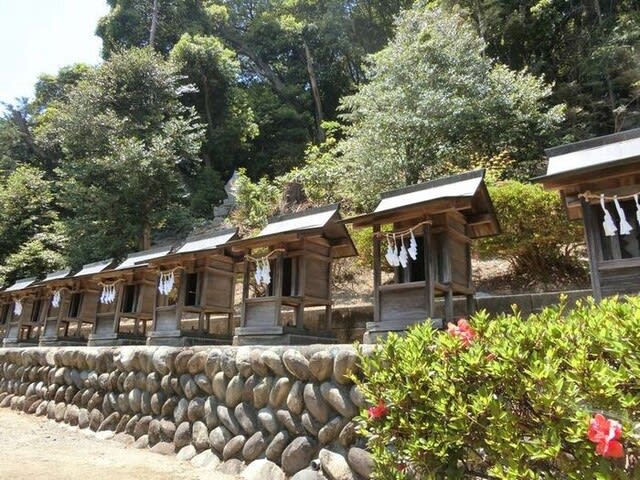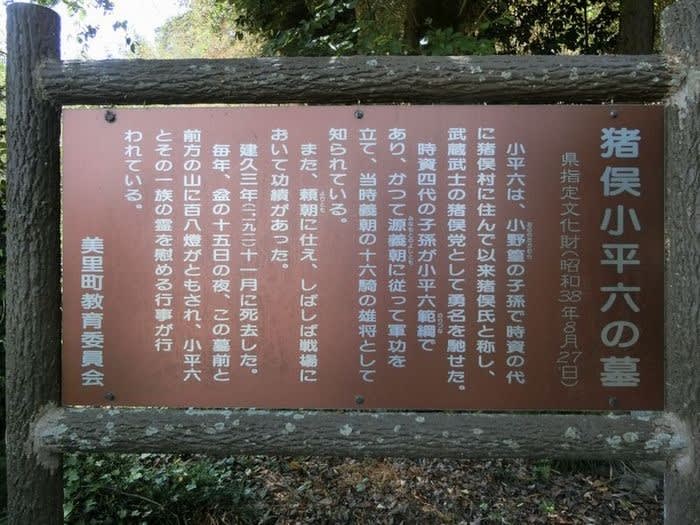埼玉県立嵐山史跡の博物館主催による
文化財めぐり 中世の城館跡を訪ねる2「戦国の山城・杉山城跡を訪ねる」
が、6月7日(金)に催行されましたので参加してきました。
縄張りの巧みさは日本屈指であり、「山城の教科書」とも言われている杉山城跡です。個人では複数回攻城して
いる城跡ですので、あらためて縄張りを確認するというよりも、参加の皆さんの城跡や文化財などにに対する考
え方や知識を少しでも吸収出来ればと参加した次第です。
生憎の雨天となったことにより、見学予定地をカットしたりコースの変更があったりしましたが、無事に終了し
ました。
本来なら、城跡の写真を多用すればよいのでしょうが、団体行動の上、雨でレンズが曇ったり雨粒が付いたりで
ほとんど撮っていません。「参加してきたよ」との意味合いで行程の写真を何枚か載せて置きますので、これで
ご勘弁の程を。

東武東上線武蔵嵐山駅が集合(9:45)・出発(10:00頃)場所です。

駅東口から線路沿いの道を

鎌倉街道上道跡の道路(歩道)を歩いて 信号機の先が志賀観音堂石仏群

志賀観音堂石仏群には寄らずに交差点を右折し嵐山町役場に向います

嵐山町役場の標識 ここから緩やかな坂を上がっていきます

そう高い山ではありませんが、嵐山町役場は山の上にあります

嵐山町役場に着きました ここで時間調整と諸々の見学

ロビーの一画にある続日本100名城スタンプ設置場所

その隣には杉山上の模型 諸々とはこれらのこと
博物館関係者や博物館のボランティアの方々を含めると60人位の大人数がロビーを占拠した形になってしまいました
「何、この人たちは?」と怪訝な顔をしている役場職員も・・・

役場を出て昼食をとる予定場所の杉山公民館に向います

杉山公民館に到着
公民館と言っても、集落の集会所のようで通常は閉まっていますので、主催者が鍵の管理者のもとへ鍵を借りに
行って使用させていただきました。ここで昼食休憩
12:30 嵐山町の観光ボランティアの方3名と合流 参加者を3班編成にして杉山城跡に向います

杉山城が続日本100名城に選定された後に整備された見学者駐車場経由で城跡に向います
今後、車で杉山城跡に訪れる人のために駐車場の場所を知ってもらうという意味も込めてのコース設定

大手口に着きました
ここからは班ごとにボランティアの方と見学です 全員一緒の見学には無理がありますので3班別々のコース取り
をしての見学

ボランティアの方の説明を受けています

今歩いている場所は馬出郭辺りか?

馬出郭口前で説明しているボランティアの方
向うに見えるのは別の班の参加者 南三の郭の上ですね

本郭跡に建つ 史蹟杉山城阯の石碑と杉山城跡説明板

北三の郭の先にある搦手口

杉山城跡の見学を終え、市野川沿いの道を歩いて嵐山町立図書館経由で武蔵嵐山駅方向に

解散場所の武蔵嵐山駅に着きました(15:00頃)
以上、城跡見学のリポートでありながら肝心の郭や土塁等の説明や写真がなく恥ずかしい限りです。
散策日:令和元年(2019)6月7日(金)