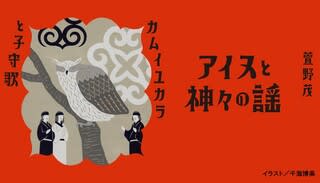アイヌと神々の物語、アイヌと神々の謡
山と渓谷 2020年12月18日
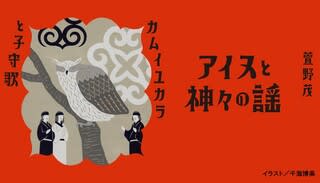
※アイヌ語本文の次の行に、日本語訳を置いています(ただしアイヌ語本文と訳文とはその位置が必ずしも一致していません。訳すにあたって、日本語の言葉の流れをよくするため、3行から5行くらい先取り、あるいは後の行へ移した場合があります)。
アイヌ語研究の第一人者、故・萱野茂氏が、祖母や村のフチから聞き集めたアイヌと神々の13の謡(うた)を収録した『アイヌと神々の謡』。ヤマケイ文庫『アイヌと神々の物語』の対となる名著です。北海道の白老町に「ウポポイ(民族共生象徴空間)」もオープンし、アイヌについて関心が高まる今、本書からおすすめの話をご紹介していきます。第12回は村を恋しがる妻に夫が贈ったあるモノの謡です。
※最後に謡に関連したアニメーションを紹介しています(動画出典:公益財団法人アイヌ民族文化財団)。
大空に描いたコタン
アンナホーレホレホレ ア・コロ・コタン・ポ
私のコタン(村)が
アンナホーレホレホレ アネシカルン
見たくなり
アンナホーレホレホレ タンペ・クース
そのために
アンナホーレホレホレ トゥ・イペ・ソモ・アーキ
食事を取らず
アンナホーレホレホレ トゥスイ・チェ・クーニ・プ
二回食う分
アンナホーレホレホレ レスイ・チェ・クーニ・プ
三回食う分
アンナホーレホレホレ トゥカリ・ケーヘ
その近くへ
アンナホーレホレホレ ア・ノテチューワ
顎(あご)もやらない
アンナホーレホレホレ アナ・ナイネ
そのうちに
アンナホーレホレホレ タネ・アナクネ
今はもう
アンナホーレホレホレ ライ・クーニ・プ
死んだ者と
アンナホーレホレホレ ア・ネ・キ・フーミ
同じだと
アンナホーレホレホレ ウネクーナッ
自分のことを
アンナホーレホレホレ ア・ラム・キーコロ
思っていた
アンナホーレホレホレ アナナイネ
そのような
アンナホーレホレホレ ア・コロ・ユーピ
ある日のこと
アンナホーレホレホレ ソイェンパー・ワ
私の兄が
アンナホーレホレホレ アフプ ・クーニ
外へ出たが
アンナホーレホレホレ カスノ・イーサム
帰る時を
アンナホーレホレホレ カスノ・イーサム
過ぎても
アンナホーレホレホレ キ・ルウェ・ネ・アイネ
帰らず
アンナホーレホレホレ アフプ ・アークス
ようやくのこと帰ってきて
アンナホーレホレホレ エネ・イータキ
いうことには
アンナホーレホレホレ ア・コロ・トゥレーシ
妹よ
アンナホーレホレホレ ア・コロ・コタンーポ
わたしたちのコタンを
アンナホーレホレホレ エ・エシカールン
慕(した)うあまり
アンナホーレホレホレ タンペ・クース
食べ物を
アンナホーレホレホレ トゥ・スイ・チェ・クーニプ
食べもしないで
アンナホーレホレホレ レ・スイ・チェ・クーニプ
いるうちに
アンナホーレホレホレ ソモ・エエーノ
今はもう
アンナホーレホレホレ エ・アン・アイーネ
死を待つばかり
アンナホーレホレホレ エ・ライ・ワ・ネーワ
お前がこのまま
アンナホーレホレホレ ネワ・ネーヤッ
死んだならば
アンナホーレホレホレ モシリ・エ・ウェンー・ペ
国土のために
アンナホーレホレホレ コタン・エ・ウェンー・ペ
コタンのために
アンナホーレホレホレ ネ・ルウー・ネ
ならないことだ
アンナホーレホレホレ キ・ワ・クース
それでわたしは
アンナホーレホレホレ ソイェネ・アーン・ワ
外へ出て
アンナホーレホレホレ ア・コロ・コターン・ポ
その昔に住んだコタン
アンナホーレホレホレ トゥ・ノカ・オローケ
二つの情景
アンナホーレホレホレ レ・ノカ・オローケ
三つの様子を
アンナホーレホレホレ ア・ヌイェー・ワ
大空の表へ
アンナホーレホレホレ アフンナン・キーナ
描いてきた
アンナホーレホレホレ ヘタッ・ソイェーンパ
さあ早く外へ出て
アンナホーレホレホレ インカラ・キー・ヤン
描いたものを
アンナホーレホレホレ セコロカイーペ
見るがよい
アンナホーレホレホレ ア・コロ・ユーピ
そのように
アンナホーレホレホレ エタイェ・カーネ
私の兄が
アンナホーレホレホレ キワ・クース
いったので
アンナホーレホレホレ ソイェンパー・アン
外へ出るのも
アンナホーレホレホレ イキ・ヤナーイネ
やっとの思いで
アンナホーレホレホレ レイェレイェーアン
はうように
アンナホーレホレホレ シヌシヌー・アン
膝をするように
アンナホーレホレホレ ソイェンパ・アーン・ワ
外へ出て
アンナホーレホレホレ インカラ・アン・ワ
いわれたとおり
アンナホーレホレホレ ネ・ワ・ネチーキ
大空を見上げると
アンナホーレホレホレ ニシ・コトーッタ
空の表へ
アンナホーレホレホレ ソンノ・ポーカ
本当にも
アンナホーレホレホレ ア・コロ・コターヌ
私たちのコタン
アンナホーレホレホレ ア・コロ・モーシリ
私たちの国土
アンナホーレホレホレ トゥ・ノカ・オーロケ
二つの姿
アンナホーレホレホレ レ・ノカ・オローケ
三つの形
アンナホーレホレホレ ア・ヌイェ・キーワ
描かれている
アンナホーレホレホレ シラーン・カートゥ
その様子と
アンナホーレホレホレ エネ・オカー・ヒ
いうものは
アンナホーレホレホレ シシリムーカ
沙流(さる)川の流れ
アンナホーレホレホレ アラパ・ルーコ
清らかに
アンナホーレホレホレ マッナターラ
光りかがやき
アンナホーレホレホレ ケナシ・ソ・カータ
川辺の平地に
アンナホーレホレホレ ノカン・ユッ・トーパ
子ジカの群れと
アンナホーレホレホレ ルプネ・ユッ・トーパ
親ジカの群れが
アンナホーレホレホレ チ・テッテレケー・レ
群れ別に走り
アンナホーレホレホレ シシリムーカ
沙流川の流れ
アンナホーレホレホレ ペトッナイー・タ
流れの中は
アンナホーレホレホレ ノカン・チェープ・ルプ
小形のサケや
アンナホーレホレホレ ルプネ・チェープ・ルプ
大形のサケ
アンナホーレホレホレ チホユプ ・パーレ
競ってさかのぼる
アンナホーレホレホレ カンナ・チェープ・ルプ
水面のサケは
アンナホーレホレホレ スクシ・チーレ
天日で背が焦げ
アンナホーレホレホレ ポクナ・チェープ ・ルプ
川底を泳ぐサケ
アンナホーレホレホレ スマ・シール
腹を擦(す)りむき
アンナホーレホレホレ チェプ ・コイキ・クーニプ
サケを捕る者
アンナホーレホレホレ マレプ ・ウ・コ・エタイーパ
鉤(かぎ)奪い合い
アンナホーレホレホレ ペッ・ケナシ・カータ
川原の原野に
アンナホーレホレホレ ルプネ・ユッ・トーパ
大ジカの群れ
アンナホーレホレホレ ノカン・ユッ・トーパ
小ジカの群れ
アンナホーレホレホレ チ・テッテレケー・レ
競い走り
アンナホーレホレホレ ユク・コイキ・クーニ・プ
シカ捕る者
アンナホーレホレホレ オロ・チパスース
後を追う
アンナホーレホレホレ トゥレプ ・タ・クーニプ
ウバユリ掘る者
アンナホーレホレホレ ノカン・サラーニプ
小さい袋を
アンナホーレホレホレ ウ・コ・エマーッパ
嫌いやがって
アンナホーレホレホレ ルプネ・サラーニプ
大きい袋を
アンナホーレホレホレ ウ・コ・エタイーパ
奪い合い
アンナホーレホレホレ スス・ニ・ターイェ
ヤナギ原は
アンナホーレホレホレ ホサ・ホチューパ
川岸に生え
アンナホーレホレホレ ケネ・ニ・ターイェ
ハンノキ原は
アンナホーレホレホレ ホ・マコチューパ
山すそに生え
アンナホーレホレホレ スプ キ・サーリ
野ガヤの原は
アンナホーレホレホレ ホサ・ホチュー・パ
川原に広がり
アンナホーレホレホレ シ・キ・サーリ
オニガヤの原は
アンナホーレホレホレ ホマコ・チューパ
後の方に
アンナホーレホレホレ アンラマース
その様子を見た私
アンナホーレホレホレ アウェ・スーイェ
気分がすっかり
アンナホーレホレホレ キ・ルウェ・ネアイーネ
さわやかになった
ア・シケトコ・ウシコサヌ
そのとたんに目の先の絵が消えてしまった
オロワノ・ピリカノ・アナン・セコロ
空の表の絵を見てから私は
もとのように健康になりました
オキクルミ・マタキ・ハウェアン
とオキクルミの妻が語りました
語り手 平取町荷負本村 木村うしもんか
(昭和36年10月29日採録)
解説
このカムイユカラ(神謡)を聞かせてくれた、木村うしもんかフチ(おばあさん)自身が解説してくれた言葉そのままを、ここへ記します。
「シケレペの向かいにオキクルミカムイが妹と二人で暮らしていたが、シケレペのコタン(村)が飢饉(ききん)になって、コタンの者が食う物がなくなった。オキクルミカムイは海へ行って魚を捕ったり、クジラを捕ったりして、それを煮て大きなお椀にいっぱい入れては妹に持たせ、一軒一軒に運ばせた。
戸から入らずに、窓から手だけ家の中へ伸ばし魚などを配り歩いているうちに、貧乏でばかな男が女の手を見て、どんな顔の人だろうと、お椀を取らずに手をつかまえた。それをオキクルミカムイが怒って、妹と一緒に神の国へ帰ってしまった。
二人は神の国へ帰ったが、オキクルミカムイの妹は暮らしていたアイヌのコタンが恋しくなり、病気になってしまった。困ったオキクルミカムイは、大空の表へ沙流川の様子を描き、妹に見せてもとのように元気になったということです」
シケレペという地名は、平取町荷負市街から一キロほど上流の所にあるコタンの名前です。
ユカラ(英雄叙事詩)とかカムイユカラに出てくる妻の表現は、マタキ(妹)という語を使うことがあります。したがって、アイヌ語をよく知らない人が、アイヌ社会では近親結婚の風習ありといい、物議をかもした例を聞いたことがあります。
ユカラやカムイユカラには、妻のことを妹と呼ぶことが多く、また夫を兄と呼ぶことをあらかじめ知っておいた方がよいでしょう。
万一にも兄妹で結婚するようなことがあったとしたら、ウコセタネ(互いに犬になった)といって大変に軽蔑されるので、絶対といってもいいほどそんな結婚話は聞いたことがありません。
本文に出てくる描写の、ヤナギは川の岸辺に、ハンノキは山のふもとになど、木の生え具合やカヤ原は他の作品にもよく出ています。
※本記事は『アイヌと神々の謡~カムイユカラと子守歌~』(山と溪谷社)からの抜粋です
https://www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=1298