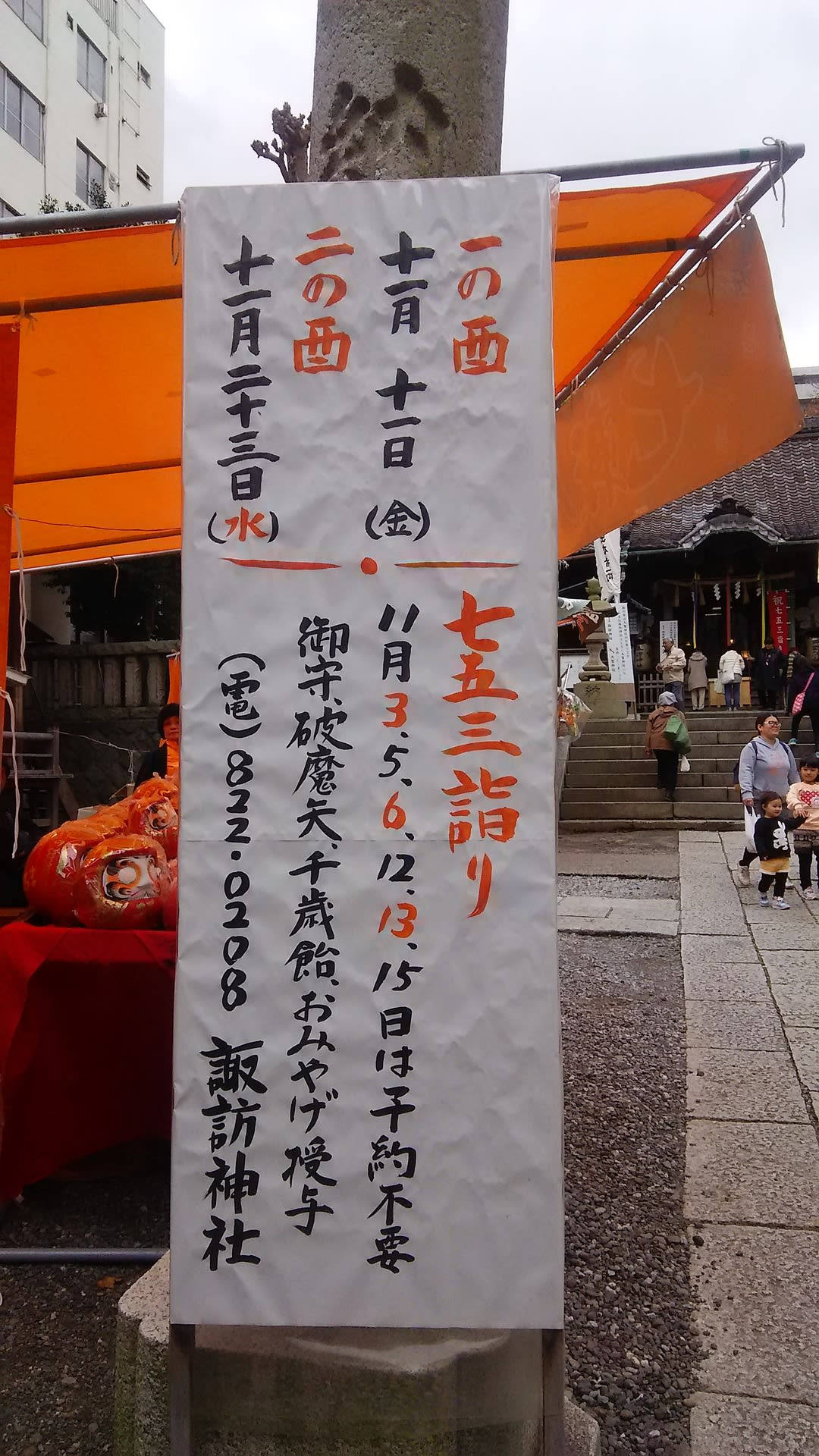昨日「てんがらもんラジオ」の藤崎さんが話の途中で歌われました。例によって耳のせいで聴き取れないところがあり、残念に思っていましたらリスナー仲間ののびたさんのブログに紹介されていました。
のびたさんのブログは、ここです。
http://blog.goo.ne.jp/new-nobita/d/20161125
藤崎さんの話では大正年間に鹿児島で歌われていたそうです。
アメリカ独立戦争で大きな役割を果たし、初代大統領になったジョージ・ワシントンを讃えたものです。のびたさんと同じようなうたごえのブログに三番まで紹介されていましたので、ここにあげておきます。

1番の歌詞、藤崎さんが美声で聞かせてくれた部分に「十三州の」とありますが、下の説明に「13植民地」というのがこの地域を指しているのです。

大正年間、大正デモクラシーといわれた時期でもありますが、イギリス本国の重圧に抗して独立戦争に立ちあがったアメリカの人々、その代表であった ジョージ・ワシントンへの賛辞です。その歌が街中で歌われていた大正年間の鹿児島、大いなる心意気を感じます。
それを21世紀の当地で歌い継いでいる藤崎さんには、余興としての歌とは思われません。県議会議員という政治家としての気概の表れとして伝わってきます、歴史を知るものの強みのひとつとして受けとめる由縁です。
県の職員さんが本を出版された話も面白く聞きました。内容は大阪の商人から薩摩藩が借財を負い、そのかかわりで1828年から1838年の間に6回行き来した旅日記を鳥瞰図も入れ紹介したものなのです。県職員としてどのような部署におられたのか、県財政に関わる部署ではとも思い、これも単に個人的な趣味に関することをまとめたものとは思えないのです。ここにも歴史を知る者の強みの一面を見る様な気がします。
2018年のNHK大河ドラマは明治維新150周年とも関連し西郷隆盛を描く「西郷どん」です。その当地での反響への関心も持って3日後には鹿児島に居るわけです。私の関心のひとつは西郷隆盛が丸ごと描かれるかということと、大久保利通がどう描かれるかにもあります。
加山雄三さんの話ではありませんが、葉山町の町会議員さんに大久保利通の血を受けた女性議員が頑張っています。そんなこともありますし、地元での大久保利通の人気なども直に知りたいと思います。歴史豊かな地で大いに学べるのも天から与えられた好機・てんがらもんです、大いに生かして学んで来ようと思います。