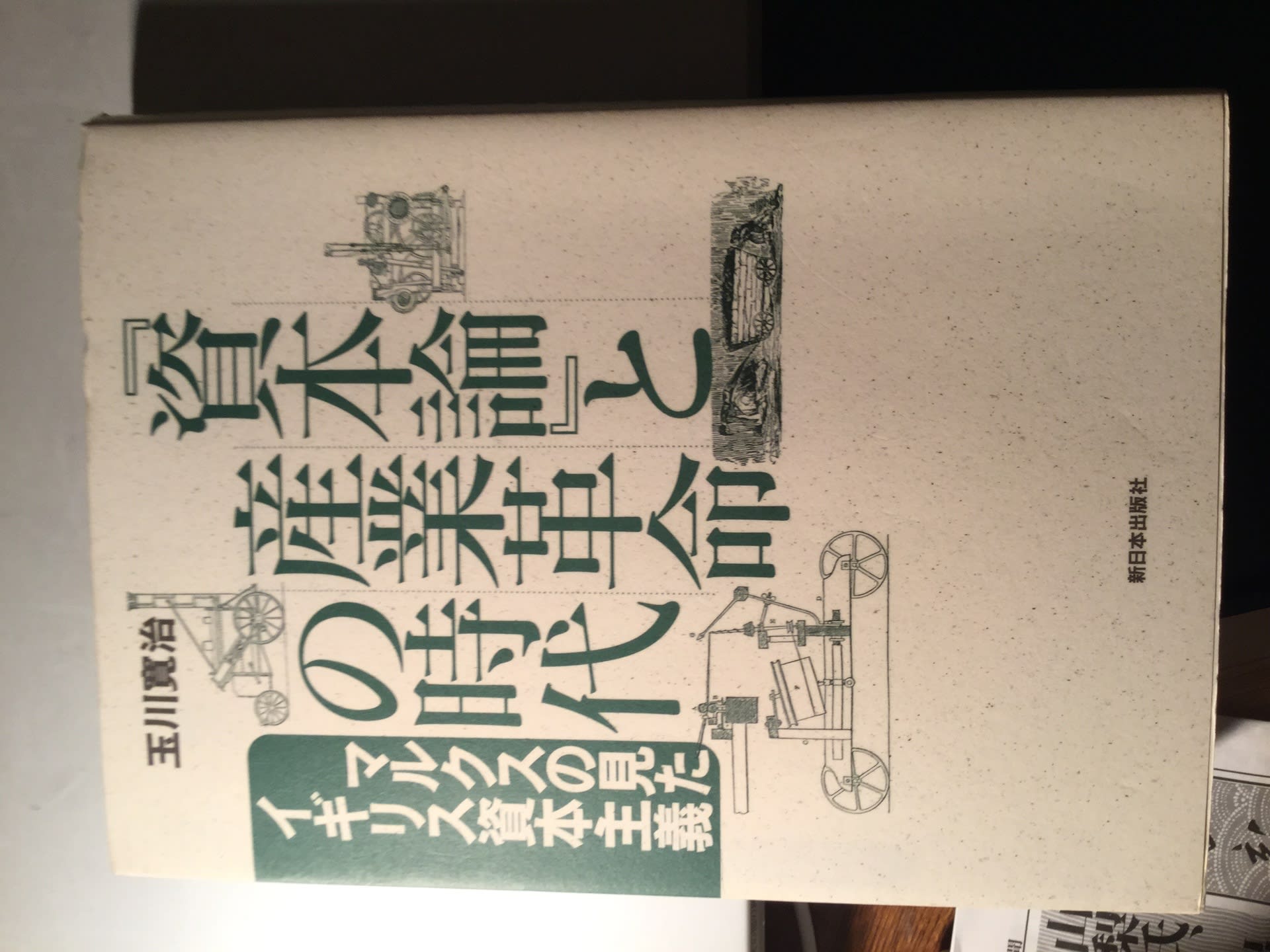3 木々の枝こまごまとある冬の水
4 冬の水平らかに木影うつしをり
この二つの俳句について《 これらの句になると理屈はない。冬の水に木影がうつっているという自然の事実を描いているだけで、つまり見る眼がもとになっている。こういう句を写生の句という。》と述べます。そして真の写生という立場からみてどうかと論をすすめます。
《 真の写生とは、まず則天去私に立って事実を尊ぶということから始まる。尊ぶということは対象をいかに深く、鋭く見るか、ということである。深く鋭くみるということは、そのものの内部にはいることである。内部にはいるには、そのものの生命に、自分の心の真実がふれなければだめだ。》
《 だから、写生の眼はカメラのレンズとは違う。ただ状態を写すのではない。実体をつかむのだ。それが人間の眼である。人間の眼は対象を尊重すればするほど、対象のなかにはいらなければならぬ。はいるには心のはたらきが自然に生じなければならない。ただ、ものをありのままにスケッチする、そいいうのではない。それは軽い技術の練習であ》ると述べています。
その上に立って《 これらの句をみると、観察している眼が皮相なのにきがつくのである。~要するに、かかる冬木水映の、自然のもつ透徹した静けさの重み、つまり生命がこの句ではとらえられていないのだ。それは作者の心が対象のなかに、じっとはいりこんで実相をつかもうとしていないからである。そこにこの句のものたらさがある。ひとことでいえば心がないのだ。》
《 スケッチの写生で終ってしまっては、詩に昇華されず、一種の報告になる。観察して深くて感動するところがあって、それがおのずからことばの表現を産むのが詩だからである。感動のない観察は、よし対象の真は描けても、作者の心象とか風懐とか、大きくいって、自己の人間的要請というものは示せない。》
このあと5、6、7について語る部分が続くのですが、これから小父さんの所で年越し蕎麦、そして森山神社へ、初詣参拝者をむかえますので、この後は来年に!