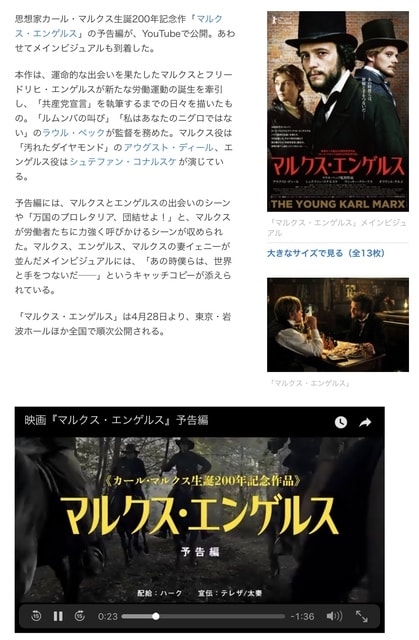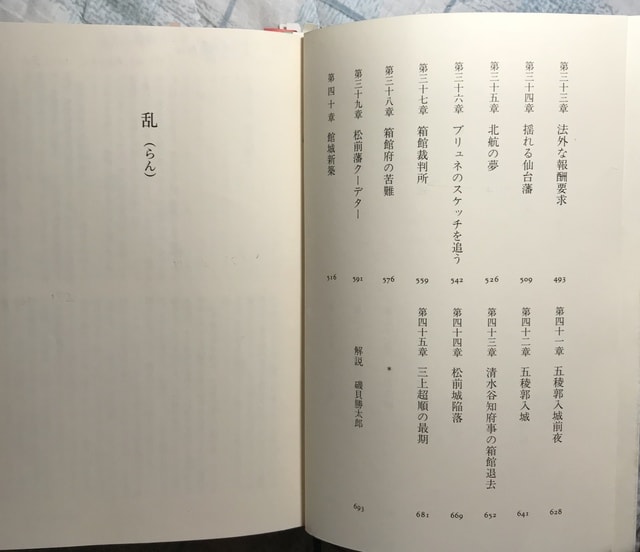「資本論」学友へ、ー1ー
先日一緒に不破さんの『「資本論」探究 上』を買いに行ってから1ヶ月以上になるでしょう。その間に下巻も出て不破さんの資本論関係書の最新版を手にすることができました。これを機に再度「資本論」通読への挑戦をと思っています。

実はあなたに渡した私の資本論学習の報告文まで(第3部第5篇第31章)で、今までの資本論輪読会が休会になってしまいました。総選挙とその後の対応に正月が重なり、メンバーの都合が揃わなくなったためです。
後の一回で信用論が終わり第6篇の地代論に入るところだったのですが、ある意味ででは一区切りついたのかとも思います。この先をとにかく読み通すという手もありますが、それよりも不破さんの資本論本を手掛かりに、「不破資本論」に基づいて資本論を読むという道の方が良いのではと思います。
例えば、不破さんが2005年の雑誌「前衛」2月号に、

という話を書いています。これは二つの「資本論学習会」での話をまとめたものですから大変分かりやすく、これから高い頂に挑戦する者にとって有難い道しるべです。
そこに、(第三部)第5篇(信用論)について、
【 第五篇は、大きく分けて、利子生み資本についての理論的研究を中心にし前半部分(第二一章〜第二四章)と、信用制度とその運動を主題にした後半部分(第二五章〜第三五章、それに第三六章の歴史部分がくわわる)とからなっていますが、とくに後半部分は難解で読者がもっとも悩まされる部分です。
しかし、編集したエンゲルスが、全体を脈絡あるものにするのはうまくゆかなかった、と率直に言っているのですから、この篇については、中身が簡単に読みとれなくても、それは必ずしも読者のせいではないわけで、安心して取り組んで下さい。】
【信用論を難しくしていることには、もう一つ理由があります。第五篇の後半の信用論の部分は読んでゆくと、ほとんど全章がイギリスの議会の委員会の議事録からなりたっている章がいくつもあることに気づかれるでしょう。(注)
(注)「第二六章 貨幣資本の蓄積。それが利子率におよぼす影響」、「第三三章 信用制度下の流通手段」、「第三四章 〝通貨主義〟と一八四四年のイギリスの銀行立法」、「第三五章 貴金属と為替相場」の四章がそれです。】
【 マルクスは、信用論の部分を執筆中の一八六五年夏、インフルエンザにかかりました。その時、病気と仕事の状況をエンゲルスに説明した手紙が残っています(一八六五年八月一九日付)。そのなかでマルクスは、『資本論』のような頭を使う本格的な仕事はできないから、いろいろほかのことをやっているんだ、と言い、その一つとして、銀行制度に関する議会報告書をもう一度調べてみた、と報告していました。イギリスの議会で銀行家とか大商人とかが、勝手放題な混乱した議論をしている。これらのでたらめな議論を根こそぎやっつけることが必要だが、この材料は、「もっとあとの本」のために使うつもりだというのです。第三部草稿のなかにまじりこんでいた議事録の抜き書きは、登場人物からいっても、議事録のページを追って書き抜きしたその形式からいっても、この手紙でいう「もっとあとの本」の材料に当たります。
エンゲルスはその手紙を受け取った当人だったのですが、編集のときにはその事情を思い出さなかったのでしょう。これも『資本論』の草稿だと思いこみ、この議事録を整理しなおして、自分のシナリオで『資本論』向けの一連の章をつくりあげてしまったのでした。(ここで不破さんは注をもうけてますが略します)この推論によれば、問題の一連の章は飛ばして読んだ方が、マルクスの理論展開の筋道が追いやすくなると思います(笑い)。】
こういう部分を読むと『資本論』読了を自己目的化して、ただ読み終わることを追求するような構えは、労多くして効少なしの思いがします。
この部分はエンゲルスの「資本論編集の問題点」としてわかりやすいのですが、理論展開のうえで問題があるという指摘は、マルクスが意図した資本論構想の全貌を掴んでの上でなければ理解できないことでしょう。そのためにはマルクスの残した資本論の準備草稿の全体を読み解かねばなりません。
その草稿についての不破さんの話です。
【 マルクスが残した草稿は、直接『資本論』草稿として書いたものだけでなく、『資本論』の準備段階で書いた草稿がいろいろありました。なかでも、二つの草稿が大事です。一つは、一八五七年から五八年にかけて八冊のノート(序説一冊、本論七冊)にびっしり書きこんだ『五七〜五八年草稿』、もう一つは、一八六一年〜六三年にかけて三十一冊のノートに書いた『六一〜六三年草稿』です。マルクスは、こういう準備草稿を書きながら、『資本論』の内容や構想を練り上げていったわけですから、そこには、『資本論』の組み立てや論点を読み解くヒントになるような材料がたくさん書き込まれています。
エンゲルスはこういう草稿があることは知っていて、ある程度は目を通したようですが、『資本論』そのものの第二部、第三部の草稿を読み取るのがたいへんで、準備草稿の内容まで本格的に読み込むゆとりはありませんでした。そこから来る編集上の弱点が、いくつかの面で、現行の『資本論』に残されていることは、否定できないところです。】
そして現在の私たちが『資本論草稿集』を入手できる状況にあることを紹介して、
【 現在では、私たちは、『資本論』の研究のさいに、エンゲルスも十分に読み込む条件のなかったこれらの準備草稿を読むことができるのです。これらの準備草稿を研究すれば、『資本論』にかかわるマルクスの考えのなかで、エンゲルスが分かっていなかったであろう点も、私たちが理解できるという場合もありうるわけで、その意味では、私たちは、第二部、第三部を編集したエンゲルスよりも、もっと有利な条件で『資本論』を読むことができる、と言ってもよいでしょう。】
【 そこに〝二一世紀ならでは〟の読み方の一側面があります。】
と『資本論』本論に入る前に触れています。