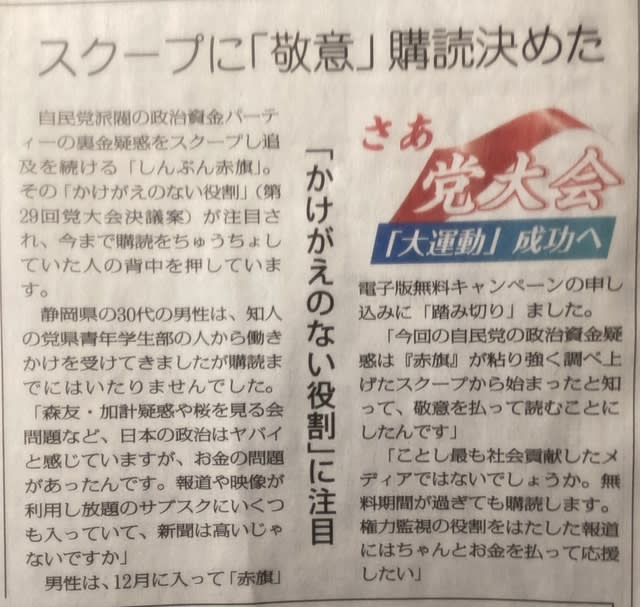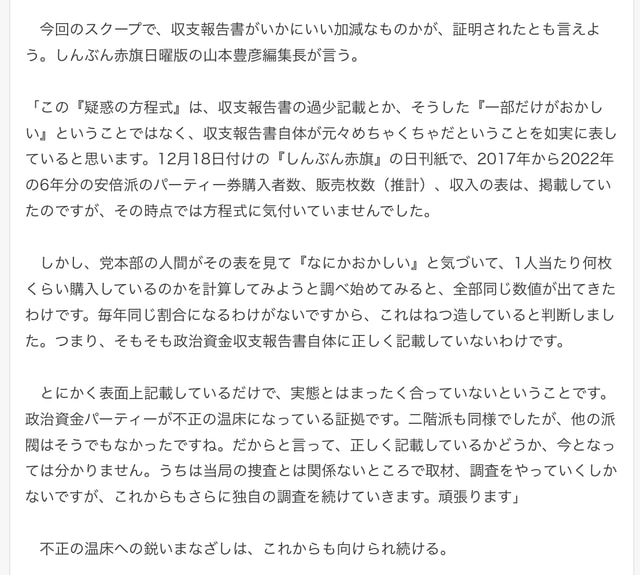冬至から七十二候に気が向き、それに関する本を探していたらこんな古本が本棚ありました、

10年くらい前に鎌倉の古書店で買ったとメモされていますが、当時俳句から季語にその関係で暦に気が向き出して、15000円の本が1000円で買えるということで買ったものでしょう。
そのあと開いてもいなかったのでしょうか、元の持ち主が挟んでいた新聞の切り抜きが2枚と雑誌のなんページかをホチキス止めしたものが出てきました。その一つが本の脇の「ゴゼンサマ向き?昔の日付」です。
今の世は夜中の〇時という時刻が1日の始まりですが、古代は更に3時間経った午前3時だった、ということが分かった、という新聞記事です。当時の記録を集めて検討した結果です。
なかなか面白いです、年末の諸事に忙殺されている頭で、古代人がなぜ深夜に日替り時刻をもってきたのか考えてみて下さい、本文を移しておきます。
古代の日本人は午前三時を昨日と今日の境界にしていた——古文書の天文現象を解読していた斉藤国治・前東大教授らのグループが興味深い事実をつきとめた。これにより真夜中に起きた歴史的事実の中には日付が一日ずれているものがあるということになりそうだ。
星が月のうしろに隠れて見えなくなる天体現象は星食といわれている。斉藤さんらは星食に関する記録を古文書から拾い出し、その記載が正しいかどうかを天文年代学的に確かめる方法をとった。
わが国最古の星食記録としては、日本書紀の中に、次のような一文があるという。「舒明天皇十二年春二月甲戌、星入月」。この日付を現在使っている暦でいい直すと「六四〇年三月七日」となる。斉藤さんらが天文年代学で使う数表をたどってみると、確かにこの日、星食が起きていることがわかった。
隠れた星はおうし座の一等星アルデバラン。月は三日月。星食は当時の都であった飛鳥京では夜八時二十七分から同九時二十五分まで続いたことも判明。日付がしっかりしていれば、内容は簡単でも天文年代学の記録や数表から、星食の起きた時・分、星の種類まで正確にとらえることができる。
そこで斉藤さんらば上代から中世末にかけての約千年間にわたるわが国の古文書から星食に関する記述を拾い出した。文献は日本書紀、日本紀略、太平記など。 そのうち、星食が夜半から明け方にかけて起きた六十四例について日付を検討してみた。
すると午前零時から午前三時までのものが二十五例。だが、そのうちの二十四例は古文書の記録が一日ずれて前日のままになっていた。
たとえば、日本書紀に「天武天皇十年九月癸丑、熒惑入月」とある。現代風にいい換えると、六八一年十一月六日、火星が月に隠れた、となる。しかし、天文年代学の数表で計算すると、火星の星食が起きたのは翌七日の午前一時十八分から同二時までの四十分間余りであった。
明らかに一日ずれている。しかし、単なる誤記と見るには似たような事例が多すぎる。 午前三時までは日付が変わらない、と考えた方がわかりやすい。
また、午前三時から同六時までの星食記録は三十五例。この場合は三十四例までが古文書と天文年代学の日付が一致。こうしたことから、斉藤さんらは「昔の日本人は午前三時を一日の始まりと考えていた」と結論づけた。
六十四例のうち残り四例は星食が午前三時をまたいで起こっており、この場合は三例が天文年代学の日付と同じだった。午前三時といえば「草木も眠るウシ三つ時(午前二時ー二時半)」に近く、昔の人はとっくに寝てしまっていたと思われるので、なぜ午前三時を一日の始まりにしたのかは、よく分からない。現代なら、この日付区分で、「ゴゼンサマ」といわれなくて助かる人がいるだろうが……。
土田直鎮・東大史料編纂所教授の話 昔の公家たちの日記などから、一日が何時ごろから始まっていたかおよその傾向はつかめていたが、天文現象という客観的事実との関係ですっきりさせたのは初めてだと思う。